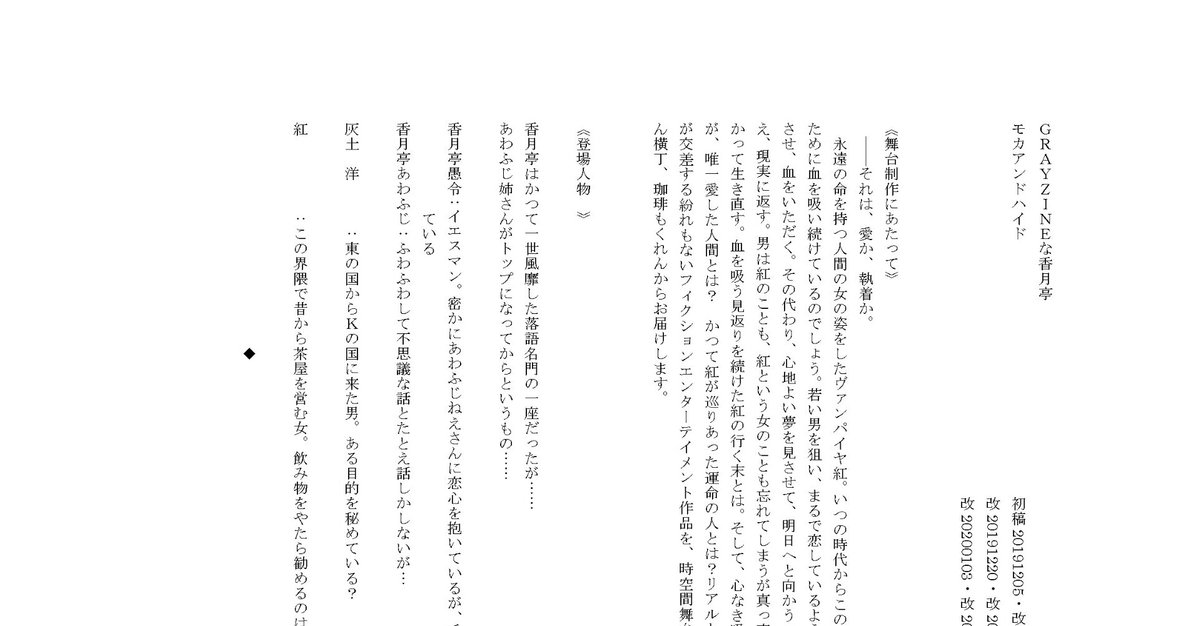
茶店〇弐壱四【BAR0214江戸編】
BAR0214(バーゼロニーイチヨン)メニュー
【現代編】RED EYEの誘惑(公開中)
やさしいBLUEeyes (公開中)
空白の丑密 (公開中)
LAST ~会釈~ (公開中)
【平安編】丑三の秘め事(2021年3月14日公開)
漆黒の恋 (2021年3月15日公開)
真夜中の絵師たち (2021年3月16公開)
つかの間の永遠 (2021年3月17公開)
鏡淵 (2021年3月18日公開)
テンバイ峠の怪(2021年3月19日公開)
【江戸編】茶店〇弐壱四(2021年4月10日公開・2018年12月発行『コーヒー文化研究 設立25周年記念号』掲載分)
茶店〇弐壱四 ~花ぞ昔の香ににほひける~
一、和歌川近くの茶店
時は江戸、吉宗が将軍になった頃である。梅のつぼみがくすぶり始め、紀伊国でもその開花の波が南からやって来ていた。虎伏山のふもとから吹いてくる風はもう、ほのかな梅の香をのせている。城から少し離れた和歌川近くの茶店〇弐壱四の裏路地にも細い一本の梅があった。亭主の壱(イチ)は香ばしい茶を淹れながら、偶然隣り合わせた薬屋の誠吉と近所の長屋に住む長介の会話を静かに聞いていた。
「家の梅はもう咲きましたけど、この梅は遅いですなぁ」
「長介さん、これは種類が違うと思いますよ。ほら、蕾の中心が紅いでしょう。いずれにしてもあの膨らみはもうそろそろかと。今夜は満月ですしね」
「さすが誠吉さんは物知りですなぁ。薬を売って全国を回られてるとか。ワシはずっとあそこで魚を釣って売ってるもんで、何にも知らんのやして。もう歳やし話を聞くのが楽しみなんよぉ」
「ずっと同じ場所で魚を釣るのもすばらしい才だと思いますよ。ひとつ不思議な話をしましょうか。この茶店も関係しているかもしれません」
「そりゃあええ。なぁ、壱ちゃん。この茶店の謎やってよ。まぁ亭主も聞いちゃんなぁよ」
「はい。どんなお話なんでしょう。いつもめずらしい茶を仕入れてきてくれる誠吉さんのお話ですから、私も聞いてみたいものですね」
「壱ちゃんは、いつも反応が薄いなぁ。これでも八つ時になればこの寡黙な壱ちゃんを見に、可愛い町娘やらその奥様やらが来るんやから。なかには大奥からお忍びで、来てるんちゃうかっちゅう噂もあるんやで。番茶ひとつで繁盛する。それこそ不思議な話やでー。壱ちゃんの花の話も聞きたいもんや」
「はははっ。わかります。この話はその大奥にも、壱さんにも関係するかもしれません。私が各地を回っているうちに耳にした噂話を纏めて話を作ってみたんですよ」
長介の湯のみの中では茶柱が浮いていた。明日もええ魚が釣れそうだと長介はひとり下を向きながらほくほくと喜んだ。その横では、ハッキリと誠吉と壱の目と目があっていた。
壱の目は『どこまで話されるのだろう』明らかにそんな動きをした。壱は自然に目を逸らしながら誠吉の湯のみに茶を足す。壱の顔とその目をじっと見ながら誠吉は話を切り出した。
「吉宗公の母君の話ですがね。この噂はご存知かと思います。湯殿番だったことから、光貞様のお手付きになったとか」
「可愛い娘が入浴中に傍にいたら、目に留まりますわな。ワシも若いころは」
「で?」
壱は長介の話が始まるのを珍しく止めた。どうやら触れられたくないところを突いたようだ。その確信を得た誠吉はさらに続けた。
二、薬屋誠吉の推理
「その紋(あや)さんのことです。大奥に入る前まで、足しげく通っていた店があるとか…。その店の亭主の助言が良くてトントン拍子に大奥、湯殿番、側室、生母様となったのではと、噂がありましてね。その噂は江戸のほうまで伝わっておりました。薬を売りに行って聞いた先の一番南が串本ですから、その店は紀伊国内に、いえ私はこの界隈にあると思いました」
「ほお。その店が、ここちゃうかって言うことやな。おもしゃいわ。さぁよ。うちの母ちゃんもよう喋るけど、女はそんな話をいっつもしてるんかぇ」
「面白いですね。ただ、そうすると、私は長さんより年上になってしまいますね」
「まあ、続きを聞いてください。今も八つ時になると、城の南東にあるこの店に女子が集まってきますね。そりゃあ壱さんの茶はうまいですから。そこは否定しません。私だってこうして旅の途中には必ず寄るんですから。ただ、それだけではないと思いましてね。行く先々のお宅でそっと聞いてみたんです。紋さんの出世のお話を。そうやってたどって行くと、紋さんは農家の出で器量も良く、誰からも好かれていたんだとわかりました」
「わかる!誠吉さん!わかるでぇ。田舎の娘は作物だけとちごて兄弟の世話しちゃうさけ器量がええんじょ。その市場に売りに来る子もまた可愛い子なんやでぇ」
「そうでしょうね。ただ、好かれる分、妬まれることも多かったようです。ほら、同じものを売りに来ても売れ残る子と、売り切れる子に分かれてしまう。長さんもそんなことあったのではないですか」
「若いころは多少あったかもしれんな。ちょっとそこで釣らせてくれと言われて、それで動いたら、またそこにやって来て釣らせてくれと言われてな。気づいたらどんどん川上に移動してたわ。それでも釣れてるワシが羨ましかったんやろな。最後はその釣り竿貸してくれと言うから怒ったこともあったなあ」
「そんなことが紋さんにも起きた。ただ、まあ若い女の子ですから、売り先を閉ざされてしまったり、明らかに嫌がらせをうけたら、もう可哀想です。それでも一生懸命柿やみかんを売っていたようです。そこに現れたのが神様でもお釈迦様でもなく、鬼女だったんです」
「はははっ。やっぱり。誠吉さんの話はいつもその鬼女がでてくる。今回もやっぱり美しい肉吸い(吸血鬼)ですか」
壱は誠吉から仕入れた唐茶の袋を開きながら、口だけで笑った。見た目は黒く、とても飲めると思えない色の豆なのに、そこからは何とも言えない芳しい香りが漂った。
「お、変わった匂いがするなぁ。また壱さんの茶研究の時間やでぇ」
「ふふ、そうです。作りながら聞いていますから、どうぞ続けてください」
「それで、その鬼女は紋さんに何かしたんかえ?可哀想によぉ」
「いえ長さん。この鬼女、話せば長いんですが、いい肉吸いです。まあまだ謎は多いんですが。少しだけ人間の血を吸う代わりにその者の夢の中に入り、本当にその者の夢を叶えてやれる術を使うんです」
「でも誠さん、その鬼女、えーっと、確か名前は紅さんでしたか。純粋な若い男を狙って彷徨っているんじゃなかったですか?確か、絶世の美男子平維盛を愛してしまったからその血筋ばかりを狙うとか。前に寄っていただいた時はそんなお話でしたよね」
「そうなんです。その紅がですね、初めて女である紋に手を貸したんです。これはすごいことですよ。約五百年で初めての出来事ですからね」
「誠吉さん五百年分の話を集めたんか。そこまで行ったらよぉ、その鬼女の虜になっているのは誠吉さんとちゃうんかぇ」
紅の名前が出た途端に話し方が熱くなる誠吉を茶化しながら、ヒャヒャヒャッと笑う長介は湯のみの中の茶柱がいつも真ん中にいるようにチビチビと口をつけた。
「その血筋を狙うということを考えると、紋さんはそうだということになりますか」
「私もそうではないかと思っています。贔屓の呉服屋さんの奥さんに聞いたところ、紋さん、いえ浄円院様はちょうどあの梅のつぼみの真ん中のような色の着物を好み、蝶の模様をあしらうのが好きだとか」
誠吉は籠から分厚い帳面を取り出し、それを確認しながら言った。五百年分には及ばないだろうがその帳面には何やらたくさん書き連ねてあり、おそらく行く先々で語っているのだろう、表紙はボロボロになっていた。
「平家の赤ねぇ。なんやワシも確かに繋がるものがあると思えてきたわぁ。それで、その紅は紋に何したん」
「売れ残った柿を全部買い取って、さらにここに来て働くように言ったらしいのです。この茶店に来て亭主と話せば道が開けると」
「あはは、やっと私が出てきたんですね。ただ、紅さんと私は面識がないのにどうして紅さんは紋さんに私と話すことを勧めたんですかね。もしもですよ。私が長く生きているとしても、たくさんのお客様がおられるので紋さんと出逢っていてもわからないですよね。仮にそうだとして、そこで私は何と言ったのでしょう。ぜひ聞かせてくださいよ」
急に壱の口数が多くなり、一瞬目が泳いだのを誠吉は見逃さなかった。仮定の話を続けて引き出し、もしかしたら答えを合わせたいのではないかと思った。誠吉は茶をひとくち、ごくっと喉を鳴らしながら飲み、落ち着いた声でゆっくりと続けた。
「壱さんはなぜか、私が全国を回って三年ぶりに来た時でも同じ艶、いやそれより若く見える時もある。私の父が付けていた日記にも同じ壱という人が出てくるんです。昔、茶店の場所はここではなく虎伏山の対角側にあったようです。その時の壱さんの性格について父は『薬よりもめずらしい茶を欲しがり、産地にもこだわる』と書き残しておりました。今日こそ壱さんに尋ねたかったのです。壱さん、あなたは紅さんと同じ類のものではないですか」
「誠吉さん、それは恐ろしい。肉吸いだとしたら、ワ、ワシャどうしたら…って、それはいくらなんでも無いわぁ。いやぁ、ないない」
「いえ、この壱さんは少し違うのです。俗にいう『桂男』と呼ばれているものだと私は考えています」
「か、桂男て、さあよ那智のほうに出るっちゅう、月を見ると招かれて寿命が縮まってまうってやつかぇ」
壱は黙って俯き、火にかけている唐茶を小刻みに揺らし続けていた。熱を帯びた豆からは袋を開けた時よりも香ばしい魅惑の香りがする。それはもう茶店全体に広がっていた。
梅の木のあるほうの戸口から足元に生ぬるい風がふぅっと通った。誠吉は肌でそれを感じ、早口で話し出した。
「この日記によれば、父も、肉吸いの鬼女、紅さんに会っていたようです。私が見る限り、父の血も何度か吸われている。おそらく私も紅さんに会っています。だから分かるんです。あなた方は陰で人と人を繋げる役を担い、この世を創っていると言ってもいい」
「面白い話ですね。誠さんもその子孫とは……。まさか私が主人公になれるとは思いませんでした。誠さんがいつもお話になる紅さんとも共演させていただきましたしね。ありがたいお話です」
「ワ、ワシ、お母ちゃんに用事頼まれてたの忘れてたわぁ」
おもしろがって聞いていた長介も今まで聞いたことのない壱の低い声に何かを感じ、そそくさとお代を置いて帰って行った。
二、壱虎と紅龍の対峙
少しの無言が続き、どちらもが相手の出方を見ていた。壱は豆を火から外し、棚の上の妙なカタチをした白く丸い器を拭きだした。誠吉は先ほどの帳面をそっと籠に直し、茶を飲みながら、壱のその後姿をじっと見ていたが、やがて口を開いた。
「不思議な話を追い求めていたら、いつの間にか薬屋になっていました。父の跡を継ぐ気もなかったんです。同じ道を通るものかと反発していました。覚えていないのですが、その時に紅さんに会ったのでしょうね。何か変わりました。良くも悪くもです。こうして壱さんの茶を飲むためにここに寄るのも、妖怪の類の話を纏めるのも、もう私の使命だと思っていますよ」
「人には見えない何か。確かに、紅と私は同じ類のものです。これを言うのも後に誠さんがすっかり今のことを忘れてしまうと知っているからです。すみませんね。毎回」
「やっぱり……。そうだと思っていました。先ほどから声の調子が変わりましたからね。これでも薬屋、様子をうかがうのは得意です。さっきは生ぬるい風が足元をすり抜けました。紅さんが近くにおられますね。もっとも壱さんがそうやって紅さんを呼び出すとは私も…」
それまで器を磨き続けていた壱が顔をあげ、誠吉の瞳の奥を虎のように鋭く見つめた。誠吉は壱のその瞳の奥の一点に吸い込まれるようにすうっと眠りこけてしまった。今までに壱は何度この手を使っただろう。それでも誠吉は茶店に来る度、どんどん紅と壱に近づいた話を持って来ていた。
情熱というかその執念は親子二代に渡って帳面に記され、刻々と迫ってくる。この先、三代目ともそのずっと子孫とも巡り逢うのだろうか。
霧のような雲が茶店の周りに立ち込め、裏路地の梅の蕾が霞んでいく。鈴がひとつチリンと鳴ると、眠っている誠吉の傍に紅が現れた。
「今日のお茶は変わった香ばしい匂いがするのね」
「やあ、紋、いや、紅。唐茶というヤツさ。まだ広まっていない茶をこの男は持ってきてくれた。どうやら薬効があるみたいだ。先ほどからこの香りを嗅いでいるだけでも高揚感がある。この薬屋は研究熱心でね、丸薬に頼らずに健康を保つ品を見つけてくるのが得意なんだ。あっ。そうか紅は江戸でも誠吉に出逢っていたんだったね」
「そうね。どこに行っても出逢う不思議なお方」
「もう何回目だろうね。こうして眠らせるのも。来るたびに君に近づいているよ。噂話から糸を手繰り編むように組み合わせ、今回は俺のこともしっかりと話に来た。もしかしたらこの男の夢は、日記に完全な君を書き残すことかもしれない。次は俺の力でも眠らせることも難しいかもしれないよ」
眠っている誠吉を見ながら紅は口元だけ柔らかく微笑んでいだ。
「そうかもしれない。今日はもっと強く吸ってみるわ。あなたとの最後の夜みたいにね」
「紅、もうその話はしないでくれと言ったはずだ」
紅はそれが気に障ると知りながらも、呼び出される度に触れていた。
「そうだったわね。私が維盛さまをお慕いしていたように、あなたは上手く化けた『紋』に恋してた。有利な助言をして大奥へ行けるようにしてくれたのを覚えているわ。茶を飲みに来る人や藩邸にお茶を納めに行くついでに声をかけたりしてね。複数人に言葉を使い分けて道をつけてくれたように思うわ。気が付いてないだけかもしれないわよ」
「恋なんて人間の男女が堕ちる錯覚にすぎない。僕は君だけを特別にした覚えはないよ。君の瞳に光るものがあったのは確かだ。そこまで上り詰めたのは君の力だろうさ。たった五百年くらいで人間が『恋』と呼ぶそれを重ねて『愛』とやらを学んだつもりかもしれないけど、僕にはまったくその感覚がないんだ。自分の中にその定義すらない」
「そう、そういうことにしておくわ。あなたのその目は間違いないもの。彷徨って飛んでいるだけの私を救ってくれたのはあなただけだったから感謝してる」
「君はいつも僕に救われたと言ってくれるね。感謝か、そういうことにしておくよ」
「ありがとう。今日も呼んでくれて」
「じゃ、俺はむこうへ」
給仕口に戻る壱の背中を紅は微笑みながら見送り、眠ている誠吉の首筋に手を当て、脈を見た。どくっどくっと波打つ熱い血。幸せそうに眠るのその横顔は美しく確かに維盛を思わせる。首もとにそっと優しく唇を当てる。
五百年のその間に吸い方は苦しみを与えず自然にチクッと刺せるようになっていた。紅がそれを吸う間は人間の情報を見ることができる。そうして複雑に絡み合う記憶を選別し自分に関するものだけを抜き取っていた。
壱が言うように誠吉の志は『紅の話を書き残すこと』だった。それは父から継がれたもので、抜き取りようのない想い。また必ず誠吉に出逢ってしまう。それを覚悟をしながらも、紅は今回も記憶の一部しか抜き取らなかった。
〇 〇 〇 ● ● ●
四、八つ時の覚醒
「誠さん、誠さん。席をひとつ寄って、お嬢さんを座らせてあげてください」
いつもの八つ時に壱は誠吉を起こした。曇の隙間から細く零れ落ちるように光が差し、ちょうど裏の紅梅の蕾を照らしていた。その横では上品な花のように笑う女の子達が立っている。
「すみませんね。どうぞ隣へ。ここに来たらいつもくつろいで居眠りしてしまうみたいなんですよ。それで、私はどこまで話したんでしょうか」
「ほら、熊野の三体月の話ですよ。見れたんですか」
「えーっ。妖怪話ですか?私も聞きたいです。今日は満月だそうですね。お月様のお話、聞いて帰って私もおっかさんにしてあげたいです」
「月、つき……。何か話そうと思っていたような……」
「少しですが、どうぞ」
「おっ。さっそく唐茶ですね」
「みなさんも少しずつどうぞ。誠さんが運んできてくれた香ばしい珍しい茶です。まだ江戸にも出回っていない貴重なお茶ですよ。飲んだ後はとっても気分が良くなるんです」
「えーっ。いいんですか」
「今日来てよかったね」
女の子たちのおかげで誠吉の妖怪話にも花が咲きそうだ。酒も飲んでいないのに陽気な空間になった茶店はいつもの賑わいを取り戻した。
誠吉が持ってきた唐茶という飲み物は、後に珈琲と呼ばれ、大衆の飲み物となっている。とある文献によれば、その漢字は当初「玉」の字が当てられ、「珈」は花かんざしの玉、「琲」は玉を繋ぐ緒を意味しているとか。
壱が人間と関わる生業として茶店を選んだのも、女性に人気なのも、誠吉や唐茶との出逢いも、まるで輪と輪の縁が少しずつ重なり合うように繋がっている。
壱は窓の外の丸く膨らんだ紅梅の蕾に目をやり、磨いていた不思議な器を棚の上にそっと戻した。
今夜は満月。澄んだ寒空の下、優しい光は紅梅の蕾にも降り注ぐ。
次の朝にはきっと温かい陽を浴びてその花を咲かすことだろう。今も昔も変わらず凛とした香を纏いながら。
完(茶店〇弐壱四)
【あとがき】
ご好評いただいておりますオンライショップでの『BAR0214』は改訂第4版の編集待ちです。
江戸編も、わたくしのとって大切な章の一つです。
約7000字のこちらは、3年と3ヵ月の取材期間を経て、和歌山城から以南、和歌川付近を調査しながら、執筆いたしました。その想いというか、執念が通じてか、「コーヒー文化協会 設立25周年記念号(2018年・12月・日本コーヒー文化学会発行)」に掲載していただくことができました。
読者のみなさま、お力添えいただいた皆様に深く感謝いたします。
感謝の気持ちをこめて、期間限定で全文公開、2021年5月までは無料掲載とさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
2021.04.10 香月にいな
※表紙画像:2020.02.14上演『モカアンドハイド』脚本より一部抜粋
