人間はデジタルだから難しい
最近のエレベータの制御技術は格段に進化していて、インバータによるディジタル可変速ドライブが主流です。
●ディジタルとアナログ
大学で研究室の人と出かけた際、とあるビルの4解まで行くのに、階段で上がるかエレベータで上がるかという話になりました。私は、5階くらいまでだったら階段を使うのが普通だったので、その時も、私を含めて2、3人が階段で上りました。
すると、エレベータ派の人が、
「こんなディジタル制御の時代に、階段で行くなんてアナログだなぁ。」
と言ったんです。その時、一緒に階段で上った人がすかさず返した一言。
「階段こそディジタルなんだよ!」
理系ならではの会話ですね。
●シャノンのサンプリング定理の示唆する事
我々が生きている実世界も「アナログ」と言われますが、本当にそうでしょうか。
「実際」の事を物理学的に言うと、エネルギ自体が、
「プランク定数 "h"」と「ド・ブロイ波の振動数 "ν"」の積
ε = hν
で定義される「エネルギ量子 "ε"」の整数倍
なので、実は「離散的」であり、
実世界は「デジタル」
なのです。しかし、人間のスケールではその量子の「粗さ」を感じる事は無いので、連続的なものとしてとらえているだけの話です。
そうでなくても人間は、一つの物事について、連続的にずっと観察する事は困難です。言い換えると、ある事象に対する人間の把握は、
時間的にとびとび
であることが普通です。すると、以下の図のような事になります。
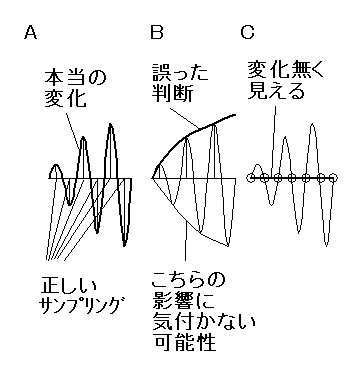
例えば上の図のように、
正弦波の振幅がだんだん増してくる変化
を考えてみます。
図 A のように観測していれば、変化の様子がすぐにわかります。しかし、図 B のような間隔で観測していると、
単なる単調増加の現象
にしか見えません。
さらに、図 C のような観測では,、
全く現象が見て取れない
事になります。
信号処理の世界ではこれを「エイリアシング」と言って、エイリアシングを避けるために、
変動周期の2倍以上の頻度でサンプリングを行う
という「シャノンの標本化定理」に従う事になっています。
こういう事ってよくありませんか?
例えば、
上り調子だと思っていたのに、注目するとやたら成果にバラツキがあった
とか、
全然問題が起きていないように見えたが、ある時突然、複数の問題が顕在化した
とか。これってまさに、
観察頻度が少なすぎることによる「エイリアシング」
が起きていると思うんです。
その意味で、人間の感覚は本来連続したアナログではなく、
デジタル的な感覚を持っている事を自覚する必要がある
のです。
これを、「アナログである」と信じ込んでしまうと、見るタイミングが悪ければ、誤った判断を招く事になるわけです。
この「シャノンのサンプリング定理」は、「物事を良く見なさい」ということを教えてくれているんだと思います。「物事を多面的に見る」というのも大事ですが、
同じ物事を、いろいろタイミングを変えて見てみる
と、思わぬ変化の仕方をしていることもあるのです。
