
10月1日より管理栄養士が必要?
食事加算に追加された要件
就労継続支援B型事業を運営している中で食事加算をとっている事業所さんは多いのではないでしょうか?
今年の2月6日に出た法改正の案を見て
「うわ、めんどくさ」と思いましたw
https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf
※食事加算の要件はP19に記載されています。


加算というのはそもそも支援の対価です。
食事の提供が十分な支援じゃないのかとお思いの方もおられるでしょうが、
支援の先にどうなるのか?
というところを重要と考えなければいけません。
今の食事加算の要件は明確にこれだ!というものはなく
個別支援計画に記載しなければいけない、なんてこともありません。
だけど、食事の提供を行うことで
『その利用者さんが自分らしい人生を送ることができるのか』
が大切なんです。
障害福祉サービスの根っこの部分を意識しながら支援していれば
要件うんぬんを厚生労働省は今回言ってこなかったと思います。
食事提供した。日誌につけている。献立を管理している。
で、どうなったの?
という結果の記録がなく、
『食事加算は利用者集めのためのツールになっているのではないか?』
と厚生労働省は思ったんでしょうね。
令和6年で終わるはずが。。。
しかも、令和6年度で食事加算は終わる予定だったのが令和9年度まで引き伸ばす経過措置になったそうです。
僕はてっきり令和5年度で終了すると思ってましたし、食事加算がまだ続くのが少し面倒くさいなと思いました。
『終了したら30単位減るじゃないか』と読者に怒られるかも知れませんが、僕が言いたいのは
『食事加算の30単位を基本報酬に組み込んでほしい』
というものです。
例えば6:1の10,000円以下の20人以下の場合、590単位です。
それに食事加算の30単位を加えた620単位にしてほしいというものです。
そうなれば、いちいち面倒くさい要件やらなんやと考えず、運営者のスタイルで食事支援ができるのになと思いました。
決まってしまったことは仕方ありませんので、どのような要件ができたか紹介いたします。
令和6年度の法改正に伴い、食事加算の取得3つ要件が増えました。
この3つはいずれか、ではなく「いずれも」満たさないといけませんので気をつけてください。

では3つの要件をお話しします。

1つ目の要件は献立の確認
2月6に発表された要件案では1つ目の要件は、
『管理栄養士もしくは栄養士による献立の確認』です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001297224.pdf
※P140に記載されています。

管理栄養士は献立を毎月確認するとは記載されていませんので、『毎月月初めに管理栄養士もしくは栄養士が確認するのかな』と思いきや、3月29日に出た留意事項通知では、まさかの1年に1回以上とまた曖昧な要件に変更されていました。
どういうこと?とまた頭を悩ませることになりました。
しかも、令和6年4月1日から適用ではなく令和6年9月30日まで経過措置。。。。どないやねんw
とにかくこのブログを書いている今日は10月になりましたので管理栄養士もしくは栄養士が献立の確認が必要になります。
僕の事業所では毎月管理栄養士に翌月分の献立を確認してもらっています。
管理栄養士との業務委託契約書なども弁護士先生に作成してもらいました。
管理栄養士による献立の確認費用には出費がかさみます(涙)

そもそも管理栄養士と栄養士の違いってなんだ?
管理栄養士は病気を患っている方や高齢で食事がとりづらくなっている方、健康な方一人ひとりに合わせて専門的な知識と技術を持って栄養指導や栄養管理を行います。
栄養士は、主に健康な方を対象にして栄養指導や給食の管理を行います。
管理栄養士・栄養士は、医療施設、老人福祉施設、介護保険施設、児童福祉施設、小・中学校、行政機関、企業、管理栄養士・栄養士養成施設、試験研究機関等で働いています。
令和6年度から!というぐらいですから、令和6年4月1日からの要件として開始するはずでした。
しかし何故か10月1日から開始と変更の通知が、、、笑
得意の後出しジャンケンですw
ちなみに弊社、管理栄養士がいます。もし管理栄養士が居ない事業所さんはぜひ相談ください。お役に立てるかも知れません。
2つ目は食事の摂取量の記録
食事の量の記録方法は2月6日の時点で明文化されておらず「どうやって記録するんだろな」と心配していましたが、
「完食」や「全体の1/2」、「全体の◯割」で良いそうです。
完全否定するつもりはありませんが、摂取量を記録することを意味あるものにするには事業所が摂取量を記録した先にどういった到達目標があるのかを意識しないとただの無意味な記録になるような気がします。
https://www.mhlw.go.jp/content/001297224.pdf
※P141に記載されています。
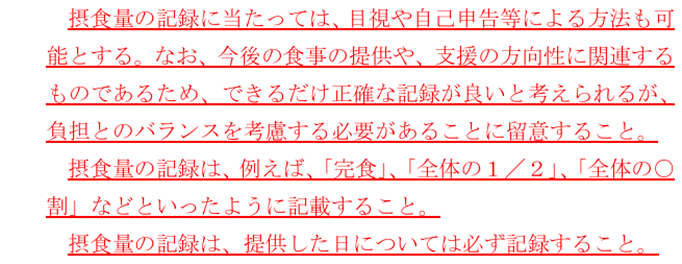

3つ目はBMIもしくは体重の計測
この要件は体重管理を行うことで利用者さんの肥満もそうですが健康管理をしっかり見ましょうということです。
『医療と福祉の連携は重要になってきますよ!』というメッセージでもあるのかなと思いました。
『概ね6ヶ月に1回計測』ということですので前回の計測から6ヶ月も経過した後ともなると恐いのが「忘れてしまう」ことが一番気をつけなければいけません。
かといって毎月計測するのも大変だし、女性からしたらとてもデリケートなところでもあります。男性もそうですが。
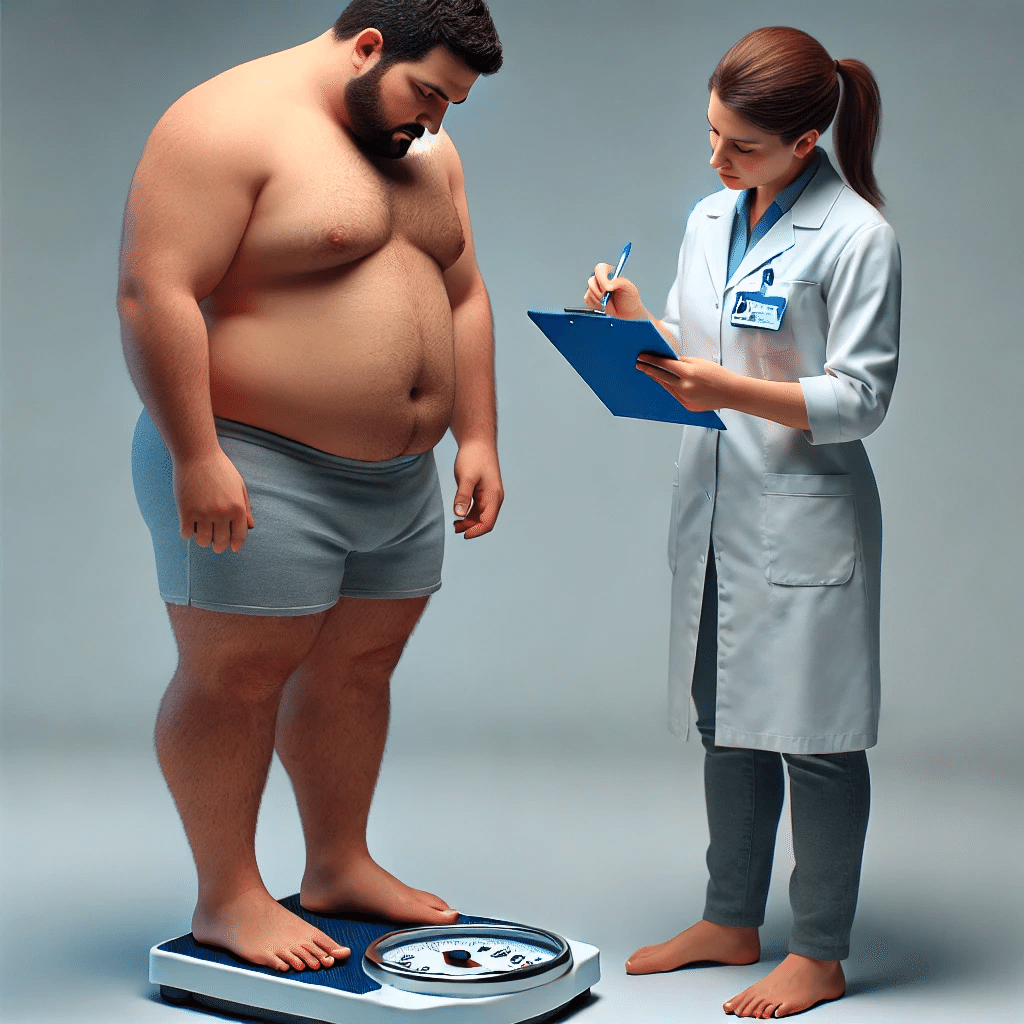
さて、計測を忘れないためのコツを考えました。
それは『個別支援計画の作成の都度、モニタリングやアセスメント時に体重を計測する』と決めておくこと。
そうすれば6ヶ月を超えることはありません。良いアイディアだと思いませんか?

https://www.mhlw.go.jp/content/001297224.pdf
※P141に記載されています。
BMIの計算方法↓
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/bmi_check.html
さて令和6年10月になりました!
6ヶ月が経とうとしています。
2回目のBMIもしくは体重測定が始まります!
管理栄養士もしくは栄養士の献立確認。
未だ見つかっていない方はぜひご連絡ください。
お役に立てるかもしれません。

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。
