
July Tech Festa 2020に、参加しました。
お疲れさまです。inoです。
7/25(土)に、July Tech Festa 2020に途中参戦させて頂きました。
今回も、記憶と備忘の意味も込めて、拝聴させて頂いた内容を
執筆させて頂きます。宜しくお願い致します。
概要
connpassから抜粋。
>今年は、「Extend Your Engineering Life!」のテーマに沿って、自分のエン>ジニアリング・ライフを共有して、みんなのエンジニアリング・ライフを>拡張していきませんか?
>ITに関わる全ての人の知的好奇心を満たすお祭りを作りたい。 その思いか>らJuly Tech Festaは生まれました。
>興味のある技術に触れ、普段会えない人の話を聞き、 参加したエンジニア>がスキルやキャリアについて考えるきっかけになれば。
>そんな場を作ろうと今年も July Tech Festa 2020 を開催します。
A5 緊急事態宣言中に大手SIer インフラエンジニア向けに実施したピープルマネジメント 倉持さん
● ピープルマネージメントとは
従業員一人ひとりに向き合い、ICTエンジニアの知識・技術向上を支援し
個人の成長を図り、パフォーマンスを最大化する
→エンジニア組織環境や文化形成を促し、企業の更なる成長、価値や成果の向上を目指す。
● 活動の動機
・古いやり方を続ける?
・仕組みや制度が形骸化してないか?
・キャリアプランを描けているか?
・チームでのコミュニケーションが足りているか?
・期待した/する人物像は?その育成効果は?
⇨みんな、楽しく働こうよ!
●1on1 とは
上司→部下に的確に助言・奉仕し
部下に自律的な行動を促すことを目的とした、対話の時間。
→アンケートを実施した結果、上司も部下も同じようなことを
課題視している
●マネージャ側への勉強会
目的の共有、自己理解、部下と向き合う「姿勢」
スキル・メソッドetc…
ー気づいたら座学になってしまった。
本当はロールプレイングがしたかった。
● 振り返りをZoomで実施してみた。
・コミュニケーションする目的では問題なし
※仕草(うなずき、リアクションなど)は大げさにする必要はあるが。
・スケジューリングはとても容易
・する側、される側どちらもカメラもマイクもon
・業務に関する相談はコンパクト
● オンボーディング
「新しく参加した従業員が、速やかに活躍できるようにするための仕組み」
・企業風土や業務を理解し、自分らしく過ごすための支援
・従業員のモチベーション&エンゲージメント向上
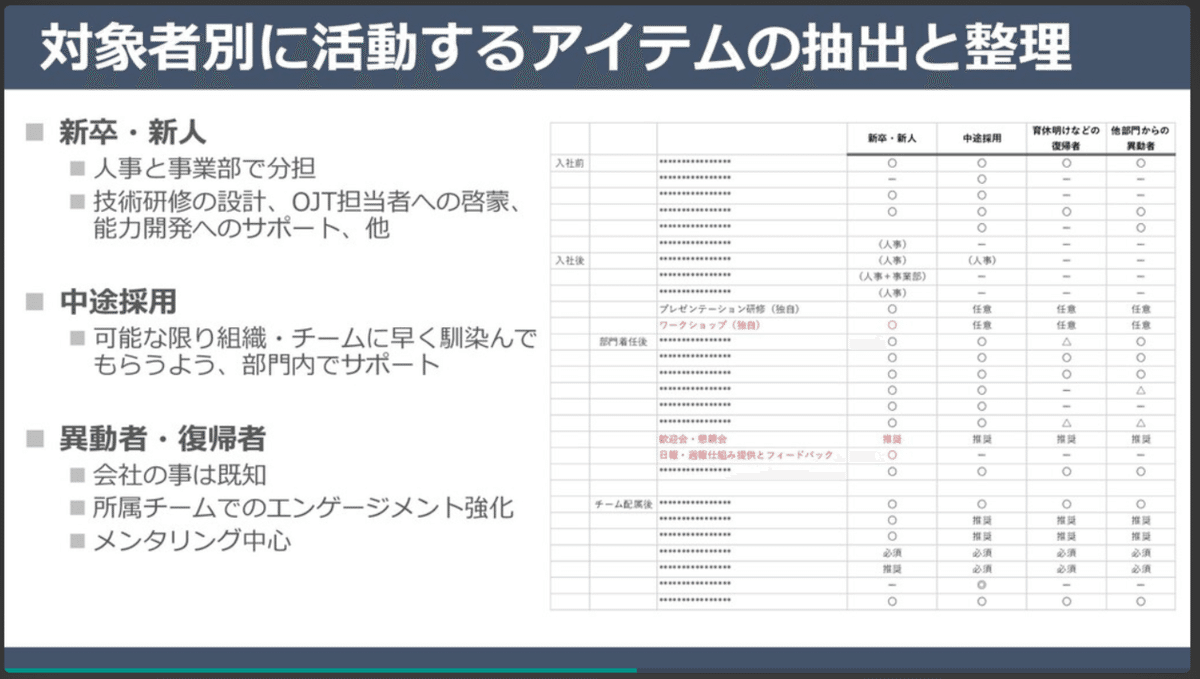
対象者別に、作り込まれています…凄い。
●ワークショップ
・在宅が続く新人/新卒に実施
・自己と他者の相互理解
・若手以上に対しての新人理解

9割以上が有意義だったと回答。
この時の、レポートがこちらにありました。
ツイートして下さった方々に感謝です。⇩
https://note.com/tklab/n/n269af1b16516
● 日報の仕組みのアップデート
新卒・新人への日報作成、それに対するフォローアップ
ー課題
・上司/先輩が見ていない。見てもリアクションやコメントをしていない
⇨日報をYWT から Fun, Done, Learn へ変更。
フォーマットに「もやもやしたこと」を追加
タイトルも、その日印象に残った事柄を記載してもらうよう工夫
● 今後やりたいこと
・キャリアコンサルティング(個人的にだが
・新卒1年目の最後にある、成果発表のお手伝い
・テックリードと働き方の可視化
・Human Resource Business Partner
日報のフォーマットを変えた話は、当初の「楽しく業務しよう!」の方針とも合致してますし、新人たちに業務の楽しさを感じられ、それに反応も貰えるなんて素敵だなー、と感じました。
僕の業務でも是非参考にさせて頂きます。
E6 ネットワークへのCI的アプローチ 田中さん
継続的インテグレーションをネットワークにあてはめようとした話。
資料はこちら⇩
https://www.slideshare.net/susumu0108/ci-237234894
● ファイアウォールを運用していて辛かったこと
・仕事が釣り合ってない
※実行者1人に対し依頼者10人…
ー起こったこと
・承認フローを迂回した闇作業によって、起こる通信断
・要件漏れによる再作業 etc.
ー発生した損失
→数百~数千万
● 何がいけなかったのか、振り返る。
・脳内試験、目grep…
・人員に対しての作業量が多い
・承認フローが機能してない(結果、信用できない etc.
⇨リソース(人員)には限界がある
⇨人が最も不正確 →自動化でカバーする!
● 何をCIするか
ACL(アクセスリスト)にフォーカスした、AnsibleのPlaybookをCIする
・何をもって検証するか?→手段は様々
ーpyATS・・機器の状態確認
ーbatfish・・コンフィグ解析して独自ロジックで
意図した通信が通るか判定する
(脳内テストの自動化のイメージ)
ー実パケットを流す
設定自動化はAnsibleで
teratermマクロだと、ちょっとめんどくさい
コード管理、CIはgitlabで
● どんな価値を提供するのか?
・人力(不正確)→自動(正確)
・精神的負荷ダウン(離職リスク低下)
→雇用、手続きなどで ん~数百万の費用効果 etc.
● まとめ
・自動化は社会(個人、社員、会社)に価値を提供する
・ネットワークのCIは価値提供のアプローチとして、十分に可能性あり
ー良い自動化ライフを!
人が不正確・・あるある過ぎて共感しかないです。
自動化の流れは、導入の話に持っていきたい時に
参考にさせて頂きます。
どういう切り口で話しを持っていくかな‥
C6 続・人生100年時代の学び方 吉岡さん
資料はこちら⇩
https://www.slideshare.net/hyoshiok/100-237232610
● パラダイムシフト
・起こっていることを知らない
・起こっていることに気が付かない
・起こった後はアタリマエになる
● 脳には可塑性がある
※可塑性って?
⇨元はお菓子用語で、自由自在に形を変えられること、だそうです。
・年齢を言い訳にしない
歳だから覚えられない、できないは言い訳
・わからないことをわからないと言う。わかろうとしないことが問題
・できないことを認識して、できるようになる訓練をする
逆上がりや自転車みたいに、何回も何回もやる事でできるようになる
いくつになっても脳はバージョンアップできる
・何も考えてないと脳は劣化する
● パラダイムシフトの時代
・古いパラダイム
ー定年退職、年功序列、能力には限界がある
・新しいパラダイム
ー定年退職は引退ではない(生涯現役)
ー新しいことに挑戦するためには、年収を下げることを躊躇しない
ー能力には限界がない
・制度/仕組みはパラダイムシフトに追従できない
→自分で考えて動く
● 酒を辞めたら人生変わった
・二日酔いにならなくなった
・本を読む時間が増えた
・本を読んだら人生変わった
● 2度めの大学生になって思ったこと
・大学は何度進学しても良い
・4年で卒業しなくても良い
・入学したことの高揚感
● まとめ
・いくつかのパラダイムシフトの時代があった。
コロナはパラダイムシフトだ。
・脳には可塑性がある。いつでも、何歳になってもバージョンアップできる
自分をバージョンアップしてみよう。
ついでに社会もバージョンアップしてほしいなぁ‥
アラフォーに差し掛かってきてるので、記憶に関して悩んでいた所でした。
登壇を拝聴して、勇気づけられました!ありがとうございます!!
年齢を言い訳にしないで、やりたいことには色々試行錯誤、足掻いてみる。
改めて認識させられました。素晴らしい、素敵な内容でした。
感想
・初めてJuly Tech Festaに参加させて頂きました。
今回拝聴させて頂いた内容はどれも良かったのですが
特に吉岡さんの内容は年齢を理由にするな、頑張れと
何だか励まされているような気分でした。
次は来年かな?是非とも参加させて頂きます!
以上です。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
