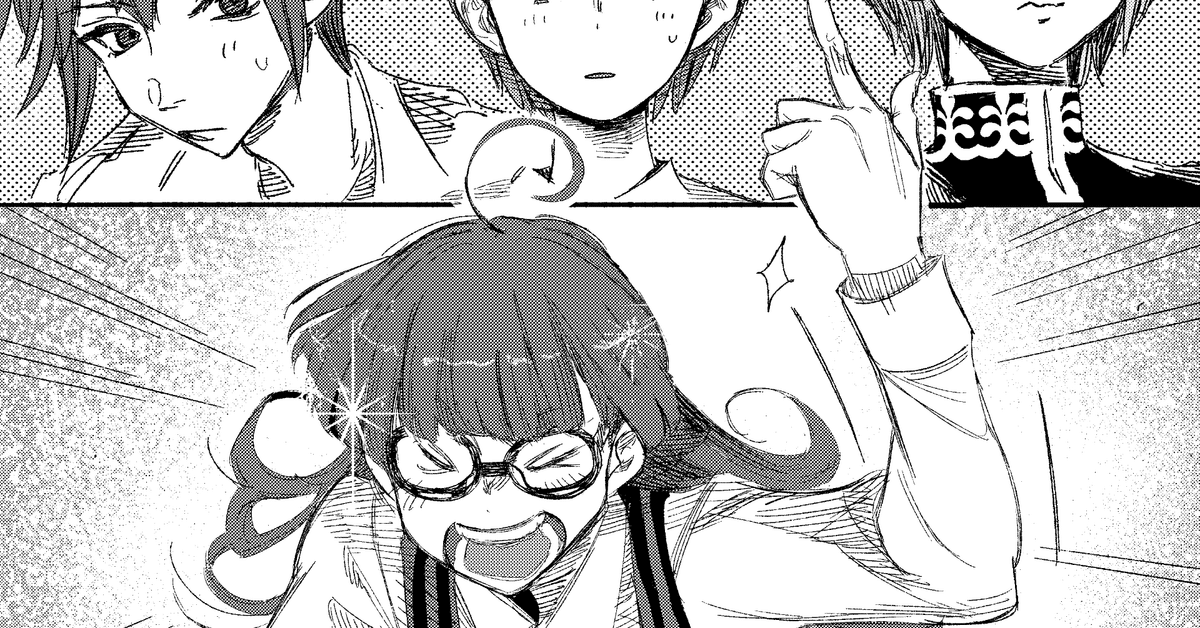
十和田シン ジャックジャンヌ1周年記念小説【ハッピー・アニバーサリー 前編】
ジャックジャンヌ発売から1周年!! 十和田シンさんがアニバーサリー記念小説を書いてくださいました!! 玉阪市の記念式典で行われるユニヴェールの歌劇。普段はしのぎをけずるライバル、オニキス、ロードナイト、クォーツの3クラスが、力を合わせてともに公演の幕を開ける!! 大ボリュームの前後編です。
十和田シン
ノベライズ作家、シナリオライター。別名義である十和田眞の名前で『恋愛台風』を執筆、小説デビュー。『NARUTO』『東京喰種』シリーズの小説を担当、ADV『ジャックジャンヌ』シナリオを石田スイ氏と執筆。また、奥十の名前で漫画家として活動する。コミックス『マツ係長は女オタ』発売中。
ハッピー・アニバーサリー
【1】
「立花くん! 立花くぅん! 聞いて聞いて! アタシ勝った、勝ったのよぉッ!」
玉阪市、玉阪座駅のほど近く。男子のみで歌劇の舞台を作るユニヴェール歌劇学校の生徒、立花希佐は、同校を対象にした歌劇のワークショップ「モナ・スタースクール」に足を踏み入れるなり、祝砲のように轟き響いた、塾長、茂成秀吾――愛称「モナ」の叫びに目を丸くした。モナは過去、ユニヴェール歌劇学校のジャンヌ生だった熱血塾長だ。
夏休みも残りわずか、モナから集中的にレッスンを受けようと思っていたのだが、それどころではないらしい。
「アタシもう、今年の運、全部使い切っちゃったかもしれないわ! ……ううん、ダメ! アタシには可愛い生徒たちが舞台で羽ばたく姿を見届ける使命があるんだから、明日から、ううん、今日から、今この瞬間から功徳を積んで運貯金しないとっ!!」
モナは盆を過ぎても夏の勢いをそのままに坂を駆け上っていく今日の風よりも熱い。
(モナさん、なにか良いことがあったのかな?)
理由はわからないが、まずは良かったと微笑む。ただ、理由がわからないので、なにがあったんだろうと首をかしげる。
「塾長。それじゃあわかりませんよ」
助け舟が現れた。モナの助手でいつも冷静沈着な安西アキカだ。
「あら、ごめんなさい! そうよね、ちゃんと説明してこの喜びを分かち合わないと! ちょっと待って、えっと……ほら、これ!」
モナが一枚のはがきを取りだす。
「『玉阪の日記念式典ご招待券』……?」
日程は約二週間後、八月終盤。
「立花くん、『玉阪の日』のこと、もう聞いたっ?」
「え、『玉阪の日』……ですか?」
パッと連想したのは、ユニヴェール歌劇学校の母体である男性歌劇の最高峰、玉阪座のこと。
「ほら、『玉阪町』の誕生日のことよ!」
だが、どうやら違うらしい。
――玉阪町? 誕生日?
「だから。説明になってませんって、塾長」
置いてけぼり状態の希佐を見て、アキカがモナを再び止める。
「だって、毎年毎年応募し続けて、ようやく今年、初めて当たったのよ!? アキカだってすごいですねって言ってたじゃない!」
「それはそうですけど……今はそれより」
早口でまくし立てるモナを諫めて、アキカが希佐を見る。
「立花くん、『玉阪の日』っていうのはね、玉阪市の前身……玉阪町が生まれた日のことを言うのよ」
玉阪町。
アキカが言うには、明治時代、全国各地で行われた市町村合併――いわゆる明治の大合併により、大伊達山のふもとから海に近い港町まで、広く点在していた町村が合併して「玉阪町」になったらしい。
「その後、人口が増えて『玉阪市』になったけど、玉阪って街の形自体は『玉阪町』のころからあまり変わってないんだ」
希佐は、
「それで玉阪町が誕生したその日を『玉阪の日』と呼んで祝っているんですね」
なるほどと改めてモナの手にある当選ハガキを見る。
「そうなのぉ~! 玉阪市役所を中心に色んなイベントが開催されるのよ~! もちろん、目玉は記念式典だけど!」
「へぇ~。……」
(そういえば、玉阪市の市役所ってどこにあるんだろう?)
こういうのは駅の近くにあるイメージだが、玉阪座駅の周りは百貨店やショッピングモールといった商業施設ばかりだ。
そんな希佐の心情を察したのか、アキカが「川を越えた向こうにあるのよ」と教えてくれる。
「玉阪市の政治機能は全部『開(ひらき)』に集まってるから」
希佐はきょとんとしてしまった。
(開……?)
聞いたことがない名前だ。
「えっとね、『玉阪市駅』の方なんだけど……」
玉阪市駅。
希佐が知っているのはこの塾のすぐ側にある、玉阪座駅。
「そこも元々は『玉阪町駅』で……」
アキカはかみ砕いて説明してくれているのだろうが、聞けば聞くほど希佐の頭は混乱していく。
(これ、私に土地勘がないせいだ)
ユニヴェールの舞台に立つと心に決め、遠方から一人、玉阪市にやってきた。稽古は当然忙しく、外に出る機会も少ない。
そんな中、学校と玉阪座駅を繋ぐ数本の坂を通れば、必要なものは全て手に入っていた。狭い範囲で生活が成り立っていた。自分の目に映るものがこの街の全てだと思えるほどに。
(私が知っている玉阪市って、ほんの一部なのかもしれない……)
急に、頭の中で地図が広がる。なにも描かれていない、真っ白な地図。そこには一体なにがあるのだろう。
「とにかく!」
モナの声に、地図が吹っ飛んだ。
「玉阪の日記念式典はとっても人気が高いから抽選になっているの! 市は公表してないけど、倍率は数十とも数百とも言われているわっ!」
「え、そんなに!? じゃあ……」
「その高い倍率をくぐり抜け、見事当選した強運の証なのよぉっ!」
モナが当選ハガキを天に掲げ、歓喜の高速スピンを披露する。
何年も何年も応募し、落選し、肩を落として、それでもめげずにチャレンジし続けた結果。なんだかこちらまで嬉しくなってくる。
「良かったですね、モナさん」
ようやく全てを理解した希佐からの祝福に、モナは「ありがとう~!」と破顔した。
「式典で立花くんたちの姿を見るの、楽しみにしてるわ!」
――ん?
今日一わからないことがきた。
「立花くん、たち……?」
希佐の疑問に、モナとアキカが「えっ」と声を上げる。
沈黙が数秒。
「……やだぁ、立花くん、まだ聞いてなかったのね、知らなかったのねっ! アタシったらごめんなさい!」
「え、でも塾長、まだ聞いてないって、大丈夫なんですか?」
「ハッ! それもそうよ、なにかトラブルかしら……。あのね、立花くん」
モナは自分を落ち着かせるように胸に手を置き、深呼吸してから言う。
「『玉阪の日記念式典』は、ユニヴェールの生徒たちが歌劇を披露するのよ」
記念式典は約二週間後。
残りわずかな夏休み、全て消えるかもしれない。
【2】
「諸君! 『玉阪の日』が近づいてきましたよぉ!」
モナのワークショップから帰寮したあと、ちょうど居合わせた同期たちと夕飯のテーブルを囲んで、今日聞いたまだ知らぬ予定について彼らに話そうとした、そのときだった。
クォーツの組長、根地黒門が突如現れ、高らかに叫んだのは。
才人であり、奇人でもある彼の喜々とした表情は、同じ席に着いていた同期たちを警戒させるのに充分だった。
「なんだぁ、一体。『玉阪の日』?」
いつも真っ先に疑問を口にするのはクォーツ一年、ジャックのホープである織巻寿々だ。
「知ってっか、立花、世長?」
スズの問いに、同じテーブルを囲んでいた希佐の幼なじみでジャンヌ生、世長創司郎が首を横に振る。
「初めて聞いたよ。希佐ちゃんはなにか知ってる?」
スズと世長の視線が希佐に向く。希佐はモナから聞いた話をそのまま彼らに伝えようとした。
「ッハー! だからお前たちは三馬鹿なんだ!」
ところが希佐たちの背後から、鳳京士が割り込んでくる。
彼も希佐の同期で、ジャック生。ただ、希佐たちとはどんなときも相容れない、独立した存在だ。
「おい! オレと世長はともかく、立花は知ってそうな感じだったぞ! なぁ、立花!」
スズに聞かれて、「実は今日聞いた話なんだけど……」と切り出す。
「浅いっ!」
それだけで鳳が一刀両断してきた。
「昨日今日で手に入れた情報なんて付け焼き刃! 『知ってる』の内に入らんな!」
鳳が勝ち誇った表情でふんぞり返る。スズが再び「おい」と制しようとしたところで、希佐は真っ直ぐ鳳を見た。
「ワークショップのモナさんとアキカさんに教えてもらったことだから、付け焼き刃ではないよ」
事実を冷静に、ありのままに。
普段、柔和に笑っているぶん、希佐の真顔には表現し難いすごみがある。
ふんぞり返っていた鳳が「ひぇっ」と一歩後退し、隣に座っていたスズと世長でさえ、ガタッと身を引いた。
「鳳! モナさんとアキカさんに謝れ!」
スズの注意はある意味鳳への救済措置。
固まっていた鳳が「それに関しては訂正し、モナさんとアキカさんにお詫び申し上げる!」と素直に認める。
希佐に対する謝罪はないが、それは希佐本人にとってそれはどうでも良いことだ。
希佐の表情がやわらいだのを見て、世長がホッと胸をなで下ろす。
「はい、そこの一年生っ子! 落ち着いたかね!」
場面転換を指示するように根地がパンパンッと手を叩いた。希佐たちは揃って「すみません!」とそちらを向く。
「一年生は『玉阪の日』に明るくなくても仕方ない! ユニヴェール生は玉阪市外から入学する子も多いからね。てなわけで! 『玉阪の日』について説明しよう! 鳳先生が!」
「えっ!」
「鳳くんは玉阪市出身だもんね! てなわけで先生! 深い情報よろしくお願いします!」
根地の無茶ぶりに鳳は狼狽える。
「おい」
だが、そこで凍てつく声が食堂内に響いた。
「早いところ説明しろ」
クォーツ二年の白田美ツ騎だ。クォーツのトレゾールとして美しく歌う彼の唇が、今は不機嫌を奏でている。なにせ彼は無駄と面倒を好まない。食事を邪魔され、話は進まず、その上、これから億劫なことが待っているのだろうという予感が彼を苛立たせるのだろう。
鳳は即座に「承知しました、白田先輩!」と返した。スズが「大変だなぁ鳳も」と同情した。
鳳の説明は極めて簡潔にまとめられており、今日、モナたちから聞いた話があっというまにクォーツ一年の共通認識となる。
「へ~、それで『玉阪の日』かぁ。なんかいいッスね、町の誕生祝い!」
「その記念式典で私たちは、なにをしたら良いんでしょうか」
希佐の質問を受けて、静かに様子を見守っていたクォーツのジャックエース、睦実介が「例年だと……」と過去を振り返る。
「クォーツ、オニキス、ロードナイト、アンバーの四クラスが、それぞれ五分、舞台に立つ。オニキスがダンス、ロードナイトが歌なのは毎年恒例で、クォーツとアンバーはその年々で変わるな」
世長が「五分……かなり短いんですね」と驚く。
「ああ。記念式典の舞台に立つのはユニヴェールだけじゃない。俺たちのあとには、本陣、玉阪座の舞台も控えている」
「ま、前座みたいなもんだな、俺たちは」
カイの説明に補足したのは、椅子にただ座る姿さえも美しいクォーツのアルジャンヌ、高科更文。
「各クラス五分、計二十分、会場をしっかり温めるのが俺たちのお役目サ。……もちろん、俺ら目当ての人たちもいるけどな」
フミは不敵に笑う。フミを見るために会場に来る人も多いだろう。
「そのとーり! やるからには我こそが主役ですよぉ! ユニヴェールファイトッ!」
根地が拳を天に突き上げる。ただそこで、世長が「あれ、じゃあ……」と、とあることに気づいた。
「今回はアンバーも記念式典に参加するんですか?」
先月、激闘を繰り広げた夏公演。その舞台にアンバーは立っていなかった。理由は明らかにされていない。
――クォーツの一年生たちには。
根地が「そりゃないね」とカラカラ笑う。
「そもそも去年の時点で記念式典に『かろうじて参加』だったアンバーが、今年参加するはずないっ!」
フミが「だなぁ」と頷く。
「なにせ去年の記念公演、アンバーのジャックエースとアルジャンヌは不参加だったし」
「あら、そうなの! 協調性のないヤツらねぇ、遺憾ですわ! 聞くところによると、去年はクォーツも散々だったらしいわよ! 出れば良いってもんでもないですよねぇ」
「クーロ?」
「あらなにかしらおフミさん。あなたのお目々、とっても怖い。まさか僕を食べちゃうつもり……!? いやっ助けて」
「コクト、フミ」
一年にとってはよくわからない話で盛り上がる二人をカイが制する。根地が「おっとすまない、ムッツーミ!」と無駄にポーズを決めて謝罪した。
「とにかく、とにかくですよ! そういう経緯もありますもんで、今年はガツンと決めちゃいたいのよね! やるからには全力で! ですよですです、ですよねぇ!」
やるからには全力で、という言葉は希佐たちにもすんなり入ってきた。
「じゃあ、その五分を全力で演じきったら良いんですね」
希佐の言葉に、世長もスズもうんうん、と頷く。
「確かにそうだが同時に違う!」
「えっ」
「だって五分て短いじゃなーい!」
根地が奇妙なことを言い出した。疑問は希佐たち一年にとどまらず、二年、三年にも波及する。白田が露骨に眉をひそめ、フミとカイは顔を見合わせた。
世長が「あの……」と怖々手を挙げる。
「今回はクォーツ、オニキス、ロードナイトの三クラスがそれぞれ五分の舞台を披露する……んですよね?」
全員が揺らぐことのない大前提だと思っている箇所を確認すると、根地が「そこ、そこなんですよ!」と叫んだ。
「今回、なにかと話題問題のアンバーさんが不参加なのよ! このままじゃ、ユニヴェールの舞台良かったねーと同じくらい、アンバー不参加だったねーが語られちゃわない? むしろそっちの方が語られちゃわないっ?」
正直、希佐たち一年は、根地の言っていることがいまいちよくわからなかった。
しかし、曇る二年と三年の表情が、根地の言葉を肯定している。そこには、拭い去れない悲壮感もあった。
(アンバー……)
複雑な響き。
同じユニヴェール生でありながら、希佐が手に入れられるアンバーの情報は極めて少ない。まるで誰かの手によって、目を、耳を塞がれているようだ。
その意図的に作られた空白が、より一層アンバーという存在を大きくしている。
「……まぁ、アンバー云々抜きにしても、いつもなら全クラス見られんのに一クラス欠けるってのは、残念がられるわな」
フミの言葉に、みんな顔を上げた。もっともな言葉であると同時に、気づけば俯いていたことが怖かった。
「それってどうにかできないんスか? せっかくやるんだから、オレたちも、見てくれる人も、全員『良かったー!!』一色にしたいッス!」
スズが声を上げる。みんな気持ちは同じだ。
根地が待ってましたとばかりに、にんまりと笑った。
「どうにかなる!」
根地が声を張り上げる。
「例年ならば揃っているはずの四クラス! 今年は一つ欠けた三クラス! その一つが目立つなら……」
眼鏡の奥、根地の目がキラリと光った。
「残った三クラス全員で、一つの舞台を作ってしまえばいいじゃないかぁ!!」
希佐たちは固まる。それぞれ顔を見合わせ、言葉をかみ砕き、飲み込んで。
「えええええええええええ~!?」
クォーツ寮に生徒たちの声がこだました。
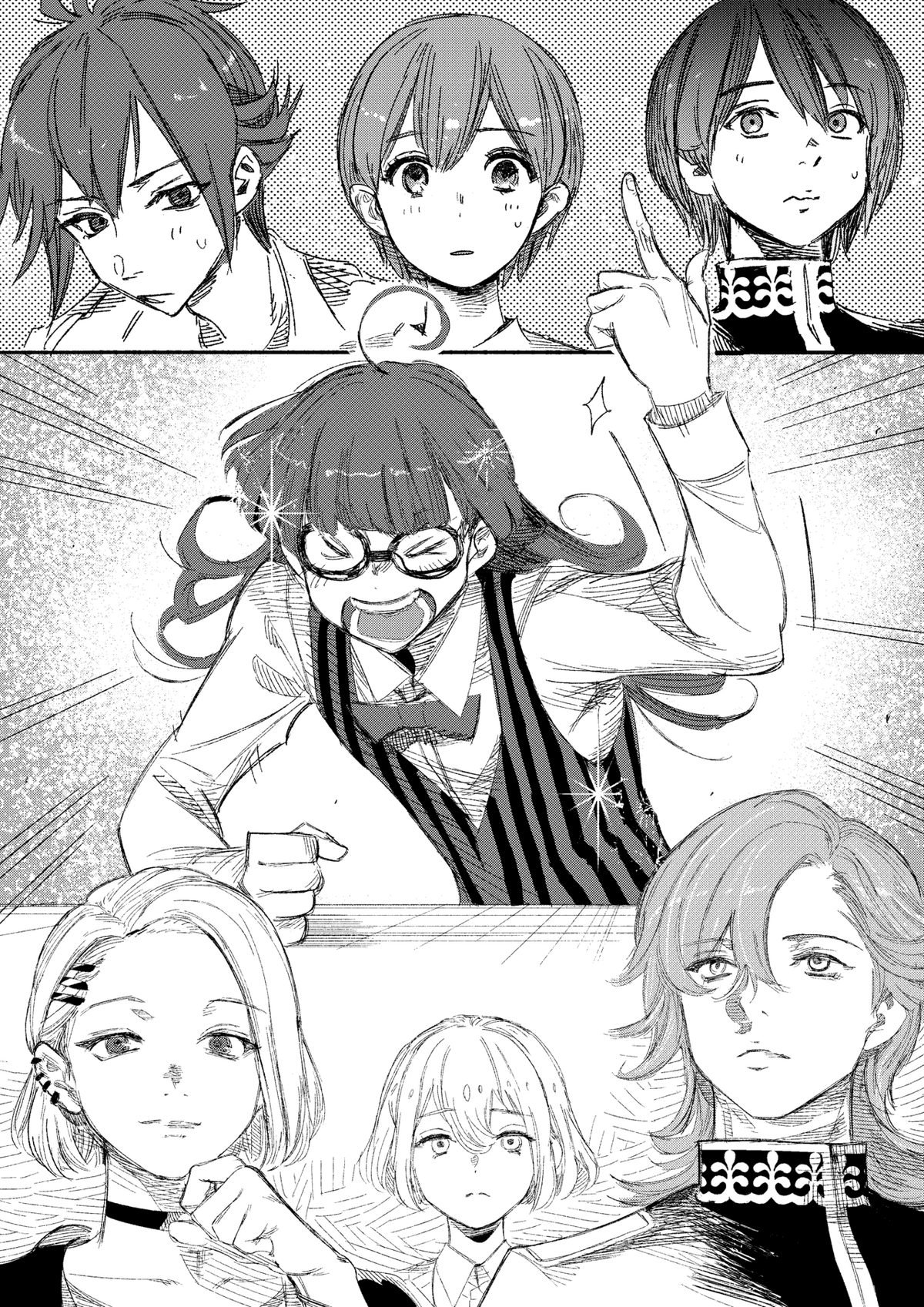
【3】
「……要するに、オニキス、ロードナイト、クォーツ連合で、『玉阪の日』に舞台を披露する、ということだな!」
オニキスの組長兼ジャックエース、海堂岳信の声がユニヴェール劇場に強く響き渡る。
「ふふ……今までにない試みだし、アンバー不在に対抗しうるインパクトもあるでしょうね」
たおやかな微笑みを浮かべそう言ったのはロードナイトの組長兼アルジャンヌ、更にトレゾールでもある忍成司。
『玉阪の日』について初めて知った翌日。
クォーツ、オニキス、ロードナイトの三クラスはユニヴェール劇場に集まっていた。
オニキスとロードナイトにも話は通っているようだ。
根地が「海堂、司、ありがとう!」と言って前に出る。
「ではでは記念式典でやる演目について……話す前に伝えとかなきゃいけないことがある!」
ユニヴェール劇場に集まった全員が、根地に注目した。
「夏休みとはいえ、全クラスが集まって稽古できる回数はめちゃ少ない! ほとんどできない!」
生徒たちが一気にどよめく。
上演時間は不参加のアンバー分も合わせて四クラス×五分の計二十分。
通常の学生公演に比べれば短いが、これだけの大所帯だ。
相応の稽古数を踏まなければ完成しないだろう。
根地が「まぁまぁ、落ち着いて」といたって軽く生徒たちに言う。
「なにせ僕ら組長やそれに準ずる生徒たちは秋公演の準備があるからね! その合間をぬって……になると時間は限られてしまうのさ!」
根地の言葉を受けて、いつも控えめな男が渋い表情を浮かべながら前に出る。
「……俺たち77期生は、訪問公演の準備もあります」
ロードナイトのジャックエース、御法川基絃だ。
ユニヴェール歌劇学校では、学校の方針により、小中学校や福祉施設での訪問公演も行っている。
この中心にいるのが主に二年生、今年でいうと77期生の生徒たちだ。
ただでさえ大変な中、前例のない公演ミッションが加わると負担も大きいのだろう。
御法川と同じように表情が硬い生徒も少なくはない。
対照的に、同じ77期生、オニキスのアルジャンヌである菅知聖治は、表情一つ変えることなく海堂の側に佇んでいる。
「そもそもぉ!」
ここで憤りを隠すことなく立ち上がったのは、ロードナイト一年、ジャンヌの忍成稀だ。
「なんでせっかくの夏休みにそんな大変そうな稽古しなきゃいけないんですか!?」
御法川が「いや、言っとくけど、記念式典の稽古自体はあったからな!?」と注意する。
「御法川先輩うるさい! だってこれ、普通の稽古より絶対厳しくなるじゃん! サボれないヤツじゃん! なーんで残り少ない夏休み、しかも突然そんなことしなきゃいけないんですか!? もっと有意義に夏休みを過ごさせてよぉ!」
いつも稀とつるんでいる一年ジャンヌ、宇城由樹も「そーだそーだ!」と声をあげる。エキゾチックな風貌で、常に無口な鳥牧英太も「……ん」と頷いた。
御法川が「やめろやめろ」と稀たちを押さえようとする。これがあるから御法川はどうしても否定的になってしまうのかもしれない。
「充分有意義だと思いますけどね、俺は」
そこで稀と逆の意見を突くように発言したのは、オニキスの一年、加斎中だった。78期生のトップジャックはいつだって向上心で満ちあふれている。
「他クラスの生徒と一緒に舞台に上がれる機会なんてそうそうありませんし、夏休みのシメとしては最高ですよ」
稀が間髪を入れず「あんたどうせ希佐と組みたいだけでしょ!」と叫ぶ。
「『だけ』って……。なにかチャレンジする上で、目的を一つに絞るの、勿体なくない? やるからにはより多くのことを吸収したいよ。他クラスのジャックを間近で感じる……とかね?」
加斎の視線がチラリとクォーツに向く。
「お」
スズが声を上げたので、目が合ったのだろう。
加斎の視線はそのままスッと横に動いた。
(……あ)
今度は希佐と目が合う。
「そういう沢山の目的の一つに、立花と組みたいって気持ちは当然あるけど」
「ほらやっぱり!! ちょっとみんな、加斎が加斎やってますよ!」
ぶれない加斎に稀が非難の声を上げる。
「……それで、結局どうするんですか。合同稽古がほとんどできない問題」
脱線ばかり続くこの状況に耐えかねて、白田が根地に問うた。
「おおっと、さすが白田くん! そうなのよ、だからこそ、負担を極力まで削いだ上に、アンバー不在の記念式典でしっかりかませる脚本書いたよぉ!」
じゃじゃん! と根地が見せたのは、既に用意された台本。
その瞬間、独特な緊張感が生徒たちの間に走った。
突如濃くなった舞台の香りがそうさせた。
「ほうら、まずはみんな、お受けとりな!」
普段よりページは少ないが、冊数は多い台本がそれぞれ配られていく。希佐の手元にも。
書かれたタイトルは至ってシンプルだった。
「……『玉阪町』」
根地が「そう!」と希佐の声に呼応する。
「この玉阪という町の誕生について描いた物語さ! さぁ、あらましをお伝えしよう!」
男性歌劇の最高峰、玉阪座をシンボルに、大きく発展してきた街、玉阪市。
この市が、もともとは異なる二つの町だったことを知っているか?
一つは当然、名前そのまま、初代・玉阪比女彦が宿場町近くに土地を賜り芝居小屋を建てて大いに栄えた芸事の町「玉阪」。
そしてもうひとつ。
その比女彦に土地を授けた領主、開松原(ひらきまつばら)ら開の一族が、城を築き居を構えた武士の町「開」。
しかし、明治。この二つの町が合併し、一つの町として生まれ変わることになったのだ。
そこで巻き起こったのが町の名を「玉阪」にするか「開」にするかの大論争。
玉阪と開の大げんか。
果たして町の名前はどうやって決まったのか――
「……ご覧の通り、実際この玉阪で起きた出来事を僕流にアレンジして制作しております!」
内容的には、玉阪の誕生を祝う記念式典にこの上なくふさわしいのではないだろうか。
「ちなみに! 芸事の町『玉阪』をロードナイト、武士の町『開』をオニキスに任せようと思っている!」
それを聞いて、クォーツ生がざわついた。
「えっ、根地先輩、オレたちクォーツは!?」
スズの言葉に根地が「慌てなさんな!」と嬉しそうに言う。
「今回クォーツは……」
もったいぶる姿は悪戯を企む子どもそのもの。
「ジャンヌ生をロードナイト、ジャック生をオニキスにわけて配属します!」
宣言に、クォーツ生のみならず、全生徒が沈黙した。
「えええええっ!!?」
声の重なりはまるで合唱。
「作戦はこうだ! 今回の頭のダンスとラストのダンス以外は、基本、玉阪側と開側、それぞれの視点で交互に話が進んでいく! 玉阪側と開側で、話が独立している!」
海堂が「なるほど」と瞬時に理解した。
「各陣営ごとに稽古ができるということか。全クラス集まるのは無理でも、クラス単位であれば小回りが利く」
「ィエス! クォーツ生にはご足労いただくことになるけど、そこはまぁ、僕のこの可愛らしいお顔を立てとくれ!」
白田がシラケた目で根地を見た。
クォーツのジャンヌ生はロードナイト、ジャック生はオニキス。
ここで、希佐の中に疑問が浮かぶ。
だったら新人公演でアルジャンヌ、夏公演ではジャックを演じた自分は、どちらにいけばいいのだろう。
だが、焦らずとも答えはくるはずだ。
「てなわけで、配役発表にいっちゃおうか!」
根地の言葉に、自然とその場の空気がピリッと張りつめた。
クォーツに限らずどのクラスでも、その『告知』には緊張が走るようだ。
「んでは、まず、玉阪座の当代であり、玉阪の町を率いる麗しの玉阪比女彦! 本来男性だけど、玉阪座の役者らしい魅力をアルジャンヌとして表現してもらう! 我がクォーツから、高科更文!」
主役はフミ。
クォーツ生たちは即座に納得し、フミが演じる玉阪比女彦の美しさまで想像できた。
「ええええええっ!?」
しかし、そんなクォーツ生とは裏腹に、ロードナイトの一年生から不満混じりのどよめきが起きる。
(あ、そうか……)
これはクラス合同。
稀が「ちょっとちょっと、根地先輩!」と大きく手を挙げた。
「玉阪側はロードナイト中心なのに、なんでお兄ちゃんがアルジャンヌじゃないんですかっ!」
稀の顔はこれまでとは違う真剣味を帯びている。
ただ、御法川ら二年生以上は違った。
「おい、落ち着け」
「だって!」
「すぐわかる」
「え……」
御法川らロードナイト二年、そして三年は、知っているのだ。
ロードナイトのボス、本来の姿を。
「コクト、早く呼んでもらって良いかしら?」
観客席に座っていた司が優雅に足を組む。
「早く呼ばれたいの、その“名前”を」
「了(りょ)! 歌だけではなく口も達者な玉阪座の『二番比女』……。これにロードナイト、忍成司! トレゾール!」
名を呼ばれ、司が立ち上がった。
その絢爛たる姿に、騒いでいたロードナイトの一年生だけではなく、その場にいた全員が息を飲む。
「よろしくね? ……アルジャンヌ」
司が微笑んだままフミを見る。
じっと、ただじっと。
その場に居る人間をヒリつかせるほど苛烈な眼差しで。
「ああ、よろしくな、トレゾール」
対するフミはゆったり髪を掻き上げ、笑い返した。いつも通りさらりと、ひょうひょうと。ただそれが逆に恐ろしく感じる。
「……久々だな、この光景」
懐かしむように彼らを見つめる海堂の眼差しは強い。
「……」
逆にカイは、居づらそうに視線をそらした。
(なんだろう、これ……)
希佐は額を押さえる。
チカチカと、閃光が走る。
思わず白田を見たのは、トレゾールという響きが耳に残っていたから。
希佐たちクォーツ生にとってトレゾールといえば、白田美ツ騎。
「………」
白田はフミと司の姿を見ている。
「では次! 比女彦の愛弟子、三番比女は白田美ツ騎! 君もトレゾールだ」
「……はい」
白田の表情に、濃い憂鬱と、いつもとは違う覚悟が見えた――ような気がした。
希佐はいったん目をつむり、息を吸う。
これは記念式典のための、合同公演。
なのにどうしてこんなにチカチカと目が眩むのか。
「他のロードナイト生たちはそれぞれ玉阪座の役者ってことで頼むよ! クォーツのジャンヌもね!」
そう長い物語ではない。その上、三クラス合同だ。役がとれる人間は限られてくる。
クォーツのジャンヌ生である世長は静かに頷いた。
「えぇ~、やだぁ~!!」
しかし、稀は納得できなかったらしい。
「ちょっと根地先輩! 配役雑じゃないですか! 高科先輩と美ツ騎様がすごいのは認めるけど! それにしたってロードナイト少なすぎます! 私にも役くださいよ!」
「そうそう~! 私たちだってぇ、ヒメヒメになりた~い!」
「……ん」
御法川が「おい」と慌てて制す。
「よし、わかった!」
しかし根地はここにきて気前が良かった。
「じゃあ、忍成弟氏は四……を飛ばして『五番比女』! 宇城由樹っぴと鳥牧の英太っちは揃って『六番比女』! んで、それなら世長くんは『七番比女』でよろしく頼むよ! 君らは可愛いがお仕事ね!」
「えっ!?」
「ぃやったー! 私にぴったりじゃーん!」
世長の戸惑いの声は、稀たちの歓声にかき消された。
御法川が「いいんですか、そんな我が儘に応えて……」と申し訳なさそうに聞く。
「あとそうだ、御法川くんにも役がある! ロードナイトのジャックエースは無視できないからね!」
「え、あ、はい。どんな役でしょうか」
忘れてしまう程度の役だろうと御法川は思ったことだろう。
ただ、根地はときにこういう悪質な演出を好む。
「君は玉阪座の『一番彦』! ユニヴェールで言うところのジャックエースだね。比女彦の相棒であり、有能な右腕。……要するに!」
根地が「じゃじゃん!」と自ら叫んで、両手をフミに向ける。
「君は今回、フミのパートナーだ!」
「………………。えっ」
根地の手がバタバタ忙しなく羽ばたく鳥のように動く中、御法川はフミと顔を見合わせた。
「……らしいぜ。よろしくな、御法川?」
御法川の額にぶわっと汗が浮かび、その雫が落ちる速度で顔が青ざめていく。
その場にいた多くの生徒たちが、御法川に憐憫の眼差しを向けた。
あの高科更文の隣に立つなんて、と。
「え、御法川先輩やばくない? できるの?」
「無理寄りの無理ぃ~!」
「ん……」
なによりロードナイト生の声が厳しい。
「さてさて、玉阪側のジャックエース的存在は御法川くんだけど、この舞台におけるジャックエースは他にいるよぉ!」
小刻みに震える御法川を置いて配役発表は進んでいく。
「ここから開側のご紹介だ!」
高らかな宣言と共に、生徒たちの視線がオニキスやクォーツのジャック生に向いた。
「大伊達山を背に、代々この一帯を治めていたのは『開』というお殿様! しかし武家政権は大政奉還によって終了し、新時代明治に生み出された廃藩置県によって開の殿様は町を去ることに! 残されたのは『開』という町の名と、主を失った開の武士たちばかり……」
(居場所がなくなった、武士たち……)
希佐の胸に、哀しく響く。
「そんな開の武士筆頭、政治家の『新田(にった)』をオニキス、海堂岳信に任せよう! 頼むよぉ、海堂!」
海堂が挙手するように真っ直ぐ手を伸ばし、その挙げた手で自身の胸をドン、と力強く叩いた。
「任されよう! 誠心誠意、舞台のために!」
反射的に背が伸びた。希佐だけではなく、多くの生徒たちが。
なによりオニキス生の顔が変わった。この瞬間から、オニキス生たちは海堂を指揮官として全ての意識を共有していくのかもしれない。
「…………」
一方で、聞こえるはずのない沈黙がなぜか希佐の耳に届いた。
(あ……カイさん……)
人が集まるときは輪の一番外れ、列で言うなら最後尾について、みんなを静かに見守っていることが多いカイ。
そのカイが、海堂を見つめ、そっと表情をほころばせる。
口元に浮かぶのは確かに笑み。
だが、カイの唇はあまりにも複雑な形をしている。感情を読み取るのが難しいほどに。
そんなカイと、似た気配を感じた。
希佐はカイがいる場所とは反対側へと顔を向ける。
「…………」
カイと同じように黙ったまま、海堂の姿を見つめるのは菅知だった。
希佐は気づく。
(そっか……、自分のパートナーが、他の人と組むんだ……)
カイならフミ、菅知なら海堂。隣にいる人が、誰かの隣になる。
それを彼らはどう受けとめるのか。
カイと違って菅知の表情に変化はない。
ただ、どちらにせよ感情は読みとれない。
次に名前を呼ばれるのは、菅知だろうか。
「次に、海堂演じる新田を兄のように慕う士族で若き起業家、『初花(はつはな)』をジャック、加斎中!」
「はい!」
名前を呼ばれ、加斎は驚くことも戸惑うこともせず即座に返事した。
「ありがとうございます、頑張ります」
彼の表情には、既に自信が漲っている。
加斎は常にどんな役でもやり通す覚悟ができているのかもしれない。
「そんな加斎くん演じる起業家の付き人として、ダンテくんと長山弟くん、頼むよ!」
「ハーイ♪」
「了知しました!」
ちょうど加斎の両隣に立っていたダンテ軍平と、長山登一も即座に返事をする。
「新田の聡明な妻にはジャンヌ、菅知聖治で!」
「はい」
流れも勢いもそのまま受けて、菅知が応える。
オニキス生の名前が次々呼ばれていく。
「…………まだか」
「……!」
スズが言葉を噛みつぶすように小さく呻くのを聞いた。
(そうだ、クォーツは……)
玉阪に比べると、開はオニキス色の強い配役になるのだろうか。
スズがカイを、そして鳳を見る。すると鳳が鋭く小さく「こっちを見るな!」と文句を言った。
ただ、彼らは目が合ったのだ。鳳もスズを見ていたのだ。
希佐は改めてカイを見る。
彼は粛々と自分の役目を待っているように思えた。
「お次は開の士族で新田とは旧知の仲である警察官 『ナラシバ』! これをジャック、睦実介!」
ここでようやくカイが、クォーツのジャックが名を呼ばれた。
「ジャックとしては二番手くらいの感覚でいてね」
「いや、一番手くらいがちょうど良い!」
根地の言葉に乗せて、海堂が言う。
「善処する」
カイは、どこまでも控えめだった。
「このナラシバの弟分、士族だけど無職の『リン』には、ジャック、織巻寿々!」
「ぅおはい! ……無職?」
「ナラシバには警官の部下もいる! これにジャック、鳳京士!」
「はい!」
カイのあとを、スズ、鳳と続く。
「そしてこちらも玉阪側と同じく、クォーツのジャック生は開側の士族として舞ってもらうよ!」
開側の名のある役はここまで。
「ちなみに! 明治だと彼らの呼び名は『武士』から『士族』に変わっているんだけど、彼らは過去への思いが捨てきれず、あくまで『武士』にこだわっている……という設定で頼むよ。わかりやすさに配慮した設定にしておりますゆえゆえゆえ。史実を扱うっていうのはなんともデリケート、僕は結構苦手、ああ哀し!」
本気で嘆いているのか、それとも口だけか、境界線は曖昧だ。
「ちなみに僕は町人A、町人B、町人C、町人Dなどを演じさせてもらう! 玉阪と開の対立に翻弄されたり、翻弄したり。進行も司る大事な役だ、しっかり演じてくれ、根地黒門くん! はい頑張ります!」
根地の一人芝居を見て、オニキス生とロードナイト生に動揺が見られた。クォーツ生は慣れたものである。
そしてここに来て、希佐はまた思うのだ。
(私はどうなるんだろう……)
根地自身の配役発表は、今回の舞台の配役発表終了の空気を醸し出している。
(私は玉阪と開、ジャンヌとジャック、どちらを演じたらいいんだろう)
名前を呼ばれなかった生徒たちが肩を落とす中、姿勢を崩すことなく真っ直ぐと自分の居場所、そして役目。希佐が視ようとしているのはそれだ。この舞台における自分の役目。
「あと最後に立花くん!」
ここにきて急に根地が希佐を呼んだ。
「君には、議長を務めてもらう!」
――議長?
「玉阪と開、双方の意見を聞き、町の名前をどちらにするか決める権限のある人物だ! 大事な役どころだけど出番は少ない! 歌もダンスもすっぱり不参加!」
他の生徒たちとは毛色が違う。一瞬で数多の疑問が湧いたが、即座に優先順位を決め、質問を一つに絞った。
「ジャックとジャンヌ、どちらで演じたらいいんでしょうか」
「どっちでもあるし、どっちでもない! 透明感出していって!」
「えっ」
根地の回答は不明瞭だ。
「てな訳で! 休憩はさんで本読みするよぉ! あと、頭のダンスシーンと、ラストの歌唱シーンもね! ここは全クラス合同だから! んでは、十分後に集合!」
根地がパンッと手を叩いて休憩の合図。その途端、観劇を終えたあとのように、劇場内が騒がしくなる。
「なんだか……配役発表だけで疲れちゃったね……」
世長がはぁ、と息を吐く。
「僕は玉阪、スズくんは開、希佐ちゃんは……どちらでもない議長? みんなバラバラだ。稽古、どんな風に進んでいくんだろう」
周囲をうかがう世長はどこか不安そうだった。
「……」
(……スズくん?)
一方、こういうとき、いつも真っ先に感想を口にするスズが、今日に限ってなにも言わない。
彼はじっと、ユニヴェール劇場の舞台を見ている。
「それに大丈夫、なのかなぁ……」
「『大丈夫』? なにか気になることがあるの、創ちゃん?」
スズの様子を気にしつつ、世長に問う。
「あ、えっと……考えすぎかな。だって舞台だし、みんなそんな、いや、でも……。……あ、ごめん! えーっと、あのね」
世長がふーっと息を吐き、この場にいる生徒たちを見渡す。
「オニキスとロードナイトって、同じ舞台で、上手くやれるのかな……?」
そう、この二クラスはユニヴェールにおいて最もわかりやすい「真逆」なのだ。
「ちょっとぉ! ダンス難しすぎるんですけどぉ!!」
ユニヴェール劇場に稀の叫びがこだまする。
「あーもう、なんなの、オニキス式の軍隊ダンス! ロードナイトの良さが全ッッッ然出ないんですけどぉ!? 汗かかせないでよ!?」
稀はゼーゼー息を荒らげながら額を拭い、いつも可愛くセットしている巻き髪をなんとか維持しようと指先でぐるぐるこねる。
「え、全然オニキス式じゃないよ?」
一方、汗一つかいていないのがオニキスの加斎である。
「ロードナイトに合わせて、かなり優しいダンスになってるんじゃない?」
「はぁー!? なにその俺たち上過ぎてレベル合わせてあげてます感!!」
「そんなこと言ってないよ。オニキス生はもうみんなダンス覚えちゃったけど」
「そういうとこ!!」
加斎が言うとおり、ダンス稽古が始まってすぐにオニキス生たちはダンスを習得してしまった。今は体が冷えないようにストレッチをしながら待機している。
ちなみに、クォーツの生徒たちは出来不出来がまばらだ。それでもロードナイトより踊れている。
「すみません! ダンスは持ち帰って稽古するので、先に進めてもらってもいいですか……!」
遅々として進まない現状に、御法川が悲痛な声を上げた。
「あいあい! じゃあ、お歌の稽古といきましょうかね」
これなら、とロードナイトだけではなく、オニキスやクォーツ生も思ったのだが。
「……ちょっっっっとおおおッッッッッ!!」
再び叫んだのは歌を十八番にするロードナイト、稀。
「なんですかこの歌?! こんな短期間でやるようなもんじゃないでしょ、あり得ないッ!!」
楽譜を見て怒り狂う稀に、加斎が「文句が多い」と素直な意見を述べる。
「あんたにはこの歌の難しさがわかってないのよ! え、怖っ! 怖っ! ガチの公演レベルじゃない、怖怖怖ッ!」
これに関しては稀の感覚が正しいのかもしれない。なにせ御法川も青ざめている。
ただ、根地は「そりゃそうよぉ!」と当たり前でしょ顔。
「最後に名前を冠するのは『玉阪』ですからねぇ。玉阪組には頑張ってもらわないと! ……と、僕は思うわけですがいかがですか、司比女!」
根地のお伺いに、司はにこりと微笑む。
「“私”は、歌えるわ。今すぐにでも」
スズが思わず「うわ、怖ぇ」と口にした。世長が「スズくんっ」と慌てる。
だが、この場にいるほとんどの生徒がスズと同じ気持ちだ。
「……フミさん」
白田がスッとフミの隣に立つ。
「かなり飛ばさないと、喰われますよ」
フミは余裕の笑みを崩さない。それが一番の武器になるからだ。
希佐は額を押さえた。急に気づいたのだ。
――そうか、火花。
(感情の交錯が激しすぎる……みんなの思念がぶつかり合って火花を飛ばしてる……)
オニキスの海堂だってそうだ。
「…………」
三クラス合同での舞台を作ると言ったときも、配役発表のときも、太い木の幹のように構えていた彼が、根地による本読みが終わってから沈黙に転じている。剣の切っ先のように鋭利な表情で。
チカチカ、チカチカ、チカチカ、チカチカ。
一つの箱に収まらない正体不明の感情が、あちらこちらでぶつかり激しく踊っている。
まるで火薬庫近くの線香花火。
稽古が進まない。
根地がうーんと首をひねって、フミと海堂を見る。
「あと、ジャックエースとアルジャンヌには手を取り合って踊ってもらいたいんだけど……」
クロ、とフミが制した。
「今日はいいんじゃね? なぁ、海堂」
「……そうだな。今はまだやるべきことが山積している」
海堂が堅く頷く。
カイも彼らの意見を尊重するようにとでも言うように根地を見た
「ぃよーし! じゃあ、それぞれの陣営ごとに課題を整理してもらおうかな! 司もいいかい?」
「ええ」
「んでは、また! 健闘を祈る!」
根地がビシッと敬礼をした。
オニキス生が「お疲れ様でした!」と礼儀正しく頭を下げる。ただ、彼らは早々にユニヴェール劇場から去って行った。
ロードナイト生たちは「どうなるのよ、これ……!」と輪になって愚痴り始める。
「……大丈夫かな、これ」
すでにいなくなったオニキスを、不満が止まらないロードナイトを見て、世長がまた繰り返す。
最初、聞いたときとは比べものにならないほどの重みがあった。
希佐は台本に記された配役を見る。
印字された文字でさえ、チカチカして見えた。
【登場人物】
玉阪比女彦 高科更文(Aj)
新田 海堂岳信(Ja)
二番比女 忍成司(jan)
三番比女 白田美ツ騎(jan)
五番比女 忍成稀(jan)
六番比女 宇城由樹・鳥牧英太(jan)
七番比女 世長創司郎(jan)
一番彦 御法川基絃(j)
初花 加斎中(j)
初花の付き人 ダンテ軍平・長山登一(j)
新田の妻 菅知聖治(jan)
ナラシバ 睦実介(j)
リン 織巻寿々(j)
部下警官 鳳京士(j)
町人A/B/C/D 根地黒門(jan)(j)
議長 立花希佐(--)
【4】
「……『それでは皆さん。町の名を玉阪にするか、開にするか、決めてください』」
今、鳴く蝉たちは、共に秋を迎えるのだろうか。
誰もいないクォーツの稽古場。希佐は記念式典で行われる『玉阪町』の稽古に挑んでいた。
「『私の意見はありません』。『では今日の会合を終了します』。……うーん」
希佐が演じる議長は、名前を決める権利を持ちながら、徹底して無関心だ。
意見を求められても素っ気なく、彼らが町への愛を語っても白けていて、時間がくれば早々に退席する。
大勢の中にいても人と交わることのない孤立した存在。
だからこそ、稽古もこうやって、他派閥に混ざることなく一人やっている。
(それにしても……)
まさかジャックか、ジャンヌかという居所さえ与えられないとは。
(性別の枠って、その人の人間性を考える上でかなり重要なんだな……)
もし、男性の議長だったら?
女性の議長だったら?
イメージする姿にはそれぞれ違いがあり、異なる器に魂が入る。
(性別……か)
自分は、あってないようなものだが。
まとまらない不明瞭な思考の中、根地の言う“透明”を見つけ出すのは難しい。
根地はといえば、記念式典実行委員会と舞台に関する打ち合わせで忙しいようだ。
だからこそ演出は、玉阪ならロードナイト、開ならオニキスに任されている。
玉阪座の美しくしなやかな役者たちをロードナイト的表現で、開の武士たちの雄々しさ、力強さをオニキス的表現で見せるのが妥当という判断だろう。
「そういえば……」
希佐がこうやって『玉阪町』の稽古をしているように、今、他のクォーツ生たちもジャックとジャンヌに分かれ、それぞれの派閥の稽古に行っている。開側は朝早くから、玉阪側はお昼過ぎからだ。
ただ、どちらもまだ帰ってきていない。
稽古は順調に進んでいるのだろうか。
「…………」
希佐は昨日の火花を思い出す。
「……あれ」
ちょうどそこで、稽古場のドアが開いた。
「あ、創ちゃん!」
ジャンヌとして、玉阪組の稽古に行っていた世長だ。
「創ちゃん、お疲れさ……だ、大丈夫?」
世長は見るからにぐったりしている。
「あ、希佐ちゃ……んんっ! ダメだ……、歌いすぎて喉が変になってる……あー、あー、あー……」
声の調子を整えようとする世長に「無理しないほうがいいよ」と声をかけ、希佐は水をとりに行った。稽古場に備蓄されているミネラルウォーターだ。
冷えているものもあるが、トレゾールである白田がいつも飲んでいる常温の水を選ぶ。
「あ、ごめんね……」
壁際に腰を下ろした世長が感謝して水を受けとった。
彼はゆっくりと喉を潤し、はぁ、と息をつく。
「ありがとう、助かったよ」
彼の声にみずみずしさが戻った。
「稽古、そんなに大変だったの? 歌に、ダンスに、芝居……」
「芝居に関しては……まだついていけている方、かな……。流れで役を貰えただけで、セリフは少ないから。大勢いる玉阪座の役者の中で、比女彦の取りまきとして少しだけ前に出させてもらってる感じ。忍成さんたちはどんどん前に出て御法川先輩に指導されているけど」
稀たちと御法川の攻防は容易に想像がつく。
「ダンスはどう?」
それが玉阪側――言ってしまえばロードナイトの懸念事項。世長はふるふると首を横に振る。
「それが全然、全くできてないんだ」
「えっ」
「歌が、大変で」
そんなに難しい歌なの? と希佐が問う。
「難しいのは、難しい。でも、それ以上に……」
なにかを思い出したのか、世長の体がぶるりと震えた。
「……戦ってるんだ。フミさんと、忍成先輩が」
――フミさんと、忍成先輩……?
チカチカと、目の奥に火花が散った。ユニヴェール劇場で見た、あの閃光。希佐は二人の様子を尋ねようとする。
だが、その瞬間、銅鑼を打つかのような勢いで開いたドアが、全てを吹っ飛ばした。
「うあああああああああ! ヤバイヤバイヤバイ!! 絶対ヤバイ、マジでヤバイすっっっげーヤバイ!!」
赤髪をかきむしって入ってきたのは開組としてオニキスに稽古に行っていたスズだ。
「鳳ぃ! さっきのダンス覚えてるか、覚えてるよな、教えてくれ!」
「断る! そんなヒマはない!」
スズの後ろから同じく開組の鳳が姿を見せる。スズに対していつも辛辣な鳳だが、今日はいつも以上に語気が強かった。
「スズくん、なにかあったの?」
「あっ、立花! いやなんかもう、オニキスのジャックがヤバすぎて……」
「オニキスじゃない!」
鳳が即座に否定した。握られた拳、滲む焦り。希佐と世長は思わず息を飲む。
「オニキスじゃない……オニキスではなく……」
鳳が鳳の“答え”を口にしようとした瞬間。
「鳳ッ!!」
今度はスズが声を荒らげた。その迫力に、希佐と世長の体がビクッと跳ねる。
(スズくん……?)
「……クォーツのジャックを見せてやりゃあいいだけだ! こんなもんじゃねぇからな、オレら! そもそも鳳はもう踊れてるし!」
いつもならスズの発言を一から十まで否定する鳳。しかし今は、ぐっと、ぐっと強くなにかを堪えるように飲み込んだ。
「……ダンスを完璧にしてからものを言え!」
一呼吸置いて、鳳が叫ぶ。スズが「それはそう!」と大きく頷く。
鳳も、スズも、いつも通りだ。
「織巻、鳳!」
そこに、カイが早足で現れた。
「ダンス、俺が教える」
まるで、今までのやりとりを聞いていたかのような声かけだ。
「うおおお、やった!! よろしくお願いします!」
「おい、織巻! 睦実先輩のお手を煩わせるのは……」
「気にする必要はない。あとは他のジャック生たちも」
カイが周囲に視線を巡らせる。
「オレ、呼んできます! じゃな、立花、世長!」
「え、あ、うん、頑張って!」
スズが稽古場を飛び出し、鳳もスズの背中とカイの顔を交互に見たあと「僕も呼んで参ります!」と駆けていく。カイが「すまない、頼む! ダンスルームで!」と叫ぶと、遠くから「うぃッス!」とスズの声が聞こえた。
「あ、あの、カイさん……」
思わず名前を呼んでしまった希佐をカイがハッと見る。
「ああ、すまない。騒がしくしたな。二人は稽古か?」
「あ、えっと、休憩中です」
「そうか。あまり無理はしないようにな。じゃあ」
そう言って、稽古場をあとにしたカイ。締まった扉の先、駆ける音が聞こえた。
「スズくんと鳳くん、すごく焦ってたね……」
世長が心配するように、扉の向こうをのぞき見る。
「ダンス、かなり大変なのかなぁ……」
世長の言葉を聞きながら、オニキスの姿を思い描く。オニキスはダンスを得意とするジャック中心のクラス。特に一糸乱れぬ群舞の素晴らしさは他の追随を許さない。
スズや鳳が焦るのは当然だ。
――ただ。
耳に残る、カイの声。
希佐の中に、もしかして、という感情が芽生える。普段は湖底の真水のように静かで落ち着いたカイの声。それが今日、激しく波立っていた。
(スズくんや鳳くん以上に、カイさんが焦ってる……?)
むしろ、スズが一番落ち着いていて、カイが一番焦っている?
でも、どうして――。
「……僕も、稽古してこようかな」
スズたちの姿を見てなにか思ったのか、世長が希佐にもらったペットボトルのキャップを締めた。
「希佐ちゃん、お水ありがとう! じゃあ、お疲れ!」
「あっ、うん、お疲れ!」
世長を見送り、稽古場にまた一人。
(大丈夫なのかな)
玉阪組も、開組も、思いがけない問題が発生しているように見える。
だが、その現場を実際この目で見たわけではない。
手の中にある砂粒程度の情報で巡らせた想像なんて、結局地に着かず、空想となって浮かび上がり、粗末な妄想に喰われるだけ。
(……チカチカするな……)
希佐は目をぎゅっと閉じてから、台本を開く。
常に他人事な議長の言葉は、今の希佐に重ならなかった。
自分自身が前に進めない日は、素知らぬ素振りで山の向こうに消えていく太陽がつれなく見える。
その日の夕刻。緋色に染まるユニヴェール校舎近くを通ったところで稀を見かけた。
「あ、稀ちゃ……」
いつものように話しかけようとしたのだが。
「あんたたち、ちゃんと歌、できてるんでしょうね!」
(……!)
稀のよく通る声が校舎の壁にぶち当たり盛大に弾ける。
瞬時に加斎がいることを悟った。
「それを言うなら玉阪組……というかロードナイトは大丈夫なの?」
稀の正面にはやはり加斎。
「オープニングを飾る大事なダンスだからね。ここをしっかり決めてもらわないと……」
「その『ロードナイトは』って言い方やめてくれる!?」
稀がギッと加斎を睨みつける。
「とにかく! 歌! しっかりやりなさいよね!」
稀がふんっと顔をそらし、校門に向かってずんずん歩いて行った。加斎は「やれやれ」といった表情で、稀とは反対側、オニキス寮へ帰っていく。
だが、歩みを止めることなく小さくなっていく加斎とは違って、稀は途中で立ち止まり、加斎を振り返った。
「……はー」
稀がぐったりと背中を丸め、大きなため息をつく。
「……『玉阪町』の稽古するの、もう、やだぁ……」
(……!)
稀はうう~と唸り、そんな自分が嫌になったのか頬をペシペシと叩いて、校門の方に駆けていった。
今から街に行くのかもしれない。気分転換のために。
「稀ちゃん……」
チカチカする。
火花が増えている。
その日の夜。寮で夕飯を食べようとしたところで、生徒の数が少ないことに気がついた。
「ジャック生がいない……?」
スズ、鳳、それにカイ。他のジャック生も全員いない。
「ん? おー、希佐、オツカレ」
「……そんな所に突っ立って、なにをしてるんだ」
キョロキョロと落ち着きなく食堂を見る希佐の背後から、声。
「あっ、フミさん、白田先輩……」
振り返ると、クォーツのアルジャンヌとトレゾールが、フミと白田が立っていた。
「なんだぁ、ジャックがいねぇな」
「ああ、それで静かなのか」
フミが瞬時に状況を察知する。ただ、希佐のように立ち尽くすことはせず、食事が載ったトレーに手を伸ばした。白田も続き、希佐も慌てて夕飯が乗ったトレーを手にする。
そのまま自然と三人、同じ席に着いた。
「……本当にジャック生、一人もいないんですね」
改めて周囲を見渡した白田が、ほんの少し困惑を滲ませそう言った。なにか面倒くさい予感を感じているのだろうか。
「もしかしたら、みんなでダンスの稽古をしているのかもしれません」
希佐は稽古場で見たスズたちの姿を思い浮かべながら言う。
フミが「『玉阪町』の?」と、確認するように聞いてきた。
「はい。なんだか大変みたいで……」
フミが「なるほどねぇ」と呟く。常に先を行くフミの目に、この現状はどう映っているのだろう。当然のように、フミの考えが聞けるのを待った。
「それより、希佐」
「はい」
「料理。冷めちまうぞ?」
ところが、ジャック生に関する会話はもう終わっていたらしい。
「あっ、そうですね」
指摘され、食事を前に完全に止まっていた手に気づいた。
手だけではなく、思考もか。
「今日のスープはどうよ、ミツ」
「ええ……? スープはスープですよ。僕は温かいほうが好きですけど」
見ればスープから立ち上る湯気がない。放置したせいで冷めたわけではなく、今日は夏野菜の冷製スープなのだ。
「たまに食べる分にはいいですけど」
白田がスープをそっと口に含む。
希佐もつられてスープを口に運んだ。野菜の甘みが優しく広がる素朴な味わいだ。
ここにきて、急に空腹を覚えた。
思考ばかりに集中していた神経が、ようやく体の中を巡り始めたのかもしれない。
ふわりと、今日の終わりを感じる。
「希佐、明日、玉阪組の稽古、見に来るか?」
「えっ、いいんですか?」
フミの提案に、驚き彼を見る。
白田はチラリとフミを見て、また視線を落とす。
「希佐は今回、議長役で、人と絡むこと少ないから、全体像が見えなくてやりづらいだろ」
フミの言葉は、希佐の悩みが、そのまま言語化されたかのようでストンと落ちてきた。
そう、だからきっと自分は飛びかう火花ばかりを追って、不明瞭に思いあぐねている。
「だから自分の目で視て、感じて、考えりゃいいサ」
そんなことを話しながら、早くもなく、遅くもなく、適切なスピードで食事を食べ終えたフミが席を立った。
「じゃーな。また明日」
去り際の笑顔も美しい。
席には白田と希佐の二人。
フミの背中を見送った白田が、少しだけ行儀悪く頬杖を突く。
「ったく……フミさんは優しいんだか、厳しいんだか。おい、立花」
「はい?」
白田が空になったスープ皿にスプーンを置いて言う。
「今日はあれこれ考えずさっさと寝ろ。いいな?」
それは、どういう意味だろう。
「考えずにさっさと寝ろって言ったろ」
「!」
反射的に考えてしまった希佐を白田は目ざとく見つけ、注意する。
「いいか、立花」
白田が頬杖を解いて語気強く言った。
「お前なんか、今、食べているスープが美味しかったって思いながら寝ればいいんだ。いいか、返事はっ?」
「は、はい!」
その夜、希佐はスープが美味しかったと思いながら眠りについた。
ずいぶんと長い一日だった。
【5】
早朝、ひぐらしの鳴き声を聞いた。
しっかり睡眠をとった希佐は指定された時間にロードナイトの稽古場に向かう。
「失礼します……」
中をのぞくと既に稽古は始まっていた。
ロードナイトといえば、どんなときでも賑やかで、和気あいあいとしているのだが。
(あれ……)
開けた扉の音が響いてしまうほど、中はしんと静まりかえっている。
その上、生徒たちはこちらを見ない。
彼らの視線は、たった一人の人物に縫いつけられていた。
「『昔から! 私ら玉阪座の役者たちは、開の武士たちに所詮役者と軽んじられてきた!』」
稽古場の中心でフミが――いや、『玉阪比女彦』が、演説を行っている。
「『芝居なんか不要の道楽だとね! それは私たちにだけ向けられた刃じゃない。いつだって笑顔を絶やさず頭を下げて商売してきた町人たちには銭臭い手だと、汗水垂らして働く農民たちは薄汚いと、私らはいつだって開の武士らに見下されてきた! ……だがどうだ!』」
比女彦がバッと両手を大きく広げる。
「『この美しい玉阪は! 座を中心に町は栄え、人は笑顔で道を行き交っている! ……飯だって旨いしね! お国の役人たちが、異国の要人が訪れるのだって、今じゃ寂れた開ではなく、この玉阪だ! 明治の世を先頭切って走るのは私たち玉阪なんだよ!』」
しなやかながらも芯があり、見る者を惹きつける美しさは花とするなら満開の桜。
誰も彼も心を囚われ動けない。ずっとその姿を見ていたい。
「……『だからこそ、開の動きには注意しなければならないのですよ、比女彦さん』」
そこで、諫めるように口を開いたのは御法川演じる一番彦だ。
「『確かに、僕たち玉阪には勢いがあります。町に住んでいる人の数だって、お国に払ってる税金だって、こっちのほうがずっと多い。ですが、プライドの高い開の武士たちが、そうやすやすと町の名を渡すはずが』……」
大事なシーン、大事なセリフ、それなのに。
一番彦がしゃべればしゃべるほど、静まりかえっていたロードナイトの稽古場に、ざわめきが広がる。
「ねぇ、やっぱり一番彦、邪魔じゃない?」
ざわめきをまとめ、刺すように言ったのは稀だった。ユキが「わかるぅ!」と両手を握る。
「比女彦様はぁ、こんなにきれーでかっこよくてぇ、天上人みたいな人なのにぃ、一番彦は平凡の極みっていうかぁ……。比女彦様としゃべるなんて場違いが過ぎるってカンジぃ!」
同意を得て、稀が「よねよね!」と勢いづいた。
「こっちは比女彦様の話聞きたいのに一番彦がべらべらしゃべるから冷めちゃうじゃん! ちょっともう静かにしてよ! ってカンジ!」
御法川が胸を押さえる。刺さったようだ。
「……あ、希佐ちゃん! どうしたの、見学?」
そこで、希佐に気づいた世長が小走りで駆け寄ってくる。
「昨日、フミさんと白田先輩に声をかけてもらえて。今は芝居の稽古?」
「うん。でも……」
世長が御法川を気の毒そうに見つめる。
「御法川先輩がかなり苦戦してて……」
「てゆーかぁ!」
稀の攻撃が止まらない。
「一番彦の威厳がないんですよ! なんかひょろいって言うか、頼りないって言うか。睦実先輩と全然違う!」
「ぐっ……」
「よねよねぇ! 睦実先輩だったらぁ、キレーなお庭のでっかい岩みたいにぃ、どっしり構えて比女彦様と話しても邪魔にならないのにぃ」
「……っく」
稀とユキは追撃の手を休めない。
「そう、邪魔にならない! 御法川先輩はなんっか邪魔なんですよねぇ」
終わらない邪魔邪魔コール。
「……邪魔邪魔言うんじゃねぇえええぇッ!」
耐えかねて御法川が叫んだ。だが、すぐにハッと我に返る。
「くそ……!! すみません、高科先輩! 次までに考えておくので、俺との合わせはいったんなしで……!」
時計も確認しつつ、御法川が訴える。
「もうちょっと試してもいいんだぜ、御法川?」
「いや、俺だけのことに時間使うのは、さすがに……! 俺はロードナイトのジャックエースなので!」
クラス全体をサポートする責任がある、と御法川は言いたいのだろう。
それでも上手くいかない自分の役が気になるのか、わずかな隙間で台本をチラリ。
「……これが結構、稽古に響いてるんだ」
世長が小声で希佐に説明する。
「ロードナイトって、いつもは御法川先輩がみんなに歌やダンス、芝居の指導をしているそうなんだ。その御法川先輩が自分の課題で手一杯になっちゃうと、進まないことが多いんだよ……」
いつもはクラスを牽引するジャックエース。その分、今回の出来事は御法川としても相当苦しいところだろう。
「それに……」
世長がチラリと稽古場の中央を見る。
「一番大きい問題が、別にあって……」
世長の視線を追って、希佐はハッと息を飲んだ。
忍成司がゆったりとした足どりでその場所に向かっている。ぞわ、と肌が粟立つような感覚が希佐に走る。
「じゃあ、みんなで歌の稽古しましょうか」
みんなと言いながら、司の目は、真っ直ぐフミを捉えている。
「ん」
フミは笑顔で応えた。
(……怖い)
先程まで波打っていた湖面が一気に凍りついていくようだ。
「希佐ちゃん、僕も行ってくる」
世長の表情にも緊張が浮かんでいる。
当然、他のロードナイト生にもだ。
「じゃあ……、音楽」
ついと浮いた司の指先。
音楽が、流れる。
(……っ!)
歌声が吹き荒れた。
(……すごい……!)
司の唇から放たれる歌声は、希佐の皮膚を刺し胸を殴る。
(これが……)
これがロードナイトのトレゾール。
暴力的な歌声はロードナイトの稽古場の中、うねる龍のように暴れ回った。
しかし、そこに、新たな歌声が響き渡る。
(……っ! フミさん)
高らかに歌うのは、フミ。アルジャンヌのフミ。
彼の歌声はこれから玉阪に訪れる明るい未来を指し示すように、強く、熱く、響き渡る。そして、“なにか”を越えようとしている。
(戦っているんだ)
アルジャンヌとトレゾール。
フミと司が戦っている。
(そう、か)
希佐の目に、突然歴史が映った。
今回、クォーツ、ロードナイト、オニキスは同じ舞台に立つ仲間。
だが、それ以前にフミと司は同じジャンヌとして競い続けたライバルなのだ。
その上、二人はそれぞれクォーツの、ロードナイトのトップ。
彼らは互いに、負けるわけにはいかないのだ。
(……あ!)
フミの歌声が、一瞬、司を上回った。
場を支配した。
(……!)
稽古場の温度が下がる。
ロードナイト生たちの歌声が鈍ったのだ。
即座に司の歌声が厚みを持って響き渡った。今度は司の歌声が、フミを圧倒する。
「……やばいよな」
「えっ、あ、御法川先輩……」
ジャンヌたちが歌う姿を見つめながら、御法川が希佐の側に歩みよってきた。
「御法川先輩。フミさんと、司先輩は……」
「バチバチにやりあってるよ。ずっとこんなカンジだ」
御法川は、全身で歌い上げる司を見る。
「意地があるんだよ」
「え」
「ロードナイトとしての意地が」
そこでフミの声に重なりが生まれた。
(白田先輩だ)
フミとも、司とも違う。クォーツのトレゾール、白田の歌声が新たに響き渡る。
御法川の表情が曇った。
「……立花、ロードナイトがどういうクラスか知ってるよな?」
「え? それは……歌唱が強みのジャンヌ中心のクラスです」
「そうなんだよ。でもさ」
御法川の横顔に、一抹の哀しさ。
「むしろクォーツの方がそれらしくないか?」
「え……」
「クォーツの方が、ロードナイトらしくないか?」
すぐには理解できなかった。
クラスそれぞれの形を疑うことなく、尊重し、ユニヴェール生活を送っていた希佐にとって、御法川の言葉はあまりにも難しかったのだ。御法川はそれに安堵するように少しだけはにかんだが、またすぐに憂いをまとった。。
「高科先輩はダンスって強みがあるからなにかとそちらが取りざたされるけど、歌もすごい。歌が強みのアルジャンヌとしても、やっていけるほどに。それから、言うまでもなく白田。あと……」
御法川が、希佐を見る。
「立花もな」
「えっ」
「夏はジャックをやってたけど、新人公演じゃアルジャンヌ。難易度の高い歌をしっかり歌い上げていた。クォーツのジャンヌはレベルが高いんだ」
それだけじゃない、と御法川は言う。
「クォーツには根地先輩もいる。あの人はいつも型に囚われず、ジャック、ジャンヌ、幅広く演じているけど、高科先輩と同じようにジャンヌとしては一線を画す人なんだよ。俺は……『去年』を、見たしな」
“去年”の残像を見ているのだろうか。御法川の視線が遠くなった。
「根地先輩は、ジャンヌの魅せ方を熟知してる。そして、トップアルジャンヌである高科先輩の存在が、クォーツのジャンヌレベルを引き上げてる。ロードナイト以上に、ロードナイトやってるんだよ、今のクォーツは」
一体どんな気持ちで、その言葉を口にしているのだろう。
「……だからこそ、負けられないんだ、司先輩は。言ってしまえばロードナイトの最後の砦。司先輩が高科先輩や白田に歌で競り負けるようなことがあれば……ロードナイトは存在意義を失う」
「……!」
希佐は稀たちロードナイト生を見る。
芝居のときとは違い、彼らの顔は真剣そのものだ。
彼らの歌声は司に捧げられているような気がした。
負けるな、負けるなと。
私たちはロードナイトなんだからと。
あなたがロードナイトなんだからと。
希佐は、ああ、と息をつく。
こんな状況で、ロードナイトが歌以外のことに集中できるだろうか。
「こっちの事情は、高科先輩だってわかってるだろうよ。だからって手を抜くようなまねはできない。そんなことされたらこっちだって気づくし……なにより高科先輩も守らなきゃいけないものがある」
ロードナイト相手に多勢に無勢。
それでも白田を傍らに、フミは堂々と歌い続ける。
それがロードナイトの自信を奪い、深く傷つけることになっても、フミは歌う。
フミはクォーツのアルジャンヌとして、クォーツの顔として、戦い続けるのだ。
(……)
稽古場に響き渡る歌声。
確かに美しいが、胸が締めつけられる。
この声は、舞台の上で混ざるのだろうか。
「……」
未だ歌声響くロードナイトの稽古場をあとに、希佐は一人歩いていた。
ふと、唐突に、昨日食べた冷製のスープが美味しかったことを思い出す。
フミも、白田も、希佐が玉阪組の稽古を視れば、なんらかの影響を受けることが想像できただろう。
それでも、魅せてくれた。
希佐は天を仰ぐ。もう八月も後半に入ったというのに空には真白い入道雲。
しかし足元には秋の入り口、萩の花。
こちら側と、あちら側。
「……」
そういえば小さい頃、兄である継希と遊んでいた公園でこの花を見たことがある。
後にユニヴェールの至宝と呼ばれる人。クォーツのジャックエースだった人。そして今は――。
希佐は止まっていた足に気づき、無理矢理踏み出す。
しかし、すぐまた立ち止まった。
「……あ」
フミというアルジャンヌを前に、戦っていたロードナイト。
だったら、と思ったのだ。
継希がジャックエースだった時代のオニキスは、一体どんな目で継希を見ていたのだろうと。
「ジャックエース……。そうだ、開……」
昨日、オニキスでの稽古が終わって帰ってきたクォーツのジャック生たち。
もしかすると、彼らも、ロードナイトと同じような問題が起きているのではないだろうか。
もし、そうだとしたら――。
「……しかし根地先輩は、とんでもない役をオニキスに任せたものだな」
しっかり筋肉のついた登一の太い手足は、見た目に反して驚くほど柔らかくしなる。
「あまり引きずられないようにした方がいいでしょうネェ。これはあくまで町のセレモニー。本懐を忘れちゃいけませんヨ。ねぇ、アタル?」
天に向かって手を伸ばすダンテ指先は、爪の先まで踊って見える。
「そうだね。なにせ俺たちは『勝利のオニキス』だから」
加斎が強く床を踏み、高く舞い上がり、ピタリと止まる。
オニキスの床に、ぴったりと。
その床には――。
「はーはーはーはー……」
クォーツのジャック生たちが座りこんでいる。
彼らの大粒の汗が頬を伝って流れ落ち、オニキスの床を濡らした。
「着いてくるだけで精一杯のようだな、クォーツ生は」
「着いてくるだけガッツありますヨ。なにせ彼らは、我々とはタラント(才能)が違います」
オニキスですからね、僕たちは、とダンテがにっこり笑う。
そんな登一とダンテの会話を聞きながら、加斎はこの場で唯一動くクォーツ生を見た。
「大丈夫か? 昨日よりずっと良くなってる。あとは精度を上げればいい」
クォーツのジャックエースであるカイが、座りこむクォーツ生ジャック一人一人に声をかけてまわっている。
次に加斎は、稽古場の隅を見た。
そこには台本を片手に一人ブツブツ呟き続ける鳳がいる。ダンスの疲れもあるのだろうに、彼の意識は次に向かっている。
そしてもう一人。
「うぉーいっ!!」
バーンと勢いよく稽古場の扉を開けて登場したのは、加斎の同期、スズだった。
彼の額には汗が浮かんでいるが、座りこむクォーツ生の汗とは種類が違う。
「菓子、持って来た!」
スズの手にはチョコレートやグミ、ドリンクなどが大量に抱えられていた。
「お、おい、織巻いいのかよ……!」
座りこんでいたクォーツ生たちがお菓子まみれのスズの行動を諫めるように言う。
「海堂先輩がいいっつってました!」
それを受けて、海堂が「ああ、言った!」と応えた。
「クォーツにはクォーツのやり方があるでしょうしね」
加斎が言うと、他のオニキス生たちも「そうだな」と同意する。
「あざます! おっし、チョコとグミ、どっちがいいッスか!」
公然と許可が下り、スズがクォーツ生にお菓子を配り始めた。
「おい、織巻。お前、そんなもの、どこから持って来たんだ」
台本に集中していた鳳が呆れた様子で問う。
「クォーツの稽古場」
それを聞いて、この場にいたクォーツ生たちが吹き出した。
「お前! この短時間でどうやって!」
オニキスの稽古場からクォーツの稽古場まで、遠くはないが近くもない。
「え、走ってですけど」
加斎は、ダンス稽古が終わった途端、勢い良く飛び出していったスズの背中を思い出す。
クォーツ生たちは差し出されるお菓子に、いらねぇよ、食えねぇよと言いながら、笑っている。ほんの少し前までクォーツ生の間で流れていた悲壮感が払拭された。
「オニキスの分も持って来ました!」
どうりで量が多いと思った。
オニキス生たちからも笑いが漏れる。
「……」
加斎はその姿もしっかり観察する。
「よし、次は芝居の稽古だ!」
エネルギー補給が終わったところで、海堂が再び指示を出した。オニキス生たちは一瞬で引き締まり、クォーツ生たちには緊張が戻る。
そんな彼らを背に、カイがスッと前に出た。頼りがいのある背中。
――だが。
カイも内心、穏やかではないのだ。
「ではいくぞ! ……『“玉阪町開”になれと、あの役者どもは言っているのか』」
馬鹿らしい、と嘲笑うように笑うのは海堂――ではなく、開の武士筆頭、新田だ。
ここは開。
集まった武士らの空気は重い。
開の武士たちは苦境にあえいでいた。
仕えるべき主は消え、開の城は空となり、町はまるでハリボテのよう。
それでも開の武士として誇りを握りしめ生きる彼らに突きつけられたのは、玉阪との合併話。
しかも、町の名はこの一帯を治めてきた開の名前一択ではない。
元は開の殿様から土地を賜り住み着いた役者どもの町の名が、開の隣に並んでいる。
「……『しかし新田』」
カイ――ではなく、新田の旧友、警官のナラシバが新田を見る。
「『現状、有利なのは玉阪だ……。なにせ玉阪座の人間たちは江戸から明治に移る動乱の最中、時勢を読み当て国とのパイプを確保することに成功した』」
それだけじゃない、とナラシバは表情を暗くする。
「『玉阪の町人たちは潤沢な資金力を活かし、議会に多くの政治家を送り込んだ。それがまた玉阪の発展に繋がっている。だが開はどうだ?』」
ナラシバは現状に不安を隠せない。
「『開様が去ってからというものの、町は弱体化する一方だ。職を失った者も多く、多嘉良(たから)川で釣った魚や、大伊達山で採れた山菜を喰って飢えをしのぐ者もいる始末』」
「『え、旨いですよ!』」
そこでスズ――無職のリンが空気を読まずそんなことを言う。
ナラシバは「『黙ってろ!』」と叱りつけて「『だから新田……』」と言葉を続けようとした。
「カイ」
しかし、そこに新田はいない。
「俺を立てるな」
鞭を打つような強さで海堂が言う。
「……! だが」
「お前も強く雄々しい警官であれ!」
稽古場が一気に強張る。
――始まってしまった。
「だが、海堂。それでは役と役がぶつかり合ってしまう。開のリーダーは新田であるお前。そんなお前が開の武士としての強さ、たくましさ、そして魅力を全て背負うくらいでちょうど良い。脚本からもそう読みとれる……」
「カイ」
海堂の声に力がこもった。
「お前のクォーツでの役割は知っている。器として花を輝かせる、確かに立派な役目だ。しかし、それはあくまでクォーツでのこと」
ここはオニキスだ。海堂の目が語る。
「脚本を読んで、力強いリーダーが二人いても問題ないと解釈した。その方が開にふさわしいとも」
海堂の目に迷いはない。きっと彼には彼のビジョンがある。それでもカイは「だが」と声を上げ、海堂が「カイ」と制する。
「開の演出については、我々オニキスに任されている。……それに。ジャックを輝かせることに関しては、俺はユニヴェール一だと自負している」
その言葉はカイの胸に深く刺さった。激しい痛みを伴うほどに。
ユニヴェールにはそれぞれにクラス色があり、カイは自身が所属する、そして根地が作り出すクォーツの形を信じている。
信じているのだが。
今のクォーツの形によって、失われるものも、ある。
その懸念はずっとあった。いつか直面する問題だと。
それが今、眼前に突きつけられている。
カイは気づかれないようにスズを見た。
ああ、しまった、と後悔する。
スズが自分を見ていた。
カイは自分の思考をいったん全て排除して、入れ替える。
ここは、オニキスだ。
ここにおける自分の役目は――。
「……やっては、みる」
「ああ! では、初めから!」
稽古が再開した。カイが、ナラシバをまとう。しかし先程とは雰囲気から違った。
「『……現状、有利なのは玉阪だ』」
頼りなく新田の顔を窺っていたナラシバが、冷たい声色で現状を語る。
「『なにせ玉阪座の人間たちは……江戸から明治に移る動乱の最中、時勢を読み当て国とのパイプを確保することに成功した』」
ナラシバの目に怒りが宿る。小ずるく動き回る玉阪の人間を侮蔑するように。
「……うん、いいな」
「ああ。こっちの方が断然いい」
新しいナラシバを見て、オニキス生たちが頷きあう。
ただ、クォーツのジャック生たちは複雑だった。
ナラシバの部下警官として背後に立っている鳳も、カイの芝居に合わせながら表情は堅い。ただ、この場においてはカイの選択が正しいと鳳は思っている。他のクォーツ生もそうだろう。
「『多嘉良川で釣った魚や、大伊達山で採れた山菜を喰って飢えをしのぐ者もいる始末』」
ナラシバが、心底嘆くように言う。開の苦しい現状が、ひしひしと伝わってきた。
ところがだ。
「『え、旨いですよッ!!』」
その空気をぶち破る、リン――スズの言葉。
生徒たちが一瞬固まり、次いで、ぼふっと口を押さえる生徒が続出した。
笑いそうになったのだ。いや、笑っている生徒も多くいる。
カイが海堂の指示に従いオニキス色を強めていく中、スズはなぜか自分色を一層濃くした。
多嘉良川の魚も大伊達山の山菜もあんなに美味しいのになんでそんな酷いこと言うんですか、なにを恥じる必要があるんですか、むしろ贅沢なくらいじゃないですか、みんなも食べたらいいじゃないですか!
スズの一言から、そんな感情が見えてくる。
それが、悲壮感に満ちあふれる開の空気をぶち壊すのだ。
笑いをかみ殺したオニキス生が「あれは良いのでしょうか?」と海堂を見る。
海堂も思うところがあったのか「織巻」と名前を呼んだ。
「はい!」
スズが元気よく返事をする。海堂はスズをじっと見た。その目は決して甘くない。稽古場が一瞬でヒリつく。だがスズはその視線を真っ直ぐ受けとめた。山で山菜を採り、川で魚を釣るリンと一緒。「なにが悪い」とでも言うように。
「……いや。お前はそれでいい」
海堂の言葉に、スズが「はい」と当たり前のように返した。
加斎が深く笑う。
「おもしろ」
クォーツが直面している問題がある。
それは立花継希卒業後から続く、ジャックの圧倒的な『華』不足だ。
クォーツのジャックの多くは器気質。ジャックの隣にジャンヌの亡霊が見える。
クラス内ではそれでいいのだろうが、ジャックだけが集まったとき、華やかさが圧倒的に欠けるのだ。それがオニキスと並べば、霞んで消えてしまう。
クォーツはジャンヌに関しては全体的にレベルが高いが、ジャックにおいては他クラスと遜色なく戦える人間がたった三人しかいないのだ。
たとえ器だろうがジャックエースとして存在感がずば抜けて高いカイ。全てにおいて高水準をたたき出す鳳。
――そして。
「…………」
一年でありながら、クォーツにおけるジャックとしての華やかさを一身に担うスズの目は、燃え続けている。
気づけばスズを見ているオニキス生は少なくない。
それを悔しがりながらも、クォーツのジャック生たちは燃えるのだ。
カイはこういうとき、強く思うのだ。
才能ばかりのユニヴェールで、一年のときから選ばれる人間は、違うのだと。
「……ジャック生、帰ってこないな……」
希佐は時間を確認する。今は十九時、ここはクォーツ寮のホール。
玉阪組の稽古を見たことでジャックの状況が気になり彼らの帰りを待っていた希佐だが、未だ誰一人戻ってこない。
「あ、希佐ちゃん? お疲れ様」
そこに、世長が姿を見せた。
「あ、創ちゃん、お疲れ様。玉阪組の稽古、終わったの?」
「稽古自体は早めに終わって、自主稽古してたんだ。なにかしなきゃいけない気分になっちゃって」
希佐はロードナイトの空気を思い出す。世長がそういう気持ちに駆り立てられるのもよくよくわかった。
「緊張感……すごかったね」
「……だよね。息苦しいくらいで……。あれが、クラスを背負うってこと、なんだなぁ……。でも僕は……」
世長はそこで口を閉じる。
「ううん、ごめん。あれ、そういえば、開組は?」
希佐は「まだなんだ」と首を横に振った。世長が「そっか」と言って、大窓の先にあるユニヴェール校舎を見る。
「開組もオニキスとの稽古は終わって自主練してるのかもね」
希佐も追うように、点々と明かりがつくユニヴェール校舎を見た。
「自主練……ならダンスルームかな……」
オニキスと並ぶうえで、ダンスは必須。
「行ってみる?」
世長に聞かれ、希佐は「うん」と頷いた。
それから二人連れ立って、寮を出る。
校舎の外から窺うと、ダンスルームに明かりがついていた。中に入って、暗い廊下を進み、ドアの隙間から明かりが漏れるダンスルームの前で止まる。
(ジャックのみんな、いるかな……)
希佐は様子を窺うように、扉を少しだけ開く。
中をのぞくと、カイや鳳、クォーツのジャックたちがダンスの稽古をしていた。
(わ……っ!)
わずかに開けた隙間をそれ以上広げられなかったのは、ジャック生たちの鬼気迫る迫力に驚いたからだ。
「……もう一度初めからだ!」
「はい!」
カイの言葉に彼らは気合いを入れ直し、踊り出す。
希佐と世長はそっと扉を閉じた。立ち入れる雰囲気ではなかった。
でも、離れることもできなかった。
ダンスルームのすぐ側に立ち、言葉少なに耳を傾ける。
ダンスルームから聞こえる音楽に。ジャック生の息づかいまで聞こえてくるようだった。
「……立花に、世長?」
扉が開いたのは、二十分ほど過ぎた頃だ。
「カイさん! お疲れ様です」
「織巻を待っていたのか?」
希佐と世長が揃っているのを見てそう思ったのだろう。
ただ、希佐と世長は気づいていた。ここにスズはいない。
ほんの少し開いた隙間の先、彼はいなかったのだ。
「……ん? なんだ、立花に世長じゃないか……」
二人に気づいた鳳が露骨に嫌そうな顔をした。ただ、それ以上なにも言わなかったのはカイに配慮してだろう。
「俺たちはこれから寮に戻るが、ひとまず一緒に来るか?」
カイがそう尋ねてくる。
希佐になにか知りたいことがあるのだと察してくれたのかもしれない。
希佐は「お願いします」と頭を下げた。
ユニヴェール校舎を出ると、空気がひやりと冷たい。
「連日稽古されているんですね」
希佐の問いに、カイが「ああ」と頷く。
「オニキスは自身の見せ方を熟知したジャックが揃っている。そんなオニキス生と肩を並べるのは……なかなか労のいることでな」
「得意とするものが違うだけです!」
希佐たちからは距離を取っているが、話はしっかり聞いていた鳳がそう断言した。
「郷に入れば郷に従え、我々はオニキス流にここまで合わせているのですから、当然労はいります! まぁ、根地先輩に鍛えてもらったおかげで器用に立ち回っていますがね! 逆に、僕らのホームだったらオニキス生の労はこんなものじゃなかったでしょう!」
鳳がフンッ、と鼻を鳴らす。憤っているが、発言にはどこか温かみがあった。カイを庇っているようにも聞こえた。
鳳は入学してからずっと、ジャック生としてカイから指導を受けている。だから鳳は――いや、クォーツのジャックたちは、カイに対する特別な思いがあるのかもしれない。
それこそスズだって。
「あの……スズくんはどうしたんでしょうか?」
だからこそ、スズの不在には違和感があった。
鳳が「馬鹿だから高いところに登ってるんじゃないのか」と言う。
高いこところ――屋上か。
カイに色々話を聞きたいところだが、連日、ジャック生の指導をする彼にこれ以上、時間を割かせるのははばかられた。
それに、『玉阪町』の稽古が始まってから、全くといっていいほど話せていないスズのことも気になる。
今はスズの元へ。
希佐は「行こうか、創ちゃん」と声をかける。
「世長は玉阪側の状況を報告しろ」
ところが、鳳が命令するようにそう言った。
「え、あ」
戸惑う世長だったが、カイが「確かに、開側で手一杯で状況が把握できていない」と言う。世長もカイが言うならと思ったのだろう。
「わかりました。じゃあ、希佐ちゃん、行ってきて」
「わかった。それじゃあ、失礼します」
希佐はカイたちに頭を下げ、クォーツ寮に向かって駆けていった。
「……あの、スズくん、どうして稽古に参加してなかったんですか?」
希佐の姿が小さくなる中、世長はカイに尋ねる。
「正確に言うと、させなかった、だ。休ませている」
「え」
「織巻には相当な負担を強いてしまっているんだ」
鳳が「全くに忌々しい」とぼやく。
「それって、どういうことでしょうか……?」
「それは……。……」
カイは言い淀んだ。
世長に聞かせて良いのか、迷ったからだ。
いや、聞かせるべきではないと思ったからだ。
「織巻のバカがオニキスと張り合って無茶しているだけだ! このまま暴走して怪我でもしたら、こちらの立場がない!」
カイが迷っている間に、鳳がそう応えた。
言い方はとげとげしい。
だが、その言葉がどれほど角を取られ、削られ、丸みを帯びていることかカイは知っていた。
それから、世長から玉阪側の状況を聞き、感謝と共に別れたあと、カイは寮食で一人食事を取っていた鳳の席に座った。
「気を遣わせてすまなかったな」
「とんでもない! 睦実先輩が世長なんかに気を割く時間をとられるのが嫌だっただけです!」
カイと話すときの鳳は、いつも真面目で気遣いのできる後輩だ。
稽古に対しても常に熱心で、一人隠れて試行錯誤する姿も知っている。
もう少し周り――具体的に言えば世長だが。世長に優しくすることができれば、鳳を取り巻く環境は大きく変わるだろうが。
ただ、鳳は鳳で、抱えているものがある。
「……世長も、立花も、もっと考えた方がいいんです。新人公演で、なぜこの僕が主役に選ばれなかったかを。どうしていつも僕の上に織巻がいるのかを」
鳳が、視線を落とす。
「社交性とか、協調性とか、パッと目を引く華やかさとか、そんなものだけで選ばれるはずがないんですよ」
鳳の表情が幼く見えた。背伸びをやめた子どものように。
それが逆に、大人を感じさせる。
「あいつらは知らないんですよ」
鳳は、ジャックとして優れた体躯を持ち、恵まれた才能も、努力を怠らない芯も持っている。
だからこそ、誰よりも近い場所でスズを見ている、感じている、考えている。
なぜ、スズが選ばれているのかを。
なぜ、自分が選ばれないのかを。
「あいつは……、クォーツの」
鳳がなにか言いかけて、ぐっと歯を噛みしめた。
言葉という形で世に放てばそれはもう、一生消えることがない。
そしてそれが自分を縛る。
どんなに吐露して楽になりたくても。
「……あいつはバカです!!」
完全に、切り替えたようだ。
「鳳の警官……個人的に気に入っている」
「えっ、そ、そうですか?」
だからカイも流れを変える。
これは、実際伝えたかったことだ。
「ああ。立ち居振る舞いが廉直で、見栄えがいい。それに、ナラシバと気持ちを共にしてくれているのがわかる」
「……! ありがとうございます! ナラシバとの関係は、心がけているところです!」
鳳の表情が明るくなったことにホッとする。
同時に、歯がゆくも思った。
スズと一緒にいてやれない自分を。
夜の屋上はいつも吹く風が違う。
希佐は風で乱れる髪を押さえながら、暗い屋上の先を見た。
「えっと……あ」
屋上の隅、手すりにもたれかかって町の景色を眺めるスズ。希佐は「スズくん」と呼びかける。
「ん? あれ、立花。どしたどした」
スズはいつも通り、希佐に向き直る。
「あ、えっと……『玉阪町』、開は……スズくんはどうなってるかなと思って。ほら、全然話せてなかったから」
「え? あー……」
スズは苦笑する。
「オニキスがすっげーイライラしてる」
「えっ」
そんな話、カイも鳳もしていなかった。
「玉阪側は開に勝って名前を手に入れるだろ? そうなるとさ、当たり前だけど、開が玉阪に負ける。それがオニキスは嫌みてーだ。『勝利』のオニキスだもんな」
「あ……そっか……」
夏公演でもオニキスの公演を見て、彼らの勝利への情念を感じた。
「そのせいか、根地先輩の台本に抵抗あるっぽい。だからオニキス的演出? ってヤツが強めになってんだ。すげーカッコイイの、開の武士たち。オレだけはオレっぽいけど。まぁ、それは今、どうでもよくて」
脱線しそうになった話をスズが戻す。
「カッコイイのはいいなって思うんだ、オレ。でもさー、カッコイイ分、最後、名前が取られたときの絶望感がハンパねーんだよ。なんでこんなに頑張ってたのに……みたいなさ。見てて苦しくなるくらい」
玉阪も、開も、それぞれ名に誇りを持ち、ぶつかり、結果が出る。喜びと絶望が共存する。
オニキスは、『勝利』への執念が強い分、負けの演技に凄みが増すのかもしれない。
「オニキスがそういう演出をすると予想して、根地先輩は脚本を書いたのかな……。より、生き様がリアルになるように、って」
希佐は、新人公演、夏公演で見てきた根地の姿を思い出す。
最高の舞台を作るためなら、どんな手段も辞さない根地の姿を。
「かもしんない。かもしんない、けど……。オレはなーんか気になっちまうんだよなぁ……」
「なにが?」
スズが腕を組んでうーんと唸る。
「……これ、見て楽しいかなって」
「え……」
なにげない言葉だが、急に視界が広がるのを感じた。
演じる自分たち。そして、見てくれるたくさんの人。
「これがユニヴェールの舞台なら違ってくるんだけど、式典に来る人は、どうなんだろ」
希佐は「式典……」と呟く。
「そういえば……モナさんが来るんだよ」
「ワークショップの?」
「うん。モナさん、記念式典に参加したくて、毎年毎年抽選に参加してたって。倍率がすごいらしいんだ。だから今年やっと当たって、すごく喜んでた」
スズが「おわー、そうなのかぁ……!」と組んでいた手をほどく。
「嬉しいよなそりゃ! うん、嬉しいわ。絶対嬉しい。うん、うん。……」
スズが急に黙り込んだ。
「スズくん……?」
「オレ、自分がなんでもやもやしてたのかわかっちまった」
「えっ」
「いや、配役発表のときからずっと、もやもやもや~ってしてたんだわ。これ、このままじゃダメになっちまわねぇか……!? あー、でもなぁ、オレがこれ言ってもなぁ~!」
スズが頭を抱えのけぞる。
「……なにか言いにくいことがあるなら、私が言おうか?」
内容はわからない。ただ、大事なことのような気がする。
「えっ、立花が?」
「うん。スズくんがよければだけど」
「あ~……立花か言った方が、いいことかも」
スズがまた黙り込む。
「……いや、やっぱダメだ! これはオレだ!」
スズがぶんぶん首を横に振った。そして、うん、と大きく頷く。
「でも、とにかく、スッキリはした! ありがとな、立花! そういや、玉阪側はどうなってんの?」
「あ、それなら創ちゃんが……」
その後、世長と合流し、世長にとっては希佐、カイと鳳、そしてスズと、三度目の玉阪組説明が始まった。
スズはその間、腕を組んで黙り込んでいた。
【6】
「さぁさ、皆さん、合同稽古の日がやってきましたよぉ~!」
最初の合同稽古から数日をおいて、ユニヴェール劇場に再び三クラスが集まった。
通常であれば、前回に比べてよりよくなっているところ。
しかし、だ。
「玉阪側……というかロードナイト、ダンスどうしたの?」
ダンスの稽古が始まって一分も経たず、加斎から素朴で、かつ鋭い質問が上がる。
「うるっさいわね、それどころじゃなかったのよ!」
稀は反論するが、声に元気がない。
一方、歌に関しては、オニキスもきちんと稽古をしたのか前回よりぐっとレベルが上がっていた。
ただ、歌唱で玉阪側を支える、という点に難がある。
「そっちも歌唱、玉阪レベルじゃないじゃん! ジャックなんだからもっときちんとジャンヌのこと支えてよ!」
反撃に出る稀。
その言葉には加斎も思うところがあったようだ。
「ジャックだから、ジャンヌだから、……じゃなくて、支えたいと思える相手か、どうかじゃない?」
「なにそれ! 自分が認めた相手じゃなきゃ本気出せません~って言いたいのっ!?」
「そんなことは言ってないよ。でも、どうせなら支えたいと思いたいよね」
「言ってるじゃん! そうやってこっちのせいにする!」
苛立ちは怒りに成長する。ここ数日のストレスが相手に向かっているのかもしれない。
「大体オニキスは!」
「ロードナイトは」
気づけば加斎や稀に呼応して、他の生徒たちも声を上げ始めていた。
(これ、まずいんじゃ)
希佐は双方の様子を見て、戸惑う。
同時に、思っていた以上に彼らの中でこの舞台に対するフラストレーションがたまっていたことを知った。
飛びかう火花。
このままでは、爆発する。
「……おい、クロ」
「あ~、よろしくない、よろしくないねぇ!」
フミが鋭く根地に呼びかけ、海堂と司にも目配せした。
それぞれの組長が頷いて、クラスと止めようとする。
まさにそのときだった。
「はいっっっっっっ!!!!!!!!」
――まるで、花火。
スズの声が劇場内に響き渡った。
全員があっけにとられ、彼を見る。
スズは右手を大きく挙げていた。
「はい、赤いの!」
根地が即座にスズを指名する。スズが「あざます!!」と一層声を張り上げる。
「オレ、正直、ここにいる全員、舞台に立つ上で足りてないものがあると思います!」
思いがけない発言に、生徒たちが顔を見合わせる。
「え、なによ……全員? ここにいる全員?」
「歌とか、ダンスとか、芝居とか……じゃなくて?」
スズは稀と加斎を見て、「もっと大事なもんだ」と答える。
「なにを言い出すつもりだ、あいつ……」
玉阪側にいた白田が眉をひそめながらもじっとスズを見る。
世長も、「スズくん……」と彼を心配するように呟いた。
開側にいた鳳は「ハッ」と息をつく。
「だからあいつは嫌いだ」
その言葉を聞きながら、カイはスズを見守る。
(スズくん……)
これが屋上で言っていたことなのだろうか。
「……赤髪、聞かせてくれないか、お前の意見」
「ええ、興味があるわ」
海堂と司がそう言うと、オニキス生とロードナイト生も聞く体勢に入った。
クォーツ生もスズを見守る。
「今のみんなに足りないもの……それは」
スズは全員を見渡し、そして、言った。
「『玉阪の誕生日を祝おう』って気持ち!!」
それはずいぶんと幼稚に聞こえる言葉だった。
気が抜けた生徒も少なくない。
「玉阪の……」
「誕生日を祝おうって気持ち……?」
いやいや、と笑おうとした生徒たちに、スズは「持ってるか、その気持ち」と問う。直接聞かれると、みんな気まずく黙ってしまった。
そして振り返る。
その気持ちを持っていたか? と。
「『玉阪の日』はオレたちが住む玉阪市の誕生日。記念式典に来る人たちは、誕生日を祝いたい人ばっかりだ。なのにその舞台に立つオレたちが、学校のこと、クラスのこと、自分のことばっかでいいんですか!」
スズの指摘に「あ……」と声が漏れる生徒が生まれる。
「舞台に立たせて貰えるオレたちこそ、玉阪市、誕生日おめでとーって気持ちがなきゃダメなんじゃないですか!」
スズが自分の言葉で、自分の声で、必死に訴えかける。
「玉阪の日の主役は俺たちじゃない。玉阪市なんだ! 『玉阪町』なんだ! だから……」
スズの目がユニヴェール劇場の舞台を見すえ、そしてもう一度、生徒たちを見た。
「もっと祝う気持ちを持つべき! ……だと、オレは思います!!」
荒くて、気持ちばかりが先走る演説だった。
「一理ある!」
しかし、海堂は真っ先にスズの言葉に呼応した。
「俺たちは少し、他のことに気をとられすぎていたかもしれない」
鶴のひと声とはこのことか。オニキス生たちが自分の行動を顧みる。
「で、でも……舞台に立つ上で、捨てられないものとかあるじゃん!」
稀がそうやって主張するのは、司がロードナイトを守るように歌っているからかも知れない。それを否定された気分になって嫌だったのだ。
「わかる!」
スズは頷いた。
「いや、わかられても! あんたが言い出したんでしょ!」
「オレだってそういうのあるし! ジャックエースになりたいとか、ジャックエースになりたいとか、ジャックエースになりたいとかな! でも、とにかく今は、色んなことが整ってないんじゃないかってオレは思うんだよ。それに、せっかくこうやってみんな集まって舞台できるんだから、いいものにしたいじゃん。いや、したいんです。そんで、見てくれる人が楽しんでくれたら、最高じゃないですか。せっかくの晴れの日なんですから!」
スズの言葉に、稀たちも黙る。
「根地! この件についてはしっかり持ち帰って考えたい!」
「珍しく同意見ね。少し方針を見直したいわ」
海堂と司の言葉に、根地は「承知の助!」とウィンクを決める。
「では解散!」
号令に、劇場内が一気にざわめいた。
「スズくん!」
「びっくりしたよ! 急に手を挙げるから……!」
開組の中にいたスズの元に、希佐と世長が駆け寄る。
「いやなんかもう、今言わないとだめじゃね? ってなって……」
「おい織巻」
白田も呆れ顔で歩みよってきた。
「織巻、お前な……」
「い、言っちゃだめだったスかね?」
「お前はどう思うの」
「でも、言っちゃったし」
「これだからお前は……。はー、急にクォーツが表舞台に上がっちゃったな」
オニキス対ロードナイトという構造が一気に崩れた。
「立てる舞台があるなら上がらないとね、そこは!」
割り込むように根地が現れる。
「……」
「あっ、なに白田くんその目つき! さては原因が僕にあると思っているね!」
自ら言うのは自覚があるからだろうか。
「だってそうでしょ。台本読んだときから思ってましたよ。これは揉めるぞ、って」
「いやー、そうだよね、あはは! 思ってた以上に揉めたよね、はははのは!!」
「……」
「ああ~、白田くんが白い目で僕を見てるよ~!」
どこまでもふざける根地だが、背後からフミが「クーロ?」と呼びかける。
「さすがに反省しないとダメだよね、僕も……」
根地が急に態度を改めた。白田が一層うんざり顔だ。
「織巻の言葉を聞いてハッとした生徒は多いと思うぞ」
カイがそう言うと、「ああ、いや、オレも立花から話を聞いて気づいたというか」と希佐を見る。
「え、私?」
「おう。玉阪の日、モナさん来るって言ってたじゃん。それで」
初耳だった生徒たちが「モナさんが?」と聞いてくる。
「あ、はい。抽選が当たったそうで、すごく喜んでいました」
「そうか……楽しみにしている人がいるんだね」
世長が噛みしめるように言う。
ただ、こういうときでも白田は冷静さを兼ね備えていた。
「……でも、ここからが大変だぞ。この公演、気持ちだけじゃ解決できない問題が多すぎる。誰かさんの脚本のせいで」
「おや、誰だろう……? いやでもまぁ、流れは変わるんじゃないかな。ほら」
根地が劇場内を指し示す。
そこにはオニキス生も、ロードナイト生もクラスごとに集まり、話し合っていた。
「前は早々にこの劇場から立ち去っていた彼らが、ここに腰を据えている。あのときに比べたら、ずっと舞台に近いよ」
