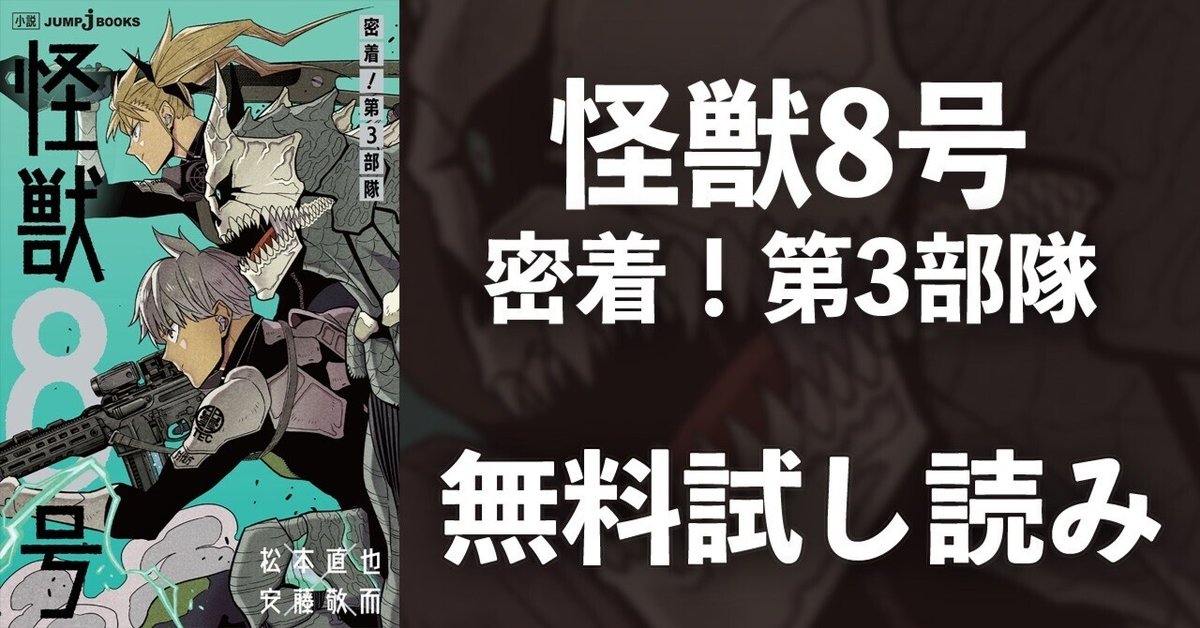
【試し読み】怪獣8号 密着!第3部隊
『怪獣8号 密着!第3部隊』発売を記念して、本編冒頭の試し読みを公開させていただきます。

あらすじ
少年ジャンプ+連載『怪獣8号』初のノベライズ作品が登場!
相模原での戦いの後、防衛隊第3部隊にドキュメンタリーの密着取材が入ることに。
カフカとレノが挑む過酷な障害走とは!? キコルは幻の専用武器を使っていた!?
刀にこだわる保科がミナにスカウトされた経緯とは!?
そして取材班の前でカフカは正体を隠し切ることができるのか――!?
小説でしか読めない物語全4編に松本直也先生描き下ろしピンナップと挿画も収録。
それでは物語をお楽しみください。
オープニング
時刻は午後九時を回っていた。車もまばらになってきた目抜き通りの歩道を、大勢の若者が連れ立って歩いていた。一見すれば大学生の集団に見える。だが、注意深く観察すればその身体にはがっしりと筋肉が付き、男も女も一様に鍛え抜いていることがわかる。
立川基地第3部隊――ここ立川市に拠点を構える防衛隊の新人たちだ。彼らの多くは十代から二十代とまだ初々しい。しかし、その列の最後尾近くを歩く男は、まるで学生たちを引率する教師然とした風貌だ。今年度の防衛隊における最高齢の新人合格者――日比野カフカ三十二歳は口元を押さえていた。顔は青く、その足はふらついている。
「うぷ……。気持ち悪っ……」
そんなカフカを支えているのは同僚の青年、市川レノだ。
「だから言ったんですよ先輩、飲みすぎだって」
「飯も美味かったからつい……」
「気に入ってくれたようで良かったよ」
爽やかに笑いながら答えたのは、出雲ハルイチ。対怪獣兵器を作る国内最大手会社の御曹司であり、今回の打ち上げの幹事を務めていた。
今から二週間ほど前、相模原に菌類系の超大型怪獣が出現した。カフカたち新人は初任務として、その討伐に当たった。しかし怪獣9号が襲来し、新人隊員の二人、レノと古橋伊春は負傷して入院。カフカたちは同期二人の退院を待ち、初任務の慰労会を開いたのだ。酒も入って大いに盛り上がり、隊員同士で率直な意見をぶつけ合うこともできた。
「おえぇ……明日まで尾を引くかもしれん……」
カフカは腹をさすりながら苦しそうに呻く。怪獣解体業者に勤めていたときは、安酒で晩酌するのが楽しみだった。再び防衛隊を目指すようになってからは酒や煙草を控えていたこともあり、随分と弱くなっていたようだ。
余韻が抜け切らず、赤い顔で楽しそうに話す隊員たち。彼らを見て、金色の髪の少女――四ノ宮キコルは「ふん」と鼻を鳴らす。
「まったく……揃いも揃って酔いすぎ。学生気分が抜けてないんじゃないの?」
キコルと仲の良い同期の水無瀬あかりは、窘めるように笑う。
「でもさ、きこるん。こんな機会は防衛隊に入ってからなかったんだし」
「あかり、それはそうかもしれないけど……」
「きこるんも二十歳になったら一緒にね」
気恥ずかしそうに顔を逸らすキコルを見てあかりが笑う。
「そう、水無瀬の言う通りや」
キコルたちの後ろから関西弁で声がかかる。細目で瘦身の男――防衛隊第3部隊副隊長、保科宗四郎。隣には丸眼鏡をかけた小柄なオペレーター、小此木が立っている。
「年数を経れば経るほど忙しくなるからな。同期皆でこんな騒げるのも今のうちだけや。楽しめるときに楽しんどき」
保科は、レノにもたれかかったカフカの背中を軽く小突く。
「なんやカフカ、返事もできてへんやんか。外周でも行っとくか?」
「ちょ、保科副隊長。さすがに今日くらいは勘弁してくださいよ……!」
「冗談や冗談。明日につけといたる」
「本気じゃないですか!」
「それくらい行っとき。日比野カフカ正隊員」
「……!」
正隊員、という言葉に胸が躍る。カフカは入隊試験でスーツの解放戦力が0%だったこともあり、これまで候補生扱いだった。しかし、相模原での功績が評価され、正隊員として認めると飲み会中に通達を受けていた。
「とはいえ、僕がしたのは事前通告。正式な辞令は亜白隊長からや」
「ミナから……」
「呼び捨てにすな」保科はカフカを小突く。「当たり前のことやけどな、それまではまだ候補生扱いや。辞令前なら取り消しもあり得るからな」
「気を付けなさいよ。そんなことになったら目も当てられないから」
「わかってる。心配してくれてありがとな、キコル」
「……別に。もしそうなったら、祝った私たちが馬鹿みたいでしょ」
カフカは静かに拳を握りしめる。
(でも、ようやくだ)
幼い時分より抱いていた防衛隊員になるという夢。一時は諦めかけたが、レノと出会い再び目指し始め、そして今日ついにその夢が叶った。
一同は駐屯地に向かい、橋を渡っていた。川上から一陣の夜風が吹く。風は湿気を帯びており、酒で火照った身体には少し蒸し暑い。
「……ん?」
カフカは思わず顔を顰めた。夜風には独特の臭気があった。これは――血と肉の生臭さだ。
「おい、あれ見ろよ!」
先を歩く伊春が河川敷を指さした。カフカたちは足を止め、その方向を見つめる。
河川敷の一角にはバリケードが張られていた。その中央に、全長二メートルほどの巨大魚が横たわっている。ただの魚ではない。肉食獣のようにたくましい四肢が生えていた。土手っ腹には風穴が開いており、ぴくりとも動かない。
「あれは……魚類系の怪獣ですね。もう売約済みのテープも貼られてる」
「みたいだな」カフカはレノの言葉に頷く。「これからの季節、死骸はすぐに腐るからな。特に魚類系ならなおさらだ」
魚類系怪獣はカフカも何度か解体経験がある。腐った怪獣の解体は思い返すだけでも地獄であり、鼻の奥にその臭いが蘇ってくるようだ。恐らくこの怪獣は明け方には解体され、通勤時間には影も形もないだろう。
「でも、来るときはなかったよな?」
「さきほど民間人から通報があったんや」カフカの問いに保科が答える。「別件で近くにいた斑鳩小隊に対処させた。フォルティチュードも小規模。死傷者は一人も出とらん」
「飲み会中ですか? いつの間にそんな――」
と、そこで気づく。カフカたち新人はジャージなどラフな格好で飲み会に臨んでいた。だが保科と小此木は、飲み会の最中も防衛隊スーツのままだった。
(万一のとき、いつでも出動できるようにしてたのか……!)
怪獣大国日本――この国では怪獣の出現はもはや日常だ。地中から、山から、川から、湖から、空から、怪獣は至るところから現れ、大きな被害を齎す。
その被害を防ぐのが、防衛隊員である。新人たちは実際に現場へ出たことで、防衛隊員としての強い自覚が芽生え始めていた。
もちろんカフカもその一人だ。河川敷に横たわる怪獣。今までのカフカは解体業者としてそれを片付ける側だったが、今は違う。
(そうだ……夢はまだ全然叶ってない。俺はスタートラインに立ったばかりなんだ)
カフカは静かに息を吐き出すと、レノから離れた。
「悪いな市川、もう酔いも醒めてきた」
「いや、ふらふらじゃないですか」
「心配するな。大丈夫……っとと!」
言われた直後、さっそくカフカは足がもつれて、後頭部から道路へ勢いよく転びそうになる。が、なんとか踏みとどまって上半身を起こした。
「うお、オッサン。今のよく耐えたな! 完全にすっ転んだと思ったぜ」
「はははっ! イナバウアー並みの仰け反りだったろ!」
どやって言うカフカだが、皆はぽかんとしている。
「なんだ、イナバウアーって?」と伊春。
「……さあ」とレノも首を傾げる。
「あ、知ってます。フィギュアスケートのやつですよね」とあかり。
「あれ? 皆、なんだその反応……?」
イナバウアーと言えば、カフカの世代では知らない者はほぼいない。しかし、皆の反応を見るにピンときていない人も多いようだ。
保科は腕を組み、神妙な様子で呟く。
「……カフカ、それはもう十代や二十代前半では知らない子もおるで」
「ええっ!?」
スマホで調べたキコルは「ふうん」と頷く。
「ずいぶん前ね。私が生まれた頃じゃない」
「生まれた頃!?」
まだ心持ちは若いカフカだったが、同期の皆とは度々ジェネレーションギャップを感じることがあった。そんなときは無性に悲しくなるのだった。
防衛隊の庁舎前にて、前に立つ保科が皆を見回す。
「ご苦労さん。明日からはいつも通り訓練が始まるからな。そこのオンオフのけじめしっかりつけること。出雲、今日のは交際費で落とすから、明日僕のとこに持ってき」
「ありがとうございました! お疲れ様です!」
カフカたちは保科に頭を下げる。
「うん。それと、明日からのテレビ取材もよろしくな。ほな」
最後、保科が何気なく発した言葉に隊員たちはぽかんとしてしまう。
「え、ちょ、ちょっと待ってください。……テレビ、ですか?」
聞き返したカフカに、保科は「ん?」と首を傾げた。
「なんや、連絡が行き渡ってないんか?」
「掲示はされていたはずですが……」横にいた小此木が眼鏡を押し上げ、補足した。「公共放送の特集です。駐屯地内に取材班が入り、皆さんに密着します」
「取材期間は今のところ五日間。その間、クルーが敷地内を歩いたり、訓練の様子を見に来たりする。ま、君らはいつも通り普通に朝礼をして、訓練をして、食事を摂って、就寝すればええ。別に気負う必要はない。……ま、一応世間に公表されるもんやからな。とんでもない醜態を晒した場合には、特別訓練でも受けてもらおうか」
にやりと不敵に笑う保科を見て、一同は身震いした。防衛隊の訓練は苛烈を極め、ふとしたことで追加トレーニングを課されてしまう。
解散となり、自室へ戻りながらカフカは思う。
(しかし、テレビか)
子供の頃は、テレビに映る防衛隊の活躍に胸を躍らせたものだ。しかし、大人になってからは「自分はなぜ向こう側にいないのだろう」という寂寞の思いを抱いていた。そんな自分が防衛隊としてテレビに出られるとすれば、喜ばしいことだ。
「よっしゃ、気合入れてくぞ!」
と一人ガッツポーズをしていると、後ろから声がかかった。
「先輩、ちょっといいですか?」
「ん、市川。どうした?」
皆の前では言い辛いことでもあるのだろうか。レノとカフカは廊下のベンチに腰かける。
「……先輩、さっき俺から離れて転びそうになったじゃないですか」
「ああ、それが?」
「ついうっかり、部分変身しそうになってましたよね」
「!」
どきり、とカフカの胸が飛び跳ねる。世間を騒がせている未討伐の怪獣8号――その正体は日比野カフカだ。彼は自らが怪獣に変身できることを隠しており、そのことを知る者はレノとキコルの二人だけだ。
「いや、なんのことだか……」
「な・っ・て・ま・し・た・よ・ね?」
レノの鋭い追及にカフカは目を泳がせる。なんと言って取り繕おうか考えるが、レノの真剣な眼差しを前にして噓は吐けなかった。
「ま、まあ一瞬な。少し酔ってたし反射的に。でもなんとかなった――」
「あ? なんとかなった?」
レノは大きく見開いた眼でぎょろりとカフカを睨みつける。
「ひっ! い、市川さん……!?」
「先ほどの副隊長の話を聞いてましたか? テレビですよ、テレビ。明日から! 万一カメラの前で正体がばれたらどうなるかわかってますか!?」
「な! 市川、お前、少し俺を舐めすぎだぞ! 俺だって変身訓練はしてるんだ! よっぽどのことがない限り変身しそうにはならん!」
「酔って変身しかけた人が言っても説得力ないですよ!」
「そうよ、日比野カフカ」
仁王立ちしたキコルがカフカを見つめていた。
「訓練場や市街地とはわけが違うのよ。カメラの前で変身されたら、さすがに私たちでも庇いきれない。正隊員剝奪どころじゃない。捕獲されて処理対象よ」
「わ、わかってる! ここのところの訓練で制御できるようになってきた。前みたいにうっかりクシャミで変身するなんてこともないしな!」
「あんた、うっかりクシャミで変身してたの!?」
「まあ、成り立てのときは」
へへ……と気恥ずかしそうに頭を搔くカフカを、キコルは心底呆れた目で見つめていた。
「レノ。こいつ、本当に大丈夫なの?」
「そう信じたい……」
「心配すんな市川! キコル!」カフカは声を張る。「ようやく正隊員として認められることになったんだ。そんなヘマはしない!」
「…………」
レノとキコルは訝しむように顔を見合わせる。
新米防衛隊員二十七名、そして候補生一人の波乱に満ちた取材が始まろうとしていた。
*この続きは製品版でお楽しみください。
読んでいただきありがとうございました。
以下のリンクより購入が可能です。
