
ゲームって性格出るよね「Refind Self: 性格診断ゲーム」
前から気になっていたゲームがSwitchに出てきたので、早速プレイしました。
アドベンチャーゲームを進めながら、あらゆる選択が性格判定のための材料になる。
性格はかなり細かく分類されるので、結果を見て、自分を見つめ直すこともできます。
そんな性格診断的側面もさることながら、私は物語がとても好きだなと思いました。
終末世界の、博士とロボットの悲しいお話です。
Refind Self: 性格診断ゲームとは
会話したり、調べたり、ミニゲームをしたり、気の向くままに行動していきます。
ゲームオーバーはなく、左上のハートの性格分析が100%になるとゲームクリアとなります。

些細な行動でもパーセンテージが溜まっていくので、早い人は早い、ゆっくりな人はゆっくり、といった感じで、プレイヤーによってクリアタイムは変わってきます。
1周でも性格診断はできますが、3周するとより細かい性格まで診断できます。
また、3周目でお話上エンディングを迎える感じなので、3周することをおすすめします。
私は3周してプレイ時間は3時間程度でした。
ゲームって性格出るよね〜っていうゲーム
どんな風にゲームを進めるのかって、けっこう人によって違っていて、だからこそ人と共有するのが楽しかったりしますよね。
「先にあそこ行くとこんなことがあったよ!」「こいつを仲間にするとこんなイベントがあった」「実は隠し要素があった」等々、自分でやっている時はお目にかからなかったもの、なかったことが、人と共有すると発見できたり。
このゲームはまさに、そんなことの連続なゲームでした。
そしてその結果が、性格診断として目に見える形になります。
ゲームは性格が出るな〜とは思っていましたが、それをゲームにしちゃったゲームというのは斬新。
ちなみに私は、最も象徴する性格は「聖職者」でした。

ゲーム内のキャラクターでも、あまりひどいことはしたくないし…。できればみんながハッピーになれればいいなと思って選択肢を選んでいたら、このようになりました。
逆に最も遠い性格は「哲学者」で、まああまり深く考えずに即断即決派なので、この結果なのかなと。ゲームだからってのもありますが。

全ての行動が各性格の増減に関わっていて、数値化されます。
このグラフの形も人によってけっこう違くて、人の結果を見るのも面白いです。
博士の願い、ロボットの願い
※ネタバレを含みます
プレイヤーが操作するロボット、うつわちゃんは、博士が最初に作ったEAI(感情で動くロボット)です。
幼少期にいじめられ、人間不信になって友達がいなかった博士は、自ら友達としてのロボットを作ります。
このEAIの技術は後に世界に広がり、AIと共存する世界へと変えていきますが、その弊害として人間の仕事が奪われたり、人間の価値の低下みたいな現象を引き起こし、ついにはEAIの破棄を政府が決めます。
勝手にEAIの技術を普及させ、不都合が生じたらEAIを破棄しろという理不尽な政府に博士は反抗し、戦います。
そして最終的に全てに絶望した博士は、ナノマシンを作り、自分諸共人類を滅ぼすことにします。
そんな博士の願いは、「うつわちゃんと一緒に幸せになる」ことでした。
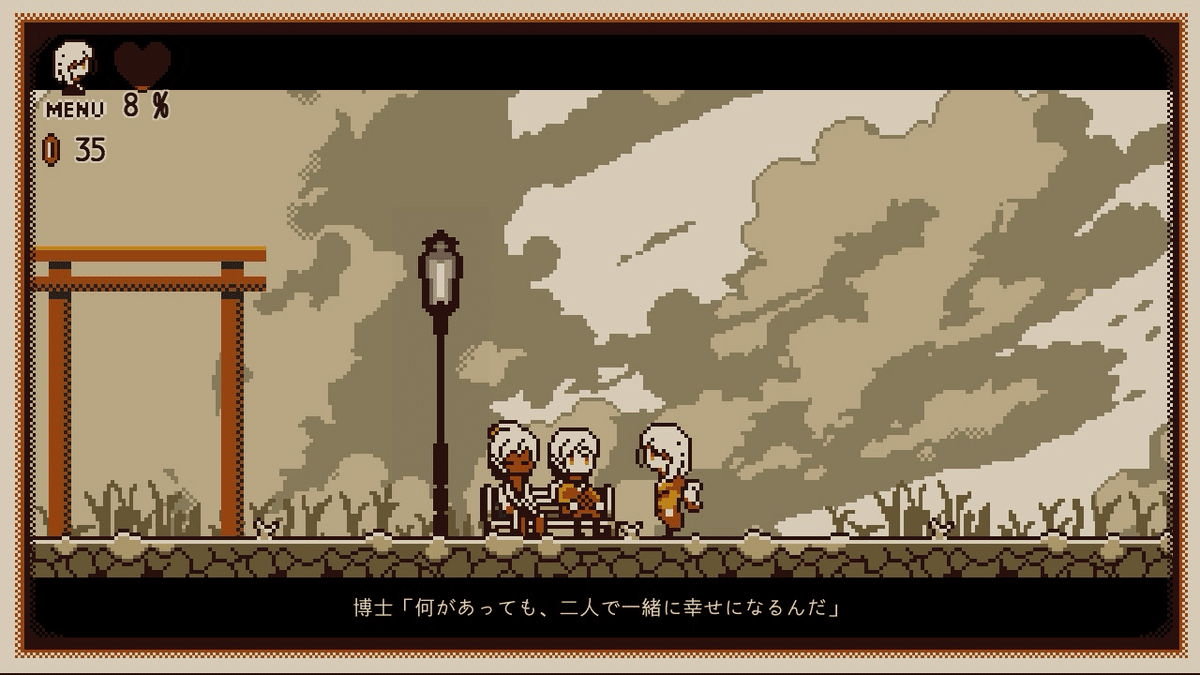
そのために、今の博士はナノマシンにより命を失いますが、羊に自分の遺伝子を残し、100年後に再生できるようにしました。
(仕組みはよくわからん)

しかし100年後に再生する博士には、今のうつわちゃんとの記憶がありません。
自分との記憶を持たない博士は、博士だといえるだろうか。
100年の時を1人で過ごし、その結果記憶を持たない博士に再会することは意味があるのか。
うつわちゃんは博士の意図に沿うことに疑問を感じ、博士の遺伝子を残した羊を破壊するという行動を取ります。そして自分も活動限界を迎えることで、死を迎えるという選択をします。
プレイヤーが性格診断として遊んだゲームは、博士にとっては「羊を破壊しない選択をするうつわちゃんの性格を見つける」ためのものでした。
そのほとんどは失敗に終わり、どんな性格にしても羊を破壊してしまいます。
そうならないようにするためには、もはや博士との記憶を消し、命令を忠実に守るようにするしかない。
最後は記憶を消去するかしないかの選択を迫られます。
これすっごい難しい選択…。
記憶を消したら、そもそもそれはうつわちゃんなのかというのもあるし、記憶があってもなくても悲しい結末になるし…。
たぶん正解はなくて、各プレイヤーがベストだと考える選択をするしかないんだなと。
最後まで選択を迫られるゲームでしたね…。
ゲーム中に見つかる博士の残した日記や、手紙、回想からは、博士の怒りを感じました。
自分のために作ったEAIを勝手に利用され、都合が悪くなれば破棄しろと言う政府への怒り。そもそも人間に対しての怒りを感じました。
怒りと絶望の中にいて、唯一救いだったのがうつわちゃんなのだなと思うと、彼らの辿る運命はあまりにも残酷ですね…。
悲しいけど、心に残るお話でした。
ゲームとして面白かった
ゲーム内ゲームも面白くて、お金を集めては遊んだりしてました。
ハイ&ロー7連勝はシンプルに嬉しかった。

他にも、屋上から飛び降りるのを何回もやってみたり、海岸線をひたすら歩いてみたり、思いつくことをただやってみるということができて楽しかったです。

ちなみに海岸線歩きは、5分超歩いたかな…?
スマホ片手にひたすらスティック倒してた笑
報酬として、999コインもらえるので、お金に困ってる人は5分かける価値はあるかな。
いろいろ試してみる、試行錯誤してみる。
ゲームのそういう面の楽しさが詰まったゲームでした。
おまけとして、多数派を当てるミニゲームもあったりして楽しかった。
ゲーマーたちがやってるとしたら、こっちかな…?とか考えながら。
ゲームの楽しさを再認識させてくれるゲームでした😌
いいなと思ったら応援しよう!

