
#全ジョーカーズ語れる説 Extra ⅩⅢ 時には龍に思いを馳せて
どうもShinです!
「モモキングの書」発売から早くも1週間が経過しました。
極めて完成度の高いこのデッキで皆さんもたくさん遊ばれたのではないでしょうか?
今回のExtraのテーマはずばり、《モモキング》とレクスターズの《メンデルスゾーン》との関係について語っていこうと思います!
1.《メンデルスゾーン》とは何か?




初登場はE2。今でこそドラゴン・主人公の代名詞ですが、その歴史はかなり異端な物。
カード名の元ネタはドイツの作曲家であるフェリックス・メンデルスゾーン。
どうして音楽家かというと、E2ラスボスであるおさむらい・VAN・おさむの使用種族キング・コマンド・ドラゴンが西洋の音楽家の名前を用いた物であるからです。


そう、《メンデルスゾーン》は最初、ヴィラン側のカードでした。
対して当時の主人公、切札勝太の主戦力は《鬼丸》を軸とする火闇のヒューマノイドにドラゴンとゼニスをチョイ足ししたデッキ。

正しく「最強のドラゴンを操る敵」として設定されたキャラの序盤を支えるカードだったのです。
この当時のカードデザインが目指すデッキとしての終着点は10〜13コスト程度を平均とする、超ターボ思考。



では強力なマナ加速の手段がなければダメなのか、という訳ではなく、コスト軽減やその他の手段に加えガチンコ・ジャッジによってそもそも構築段階の高コストが許容されている時代でした。



その結果、マナ加速と軽減の費用対効果がかなり平均化されてきた時期でした。


従来の主人公戦略の中に軽減とマナ加速を両立するようなカードは多数存在し、それらは併用することで平均的な出力を安定させることはできましたが、その出力先の質は保つ事ができませんでした。
また、軽減にせよマナ加速にせよそこまでゲームスピードを上げられず、比較的緩やかなゲームをしていたカード達でした。



しかし、インフレした超次元が従来の前提を覆します。
軽減クリーチャーのバトルゾーンへの維持、マナ加速その物のスピード低下が頻発するようになると、それ以前に軽減し切ってしまう、マナ加速し切ってしまう、 という戦術にシフトせざるを得なかったのです。
その結果少し全体のゲームスピードは早まりましたが、以前のように「時間がかかってすぐに負けてしまうドラゴンデッキ」ではなくなり、活躍が目立つようになったのです。
しかしほんの数年後。事態が急転します。
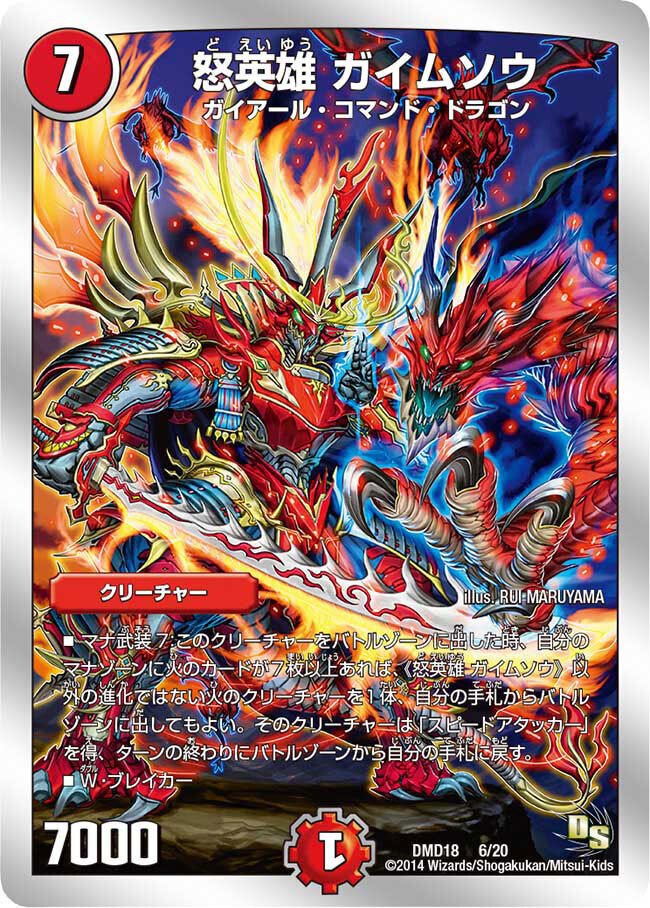


10マナも貯めなくても、別に勝てるようになったのです。
火・自然のドラゴンデッキが主人公の元に戻ったと共に、その一撃の重みがこれまでの比ではなくなりました。
更にそれから少しして。


5マナ域は、理論上の決着を意味し始めました。
ここからドラゴンデッキはこの5マナ域に収束するカードの出力を上げることによって、その出力の高さと安定性を絶対の物としていきます。



他のデッキの平均出力が5マナ域に追いつく頃には、ドラゴンデッキはそれを追い抜く形となったのです。
2.ジョーカーズの「ドラゴン」とは
2-1.「ドラゴン満載」に頼らない
肝心要のジョーカーズ、その物語は新章DMから超天編でジョーがドラゴンを求め、ドラゴンである《ジョラゴン》が生まれてからジョーの元を離れるまでを描いていました。
そして十王篇で新たなドラゴン、《モモキング》が生まれ、以後は彼によって物語が紡がれていきます。
実はジョーカーズには十王篇まで、極めて一貫したコンセプトが存在しています。
それは「サブとなるカードには、絶対にドラゴン種族を付けない」ということ。


これは、チームボンバー・チーム零の味方勢力が主役であるカード以外にもドラゴンを獲得した事と対照的です。




鬼札王国のデモニオは後年で背景ストーリー上、龍と異なる歴史のクリーチャーであり、ドラゴンと同位の存在であるということが明かされていますが、ジョーカーズに特別そういった事情はありません。
ジョーカーズはシリーズで初めて、「赤緑を軸にしながら、ドラゴンの爆発的なマナリソースをその戦術の基盤としない」という事に挑戦したのです。
それを成し遂げた要因は、ジョーカーズや魔導具、裁きの紋章等が築き上げてきた「視覚的に分かりやすいマークで、デッキとしての繋がりを示す」というデザインを、全文明的に広げた物が示した到達点でした。
新章DM以前のデュエル・マスターズは、カードテキストを広範的に把握したり、アニメ・漫画メディア等を通さなければ、ゼロからカードの繋がりを把握してデッキを組む、ということが難しいゲームでした。
これはカードゲームの選択的・開拓的楽しさを重視した遊び方を促進するものでしたが、デッキ構築のある種の「お手本」がインターネットを通してすぐに普及するようになるとあまり面白さを感じ得なくなるものでした。
そこに対し、ある程度のまとまりを持った中からの選択によって、他のゲームの「持ちキャラ」や「得意武器」のように戦術単位で選択できるようにしたデザインが先に述べた群であると言えるでしょう。
そうして、選択肢として10体のキングマスターを示し、そのカードの持つ文明でデッキを組めるようにした導線が張り巡らされているのが十王篇だと言えます。
この時、ただの2色のキングマスターのキャラ選択ではなく、プレイヤー自ら色を追加することで3色のデッキをオリジナルに作れるデザインが十王篇には仕込まれています。
マークだけでなく、視覚的な色のまとまりであっても構築しやすいという点が面白さを増したのです。
さて、このテーマと大きくぶつかるのが、「ドラゴン基盤」のような既存の強力なマナのアドバンテージを得る組み合わせです。
新しく出たカードでデッキを組みたいのに、その組み合わせは別に強くない……というのはユーザー体験として好ましいものではありません。
それに、仮にパックから出たカードが特定のカードとだけ強いシナジーを持っていても、色やチーム・王国を縦断してデッキを組む、という楽しさも損なわれてしまいます。
結論として出したのは、《勝熱英雄モモキング》というカード。

ドラゴンを用いない自然なマナカーブにおいて、既存のドラゴンフィニッシャーと変わらないかそれ以上の出力を出せるキリフダッシュ6というコスト設定、デッキが2色以上でなければその攻撃を止めることのできない一点突破の攻撃力を持つ1枚を作り、それを支えるカードとしてチーム切札、ジョーカーズの面々を作っていったのです。
このカードによって、他のデッキも2色以上の構築を求められ、多様な戦術の導線は他のチーム・王国が示している。
正に十王篇を形作ったカードデザインと言えるでしょう。
2-2.縦断的デザインが進化する
続く王来篇。こちらは更に「遊び」の要素を強めたようなゲームデザインとなりました。
さながら変身アイテムのようにカードを用い、主役のようなロールプレイとして多彩な切り札を繰り出すレクスターズと、とんでもない強さの合成怪獣をどんどん出して相手を圧倒する敵側のロールプレイのできるディスペクター。
これは、十王篇におけるカードの縦断的なデザインを2つの大きなカテゴリに分けることで成立しています。
ディスペクターは「3色の結び付き」。
強力なディスペクター・クリーチャーの持つ色に沿って、その配下たるディスタスを選んでいくと自然とデッキが組み上がるようになっています。



ササゲールはマナ加速を持たないクリーチャーのマナ加速手段として機能し、ここでも強力なマナ基盤に頼らなくともデッキ構築できることが示されています。
対するレクスターズは進化元の残るスター進化という能力を持ち、更に数年かけて作り上げてきた進化条件の緩和を文明を縦断するレクスターズ種族という形で生み出し、デッキ単位で自由に進化クリーチャーを使えるようになっています。
極端な例で言えば、パックを買ってレクスターズを抜き出し、色を合わせて組めばどんなカードでも使えます。


《パーリギリス》の上に《ゲラッチョ<チッチ.star>》を乗せる、なんてこともレクスターズによってしっかり再現できます。



このように性質を同じくしながら、進化条件が年々緩和されて行く様子が、上のカード達によって示されています。
ここで、王来篇以降の《モモキング》デザインに立ち返ると、以下のようになります
十王篇までの《モモキング》がデッキで一番強いカードというスタイルは踏襲
レクスターズは全てのスター進化の進化元になれる
という条件によって、レクスターズの全てのカードが理論上《モモキング》のサポートカードとなりました。
またこれまでの「ドラゴンはモモキングだけ」というスタイルも変化し、スター進化は過去のクリーチャーの力と共鳴することで起こる、というフレーバーを加味して、進化クリーチャー達のドラゴン種族が見えるようになってきました。


《モモキング》も当然ドラゴン。また、デュエル・マスターズの象徴たるカードはドラゴンが多いので、受け継ぐ力もドラゴン。


これまでのチーム切札基盤でももちろん強いのですが、チーム切札で必ず構築しなければならない……ということはありません。
結果、進化軸の【モモキング】は最適化の末、《メンデルスゾーン》軸に回帰したのでした。
3.「モモキングの書」が示した、レクスターズの到達点

新カード《鬼退治の心絵》。
このカードはマナと手札にアクセスできる3マナのカードながら、単色のドラゴンという特性を持ちます。
レクスターズ本来の戦術と、《メンデルスゾーン》から《王来英雄モモキングRX》を使う動きの両方を内包すべく作られたカードと言えるでしょう。
レクスターズの《モモキング》の戦術の始まりは、マナカーブの到達点として《モモキング》を配置し、それを支えるカードに既存のドラゴン基盤を用いるという既存の火自然の戦術にチーム切札的デザインを織り交ぜた物になっていました。
それに《蒼き守護神ドギラゴン閃》などを混ぜた【RX閃】というデッキタイプが成立。
結果的にはデッキ内の《モモキング》比率を高め、最終的に《禁断英雄モモキングダムX》と《未来王龍モモキングJO》の退化コンボを基盤とした【JO退化】が最強として君臨し殿堂入りするまでその形を保ち続けました。
結局《モモキング》をフル投入するデザインへ変化した為に、下級レクスターズの役割は薄くなってしまいました。
縦断的なデザインが故に、汎用的なカードを作るとバランスを崩しかねない。
その懸念に対しやや消極的なカードデザインをした結果が、既存カードと同じ土俵で戦わなければいけない際のカードパワーの相対的な低下でした。

王来篇は20周年のお祭り期間。結果として過去の強力なカードも目立つようになった事によってそれが顕著に現れることとなったのでした。
しかし、レクスターズは王道編に突入し、強力な基盤を多数獲得。



《夢双英雄モモキングDM》は、マナゾーンの進化クリーチャーをダイレクトに呼び出すことができるので、レクスターズにおけるマナ基盤の強化は必然とも言えます。
こうして、時を経て求めていたカードデザインに辿り着いた《モモキング》の、レクスターズの夢は終わることがないのでした。
4.終わりに
いかがでしたでしょうか?
今回は《メンデルスゾーン》によるデザインの革新、十王篇から王来篇におけるデザインの変化と、その中の《モモキング》の変化、そして王道編が獲得したレクスターズの夢について語って参りました。
さて、本シリーズの本編、#全ジョーカーズ語れる説 では、週に3回ジョーカーズ1枚について深く語っています!
という訳で来週のジョーカーズはこちら!



月曜日:《ジョット・ガン・ジョラゴン》
水曜日:《熊四駆べアシガラ》
金曜日:《ジョルネード・グランドライン》
の3枚!
是非とも来週からの本編もよろしくお願いします!
それではまた次回!お相手はShinでした!
〜これまでのジョーカーズ〜
〜感想・要望用質問箱〜
