【COTEN RADIO まとめ】障害の歴史 第6回 『その主張、異議あり!』優生学を批判する遺伝学者たちに引き継がれしダーウィンの情熱
今回は以下の動画についてのまとめになります。
前回の記事はこちら:
優生学への異議――遺伝学者たちの批判が示すもの
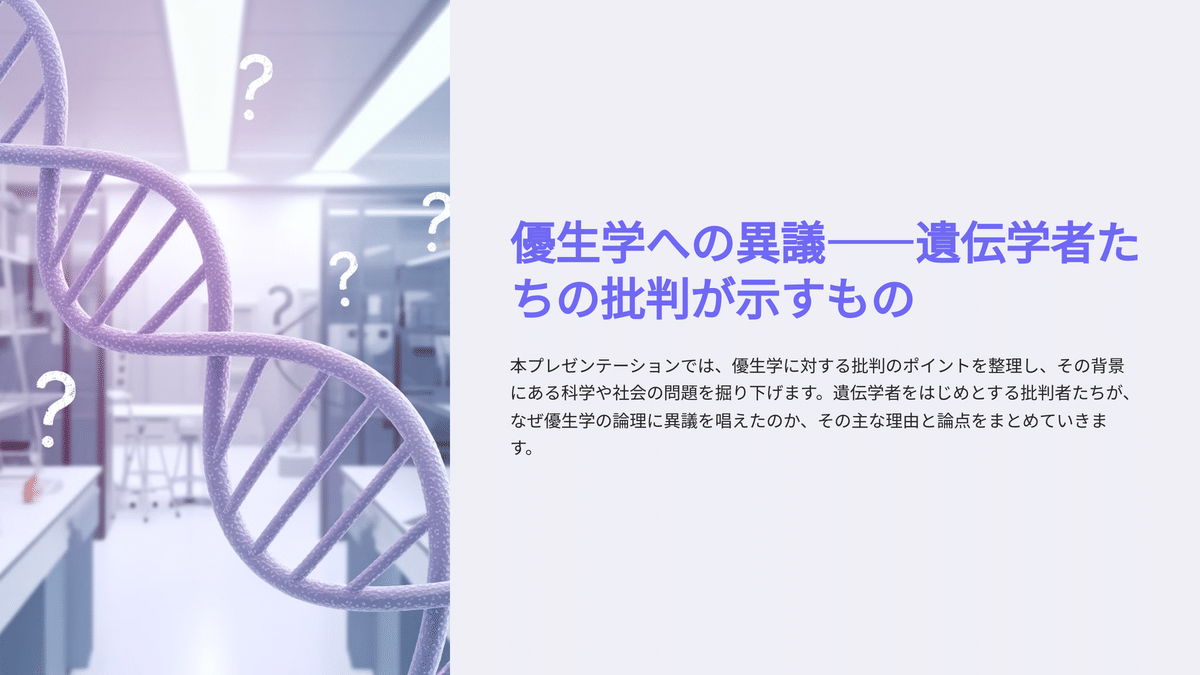
以下では、前回までに取り上げた優生学に対する批判のポイントを整理しつつ、その背景にある科学や社会の問題を掘り下げます。遺伝学者をはじめとする批判者たちは、なぜ優生学の論理に異議を唱えたのか。その主な理由と論点をまとめます。
なぜ優生学は批判されたのか

前回までに、優生学はダーウィンの進化論の誤読から生まれた「科学」を装う思想であることや、各国で強制断種や中絶を正当化する手段として実行されたことを見てきました。しかし、実はその優生学の台頭と同時期、1930年代にはすでに批判する学者たちが現れていました。
遺伝学者ドブジャンスキーの三つの批判
代表的な批判者として、ソ連(当時は帝政ロシア期のウクライナ生まれ)出身でアメリカに移民した遺伝学者テオドシウス・ドブジャンスキーが挙げられます。彼はダーウィンの自然選択説をさらに発展させた“ネオ・ダーウィニズム”の構築に貢献した人物ですが、優生学的な主張にははっきり異議を唱えました。以下、ドブジャンスキーによる代表的な三つの指摘を見てみます。
自然界の遺伝的多様性は「普通の状態」
優生学者は「優れた遺伝子」だけを残し、「劣った遺伝子」を排除すべきだと主張します。しかし、ドブジャンスキーによれば、生物界では多種多様な遺伝が「通常の姿」であり、ある程度の“遺伝的揺らぎ”こそが進化を支える重要な蓄えだといいます。
多様性は不利より有利が多い: 多彩な遺伝子がないと、生物は変化に柔軟に対応できず、最終的に進化力を失ってしまう。
唯一の良さなど存在しない: 優生学がいう「これが優れた遺伝だ」という考え方は、生物界の現実とは噛み合わない。
突然変異は制御不可能
優生学的には「遺伝形質をコントロールすれば目的の方向へ人類を改良できる」と捉えがちです。しかし、ドブジャンスキーは変異そのものがランダムであり、有利・不利の判断は環境と相互作用で決まると指摘します。
ある変異(例えば毛色が白くなる、首が伸びるなど)が有利かどうかは、現行の環境次第で変わる。
変異は“一つの遺伝子のスイッチ”で生じるわけでなく、複数要因が複雑に絡み合うため、狙って特定の形質を固定することは不可能に近い。
複雑な遺伝と環境の影響
優生学者が狙う「知能・道徳性・美しさ・身長」などは、単一遺伝子で説明できるほど単純ではないです。多くの遺伝子が複合的に作用し、さらに育つ環境が大きく影響します。
よって、特定の人間同士を掛け合わせたり、ある人々を排除したりしても、狙った形質を完全に制御するなど不可能です。
それでも無視された理由
ドブジャンスキーをはじめ、1930年代にはすでに優生学への批判が提出されていました。しかし強大な政治権力や社会的要請が優生学を支持していたため、批判は顧みられず、各国での強制断種・強制隔離が続いてしまいます。そこには、
社会ダーウィニズム: “進化=進歩”と取り違え、人間社会の優劣を固定しようとする発想。
国力強化の緊急性: 戦争や経済競争下で、弱いと見なされた個体を排除し国民の「質」を高めようとするニーズ。
統計学の誤用: IQテストや身体測定などを安易に「客観的指標」として用い、平均以下を“異常”と決めつける。
といった事情が絡み合っていました。
優生学の論理はどう否定されるか

前回の話で示したように、優生学は何重にも誤った前提を重ね、科学を装っていたといえます。まとめると以下の点が大きな否定理由になります。
ダーウィン進化論の誤用
ダーウィン自身は 「生物が目的的に進化している」とは言っておらず、進歩・優劣という概念を持ち込んでいないのです。ところが優生学者は「強い個体が生き残り、弱い個体は滅びる」図式を社会に当てはめてしまいました。
これは “自然淘汰” の観点からいっても単純すぎる解釈であり、そもそも自然界の生存は環境や偶然に左右されるもので、「絶対的に優れた形質」を残すようなストーリーは存在しません。
社会問題を遺伝で片付けるメディカリゼーション
貧困や犯罪、知的障害などの複雑な要素を「遺伝が原因」と決めつける発想も誤りです。こうした社会的課題を医学的理由にすり替えるのをメディカリゼーションと呼び、そこには環境要因を無視した単純な論理が潜んでいます。
実際には、黒人コミュニティが貧困なのは歴史的な人種差別が原因だったり、障害者が生きづらいのは社会的バリアが大きいからだったりと、環境や社会構造の側に大きな責任がある場合が多いです。
科学を名乗る思想
優生学は“一見すると”科学に基づくように見えますが、実は社会・政治的ニーズを満たすための「思想」に過ぎないことがはっきりしています。
統計学や遺伝学の知見を都合よくつまみ食いし、結婚や出産など人権に直接関わる問題まで国家が介入することを正当化してきました。その背景には
国力の拡大や福祉コストの抑制を狙う政治的圧力
遺伝学の発展途上段階で生じた過度な単純化
国民国家間の競争意識
などが複合的に絡んでいます。
生きる上での人権への軽視
優生学的政策を実行すると、障害者や特定のコミュニティが生きる価値を否定されることになります。人間が、人間の命を安易に序列化して切り捨ててよいのかという倫理問題が大きく横たわります。
実際にナチス・ドイツのT4作戦は安楽死と称した大量殺害を行い、アメリカや北欧各国では強制断種が数万件規模で行われました。日本でも「優生保護法」によって1万6000件以上の強制不妊手術が行われた事実を見れば、人権軽視がどれだけ広がっていたかが分かります。
現代への問い:出生前診断と優生学の影

こうした優生学への批判が学問的にも社会的にも確立している一方で、現代でも“似た論理”が形を変えて残っている可能性があります。その一例として、障害の有無を判定できる出生前診断が挙げられます。
出生前診断がはらむ問題
高度な診断技術により、胎児の遺伝的障害の可能性が早期に分かるようになりました。すると、
その情報を得て「中絶するかどうか」を決定するのは両親の自由。
しかし実際には社会的圧力や福祉不足などが影響し、「障害児を産むのは負担」という空気が生まれている可能性がある。
医学的な場面でも本人の意思決定が尊重される形が整っているかどうかは、まだ不十分な部分が多い。
こうした状況で「果たして、出生前診断は優生学的選別になってしまわないか」という批判や議論は絶えません。たとえ法的には障害の有無を理由とする中絶を認めなくても、現実には家庭の事情などで中絶が行われている場合があるのです。
個人の自由 vs. 社会的責任
この問題は単に「中絶が良い悪い」の二元論では片づきません。
福祉体制や社会の理解が充実しないままに「障害児を育てる自由」と「中絶する自由」を提示されても、実質的にはどちらにもリスクがあります。
「障害を排除するのは不当だ」と主張して強制的に出産を義務づけるのも、また別の人権問題を引き起こすかもしれません。
優生学が散々に否定された今でも、出生前診断をめぐる意思決定が優生学的思考から完全に自由であるとは言い切れないのが現状です。
まとめ:科学の衣をまとった思想を見抜くために

優生学に対する批判は1930年代にはすでに提示されていた。
ダーウィンの進化論を誤用し、「優れた遺伝子」を選べば社会が進歩すると断言した優生学者への反論として、遺伝子の複雑性や環境との相互作用が挙げられた。
それでも当時は政治や社会の要請(戦争・経済競争・福祉コスト)により、各国が強制不妊や障害者隔離を続行。科学とされながら、実際には社会的ニーズに動かされていた。
現代に残る出生前診断の問題などは、「障害者を生まない選択」といった優生学的思考と結びつく懸念がある。自己決定という概念だけでは社会的プレッシャーを解消できるわけではなく、十分な福祉や理解が必要とされる。
大きな問いは、「何をもって優れているとするのか? その基準は誰がどうやって決めるのか?」ということです。進歩や優劣の指標が本当に絶対的に存在するのかどうか。科学を名乗る発想に飛びついてしまわないよう、私たちは歴史を参照し、批判的な目を持って議論を続ける必要があるのです。
