
人生100年時代の安心住まい|長く住める価値の落ちない家(後編)
人生100年時代、マイホームを考えるひとつの指標は「長く住めるかどうか」。災害の多い日本で、長く安心して暮らせるだけでなく、第三者から見ても価値の落ちない家づくりは可能でしょうか?不動産コンサルティングの第一人者・長嶋修さんに聞きました。(後編)前編はこちら

住宅選びは土地選びから
ここまで建物の話をしてきましたが、不動産の価値はまず「土地」で決まります。立地が良ければ、同じ評価の建物でも不動産価値は高くなります。
土地選びをする場合、まず地域の都市計画がどうなっているか、将来的にどうなっていくかを確認すると良いでしょう。地域によっては、都市機能をひとつのエリアに密集させて、そのエリアの地価を10%上昇させる計画を立てているようなところもあります。
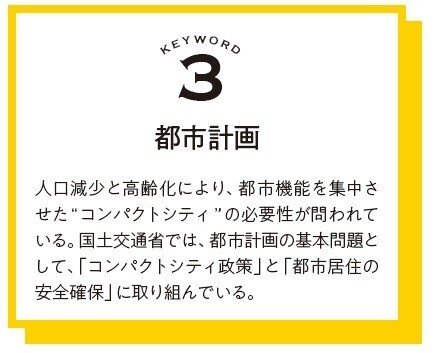
また、都市計画だけでなく「都市政策」も不動産の価値に直結します。良い例は、北海道の下川町です。北海道の中でも超過疎地域ですが、中心地は数年前から地価が下げ止まっています。
下川町は、昔から林業が盛んな町で、そのつながりからドイツに勉強に行っていたそうです。そこで、ドイツの省エネ政策に注目するようになり、「域内総生産(GRP)」つまり、地域単位でどうやって生産性を高めるか、という取り組みが始まりました。これは、国内でもとても珍しい例です。
省エネ性の少ない住宅や建物ばかりになってくると、電気を買うために地域からお金が出ていってしまいます。下川町では、バイオマスボイラーの開発などで、建物の省エネ性を地域全体で高めることによって、域内総生産(GRP)を高めていったそうです。
こうして、「面白い政策に取り組む町」ということで注目が集まり、住民が増え、税収が増えたことで、子育て支援政策を充実させるようになりました。するとさらに住民が増える、という好循環が生まれているわけです。
下川町の例から、自治体も、企業と同じ「経営感覚」が大事だということがわかります。自治体の経営によって、日々の暮らしだけでなく、不動産価値にも影響があるため、土地選びでは「自治体選び」も大切なのです。
もうひとつ、土地選びで重要なポイントは、当然のことながら「災害対策」です。今のところ日本では災害に強い家・土地の評価はないため、ますます個人での見極めが重要になります。
水害対策では、各地域のハザードマップが土地選びにも活用できます。例えば、都内の住宅地として人気のエリアでも、2メートル近く浸水する可能性のある場所もあります。しかし、同じ区内でも浸水の可能性のあるところとないところで、今のところ不動産価格に差はないのです。このようなリスクは、自分自身で避けていくしか方法がありません。
一方、地震対策では、「地盤の強さ」を確認したいところです。地盤の強さ・弱さは、国土地理院の地図で確認することができます。最近では、土地の「揺れやすさ」を測る微動探査機を国が推進しています。これまで地盤調査というと、土地の「硬さ」を測るボーリング調査などが一般的でした。しかし、地震で家がどうなるかは、土地の「硬さ」よりも「揺れやすさ」に影響されるものです。どんなに頑丈な家を建てても、土地が揺れやすいと話になりません。具体的な揺れやすさがわかるようになったことで、その土地に必要な耐震性を備えることができます。このような新たな調査方法も、積極的に利用されると良いでしょう。

ライフサイクルコストで考えよう
これまで家の常識と言われていた、「築30年で使えなくなる」あるいは「地震が多いから長持ちしない」ということは、すべて戦後の経済成長期の話です。建物は長持ちさせることができるし、価値が落ちない状況も他国で実現できています。
省エネ性・断熱性を最高水準のレベルで追求しておくことが、「長く住める」また「価値が落ちない」ことに直結するということをお伝えしてきましたが、こういった要件を満たした住宅は初期コストが10%から15%程度多くかかります。しかし、ここで投資した分は必ず報われます。
なぜ報われるか。理由のひとつは、健康寿命です。日本では年間、室内で亡くなる人が3万人程度と言われ、その大半はヒートショックです。死亡の数値に入っていなくても、寝たきりの人もたくさんいます。健康ということだけを考えても、省エネ性・断熱性を追求するのは十分見返りがあります。
また、目に見えるコストという点では、「生活コスト」が大きく変わります。高い省エネ性の家とそうでない家を比較してみると、エネルギー効率の違いは歴然で、逆に儲かる家をつくることも可能です。

そして何より、建物はめっぽう「水に弱い」ものです。省エネ性・断熱性の高い住宅は結露しないので、建物が長持ちします。
不動産投資の世界では常識になっていますが、住宅のコストは「イニシャルコスト」と「ライフサイクルコスト」の両方で考える必要があります。
一般ユーザーが家を建てる時には「少しでも安く、いいものを」と初期のイニシャルコストである建築費、建築坪単価などに目がいきがちです。ところが、当初の建築費は、建物の一生にかかるライフサイクルコストと比較すれば、小さなものです。
木造や鉄筋コンクリート造など、どのような造りでも、現代の技術で普通に設計・工事をして、点検メンテナンスをしていれば、100 年以上は住めます。子どもの世代まで残すことができる、または資産性があるということです。
初期投資のコストを削って30年程度で住めなくなるのと、生活コストの低い住宅に100 年以上住めるのと、どちらが良いかは明らかだと思います。高い基本性能を追求できる工務店を見極めて、価値ある住まいを残していきたいものです。
※本記事は雑誌「だん05」に掲載されています
★高断熱住宅専門誌「だん」についてはこちらをご覧ください
