
見えない人(短編)
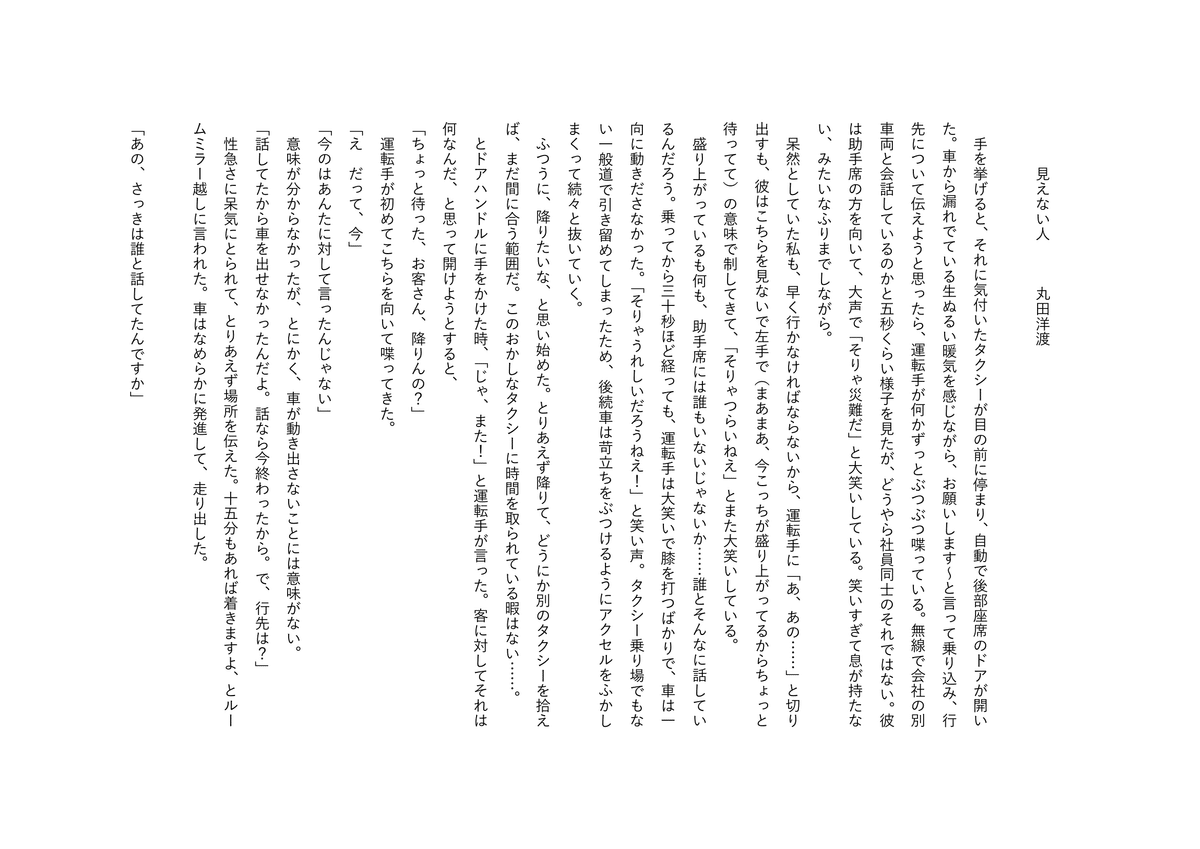




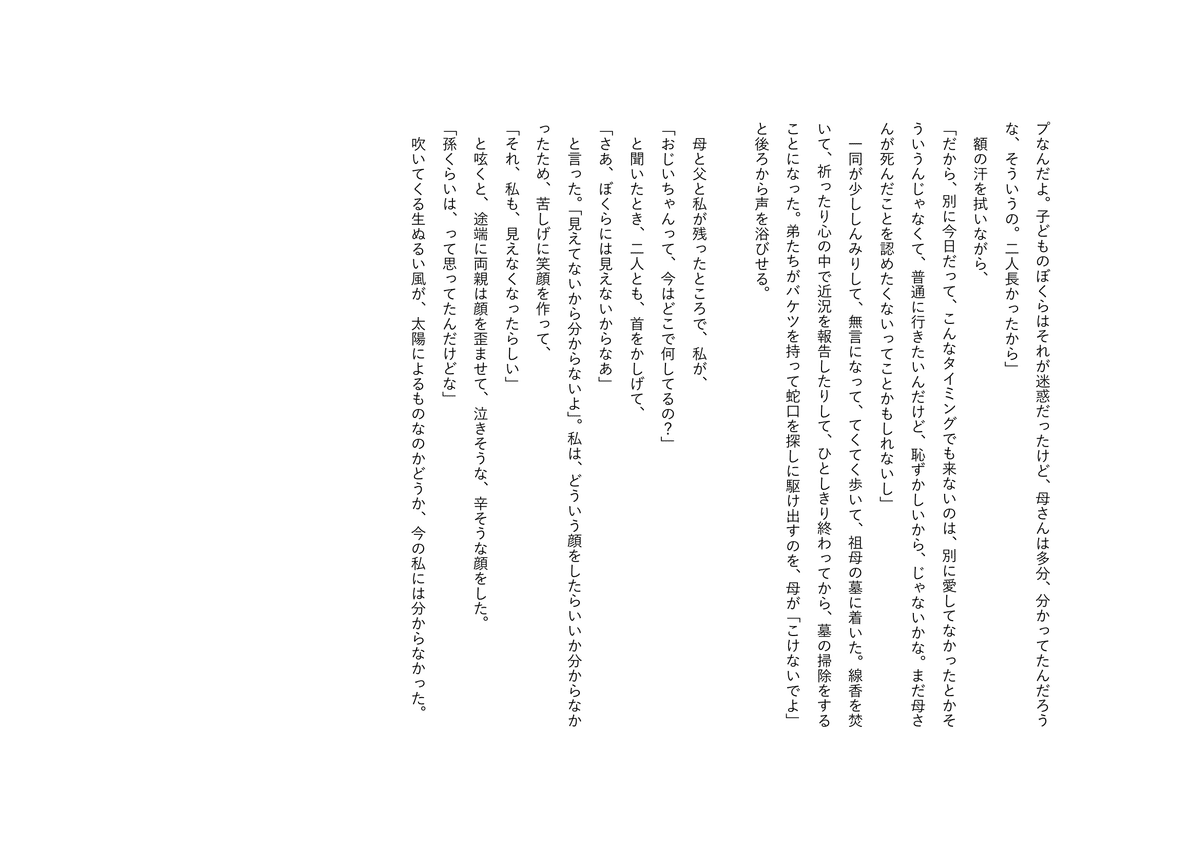
見えない人 丸田洋渡
手を挙げると、それに気付いたタクシーが目の前に停まり、自動で後部座席のドアが開いた。車から漏れでている生ぬるい暖気を感じながら、お願いします~と言って乗り込み、行先について伝えようと思ったら、運転手が何かずっとぶつぶつ喋っている。無線で会社の別車両と会話しているのかと五秒くらい様子を見たが、どうやら社員同士のそれではない。彼は助手席の方を向いて、大声で「そりゃ災難だ」と大笑いしている。笑いすぎて息が持たない、みたいなふりまでしながら。
呆然としていた私も、早く行かなければならないから、運転手に「あ、あの……」と切り出すも、彼はこちらを見ないで左手で(まあまあ、今こっちが盛り上がってるからちょっと待ってて)の意味で制してきて、「そりゃつらいねえ」とまた大笑いしている。
盛り上がっているも何も、助手席には誰もいないじゃないか……誰とそんなに話しているんだろう。乗ってから三十秒ほど経っても、運転手は大笑いで膝を打つばかりで、車は一向に動きださなかった。「そりゃうれしいだろうねえ!」と笑い声。タクシー乗り場でもない一般道で引き留めてしまったため、後続車は苛立ちをぶつけるようにアクセルをふかしまくって続々と抜いていく。
ふつうに、降りたいな、と思い始めた。とりあえず降りて、どうにか別のタクシーを拾えば、まだ間に合う範囲だ。このおかしなタクシーに時間を取られている暇はない……。
とドアハンドルに手をかけた時、「じゃ、また!」と運転手が言った。客に対してそれは何なんだ、と思って開けようとすると、
「ちょっと待った、お客さん、降りんの?」
運転手が初めてこちらを向いて喋ってきた。
「え だって、今」
「今のはあんたに対して言ったんじゃない」
意味が分からなかったが、とにかく、車が動き出さないことには意味がない。
「話してたから車を出せなかったんだよ。話なら今終わったから。で、行先は?」
性急さに呆気にとられて、とりあえず場所を伝えた。十五分もあれば着きますよ、とルームミラー越しに言われた。車はなめらかに発進して、走り出した。
「あの、さっきは誰と話してたんですか」
ルームミラー越しに運転手が睨みつけてくる。睨んでいるわけではないかもしれないが、目つきが悪いため普通にしていても睨んでいるように見えるタイプの目をしている。
「それを知ってどうにかなるもんなの? あんたの人生の何かが変わるの?」
普通に睨んでいるだけだった。やけに突っかかってくる言い方だ。
「いや、じゃあいいです」
運転手は一拍開けて、
「冗談冗談! 本気にされると困るなあ、お客さんにそんな言い方するわけないでしょ。聞いてくれて嬉しいですよ」
さっきとは少し違う笑顔で、笑っている。
「さっきのね、助手席の、見えてた?」
と運転手が言う。右ウインカーを出しながら交差点の中心にのろのろと近づいていく。
「誰か乗ってたんですか」
「あー」
やれやれ、の顔で、
「見えない人ね。でもそれがノーマルだから、落ち込むことは無いよ」
まるでこちらが落ち込んでいるかのような言い方で、そこは訂正したかった。
「さっきね、ここにおじいさんが乗ってたのよ。ああ、これは紛らわしいか、なんて説明すればいいかな」
右矢印の信号が出てからゆっくり曲がって、直線に乗ってから緩やかに加速した。
「あなたの前のお客さんは、おじいさんだったのよ。面白い人でね。たまに使ってくれるんだけど、その度に違う話をしてくれてね、なかなか話しがいのある人なの。最近の人はみんなスマホ見てばっかりでしょう、こっちとしては話さなくていいし運ぶだけだから楽っちゃ楽なんだけど。でも、ただ運送したくてこっちもタクシー運転手になったわけじゃないからね。楽しく話せる人、話すこと自体を許可してくれる人、っていうのは、ありがたい存在なのね。ああ、脱線したな。そのおじいさんがさっきまで乗ってて、で、あなたが手を振ったのが見えて、すぐに停めて、あなたを乗せたんだ」
もう一度信号で止まった。ここの道は五叉路になっていてやたら信号が長い。
「ちょっと待ってください。そのおじいさんは生きている人ですか? さっきの話だと、てっきり、幽霊なんだと思ってましたけど」
チッチッと舌で音を鳴らして、
「幽霊じゃあない。こっちは幽霊とは一言も言ってないよ。ただ、あんたが見えてなかったってだけだ。──ああ、あんたって言ってごめんね。つい、言っちゃうんだ。おじいさんは確かに生きてるし、さっきまで、確かに乗ってたよ。で、さっきの話を端折らずに言うと、あなたが手を振ってきたのが見えて、おじいさんが急に、ここで降りるのでいいよ、って言いだしたんだ。そっか、申し訳ないね、って言って、料金を貰って、おじいさんが降りていって、あなたが乗ってきた。でも、見えてなかったってことは、おじいさんが降りて行ったのも見えてなかったろ?」
そんな姿は見なかった。それに、そもそも、
「見ませんでしたし、そもそも、空車って書いてましたよね?」
「ああ、よく見てたね。本当は駄目なんだけど、そのおじいさんが乗ってきたときだけ、いつも空車で走るようにしてるんだ」
「何でですか」
「じゃないと終わらないからだよ」
ようやく信号が青になり、発進する。この目つきの悪い運転手は、運転スキルはかなり高いようで、車体の揺れや突っかかりが全く無い。
「話好きな人だからさ、一回乗せちゃったら、終わんないのよ。目的地に着いても、やっぱりあそこまで、って変えちゃったりするから。だから他のお客さんを口実に、降りてもらうしかなくなるのよ。こっちとしてはありがたいというか迷惑というか、でね。話自体は面白いから、俺にとってはありがたい方が上回ってるんだけど、他のドライバーからは評判悪くてね、見かけても乗せないって話だよ。酷いでしょ? おじいさんもそれを自覚してきちゃってさ、タクシーは俺を目掛けて乗ってくるのよ。ありがたいんだけどね」
苦笑い、みたいな顔で笑っている。この人は笑いの種類が多い。さすがプロだ、と思う。
「で、その人が降りて行ったあとは、誰と話してたんですか?」
「え?」
「そのおじいさんは降りて行ったんですよね。私には見えなかったけど。で、そこに私が乗り込んで、そのときにはまた誰かと話してたじゃないですか、助手席の人と」
「あんたも要領悪いなあ」
赤ちゃんに話しかける時みたいな甘い発声で、
「だから、さっきとおんなじおじいさんだって。体は降りて行ったけど、それ以外が残ってたんだよ」
何を言っているんだこの人……の私の顔を見て、
「まあ通じないか。そこの仕組みから説明してたら先に着いちゃうからさ、そんなことは気にしなくていいよ。あと七分もあれば着いちまうんだから。要は、体で降りて行って、心だけ置いていったわけだ。おじいさんも、あれだよ、あなたと一緒で、ふつうに後部座席に乗せたんだ。いっつも、体はうまく降りれるんだけど、心がね、ついていかないのよ。ほぼ毎回。で、分離したままってわけにもいかんでしょう、だから、心の方を、降りさせないといけない。それはいったいどうするかって言うと、話を聞いてやる、ってことなわけ」
信号を勢いよく左折する。曲がるべき信号はあと二つ、そこを越えるとあとは道なりに上っていけば着く。
「心はね、軽いらしいんです。そのくちの、他の人から聞いた話だけど。だから、前でもいいか、って助手席にふわんと移って来て、話の続きをするわけ。で、体が降りてるでしょう、だから口が無いのね。心が、直接話しかけてくる感じでね、なかなか味わえない感覚なのよ、これが。でね、皮肉なことに、おじいさん滑舌悪いから、心だけになった方が、はっきり聞き取れるのよ。口使わなくていいから。これはもう、心と心の問題だから、他の人には見えんわけで。あなたには見えてなくても、こっちはかなり明瞭なコミュニケーションを取り合ってたわけね。おじいさんが、話したいことをすべて話しきったら、盛り上がって終わったら、じゃあそろそろ降りるわ、って言って、そこの窓からタクシーの外にすり抜けて、置き去りにしてる外の体にすぽんと入って、普通に歩いて帰っていく。それが毎回のルーティーンでね。成仏、って言うと分かりやすいかな。でも死ぬわけじゃないから成仏とは違うんだけど。最初あなたが話しかけてくれたのに手で止めたのは、折角盛り上がってるのを盛り下げるわけにはいかなかったから。じゃないと、終わんないからね」
ずっと、饒舌に嘘をつかれ続けている感じで、あまりいい気分ではない。
「嘘だって思ってるでしょ」
「いや、思ってないですよ」
「いいのいいの、嘘ってことでも。これが嘘でも、本当でも、誰も傷つきはしないんだから。よく分からない常連客がいて、他の人からは見えにくいってだけで、別にお金もちゃんと払ってくれるし、こっちとしては本当に何でもいい。たまに次の人が乗ってきても話が全然終わらない時があって、そういうのは営業妨害だけど。言っとくけど今日のは早い方だから」
と、言われても……。信号を二つ曲がり終え、あとは道なりで、すぐに着く。見るからに電子マネーは対応していないようなタクシーだから、現金を準備しないといけない、と財布を取り出して見ていた。
「もうそろそろ着くから用意お願いします」
あ、そうそう、と言い、
「……ところで、お客さん、家族とかと待ち合わせしてるんですか?」
ルームミラー越しにこちらを見ている。
「はい、家族と」
「ちょうど一周忌でしょう?」
小銭を確かめる自分の指が止まった。何で知っているんだろう。
「あ、いいですいいです。プライバシーに関わるんでそれ以上はこっちも言わないから」
きつい坂を上がり切って、タクシーは霊園の小屋の前に停まった。
「じゃ、料金……ぴったりですね、ありがとうございます」
少し離れた向こうで、家族が集合しているのが見える。向こうも、こちらに気が付いたようで、来た来た、みたいな表情をしている。
私はドアから降りながら、首だけ車内に入れて、
「もしかして前の客のおじいさんって、」
運転手は遮るように頷いて、
「そうです。だから、あなたの話はよく聞いてましたよ」
じゃ、と手をあげて、タクシーは急発進で坂を降りて行った。客を乗せていない時のタクシーは速い。
「バスに乗ってなかったからもう来ないのかと思ってたけど」
母が、心配したのよ、みたいな顔をして言う。他の家族にも、タクシーを使うなんて金持ちになったとか、社会人なのに遅れてくるなんて、といじられながら、祖母の墓へとみんなで歩いて行った。
「おばあちゃんが死んでからもう一年かあ、早いねえ」
弟が汗でべたべたになったTシャツの首元を掴んであおりながら言う。
「結局、おじいちゃんは来なかったね」
「本当は来たいんだと思うけどな、父さんも」
父が石段を一段飛ばしで歩きながら笑った。
「父さんはかなりシャイだからな。思ってること言えないし、やりたいことをやれないタイプなんだよ。子どものぼくらはそれが迷惑だったけど、母さんは多分、分かってたんだろうな、そういうの。二人長かったから」
額の汗を拭いながら、
「だから、別に今日だって、こんなタイミングでも来ないのは、別に愛してなかったとかそういうんじゃなくて、普通に行きたいんだけど、恥ずかしいから、じゃないかな。まだ母さんが死んだことを認めたくないってことかもしれないし」
一同が少ししんみりして、無言になって、てくてく歩いて、祖母の墓に着いた。線香を焚いて、祈ったり心の中で近況を報告したりして、ひとしきり終わってから、墓の掃除をすることになった。弟たちがバケツを持って蛇口を探しに駆け出すのを、母が「こけないでよ」と後ろから声を浴びせる。
母と父と私が残ったところで、私が、
「おじいちゃんって、今はどこで何してるの?」
と聞いたとき、二人とも、首をかしげて、
「さあ、ぼくらには見えないからなあ」
と言った。「見えてないから分からないよ」。私は、どういう顔をしたらいいか分からなかったため、苦しげに笑顔を作って、
「それ、私も、見えなくなったらしい」
と呟くと、途端に両親は顔を歪ませて、泣きそうな、辛そうな顔をした。
「孫くらいは、って思ってたんだけどな」
吹いてくる生ぬるい風が、太陽によるものなのかどうか、今の私には分からなかった。
○
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
