
時間ギリギリに、刀剣博物館いってみた
皆さん、はじめましてYoutubeで自由気ままにブログをあげている単位ジュールです。
このブログでは、動画での撮影が禁止されているところやふとした出来事など、動画にしにくいものを載せていきます。
さてさて、、記念すべき1つ目の記事には、東京都墨田区横網に位置する『刀剣博物館』を訪れた際の感想を紹介します!!!
*刀については全くの素人のため、意図せず不快にさせてしまうことがあるかもしれません。その点ご理解いただき、お読みいただければ幸いです。
基本情報
【刀剣博物館】
刀剣博物館では、日本の刀剣や武具の展示をはじめ、刀剣文化の保存や普及活動、特別展や講座の開催も行われています。また、周辺には江戸東京博物館(※2024年10月24日時点で長期休館中)や相撲の聖地・両国国技館もあり、観光スポットとしてもおすすめです。
アクセス:
🚋最寄り駅のJR総武線「両国駅」西口から徒歩約7分、または都営大江戸線「両国駅」から徒歩約10分。
🚗首都高速6号向島線の駒形出口から約5分、7号小松川線の錦糸町出口から約15分。*駐車スペースが限られているため、周辺の有料駐車場の利用がおすすめ
開館時間:9:30 ~ 17:00 (入館は16:30まで)
休館日:毎週月曜日(祝日の場合開館、翌火曜日休館)・展示替期間・年末年始
通常展の入館料:
大人 1,000円(700円※)
会員 700円
学生(高校・大学・専門学校) 500円
中学生以下 無料
*詳しくは右下を参照に
現代刀職展
こんな時間に来るつもりはなかったんですよね。
あのですね、
着いたらもう16時だったんです。それに閉館時間が17時だったのを知らなかったんですよね。
みなさん、気を付けましょう🫠

エレベーターで3階まで上がり左のカウンターでチケットの確認をしてもらったら早速探検!
この1時間、無駄にはせぬぞ。
以下フォトギャラリー形式です。
トロフィー【高松宮記念賞】



作刀の部
刀剣そのものを制作する工程。たたら製鉄で作られた玉鋼を原料とし、鍛錬・素延べ・火造り・焼入れの工程を経て一振りの刀剣が出来上がる。鉄を鍛え、刀剣の姿へ成形し、地鉄や刀文といった模様を出す作業はまさに芸術である。
日本刀の製作工程は、目次:「1階」へ移動すべし⇉
玉鋼

ところで炭治郎、君は玉鋼の違いなんてわかったのか?
研磨の部





刀銘 ○○○○
➤国と人名
無銘
➤持ち主がいないもしくは記されていない
刀銘というのは名札みたいなものなのだろうか?
刀を落とした時に届けるためか、、?





ここでも日本の得物は突きや叩きよりも『斬る』をベースとしているのがわかるなぁ、かっけぇ
鐔

日本を象徴する二つの花を刻むってことは「日本」がテーマだったのか?
塗りつぶされていたり逆にくりぬかれたり
これって陰と陽を表している、、?
出品者コメントは専門的に感じてよくわかりませんでした。
彫金の部
刀装具の中で、主に鐔を中心とした金具の技量を審査する部門。様々な意匠の作品を、作家達はほぼ一年かけて制作し、成果を競う。小さな世界の種々の思いが詰まった作品には、まさに作家の生命が宿る。
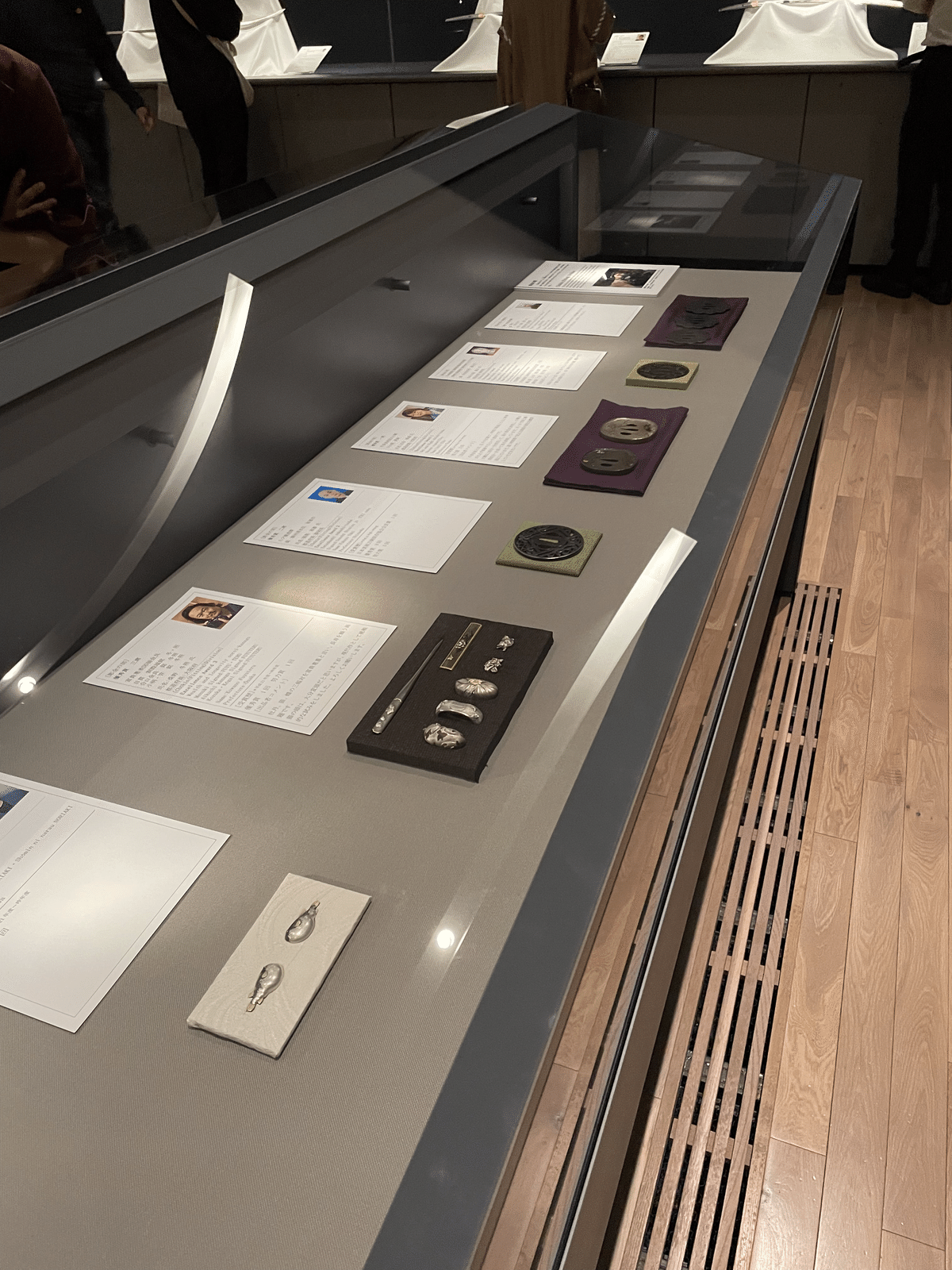
白鞘の部
刀身を保存するための鞘を白鞘という。古くは休め鞘とも言われたが、朴の木から白鞘を作る工程を競うため、設けられた部門。表面に出ない、掻き入れという工程に職人は人一倍神経を注ぐ。


柄前の部
刀装の柄の製作工程。大きく2工程に分かれる朴の木で作成した柄木の上に鮫皮(エイの皮)を巻き、さらにその上に組紐を主に菱形に巻いて、滑り止め効果を上げ手持ちを良くする工程のこと。エイは貴重品であったため、献上鮫として大名や将軍への贈答用とされた。


これってエイの皮のなごりなのかな


自分らの財力を誇るためか?
↓↓↓
非常に硬く水に強いため、メンテナンスは特に必要なく、汚れたら固く絞った布で優しく吹き上げる位で十分です。 『牛は30年、エイは100年』と言われるくらい、強度と耐久性があると言われております
私こそ金に目がくらんだ愚か者です。💣😇

、、なのか?
有識者求む
刀身彫の部
芸術性を高めるため刀身に彫を施す工程のこと。彫の画題は信仰心に基づいた神仏の姿や名号、あるいは植物などが多い。彫師は刀身の持つ潜在的力量を引き出し、刀剣自体の荘厳さをさらに高めるために、全力を傾注する。



木肌っていうのがいまいちわからない。
もっと近くでみれば、わかるかもしれない、、にしても、見惚れる彫り物だなぁ

↪そりゃこんな存在感を放つだろうな🤔
てか仏に短刀って、、逃げ若じゃね?え、非公式グッズ、、?

屋上

一階
入口はいってすぐ右に小さな展示室があります。刀についての基本的知識+詳しい説明や分かりやすい図が展示されていました!3階の展示室よりも先にここを見学すべきでした😫

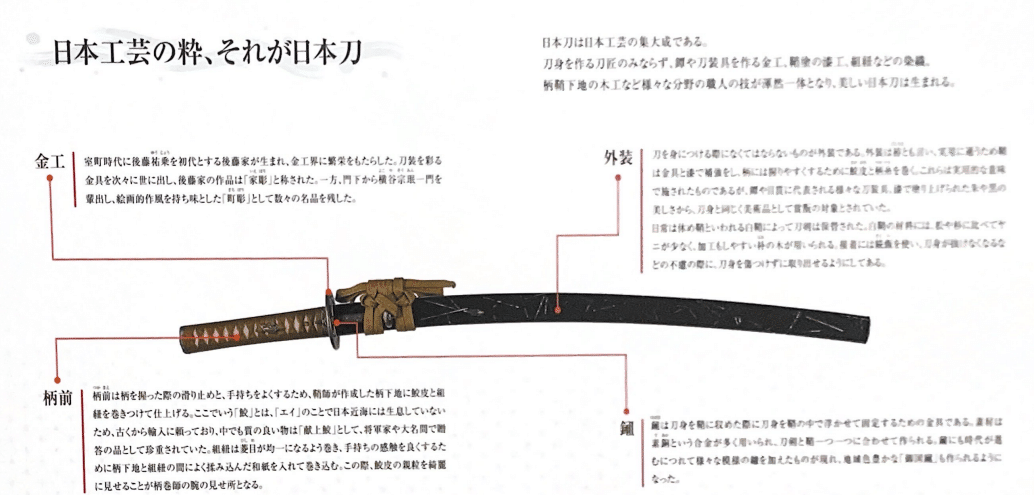

刀を制作するうえで自然も大事だったなんて、実感しがたいです、、





たたら製鉄の段階の実物が番号札とともに飾ってあります。

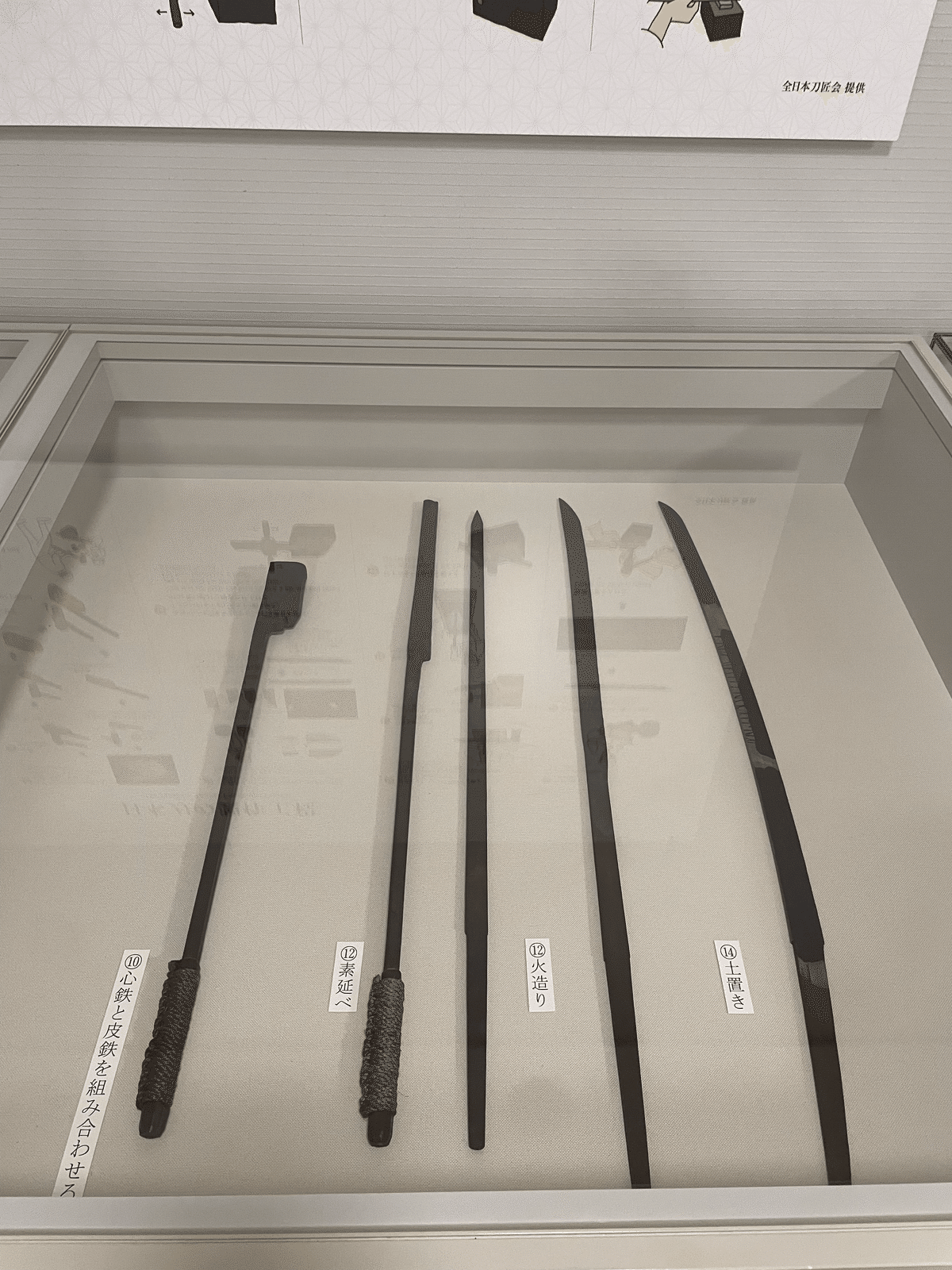

1キロを手に収めて思うままに振るのって意外と難しいのでは、?
もし刀をもったばかりの侍同士が戦ったら、、


時間がなかったので私は流し目でビデオを見ましたが。
今度こそ余裕をもってッッ

上映時間:50分!!
ここだけで1時間も過ごせますよ😁



以上。
