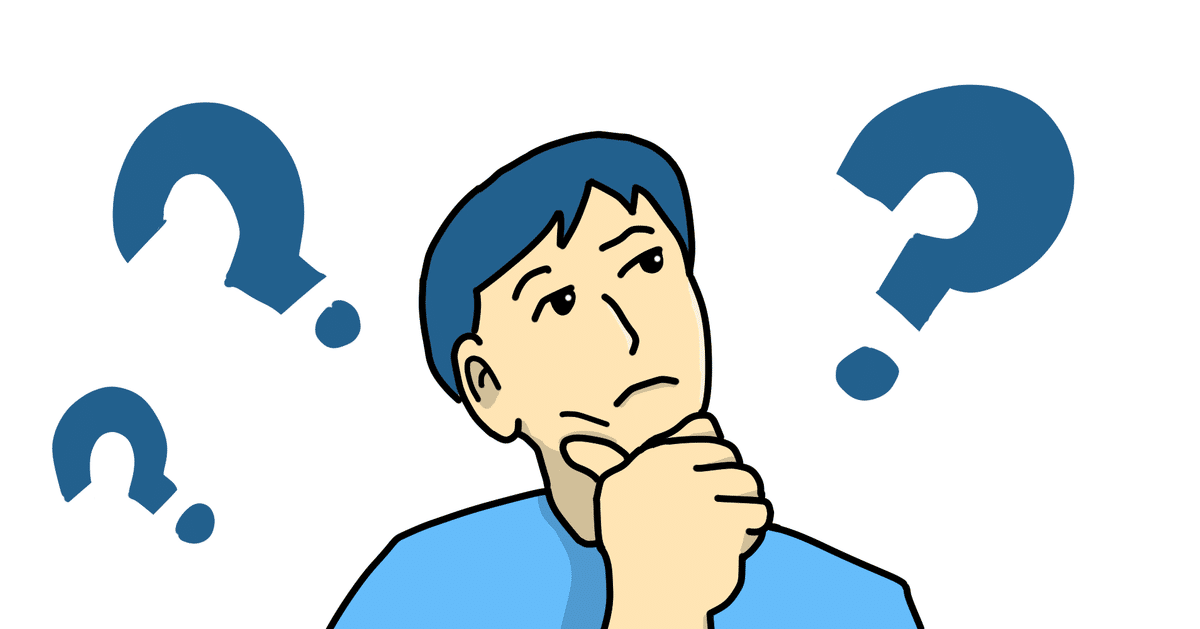
電力会社の発販分離について妄想してみた!(発電と小売の分離)
先日、自身のYouTubeで大学生向けのサンプル講義として「電力システム改革?」という動画を配信してみた!
ここで「送配電分離」のネタが出てくるのですが、視聴者から
発電ど小売はどうして分離しないんですか?
との質問があり、「いいとこついてくるなあ!+難しいところついてくるなあ!」と正直思いました。
ものすごくあっさり回答すると、「送配電しか分離を強制されていないから」にはなるのですが、視聴者の方は「なぜ送配電は分離させたのに、発電は分離させなかったのか?」が疑問の根っこにあると思うので上記回答では不十分なので少し妄想してみたいと思います!
<送配電分離 エネ庁HPより>https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/denryokugaskaikaku/souhaidenbunshaka.html
まずは、送配電分離の大元となる電力システム改革の目的を見てみましょう!
①電力の安定供給を確保すること
②電気料金を最大限抑制すること
③需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大すること
つまり、上記を実現する手段として「送配電分離」をするということですね。
では上記の目的と送配電分離はどうつながるのでしょうか?
送配電部門のミッションは、「安定供給」になるのでその部門だけが別会社になって安定供給第一に考えられるのでなんとなく①とのつながりはイメージできますよね?(電力小売の売上気にしながら安定供給を両方考えるのって結構矛盾する行動があったりするので)
②③については、どちらかというと「小売電気事業者」に直接関わってくることになりますね。ただ大手電力の小売部門と送配電部門が一緒だと内部で結託して、他の新電力の邪魔?(例えば、小売部門にだけ送配電接続で特別な対応をするとか・・・)みたいなことを仮にすると、新電力が競争上不利になって、「電力料金のコスト削減が難しく」なったり、「多用なサービス提供が難しく」なったりすることも考えられなくもないですね?
そこで「送配電分離」をして送配電業務を中立化することで、大手電力の小売部門も他の新電力と同じ立場で競争できる環境を外形的にも作っていこうという取り組みだと思います!
ここで法制度とか言われるのが「エッセンシャルファシリティ理論」というもので、事業をする上で不可欠な設備は、中立化して利用の公平を担保する仕組みにしようという考えですね(超ざっくり!)。
<エッセンシャルファシリティ理論 抜粋>
①電力会社が保有する送電網は発電市場や小売り市場における競争にとって必要不可欠であり,代替物も存在しないので,エッセンシャル・ファシリティ
②エッセンシャル・ファシリティの利用拒絶が違法であると判断されるのは,拒絶の目的が市場支配力の維持・拡大の意図を持っており,正当な理由がない場合に限定される。従って,送電線の容量に余裕がない場合,電力会社が利用している容量を削減したり,送電線の増設を行うことで,競争者のための容量を確保することはエッセンシャル・ファシリティの法理による義務の範囲外であるし,利用に際しての技術的要件を満たしていない場合なども利用を拒絶できる。
まあ、送配電網は「小売電気事業者の事業に必要不可欠」かつ「代替物存在しない!」ということで、「送配電分離」(手段はいろいろある中でかなり強い規制に落ち着いたのはまた別論点としてありますが)になったということですね!
ここで話を「発電分離」に戻しましょう!
大手電力の発電事業が「エッセンシャルファシリティ」に該当するか?
つまり、
「小売電気事業者の事業に必要不可欠」かつ「代替物存在しない!」
かが分離するかどうかの判断軸になりますね!
確かに、下記の発電所の所有ランキングを見ると、10電力会社+電源開発がほぼ多くの発電所を所有しており、「小売電気事業者の事業に必要不可欠」かつ「代替物存在しない!」ようにも見えますね?
ということで、おそらく程度の問題はあれ、「エッセンシャルファシリティ」的な要素がゼロではない感じなので、エネ庁さんもちゃんと対策しているんですよね!
つまり「代替手段をつくればいいんでしょ?」みたいな。
ということで
②電力卸市場による電力調達
の2つの「代替手段」を準備しているので、「発電分離」までしていないという考えもとれるかなあと。(実態はいろいろな政治的駆け引きもあるので一筋縄ではいきませんが、イメージとしては大筋近いと思います!)
まあここで、
「ほとんどの発電所を10電力会社が持っているんだから、常時バックアップの値段を高くしたり、電力卸市場に電気を出し渋れば邪魔できるじゃん!」
という意見も出てくるでしょう!そのためエネ庁もこの2つの代替手段に実効性をもたせるため
・常時バックアップの価格を監視
・電力卸市場へのある程度の電力入札要請(グロスビディングと言われてます)
という対策もとっています。
実は常時バックアップの後継(期待)として
ベースロード電源市場
も2019年に開設され、新電力がベース電源を調達できる選択肢も追加されています。
まあ「送配電分離」「発販分離」の議論も時代とともに変わってくる可能性は十分あるので注視してみるのも面白いと思います!
いいなと思ったら応援しよう!

