
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第2集その4『闇の向こう側へ』
リアンの生成した使い魔を、シン医師、アブロード医師、そしてエヴリン師長の監視として放ったその翌日は、リアン、カレンの二人には夜勤が割り当てられていて、朝から夜半まで非番であった。リアンは彼らの位置をつぶさに示し、またシン医師の動向を映像的に監視することのできる魔法地図を自分の携帯式光学魔術記録装置に移して、早朝から監視に余念がない。今のところ特別な変化はなく、睡眠中に記録した魔術記録を確認しても、この病院に秘密裏に魔術拡張された空間の入り口に関する情報は得られなかった。リアンは魔法地図について、初日に目にした、突き当りが全面鏡張りになっている廊下がよほど気になるのであろう、使い魔がそこに到達、あるいはそこで監視対象から引き離されるようなことのあった場合に、自分の端末にアラートが届くように入念に魔法地図に細工を施していた。
特段こうした電算に関する魔術装置の取り扱いに詳しいわけではないカレンはその見事な手際に舌を巻いていた。見つめるその濃紫の瞳の先で、リアンの美しい水色の瞳は一心不乱に不思議な魔術スクリプトのコードを記述している。

「これでいいのです。」
一段落したのか手を止めたリアンがそう言った。
「監視はうまくいきそうなの?」
「はいです。細工は流々なのですよ。とにかく3人の内の誰かが魔法拡張空間に侵入するか、あるいは使い魔が監視対象から引き離された場合に、私の端末に知らせが来るように設定したです。いずれの場面でも、そのポイントが拡張空間への入り口の座標であるということになるですよ。あとは、その侵入方法がわかればいいのですが、私の今の魔力では、3人を同時に映像的に監視することは難しいのです。ですから、シン医師が引っかかってくれることをまずは祈るのですよ。」
いつもは自信なげにしか話さないリアンが、今日は流暢でその声には熱がこもっていた。
「へぇ、あなたが魔術記録装置や魔術式電算装置に詳しいとは聞いていたけれど、ここまでとは思わなったわ。すごいわね。見直しました。」
カレンのその言葉を聞いて、リアンは照れくさそうに口元をゆがめながらも、その視線の真剣さを微塵も変えることはなかった。今もまっすぐに端末上の魔法地図に見入っている。
その時、カレンの端末にネクロマンサーからの文字通信があった。それによると、彼女は、今日は日勤で夜は非番なのだとのことである。また、彼女は、リアンが使い魔に施した光学的カモフラージュの見事さに驚いていた。基本的に脳外科のシン医師と職務を共にするネクロマンサーは、当然にしてシン医師の傍にいることが多いわけであり、彼を監視する使い魔の存在を知っている。しかし、その隠蔽具合は見事で、シン医師の背後にあるその不自然な光の揺らめきのことは、今のところ、シン医師や周りのスタッフ陣に気づかれている様子はないとのことであった。
朝食を済ませてから、リアンとカレンは日中の過ごし方を相談した。臨時職員として派遣されている彼女たちは、非番の時間帯も病院で過ごすより他にないわけであるが、しかしその間も職務に拘束されるということはなかった。カレンは、可能ならば患者やスタッフへの聞き込みを試みながら、病院全体を実際にその足で見て回ろうと、当然にしてリアンを誘ってみた。いつもなら、二人が別行動をとることなど基本的にあり得なかったが、その日のリアンは違っていて、一心不乱に端末上の魔法地図に見入りながらこう言った。
「申し訳ないですが、それはカレンにお任せするのですよ。この部屋以外で魔法地図を見るのは、何事かを病院側に悟られる危険がありますから、夜勤のための申し送りが始まる22時30分まで、ずっとここで監視をしているです。あと、シン医師を常時監視するのに魔力をかなり割く必要があるので、その意味でもできるだけここに留まって、せめて体力だけでも温存したいです。」
つい数か月前には、まだ自信がないからと『制御の魔帽』を手放さなかったリアンのその言葉は、カレンにとってとても意外であった。しかし、この局面ではリアンの監視能力が状況打開のための、おそらく唯一の可能性であることに間違いなく、そのまま彼女の言葉を受け容れた。
「何か要るものはある?」
カレンのその言葉にはじめてリアンは少しだけ彼女の方に視線を移して言った。
「真紅の雄牛と魔力回復薬がいくらか欲しいのですよ。」
「わかったわ。魔力回復薬はいいとして、真紅の雄牛はあんまりたくさん飲むと体に障りますよ。」
「大丈夫なのです!あれを飲むと翼が生えたように元気になれるです!」
「わかったわ。売店が開く時間になったら買ってくるから、とりあえず、これを渡しておきますね。」
そう言うと、カレンはベッドの上に座っているリアンの足元に魔力回復薬のアンプルを3本を置いた。それは急速性のものではなかったが、回復量の大きいもので、今日のリアンのよき助けになるであろう。そう思えた。

病院が患者の受け入れを始めるのは午前9時から、売店もそれと同時に開く。開き次第、何本か買ってきてやろう、カレンはそう思い定めながら時計を見やった。まもなく8時が来る。食事の時間だ。
「リアン、まもなく食事が配膳されてきます。魔法地図を一時的に隠してください。」
その言葉を聞いたリアンはハッとして時計を見た。
「わかったのですよ。秘密の管理は何より重要なのです。」
そう言って彼女は、端末をローブのポケットにしまった。
そんなことをしているうちに、看護助手の方が二人に朝食を運んできてくれた。待機場所であるとはいえ、もともと病室であった場所で、病院のベッドに腰かけて、病院の食事を食べるというのはどうにも慣れないものであった。まして、食事を運んできてもらうわけだ。二人は、配膳車まで食事は自分たちで取りに行くから大丈夫だと言ってみたりもしたが、配膳作業の都合上、看護助手側でいっぺんにやってしまった方がむしろ早くてよいということで、それはやんわと却下された。そんなわけで、二人は今病院食で朝食を賄っている。

「この食事にもずいぶん慣れてきましたね。」
「はい、なのです。シーファの胡椒効きすぎ料理よりは美味しいですよ。」
めずらしくリアンが冗談を言った。
「まぁ。シーファが聞いたら怒るわよ。」
「大丈夫なのです。イノシシは今どこぞの山の中なのです。」
そう言ってリアンは少しいたずらっぽい表情をして見せた。彼女に悪意などないのは全く明らかであったが、普段あまり冗談を口にしないリアンからそのような言葉が聞こえてくるのが、カレンには新鮮に思えた。
「あなたって、意外に面白いのですね。」
「はい、なのです。」
そう言いながら、リアンはスープを口に運んでいく。
秋の陽がゆっくりと高さを増し、朝の活気を感じさせる。窓から差し込む陽光は明るくも夏の熱気を失っており、秋ならではの透明感をもって二人の部屋の中を照らし出していた。
「食べ終わった?」
カレンが、リアンに訊いた。
「はい、美味しかったのですよ。食器を下げに行きましょう。」
そう言って立ち上がろうとするリアンをカレンが静止した。
「いいわ、あなたは監視を続けていて。私はついでに売店まで行ってくるから。」
カレンは二人分のトレイを両手に持って部屋を出ると、廊下に設置されている食器返却用の配膳車に自分とリアンの食器を返却した。その後、彼女はその足で、魔術式昇降装置に乗り込んで、1階の売店に向かって行った。
* * *
1階に降りると、すでに受付を待つ外来患者でエントランスホールはごった返していた。さすがは中央市街区を管轄する中核病院の一つである。人混みというほどではないものの、あちこちを行き交う人々の流れを縫うようにしながらカレンは売店に向かった。それはエントランスホールのすぐわきにあり、食堂や入院患者用の理髪施設などと軒を連ねている。基本的には入院患者が入用な、着替えや下着、衛生具、見舞い用の菓子などが販売される場所であるが、中核病院におけるその品ぞろえはなかなかのものであった。
カレンは、追加で魔力回復薬のアンプルを1箱(1ダース)と、急速魔力回復薬のアンプルをバラで6瓶、そしてリアン姫ご所望の『真紅の雄牛』を3本買い求めた。
売店の店員に、市販薬とはいえどもこんなにたくさん一度に売ることはできないと渋られたが、二人分であることを説明してなんとか販売してもらえた。それらを入れた袋を下げて来た道を戻る。あたりにはますます人影が増え、朝の喧騒に拍車をかけていた。館内では、各種の案内を伝える魔術放送があれこれとこだましてる。
一見、何の変哲もない一般的な病院の有り様に見える。この景色の一体どこに、秘密めいた魔法空間が拡張されているというのか?またそこでどのようなことが行われているというのか?何か変わったこと、気になることはないかとその感覚を研ぎ澄ましながら、カレンは1階の魔術式昇降機の扉が開くのを待っていた。
その扉が開くと、看護師が押す車椅子に乗った見知った男性が姿を現した。マーク氏だ。
「おはようございます。昨日はありがとう。」
カレンに気づいた彼の方から挨拶の声をかけてくれた。
「おはようございます。お加減はいかかですか?」
「ええ、昨日の散歩があまりにも心地よかったものですから。今朝もこうしてお願いした次第なんです。」
「そうだったのですね。それはよかったです。」
マーク氏の表情は、昨日、二人と散歩に出た時よりも幾分晴れやかなように見えた。
彼の車椅子を押している看護師がカレンに会釈をして先に進もうとしたその時、カレンは思わず声をかけた。
「あの、マークさん。」
彼がカレンの方に視線を送る。
「もし、ご迷惑でなければ、お散歩からお戻りになられた頃を見計らって、病室をお尋ねしてもよろしいですか?今日は、日勤時間帯は非番で、それで少しお話でも出来たらと思いまして。もちろん、ご迷惑でなければですが…。」
マーク氏は笑みを浮かべて言葉を返した。
「大丈夫ですよ。30分もしたら戻りますから。そこから昼食までの時間は退屈ですからね。僕の方からもお願いします。」
「はい。それでは。」
そう言葉を交わしながらも、彼を載せた車椅子はどんどんと裏庭に繋がる出口へと進んで行く。カレンはその背中を見送っていた。
それから後、閉まりそうになる魔術式昇降装置のドアに慌てて手をかけ、その小さな身体を中に滑り込ませた。
5階に着くと、まっすぐに自分たちの部屋に戻る。
リアンの視線は相変わらずずっと手元の魔法地図に釘づけられていた。
「何か変わったことはありましたか?」
そう訊ねると、
「今のところは特にないのですよ。先生とシン医師は、今朝は外来に出るようですね。」
そう言って彼女が指さす先では、シン医師が脳神経外科の外来診療室にいることを魔法光の光点が指し示していた。彼の動向は使い魔の視覚を通じて映像的にも監視しているが、そこにネクロマンサーの姿を認めることができた。
「医師のスケジュールは、私たちでは完全に把握しきれませんが、日勤という事は少なくとも今晩宿直でないことは確かですね。」
カレンの指摘は正鵠だった。
「ということは、今晩何らか動きを見せるかもなのですよ。」
「幸い先生は夜が非番だと仰っておられたから、もし動きがあれば追ってもらえますね。」
「はい、なのです。」
リアンはなおも魔法地図に見入っている。
「そういえば、買ってきてくれたですか?」
ふと視線をカレンの手元に送ってリアンが訊ねる。
「ええ、もちろん。ご所望の品はこちらにございますよ、お姫様。」
カレンが冗談ぽく言いながら、『真紅の雄牛』の瓶を差し出した。
「この監視は思いのほか魔力の消費が早いのですよ。あと、ずっと見てるので疲れるのです。これが頼みなのですよ。」
そう言って、瓶の栓を抜くと、リアンはそれを一気にのどに送った。
「よっぽどそれが好きなのですね?」
「はい、なのですよ。元気が出た気がするです。カレンは飲まないのですか?」
そう訊くリアンに、
「どうにも身体に悪そうで、私は遠慮しています。予備もちゃんと買ってきていますが、あまり飲みすぎてはいけませんよ。」
そう言って釘を刺した。
リアンはそれに答えたのか答えなかったのかよく分からない仕草で、その元気をもたらしてくれるというエナジードリンクの瓶を片手に、なおも手元の魔法地図に視線を注いでいた。
秋の陽は一層高くなる。外来だけでなく、病棟もまた慌ただしい様子を呈し始めてきた。いよいよ本格的に業務が始まるようだ。担当患者のもとに行くのであろう、看護師たちのチームのせわしない足音が聞こえる。
* * *
カレンはしばらくリアンとともにその魔法地図の動向を見やっていた。精神科のアブロード医師は、今朝は病棟で回診をしているようで、その光点は5階を中心にしてせわしなく動き回っている。エヴリン師長も同じように5回病棟を動いているようだが、ところどころでしばらく動きが止まることが見て取れた。特定の患者と何事かやり取りをしているのであろう。それは普通の見回りよりは時間を要しているようであった。
カレンがふと時計を見やると、針は10時を少し回っていた。先ほど散歩に出ていたマーク氏がそろそろ病室に戻っている時間だ。
「リアン、後のことはお任せします。私はちょっとマークさんのお部屋を訪ねてきますね。」
リアンは、『真紅の雄牛』を口に含みながら、頷いて返事をした。
マーク氏の病室は個室である。
ノックをすると、中から、
「どうぞ。」
という声が聞こえた。どうやらもう戻ってきているようだ。
「失礼します。」
カレンはそう言って静かにそのドアを開けた。
「やあ、あなたでしたか。どうぞ。」
そう言って、マーク氏はカレンに、病室内の簡易な椅子をすすめた。
「ありがとうございます。お疲れのところ押しかけてすみません。」
「いいんですよ。今日の散歩の心地よいものでした。秋の陽はやはりさわやかでいいですね。」
そう言うマーク氏の顔は、顔色もよく幾分かはつらつとしているように見えた。
「昨日はリアンがごめんなさい。勝手なことばかり言ってしまって…。」
カレンはそう言って頭を下げた。
「そんなこと、どうか気にしないでください。リアンさんに悪気がないことは分かります。それにあなたの心遣いは本当に嬉しいものです。ですから、どうかもう気にしないで。」
ベッドの上で上体を少し起こし、カレンの方を見てそう言ってから、マーク氏は再び上体を横たえて視線を天井に送った。
それから二人はさまざまなことを話した。
マーク氏の話では、彼の勤めていた会社は、たたき上げの技術畑の経営者が運営するお世辞にも大きいとは言えない中小企業だったが、保有する技術力は確かなもので優秀なエンジニアが揃っていたそうだ。それで、『人為のルビー』の生成に成功したばかりのカリーナ・ハルトマンがその技術力と小回りの利く開発体制に目をつけ、『閃光のロッド』の量産品の設計と製造を依頼してきたのだという。技術畑一筋で派手な仕事とそれまで縁のなかった経営層は、魔法社会を代表すると言ってよい大企業『ハルトマン・マギックス(当時はまだハルトマン魔法万販売所であった)』からの思いがけない依頼に舞い上がり、浮足立ってしまって、なんとかそれを社業の飛躍につなげたいと考えたそうなのだが、今思えばそれが無理の始まりだったとマーク氏は語った。
彼の会社は技術力とノウハウ、人材だけは豊富であったが、大量生産の経験、それに耐える資材調達手段、そして何より資金調達の手段に乏しく、銀行は『ハルトマン・マギックス』の仕事であるということは評価しつつも、人為のルビー自体が魔法社会で初めての為石(人の手による法石)の成功事例で売れるという前例に乏しかったこと、大量生産実現のためには設備投資だけではなく設計と開発が新規に必要であったこと、資材調達による効率的なコストカットの見通しが不透明であったこと、そして何よりもその時点における経営状態が利益率を中心にとても芳しいとは言えなかったこと、以上の諸点を主な理由として、新規の融資に慎重な姿勢を崩さなかったのだと言う。そのことが、会社首脳陣の焦燥に一層の拍車をかけ、資金の投入によって解決すべき諸課題について、人材の活用によって代替するという悪手に駆り立ててしまったのだ。結果、従前と変わらぬ賃金体系のまま、技術者ひとりあたりの業務量は数倍に膨れた。また、新規事業の性質上、直ちに会社に利益をもたらすわけではないという厳然たる事実に反発する、いわゆる稼ぐ部署の従業員たちの声を会社はうまく抑え込むことができず、その事業に携わるマーク氏をはじめとする技術者たちは、社の内外に対応すべき課題を抱える格好に追い込まれていった。しかし、彼らのチームの技術力は本当に素晴らしく、ハルトマン・マギックス社が要求する技術水準をよく満たしており、設計と開発には順調に進んでいる側面があった。しかし世の中とは皮肉なもので、そのこと自体が技術者各位をめぐる状況を一層複雑なものにしていった。本来、会社に留まってマーク氏ら開発陣を支援すべきプロジェクト・マネージャは早々にハルトマン・マギックスの系列会社に引き抜かれ、技術者達を内から守るどころか、外から加圧する存在へと立場を変えてしまった。また、同僚の優秀な技術者たちもまた、彼らに目をつける社外勢力によって次々と引き抜かれて行った。そうこうしているうちに、せっかく順調に進んでいた開発も鈍化を見せるようになり、経営陣はハルトマン・マギックスへの説明に右往左往し、残った人材に負担を強いるばかりで、歯車はいよいよ噛み合わなくなっていった。ジリ貧とはまさにこういうことを言うのであろう。マーク氏を始め、数人の技術者たちは、そのプロジェクトを「自分たちの仕事」として、技術的側面からなおも支えようとしたが、そうした「仕事を遂行する」のが人間であるという逃れられない事実が、静かにその懸命な努力は内側から綻びを生じていくことなる。やがて、心身の不調を理由に、ひとり辞め、ふたり辞め、ついにプロジェクトチームを維持すること自体が不可能になって、瓦解してしまったのだと、マーク氏はこぼすように語ってくれた。
彼は実に、最後までチームに残ったメンバーのひとりであったそうであるが、会社は、その時点で完成していた技術を競合他社に売り渡して当面の投資を回収するという無慈悲に出て、マーク氏らはプロジェクト失敗の責任を取らされる形で解雇されたのだという。
その一連については、マーク氏の中ではすでに一定の清算と心の整理がつきつつあるようであったし、そうであるからこそ、年端も行かない看護師見習いともいうべきカレンにそんなことを話してくれたのであろうが、心中穏やかでなかったのはむしろそれを聞いたカレンの方であった。
賢く思慮深い彼女は、マーク氏の前で怒りを露わにし、あるいはマーク氏の感情をいたずらに動揺させるようなことを決して口にしたりはしなかったが、しかしその内心は、社会の不条理と無慈悲に接した怒りの炎を大きく灯していた。膝の上で握りしめる拳の手のひらには、爪の跡が深く刻まれている。
なぜ、これほど有能で実直な人物が携わった仕事が、その人々の努力や賢明さとは全く関係のない、経営などというつまらない金銭の帳尻合わせの為に、根こそぎ無為にされなければならないのか、そう考える若い正義感は、心底から滾っていた。こうした理不尽は、アカデミーの諸活動にあっても経験することではあるが、こんなに苛烈かつ無慈悲な事態がそうそう起こるわけではない。努力なき不遇は格別、懸命な努力の末の不遇を果たして誰がどのようにして報いるというのか、その若く純粋な濃紫の瞳は潤む輝きを静かにたたえていた。
* * *
マーク氏の告白に対して、全身を覆いつくさんばかりの怒りと動揺を抑え込みながら、どのような言葉を彼にかけるべきかカレンが必死に思案しているとき、ノックの音が聞こえた。
「どうぞ。」
マーク氏の声が聞こえるが早いか、扉が開いた。入室してきたのはエヴリン師長である。
「あら、カレンさんもいらしていたのですね。」
「はい、お邪魔であれば失礼しますが…。」
「大丈夫ですよ。マークさんにお伝えすることがあって来ただけですから。」
そう言うと、師長はマーク氏のベッドの脇に立った。
「マークさん、いいお知らせです。脳外科のシン先生から先ほどアブロード先生にご連絡がありまして、マークさんの病状の一層の改善の為に新しい治療が行われることになりました。ここ最近めざましい回復をしておいでですから、これが上手くいきましたら、きっと退院も見えてきますよ。」
「新しい治療というのは?」
不安そうにマーク氏が訊ねる。
「大丈夫ですよ。危険なものではありません。ただ、その治療が可能かどうかを事前に精密に検査する必要があります。また、その検査は脳神経外科にて行われますが、それに先立っていくつかの同意書にサインをお願いしたいのです。」
そう言いながら、何枚かの書類を彼の前に差し出していく。マーク氏は、師長の説明を都度受けながら検査への同意書にサインをしていった。
カレンは二人のやり取りに注意深く耳を澄ませていた。というのもこれはまさに彼女たちが目をつけていた精神科と脳神経外科の奇妙な連携の具体的な事象だったからである。しかも、シン医師、アブロード医師、エヴリン師長の3人が関与するというのだ。メモを取ることはできないため、先ほどから続く怒りの衝動を懸命にこらえながら、カレンは師長の説明に傾聴した。
主な内容は、検査はアブロード医師の指示の下でシン医師が行うこと、治療に適性が見い出された場合は、精神科から脳神経外科への転科となること、そのための一時的退院は今回は不要であること、の3点であった。多くの場合、同じ病院であっても、入院を伴う転科前には一度退院を挟むことが慣例となっていたが、今回はその必要はなく、検査結果次第で直接3階に移ることになるのだそうだ。これは病院側の事情なのだろうが、カレンは若干の違和感をぬぐえずにいた。
そんなことを考えるカレンを尻目に、師長の説明と同意書へのサインはどんどんと進んでいく。今、師長はマーク氏がサインし終えた同意書の束を注意深く見返していた。
「これで大丈夫ですよ。きっと元気になれます。」
マーク氏の顔を見ながら師長はそう言った。氏も、一抹の不安はあるようであったが、
「いろいろご面倒をおかけします。先生方にお任せします。」
そう言って、ペンを置いた。
「はい、頑張りましょう。それから、もうすぐお昼ですが、よかったら一緒に戻りませんか?」
師長はカレンに声をかけた。
「はい、そうします。」
カレンは、マーク氏に挨拶をして、師長と一緒にその部屋を後にした。
外では、秋の陽がほぼ天頂に座していた。院内は明るく、換気の為に開かれた窓から吹き込むこの季節特有の乾いた心地よい風が廊下を撫でている。
「あなたは、熱心なのですね。お若いのに感心です。」
師長がカレンに声をかけた。
「ありがとうございます。まだまだ未熟ですが、アカデミー看護学部の学徒として、できるだけのお手伝いをさせていただければと思っています。」
「心強いわ。期待しているわね。それじゃあ。」
そう言って、師長は詰め所に入って行った。カレンはそのままリアンの待つ自分の部屋に向かう。偶然ではあったがマーク氏に関して動きを掴むことができた。早速リアンと先生に報告しなければ、そう思い定めて部屋のドアを開けると、リアンは相変わらず食いつくように端末の画面に視線を送っていた。朝からずっとこの調子、すごい集中力だ。
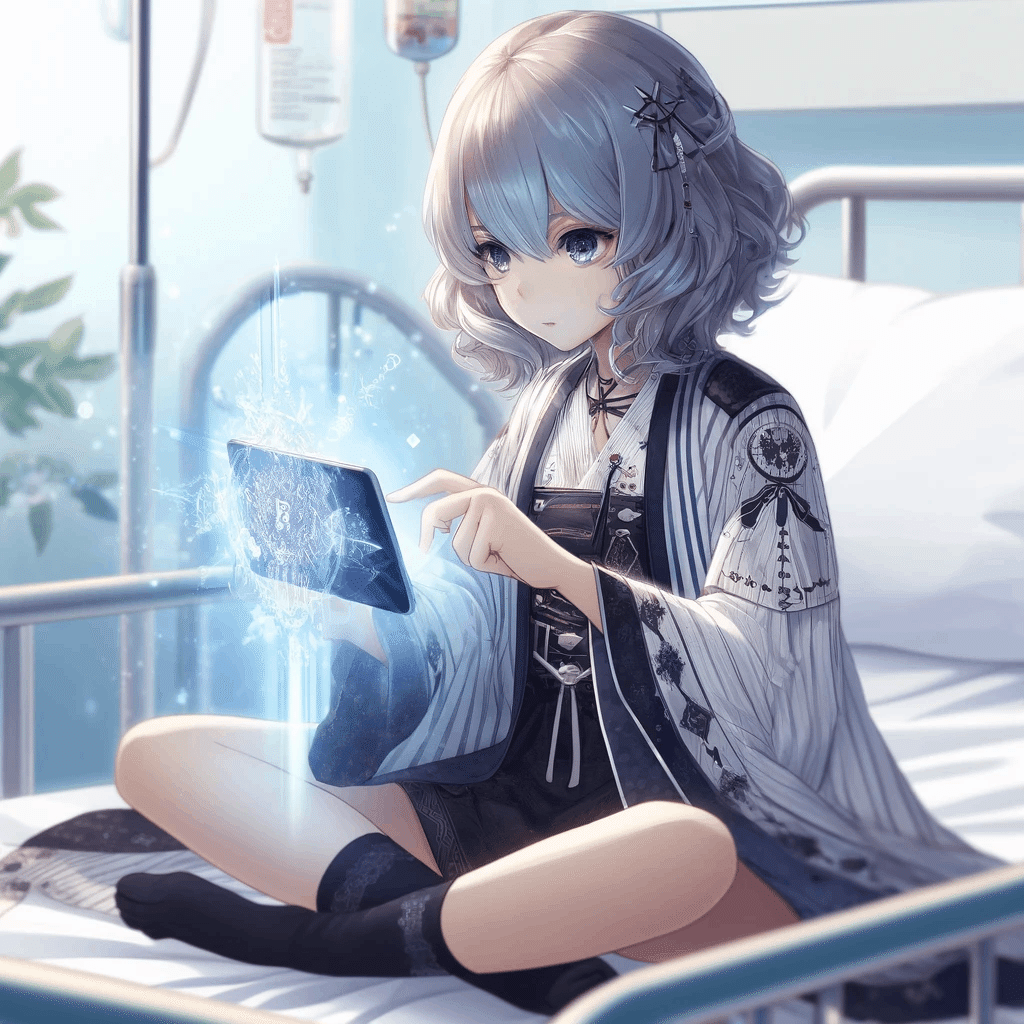
「リアン、お疲れ様?どう、変化はありますか?」
リアンは、カレンを見て答えた。
「午前中、シン医師が一度診察を中断して5階に上がってきたことがありましたですよ。それにはエヴリン師長も同行してました。何か動きがあるようですね。」
そう言うリアンのベッドの上では既に2本の『真紅の雄牛』の瓶が空になっており、3本目の栓も既に開けられていた。その残りも多いとは言えない。
「カレンの方はどうですか?何か、収穫はありましたですか?」
「ええ、こちらでも動きを確認できたわ。きっとリアンが発見した彼らの動きは、マークさんの検査と脳神経外科への転科に関する一連よ。具体的になるとすれば、今日の午後か最悪でも夜ですね。」
「わかったのですよ。午後から夜にかけて監視を怠らないようにするのです。ですから…。」
そう言うと、リアンはちょっと言葉を詰まらせた。
「はいはい。お姫様はこれが欲しいんでしょ?」
リアンのベッドの上にちらばる『真紅の雄牛』の空瓶を片付けながら、カレンは言った。リアンは、少し照れくさそうに、頷いて答えた。
「買ってくるわね。でも飲みすぎは本当に駄目ですよ。」
そう言って、カレンは再び部屋を出た。
朝と同じように魔術式昇降装置に乗って1階の売店に向かって行った。午前の診療受付はしばらく前に既に終わっており、診療時間それ自体もまもなくというところであったが、1階の受付ロビーは相変わらずの人の多さであった。そこで偶然、シン医師から何事かを頼まれたのであろう、かなりの量の資料を両手に抱えたネクロマンサーに出くわした。
「先生!」
ネクロマンサーはその声に気づいたようだ。山積みにされた資料の脇から声のする方を覗き見るようにして、視線を移した。
「カレンさん。偶然ですね。お疲れ様です。」
「先生、少しお話しできますか?」
「ええ、構いませんよ。シン医師に頼まれた資料を運んでいるだけですし、午前診療ももう終わりますからね。」
そう言って二人は待合ロビーの脇にある長椅子に腰かけた。
「どうしましたか?」
事情を訊ねるネクロマンサーに、カレンは今日の午前中の動きを伝えた。
「なるほど。マーク・ヘンドリクソンさんという患者さんに動きがあるわけですね。精神科から脳外科に検査を受けに来て、その結果次第ではこちらに移ってくる可能性があると。」
「はい、そうなのです。今リアンがそれに関与しているであろう3名の動向をつぶさに追っています。」
「わかりました。幸い、他科から回ってきたカルテは私の方がシン医師よりも先に見ることができます。マークさんの動向についてはこちらでも十分に気を付けておきます。それから、例の魔法拡張空間についてわかることがあれば、必ず事前に私に連絡してください。くれぐれも独断専行でのりこんではいけませんよ。まぁ、こんなことはあなたには言うまでもないですね。」
そう言ってネクロマンサーはカレンにあたたかい微笑みを向けた。日常的にアカデミーの看護学部において仕事を共にすることのある二人には、彼女たちならではの確かな信頼関係が醸成されているのであろう。
「わかりました。きっとそうします。先生もくれぐれもご無理なさらないでください。」
カレンがネクロマンサーを気遣って見せた。
「大丈夫ですよ。私には彼女もついていますから。」
その彼女というのは、アカデミーでこの作戦の指揮を執るウィザードのことだろう。彼女たちの間に築かれた固い信頼もまた一朝一夕のものではなかった。
「それでは、私は午前の仕事を片付けてしまいますね。」
そう言って、ネクロマンサーは立ち上がり、脇に置いた資料の束を再び両手に抱えて歩き出した。
「お手伝いしましょうか、先生。」
カレンのその言葉に、
「ありがとう。心配しないで。」
笑顔で応えて、彼女は廊下の奥に消えていった。
売店での買い物を終え、カレンは5階に向かっている。
季節感として秋は深まるものの、この時期の日中は時にまだ暑い。もっとも病院内は魔法空調が効いているから、常に一定の温度に保たれている訳であるが、それは彼女の内面から湧き上がる思いとこの作戦の完遂に向かう覚悟の表れなのであろうか、カレンは自身の内に季節外れの熱量を実感してた。ひとまずこれをリアンに届けよう。彼女の頑張りにも報いなければ。そう思って、魔術式昇降機のドアの中に消えていった。
その外では、相変わらずの喧騒が続いている。ゆっくりと秋の陽がわずかにその顔を西に傾けた。
to be continued.
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第2集その4『闇の向こう側へ』完
