
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第6集その3『カリーナの依頼』
ウィザード、ソーサラー、ネクロマンサーの3人とカレンがアカデミーに戻ってから、数日が経過した。9月ももう下旬に差し掛かろうとしている。逃走したトマスの足取りはようとして知れなかったが、しかしあれ以降、学内を騒がせた破廉恥な下着泥棒はなりを潜め、またウィザードたちが帰ってきたことで、すっかり以前の日常を取り戻しつつあった。
そんなある日の昼下がり、全学に向けて魔術放送による呼び出しが突然にしてかかったのである。それは、午前中試験で午後休講の半ドンの日であった。
「緊急御呼び出しを申し上げます。魔法学部長代行、ソーサラー科専門研究員、並びに看護科責任者の各先生方は、至急、中央尖塔5階アカデミー最高評議会の応接室までお越しください。最高評議長とお客様がお待ちです。繰り返します…。」
同じ内容が二度全学を駆け巡った。最高評議長直々の呼び出しとはよほどのことである。ウィザードたちは大至急で中央尖塔の5階へ向かった。応接室前の広間に集合する3人。いったい何事であろうか?また、突然訪ねて来て最高評議会経由で呼び出しをかけてくる客人とは何者であるのか?いずれにしても尋常な事態でないことだけは容易に想像された。
「ずいぶんと急な呼び出しですね。何事でしょう?」
ネクロマンサーが訝し気に訊ねる。
「本当ね。最高評議会議長の公式呼び出しなんて初めて受けるわ。」
ソーサラーも疑問を隠しきれないようだ。
「とにかく議長と客人を待たせるわけにはいかない。三人揃ったことだし、すぐに行こう。」
ウィザードが促すと、あとの二人が頷いて答える。それを確認して、ウィザードは応接室の入り口をノックした。
「大変、お待たせいたしました。魔法学部長代行ほか二名、お呼びにより参上いたしました。入室してよろしいでしょうか?」
今日のウィザードはいつかのよそ行きである。
「どうぞお入りください。」
中から秘書の声が聞こえ、それと同時に内側から扉が開いた。
「失礼いたします。」
そう言って、ウィザードたちは入室した。
秋の陽が西から窓に差し込んでいるが、その光はまだ赤みを帯びていない。さわやかな風が、ガラスの外で木々の枝を頻りに揺らしていた。
「急にお呼びだてして申し訳ありませんな。」
声の主は最高評議長のものだった。秘密主義の前最高評議長パンツェ・ロッティのときとは異なり、後任の議長は教職員や学徒の前に滅多に姿を見せないということはなかったが、それでも直々に面談をするなどというのはやはり珍しいことに違いはなかった。
その前におずおずと進み出る三人。
「よくおいでくださいました。実は先生方をご指名で依頼を持ってこられたお客人がおられましてね。お名前はよくご存じでいらっしゃるでしょう。『ハルトマン・マギックス』社のカリーナ・ハルトマンCEOです。」
そういって議長が手を差し伸べた先には、魔法社会で一、二を争う大企業の最高経営責任者であるカリーナ・ハルトマンが三人を待っていた。
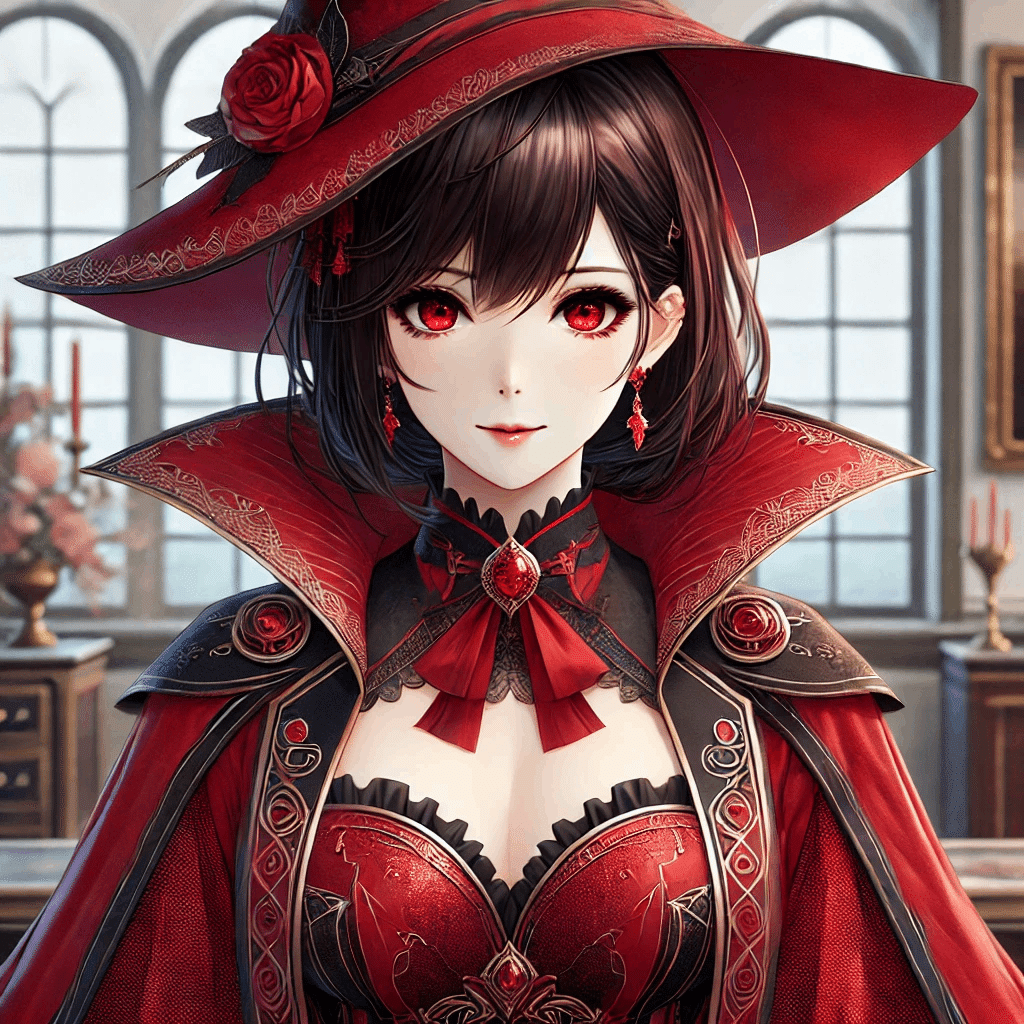
「カリーナCEO、お待たせしております。彼女らがおたずねの先生方です。私めは公務がございましてこれで失礼いたしますが、どうぞごゆっくりとお話しください。」
そう言うと、最高評議長はカリーナCEOに軽く会釈をし、ウィザードたちによろしくと声をかけてから応接室を後にした。
その背を見送ってからゆっくりと、カリーナが三人に声をかける。
「いつも義妹のアイラがお世話になっております。」
「いえ、こちらこそいつも大変お世話になっております。それで、私共に御用とのことですが、どのような事柄でございましょうか?」
ウィザードがうやうやしく応対した。
「リセーナのことですわ。」
その意外な人物の名前が飛び出したことで、三人は表面上の冷静を保ちながらも、内心では驚きを隠せないでいた。リセーナ・ハルトマンと自分たちの縁(よすが)、特に彼女の最後に立ち会ったことについて、目の前の御仁は知る由もないはずだったからだ。
「まずは、どうぞおかけくださいまし。」
カリーナはそう言って三人に席を勧めてくれた。ウィザードたちは、カリーナの前に並んで席をとる。
「実は、先生方がリセーナの最期を知っていると、ある人物から伺いまして…。」
カリーナが話を始めた。やはりそのことか。三人に、俄かに緊張が走る。
* * *
「と、おっしゃいますと?」
「先日、ちょうどアイラが先生方をタマンまでお迎えに上がっているときに、『天翔ける船頭の僕(しもべ)』という人物が、私共の会社を訪ねてまいりまして。それで、その者が言うには、リセーナは実はまだ生きており、助け出す手段があるということなのです。今、リセーナは時空の狭間にある時の檻に捕らわれているのだと、そのように話しておりました。」
「そんなことが…。」
三人とも驚きを隠せない。
「もちろん、そんな荒唐無稽な話、俄かに信じることはできません。それで私がお引き取りを願うと、アカデミーのある先生方、つまり皆様方がその事実を知っていると、そう言うのです。疑うのならアカデミーを訪れて、先生方に会って直接確かめてみるがいいと。」
「そうでしたか…。」
「はい。それで、お忙しいとは存じながらも、今日このようにしておたずねした次第です。どうぞ、ぶしつけな訪問についてはご容赦くださいまし。」
カリーナはそう言って軽く頭を下げて見せてから続けた。
「それで、その者の言うことに、先生方はお心当たりがおありですか?」
それを聞いて互いに顔を見合わせる三人。カリーナは一口コーヒーを含んだ後、ため息をついてからカップをソーサーにそっと戻した。
「やはり、ご存じのようですね、リセーナの最期のことを…。よろしければ詳しく聞かせていただけませんか?」
身体を椅子の背に預けるようにして、カリーナは言う。どうしたものかと思案しつつも、ウィザードが口を開いた。
「これまで、お話しなかったことについて、まず初めにお詫び申し上げます。以前にありました天使によるアカデミー急襲事件の折、とある重大事態にリセーナさんは巻き込まれてしまし、それでこの世界を離れました。」
「『この世界を離れた』ですか…?ずいぶんともってまわった言い方をなさいますのね?」
カリーナの声の調子が僅かに変わる。
「ええ、説明が難しいのですが、リセーナさんはある男とともに神秘の空間を目指したのです。」
なお慎重に言葉を選びながらウィザードは続けた。
「パンツェ・ロッティのことですわね?」
「はい、やはりご存じでしたか…。実は、亡きロッティ教授と、リセーナさんは、とある神秘を巡る、その、一種の研究に携わっておいででした。それで、リセーナさんがそれに到達する方法を発見なされたのですが、その方法というのが、彼女自身の犠牲を求めるものだったのです。」
とても言いにくそうにして、ウィザードはその時の様子を話した。
「犠牲とは、具体的にはどのようなものだったのかお話し願えますか?
どうやらカリーナには事実を受け止める覚悟ができているようだ。その心持を察して、ウィザードも意を決する。
「実は、ロッティ教授は『神秘の門』を開くことによる新しい世界の創造を目指していました。これこそ荒唐無稽に聞こえるかもしれませんが、我々が実際に体験した事実です。」
「詳しく。」
カリーナに動揺はない。
「その『神秘の門』は、この世界とは隔てられた高次元空間に至るための奇跡の門で、それを開くための鍵として、リセーナさんは、その…、ご自身の存在を引き換えられたのです。」
ウィザードの声は重い。
「なるほど。ということは、私を訪ねてきた『天翔ける船頭の僕』なる者の言う、『リセーナは今なお高次元空間に存在する時の檻に捕らわれている』というのは、あながちあり得ない話ではないということですわね?」
カリーナは、コーヒーをもう1口含んでから静かにそう言った。
秋の風が窓を揺らす。応接室の中の気配は、透き通る日差しに照らされた屋外とは対照的な様子を呈していた。
* * *
「それについては、確かに、全くあり得ないことではないと認識します。我々の目の前で、リセーナさんは確かに『神秘の門』の中に姿を消されましたが、お亡くなりになられたのかどうかは必ずしも明らかではありません。『神秘の門』を開き、そこに身を投じた後、実は時空の狭間に囚われたのだという事態は、十分に考えらえることであると言えます。」
当時の状況を思い出しながら、ウィザードはそう答えた。確かにあの時、リセーナは門を開くために光の中に消えたが、その死を確かにするものが何一つなかったことは事実であった。
「そうですか…。」
カリーナはこぼすようにそう言った。
「それで、貴女を訪ねてきた、その『天翔ける船頭の僕』と名乗る存在がどのような者かわかりますか?」
そう訊ねたのはソーサラーだ。
「ええ、実は店の者に、秘密裏に魔術記録を取らせました。これをご覧ください。なにか心当たりはありますか?」
そう言って、カリーナは1枚の魔術記録を三人の前に差し出した。

「これは!!」
声を上げたのはネクロマンサーだ。
「この人物はカレンさんが話していた『ダーク・サーヴァント』の特徴に似ています。あるいは、先ごろアカデミーを騒がせたトマス・ブルックリンにも通じている可能性が…。いずれにしても、この魔術記録を彼女たちに見てもらった方がよさそうに思います。」
それを聞いて、カリーナが言った。
「その彼女たちというのは、アイラたちのことですわね?もし差し支えなければ、アイラとそのお友達をここに呼んでいただくことはできないかしら?」
「ええ、もちろんです。幸い今日は午前の試験だけで、すでに放課後を迎えていますから、すぐに呼んできましょう。少々お待ちください。」
そう言って立ち上がったのはソーサラーだった。美しい二つ括りの銀髪をなびかせて応接室を出る。
しばらくして学徒呼び出しをかける全館放送が流れるのが聞こえた。
陽はゆっくりと西に傾いていく。透明だった光はいくばくかオレンジ色の輝きを含むようになった。まどからまっすぐ差し込むその光の中で、埃がちらちらと舞っている。
ほどなくして、扉をノックする音が聞こえてきた。
「どうぞ。」
それに応じるカリーナ。戸が静かに開いて、シーファ、リアン、カレン、アイラを伴なったソーサラーが入室してくる。ソーサラーは元の席に座り、少女たちはその脇に並んで座った。
「これを見ていただけるかしら?」
カリーナが差し出す魔術記録を覗き込む少女たち。
「お前たち、この人物に見覚えがあるか?」
ウィザードが訊く。
「はい、これはトマス・ブルックリンか、あるいは『天翔ける船頭の僕』と名乗る『ダーク・サーヴァント』のいずれかです。」
その両者と交戦経験のあるシーファがそう答えた。
「やはりそうでしたか…。」
何か確認するようにそう言ってから、居住まいをただしてカリーナが言った。
「それはそうと、お久しぶりですね、皆さん。過日はすっかりお世話になりました。また、いつもアイラと仲良くしてくださりありがとうございます。」
「いえ、とんでもありません。こちらこそあの時はお世話になりました。アイラにも、いつも助けてもらっていて感謝しています。」
恐縮した様子で答えるシーファ。リアンもそれに続いて会釈をする。カレンはカリーナに会うのは初めてだった。
「この者がどうしましたか?彼は現在指名手配中の者です。」
そうシーファが言うと、カリーナは、その者が自分の店を訪ねてきたことなど、一連のことを話して聞かせた。アイラはそれを事前に聞いていたようであったが、初めて耳するシーファたちはその内容に驚きを隠せないでいる。
「その魔術記録の者が『天翔ける船頭の僕』と名乗ったのであれば、それは『ダーク・サーヴァント』に違いありません。おそらくは指名手配犯トマス・ブルックリンの手の者です。非常に危険な輩ですが、大事はありませんでしたか?」
そう、カリーナに訊ねるシーファ。リアンも心配そうだ。
「ええ、幸いにして彼はリセーナを救出したいと思うならば自分に手を貸せとそう言ってきただけで、特段の危険はありませんでした。」
「そうですか…。それは何よりでした。」
少し肩の力をやわらげるシーファ。その姿を見て、目を細めながら、カリーナが言った。
* * *
「なるほど。先生方と皆さんのお話からすると、この者の言うことは間違いないように思えます。しかし、私としては、こんな正体不明の者にリセーナの帰趨を任せるつもりはありません。」
「ごもっともだと思います。」
応じるウィザード。
「そこで、先生方にお願いがございます。」
「どのようなことでしょうか?トマスたちの逮捕ならすでに『アカデミー治安維持部隊』が全力を挙げていますから、心配はございません。必要ならお店を警備させましょう。」
そう提案するウィザーに、
「いえ、そうではなくてリセーナのことです。もし、リセーナがまだ生存していて、救出する機会があるのならばぜひ彼女を助け出してやりたいのです。リセーナは私の妹であり、アイラの大切な義姉ですから…。どうか、リセーナ探索を引き受けてはもらえませんか?」
そうカリーナは応えた。
「リセーナさんの捜索ですか…。」
ウィザードの返事は重い。それもそのはずである。時空を行き来する方法など、皆目見当がつかないからだ。ウィザードが当惑しているのを見てか、
「カリーナCEO、この件、少しだけ預からせていただくことはできませんか?」
そう言ったのはソーサラーだった。ネクロマンサーもその言葉に頷いている。
「構いませんが、何か手だてがありますか?」
「はい。絶対の約束は致しかねますが、何らか打開策を知っていると思われる人物に心当たりがあります。その人物に訊ねてみて、それから正式にお返事するというのではどうでしょうか?」
そう語るソーサラー。ウィザードも得心のいったような顔をしている。
「先生方がそうおっしゃるのなら、お任せしたいと思います。連絡はアイラを介してくだされば結構です。朗報をお待ちしておりますわ。」
そういうとカリーナは立ち上がって、ウィザードの前に手を差し出す。それを取ってウィザードが言った。
「きっとお役に立てるよう、出来るだけのことをやってみます。とにかくも周辺にはくれぐれもご用心なさってください。何かあれば『アカデミー治安維持部隊』がお守りいたします。」
「心強いことですわ。ありがとう。それでは諾否のご連絡をお待ちしております。」
「承知しました。」
そう言って、二人は固い握手を交わした。
「ところで…。」
「なんでしょう?」
「この後、アイラだけここに残していただけませんか?引き渡したいものがありまして?」
カリーナがそう言った。
「構いません。私共は早速その手がかりとの接触の準備を進めます。どうぞアイラさんとゆっくりお過ごしください。」
「ありがとう。」
「それでは、私たちと、それから学徒達はこれで失礼いたします。アイラは義姉様とともに。」
そう言うと、ウィザードたちは席を立って、応接室を後にした。扉が閉まると、室内は一気に閑散となる。今、カリーナとアイラの義姉妹が差し向かいで座っていた。
* * *
「お義姉さま、どうなさいましたか?」
アイラが訊ねた。
「ええ。もし、先生方が先ほどの依頼をお引き受けくださった暁には、きっとあなたにも役目が回って来るでしょう。そこで、存分な働きができるようにと思って、これを持参しました。」
そう言うとカリーナは同席させ、待機させていた執事に合図をした。
「あれをこちらに。」
「かしこまりました、CEO。」
執事は応接室の奥から、大きな荷物を抱えて戻って来ると、それをテーブルの上に置いた。
「開けて頂けるかしら?」
「はい、お待ちください。」
そう言うと、執事は荷を開いてその中身を見せた。それは黄金色の見事な剣と軽鎧、そして指輪の揃(そろい)であった。
「お義姉様、これは『黄龍の揃』ではありませんか?」
驚いた声でそれらを見やるアイラ。



「そうですよ。あなたはこれまで様々な経験を通して、これに相応しい力を身に付けました。これからは、これを用いて存分に働きなさい。」
そう告げるカリーナ。
「しかし、このように貴重なものを戴くわけには参りません。」
恐縮するアイラ。
「何を言うのです。あなたは私の大切な義妹です。リセーナ探索に向かうとなればこれくらいのものはあって当然。これできっとリセーナを助け出してきてください。」
「お義姉様…。」
そう言って、カリーナとアイラはしばし見つめ合った。両者の間で、黄金色の揃が見事な輝きを放っている。
「わかりました、お義姉様。これできっとリセーナ様を救い出してご覧に入れます。お心遣いに、心より感謝いたします。」
意を決してアイラが言った。
「ええ、頼りにしていますよ。無事に姉妹三人が揃う日を楽しみに待っています。」
「はい、お義姉様、必ず。」
「では、これはあとであなたの寮室に届けさせます。あなたはもう行きなさい。」
「わかりました。お義姉様もくれぐれも身辺にお気をつけて。」
「ありがとう。」
そう言って、アイラもまた応接室を後にする。
窓から差し込む陽は西日となり、茜色の光がその見事な揃にあしらわれた竜の瞳を赤く染め上げていた。まもなく夜になる。
アイラが廊下に出て、階段を下り始めると通信機能付光学魔術記録装置が着信を告げた。ウィザードからだ。すぐに応答するアイラ。
「アイラ、すまない。お義姉様とのお話はもう終わったか?」
「はい、先生。今応接室を出たところです。」
「実は、先ほどの件でこれから全員で『アーカム』に行くことになった。アイラにも同道してほしい。行けるか?」
「はい、もちろんです。いまどこにいらっしゃいますか?」
「アカデミーのゲート前に集合している。すまないがそこまで来てくれ。」
「わかりました。すぐに参ります。」
そうして通信は終わった。階段を急いで駆け下りるアイラ。ここを1階まで降りれば、ゲートは目と鼻の先だ。
ゲート裏から表に出ると、先生たち三人と、それからシーファたちがそこで待っていた。
「よし。全員揃ったな。早速だが、それではこれから『アーカム』に行こう。」
「時空を旅する方法について調べるのですね?」
シーファが言う。
「そうだ。あそこになら、きっと何かヒントがあるだろう。なによりアッキーナの話では、今日はエバンデス婦人もいらっしゃるそうだ。彼女にならわかることがあるだろう。」
その言葉に、その場の全員が頷いて答えた。
「では、行こう!」
ウィザードの号令と共に、7人の影は例のM.A.R.C.S.をたどっていく。彼女たちは『キュリオス骨董堂』が『アーカム』であることを知っている。しかし、それを知る彼女たちでも、そこに至るためには道順暗号をたどる必要があった。それくらいに『アーカム』は神秘の場所として秘匿されていてたのだ。地平線がゆっくりと濃紺に染め上げられていく。
* * *
暮れ行く秋夜を覆う白い霧をかき分けて、今彼女たちは神秘の地で、神秘の人々と向き合っている。ドアは引き開きで、少女アッキーナが出迎えてくれた。ぼんやりとした魔法光が差すカウンターを挟んで、貴婦人ことキューラリオンとアッキーナ、そして先生たちと学徒達が向かい合っている。皆、神妙な面持ちだ。今日カリーナから持ち掛けられた話をつぶさに伝えるウィザードたち。キューラリオンはそれに静かに耳を傾けていた。

「そう、お話はわかりました。あなた方は、かのリセーナ・ハルトマンを探しに行きたいと、そうおっしゃるのですね?」
婦人は静かにそう言った。
「そうなんだよ。でも、あの時はパンツェ・ロッティの野郎が勝手に高次元空間への途を開いたわけだが、あいつがいなくなった今、そこに至る方法がてんでわからない。それで、あんたたちなら何か知っているんじゃないかと思ってこうして訪ねてきたんだよ。」
ウィザードが応える。
神秘の光が店内をゆらゆらと揺れ、芳醇な香のかおりが鼻孔をくすぐっていた。
「時空を旅する方法は確かにあります。」
「本当か!?」
あたりが俄かに騒然となった。
「方法はありますが、それは簡単なことではありません。」
いつになく婦人の言葉から余裕の色が消えていた。
「どうすればいいんだ?」
そう訊ねるウィザードたちに、婦人は具体的な説明を始めた。
「時空を旅するためには、古(いにしえ)の魔法の力を使う必要があります。そして、そのためには太古の魔法使いの力を借りねばなりません。しかし、彼女たちに会うには、まずそのための許可をその伴侶である戦神からもらう必要があるのです。」
それが如何に困難なことであるのか、いつもの軽やかさを欠いた夫人の言葉が、それを如実に物語っていた。一同固唾を飲んでその続きに耳を傾ける。
「まず、船体を手に入れなければなりません。その船は『星天の鳥船』といい、太古の魔法使いの一人、緑のルクスが管理していますが、彼女に会うには、まず夫の戦神ミーウに会わねばなりません。」
「それは、難しいことなのか?」
そう訊ねるウィザードに、
「ええ、とても。」
そう応えてから、婦人は説明を続けた。
「次に、船を動かすための動力と燃料が必要です。それは北の『バレンシア山脈』に隠されている『アインストンの工房』にて紅(あか)のアインストンが守っています。彼女の夫、戦神ターガを通して彼女と接触できるでしょう。
最後は、南方『タマヤの洞穴』の最奥にある『古代のポータル』からたどり着くことのできる『時空の港』の使用権を、黄金のブレンダからもらうことです。同様に彼女の夫ハーマの許可を得なければなりません。
このようにして、三戦神を通じてその伴侶たる太古の魔法使いに会い、彼女たちからそれぞれ必要なものを与えてもらう必要があります。しかし、戦神という名からわかる通り、彼らが課す試練は文字通りに戦いとなるでしょう。そして神の名は伊達ではありません。」
そう言うと、婦人はグラスから神秘の酒を飲みほし、ため息とともに開いたグラスをテーブルに返した。その場の緊張が高まっていくのがわかる。
「でも、エバンデスさん。天使の力をもってすれば、出来ない相談ではないのではないですか?ましてあなたやあなたの力を受け継ぐ私がいれば…。」
そう言ったのは、ユイアことウォーロックであった。それを聞いて、婦人が応える。
「残念ながら、古い約束があって、私とあなたはこの件に関与できません。従って、もし時の檻まで旅をしようというのであれば、彼女たちだけでそれを成し遂げることになります。しかし、彼女たちの天使化は、偽物というわけではありませんが、人為的な天使の卵によるものなので、あなたの天使化と全く同じというわけにはいきません。ですから、その困難は相当に大きなものになるでしょう。まして、学徒の皆さんの中で、天使化しているのはカレンさんだけですから、無謀なのは目に見えています。」
「そんな!私はみんなと一緒に行けないのですか?」
そのウォーロックの言葉に、婦人は静かにただ頷いて答えた。
「しかし、リセーナさんとあたしたちには特別な縁(よすが)がある。最後に会った彼女はとても悲壮で、幸福からは遠い存在だった。もしもう一度、彼女に人生を紡ぎ直す機会があるのだとすれば、あたしたちはそのために力を尽くしたい。」
ウィザードは、遠い日の『神秘の門』を巡る出来事を思い出しながらそう語った。同じ時を共有したソーサラーとネクロマンサーも大きく頷いてそれに同調している。更に、ウィザードが続けた。
「また、アイラはもちろん、学徒達はカリーナさんと特別な縁を結んでいる。だから、こいつらもカリーナさんの願いをかなえたいと思っているに違いない。なぁ、エバンデス婦人。何かあたしたちにできることはないのか?」
意を決してウィザードがそう訊ねた。ソーサラーとネクロマンサー、そして少女たちにも、覚悟はできているようだ。
「わかりました。ただし、成功についてはなんらの保障もできません。また先ほどもお話ししたように、私とこの子は今回のことであなたたちに力を貸すことはできません。とても大変な旅路になりますが、覚悟はおありですか?」
その言葉は、暗に思いとどまるよう求める響きを含んでいた。それはもちろんウィザードたちにも伝わったが、ウィザードは頷いて答えた。
「やってみるよ。人の縁が貴重でかけがえのないものであることを教えてくれたのはあんたたちだ。いま、その縁の強さが試されようとしている。まして、縁者の求める助けを無下にするのは人間の仕業としてもとるものだ。」
そう言って、ウィザードは夫人のサファイアの瞳をまっすぐに見据えた。
「そこまでいうのなら…。いいでしょう。」
婦人もまた、逃げることなくウィザードの視線を捉えてそう返した。
カウンターの周りを現生のものではない光と香りが包んでいる。その神秘の空間の中で、ただ時だけが日常と変わらぬ仕方で進捗を刻んでいた。
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第6集その3『カリーナの依頼』完
