
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚最終集その9『束の間、そして…』
修学旅行初日の、あの夢のような一夜が明けて、次の朝が訪れた。今日は初等部全体での、遺跡『聖天使の墓標』の歴史学習の日である。朝食を終えると、各クラスごとにホテルのエントランスに集合した。
「これから、全体歴史学習に出掛けます。目的地は既報の通り、この魔法社会の創造にまつわる重要な土地として伝わる『聖天使の墓標』です。旅行ガイドの方がご説明をしてくださいますから、各自それに耳を傾けるように。今日学習したことについては、後日レポートにまとめて提出してもらいます。また、この、魔法社会創造の経緯と神話については、みなさんがまもなく臨むことになる中等部への進級試験『魔術と魔法に関する一般教養試験』でも重要な出題範囲となりますから、各自しっかり学習して下さい。」
マリクトーンからの指示が飛んだ。今日は全体行動日なので、全員制服であり、ルイーザはやはり「フィナを守る力の象徴」としてローブをまとっている。わだかまりを解いてローブを脱いだフィナとは対照的であった。
全体歴史学習という触れ込みではあるが、初等部最高学年に属する学徒全員が本当に一斉同時に活動するわけではなく、各クラスごとでの活動となっていた。そのため、マリクトーンの言う旅行ガイドも、各クラスごとに1名が随伴し、順次その遺跡を巡ることになっていた。
フィナたちのクラスを担当してくれることになった旅行ガイドは、30歳前後のまだ若い女性で、名をオヨネ・マルコスといった。南方出身の少し浅黒い肌で、快活そうな魔法使いで、ガイドだけでなく、学芸員の資格も併せ持つらしく、その知識、とりわけ太古の創世神話に関するものには並々ならぬものをがあった。
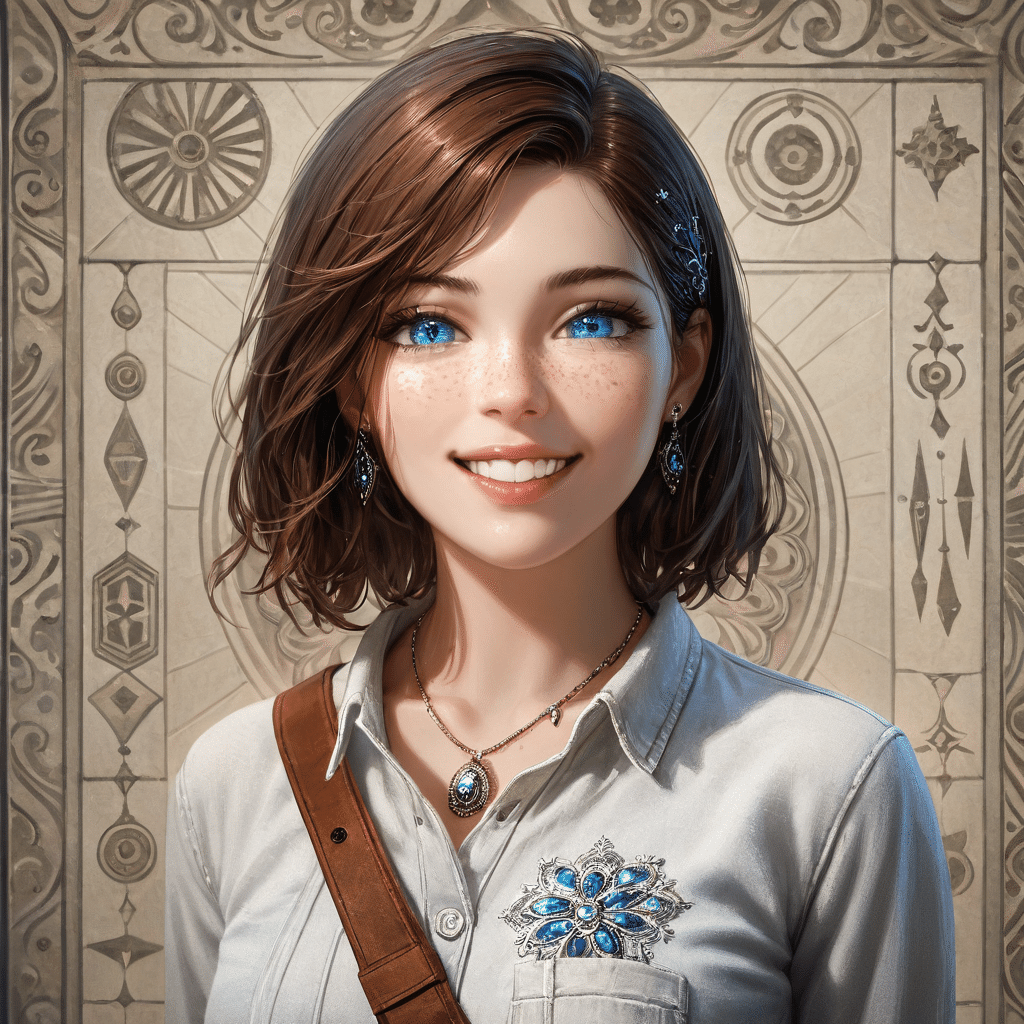
彼女のその卓越した知識は、『聖天使の墓標』に並々ならぬ関心を寄せるルイーザの心を大いに捉えたようで、彼女は、例の古文書を取り出してはオヨネに様々な質問を投げかけていた。
ホテルから『聖天使の墓標』までは、徒歩で40分ほどかかり、小高い円形の丘を登った先にその神秘の遺跡はそびえている。といっても、今ではすっかり観光地で、フィナたちだけでなく、大勢の観光客がそこに押し寄せていた。
* * *
道すがらオヨネが語ってくれた創世神話は実に興味深いものであった。それは、魔法社会一般に昔話として知られているものとは、ずいぶん違っていた。彼女は言う。遥か昔、まだこの世界に形というものがなかったとき、創造主の命を受けた1柱の天使が、天界である『至福の園』からこの地に降り立ったのだと。
その天使は、世界創造の命を受け、『生命の源』という名の、特別な神秘の水から、まず5人の聖人を創造した。『5聖人』として知られる彼女たちには、それぞれ、マリア、アグネス、リタ、クララ、スザンナという名が与えられ、創造の聖天使は彼女らと共に世界の創造にとりかかった。
彼女たちは、自然法則による魔術の要素と、創造主の神秘性の具現化である魔法の要素をこの世界に取り込み、それらを巧みに織り込んで、何もなかったところを、まず天と地の二つに別(わ)けた。それぞれは、光と影によって輪郭を与えられ、自然法則と魔の神秘の両方によって、運航と変化という息吹を吹き込まれたのだと言う。

次に、彼女らは、地を海と陸に別(わか)ち、海を生命の根源と発生の場所とする一方で、陸をその実践と営みの場所に位置づけて、そこに数多(あまた)の生命を形作っていったそうだ。こうして、海と大地は生命在に満ち溢れ、その中にやがて人が姿を現すに至る。

『創造主』によって人には愛が与えられ、他人と縁(よすが)を結び、互いを愛しみ、隣人と取り結ぶ関係の連鎖によって、その世界のすみずみにまで絆を紡いでいったのだそうだ。愛と絆に満たされた創生の時代は、きわめて幸福なものだったと言う。しかし、時と共に、人の魂の座に据えられた愛の内に「澱(よど)み」が生まれるようになった。それが果たしてどこから来たのか、何に由来するのか、『聖天使』と『5聖人』は大いに頭を悩ませることになった。しかし、その出所は一向に明らかとならぬまま、なお一層世界の創造は進んで行った。ただ、不思議なことに、人の心が穢れれば穢れるほど、それらが織りなす世界は輝きと多様性を増し加え、外延を広げ、発展し、成長したのである。まるでそれは、世界それ自体が「穢れ」を糧として茎を伸ばし、葉を広げ、花をつける存在ですらあるかのようにすら思える不思議であった。そしてついに、世界は完成する。

創造の業が終わったあと、人の世界は大いに繁栄した。しかし、繁栄と共に愛の半面である澱みはどんどんと大きくなり、やがてそれは1つの結晶となってこの世界に影を落とすようになっていく。次第にその澱みは、絆を壊し、愛を裏切り、心の内を猜疑と憎しみに満たしていった。だが、その時代にもなお、人の縁(よすが)はまだ潰えることはなく、危うく、儚く、哀しいものではあったが、それでも人々は互いを求め、縁(よすが)と絆を結び、関係という営みの中で世界を彩っていた。ところが、人と人の縁(よすが)と絆が深まるほどに、なお一層その内なる穢れは大きな染みとなって、遂にそれは互いに対する無関心を生じるようになったのである。
この、猜疑、憎しみ、そして、無関心へと繋がる一連の運動は、時と共に人々の結合を解体し、孤立と絶望の色に世界を染めていった。この出来事を、『最初の黄昏』というのだと、オヨネが教えてくれる。サファイアの瞳はその太古の神話に全霊を傾けて聞き入っていた。
「愛に満ちた絆の世界」を創り上げることを創造主から託されていた『聖天使』と『5聖人』は、『最初の黄昏』に暮れていく世界に大いなる焦燥をおぼえ、人のもつ魂の座に宿った「穢れ」の正体を突き止めようと奔走し、そして遂に、その正体を突き止めることになるが、なんとそれは創造に伴う必然のなせる業であった。
光を照らせば影ができ、影は光によって認識されるように、引き離しがたい両者の相補関係を象徴するようにして、愛と穢れは、創造の過程の中で自然的に生じたのである。『聖天使』の存在は、その対となる『魔王』を生み出し、魂の座に宿る愛の内側には、憎しみという汚点が必然的に広がるようになった。そして恐ろしいことに、愛それ自体が、それと対を成す憎しみの権化、邪神『セト』を孕むに至ったのである。やがて、人が、縁(よすが)と絆を求めるのとちょうど同じようにして、『魔王』と『セト』は互いを求めあい、それはひとつに溶け合って『大魔王』となる。そして、それが支配したものが、力と傲慢、堕落、そして『無関心』であった。
『無関心』による愛の侵害は憎しみによるそれよりも遥かに苛烈で、人と人、人と世界、人と創造主の間の縁(よすが)を完全に断ち切ってしまうほどに徹底していた。
『最初の黄昏』の時代、世界は闇に閉ざされ、暗雲が空を覆い、そこから降り注ぐ血の雨が放つ黒い靄(もや)によって、人々の内にある愛は根底から破壊され、他人、世界、創造主を顧みることはもはやなくなり、ただ孤立と孤独の中で死に抱かれていった。
愛が自ずから孕む穢れによって、愛それ自体が破壊されるという哀しき命運は、あたかも、光が影を消し、影が光を覆いつくすのと同じであるように思えた。
この事実に直面した『聖天使』と『5聖人』は、やがて、翳(かげ)りの原因である愛の半面を、その内から取り除こうとして、『大魔王』に挑むことになる。彼女たちは、『大魔王』を『魔王』と『セト』に別ち、それぞれの残滓を封じ込めることに、ついに成功することになる。
そして、まず、人の心に穢れをもたらす堕落した君主として『大魔王』が『奈落』の底に繋がれた。
続く『セト』との戦いは熾烈を極めた。その最期、『聖天使』は『セト』の首をへし折ったが、『セト』はその足を噛み砕いて毒に犯し、結局にして両社は共に斃れることとなる。『5聖人』は、『聖天使』と『セト』を共にこの地に葬り、最も深いところにセトの亡骸を安置したうえで、文字通り『蓋(ふた)』をするように『聖天使』の墓標を設置した。こうすることで、『魔王』がいかに奈落から激しい穢れを放とうとも、その穢れからなる憎しみが『セト』との邂逅を永劫果たせぬようにしたのだ。こうすることで、憎しみが無関心に変じることを防ぐことが図られた。
憎しみは、相手との縁(よすが)をいまだ忘れていないという点で、憎しみよりは愛に近い、とオヨネは言った。本当に恐ろしいのは、魂の座の穢れが、再び『セト』と触れて、憎しみを無関心へと変じてしまうことなのだと言う。オヨネの言葉に聞き入るサファイアの瞳には、何か燃える輝きが揺れているような気がした。それが、この時期の南国特有の、まばゆい陽光のなせる業であったのかどうか、この時はまだ、誰にも知る由はなかった。しかし、時の歯車だけは、ゆっくりと、しかし確実に、告げるべき時を告げるべく、刻々と回転を続けていたのである。
愛が必然的に穢れを孕むことを知った創造主は、人に愛を与えることの不確かさと危うさを痛感し、以後、穢れと憎しみが二度と融合することのないよう、時と時空の運航に関わる力を自ら放棄して、愛が無関心へと変じる契機、すなわち「時間」の管理に、一切干渉しないことを決めたのだと、オヨネはそう綴った。
彼女が紡ぐ創生の物語は、魔法学の教科書に通説として載せられているそれとは随分違っていた。そもそも魔法学の通説には『魔王』も『セト』も登場しない。ただ、創造主の命を受けた『聖天使』が『5聖人』とともに創造の業を成し終え、その後静かにこの地に眠っているというただそれだけであった。学徒の多くは、到底試験に出るはずのないその異端神話を真に受けることなく聞き流していたが、唯一サファイアの瞳だけは、それに釘付けとなっていた。
オヨネは最後に、「至るまでに2つ、捧げるのに2つ、最初に1つ」という謎めいた言葉を語って、その創生の語りを終えた。『聖天使の墓標』という名の、入り口のない珍妙な遺跡は、陽光の中に冷たい石造りの巨躯を静かに横たえている。
誰もが、友との話に花を咲かせ、魔術記録の撮影に勤しむ中で、ルイーザだけはひたすらに、その墓標に刻まれた文字のような記号のようなものを追っていた。「至るまでに2つ、捧げるのに2つ、最初に1つ」というオヨネの最後の言葉を、ルイーザはその間ずっと反芻していた。
* * *
「ルイーザ、ずいぶん熱心ね。」
フィナが言った。
「ええ、とても面白いと思わない?オヨネさんの語る創世神話は、私たちが普段魔法学の教科書で習う創世神話とはまるで違うけれど、世界を無に帰す黄昏がかつてこの世界にあったなんて感慨深いじゃない?」
「うーん、私にはよくわからないけど…。」
「愛は穢れを伴ない、穢れが憎しみに触れると無関心に至る。じゃあ、無関心の先は滅びだけなのかしら?そこに強い興味を惹かれるの。もしかするとその先に、創造の業以上の、なにかしらの『力』や新しい可能性があるのかみしれない、そう思うと、なぜか胸が高鳴って興奮が止まないわ。」
ルイーザは陶酔したような口調で言った。その姿に、フィナは当惑するしかない。
「正義は力、力こそ正義。もしかしたら、無関心を乗り越えた先に到達できる純粋な力こそ、正しさの極致、正義そのものなのかもしれないわ。正義、とりわけ『力』によって実現する絶対の正しさは、きっと愛なんていう、虚ろで穢れた脆弱な存在なんかより、もっとずっと遥かに強固で完全なものを私たちを示してくれるのかもしれない。オヨネさんの話には、そんな可能性を感じてやまないのよ。」
そう言うルイーザの瞳は、濃厚な光をたたえていた。
「愛よりも完全なものなんて、そんなもの本当にあるのかしら?」
そう言うフィナをよそに、古文書を片手にルイーザは、遺跡の周りを食い入るように観察していた。
必然的に穢れを孕む愛、それは愛が光と影の両面を持っていることを意味していた。しかし、ルイーザの美しい瞳は、そうした二項対立的な要素を超越した、なにかもっと「強力で完全なもの」を見つめているようであった。そんなものが果たしてこの世界にあり得るのか?もしあるのなら、創造主はなぜ敢えて人に「それ」ではなく「愛」を与えようとしたのか。取るに足りない異端の物語が、思わぬ興味を駆り立ててやまなかった。
秋の日が、やや急ぎ足に西に傾いていく。常夏のこの南方にあっても、それは変わらなかった。この時間の運航が、愛を憎しみに、憎しみを無関心へと再び遷移させることがあるのだろうか?ルイーザの瞳はその先に何を見るのか?
昨日と同じ豪奢な食事の後に訪れる、睡眠という無意識の作用の中で、フィナはルイーザとの縁(よすが)と絆が永遠であるべきことをただただ願っていた。新しい朝が来る。
* * *
明けた翌日には、各クラス、各班ごとの自由行動が割り当てられていた。学徒達が最も心待ちにしていた期日の到来である。フィナたちのクラスでは、班の大半がプライベート・ビーチでの、非常に珍しい秋の海水浴を希望していた。買い物は次の日の全体行動でも可能だから、ということもあって、ほぼ全員が今日という日を娯楽一色に染める選択をしていた。朝食を終えると、各自ビーチに繰り出し、めいめい思うままにそこでの時間を堪能していく。

フィナとルイーザもまた同様であった。そこには引率兼監視役として、マリクトーンとヴァネッサの姿もみえる。
「おい、貴様ら!いきなり海に駆けるやつがあるか!その前にしっかり準備運動をしろ。ほら、貴様らのことだ。さっさと戻って、十分に身体を慣らせ。波と戯れるのはそれからだ。」
相変わらずのヴァネッサの檄が飛ぶ。
「そんな固いことをおっしゃらないで、先生も一緒に泳ぎましょう!」
何人かの女学徒たちがヴァネッサを誘った。
「若く力溢れるお前たちと一緒にしてくれるな。私はここでお前たちの安全を見守っておいてやるから、しっかり準備運動したら思う丈遊んで来い。今できることは、今のうちにだ。」
学徒達からの誘いをやんわと断って、サン・パラソルの下に設置したビーチ・チェアに全身を横たえながら、ヴァネッサはどうやらトマトをベースとしたカクテルらしきものを口に運んでいた。これが彼女なりのビーチの満喫の仕方のようだ。

マリクトーンは、ルシアンと波打ち際で戯れている。大会以降、クラス内での孤立を深める二人であったが、それでも二人の間には特別な縁(よすが)があるようで、この場所の開放的な空気が、彼女たちの心を幾ばくか軽くしているようであった。そのマリクトーンの無邪気な姿を、ヴァネッサはサングラス越しに見守っている。
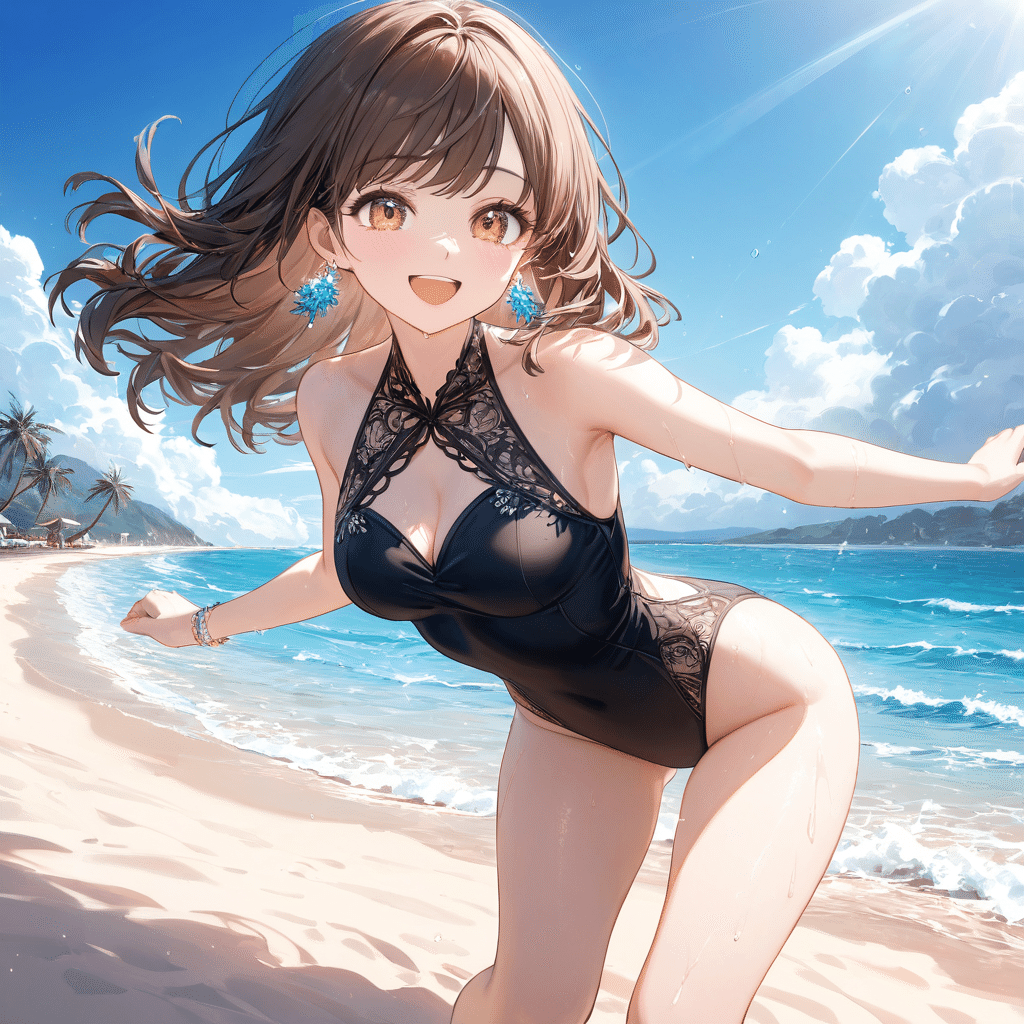
フィナとルイーザもまた、この美しいビーチを心行くまで満喫した。束の間の楽しいひと時が、これまでずっと続いてきた緊張をやわらげてくれているようだ。空にはまるで真夏の時期のように白い入道雲が浮かび、太陽は斜めになりながらも、まばゆい光でその穏やかな時を演出していた。吹き抜ける潮風は心地よく、あちこちから顔をのぞかせるヤシの枝葉を、頻りに揺すっていた。若者たちの奏でる黄色い声が、いつまでもその場を彩っている。
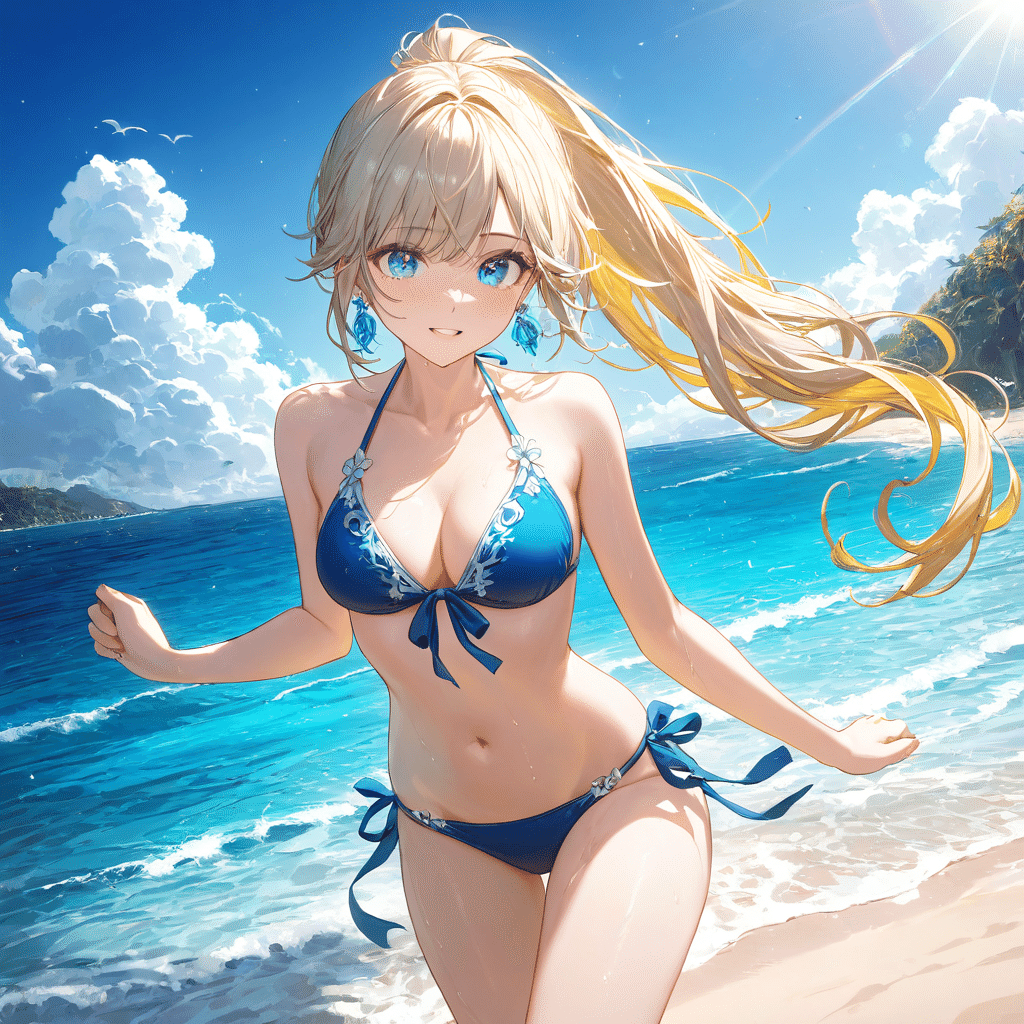

やがて、太陽はゆっくりと地平に近づき、空と海の境界を二色に別(わか)っていく。それはオヨネの語った、天と地の創造の時のようでもあった。しかし、少なくとも傍目には、フィナとルイーザが紡ぐ友愛の中に、穢れの染みなどあるようには見えなかった。
心ゆくまでビーチを堪能した学徒達は、夕飯の為にホテルに引き上げていく。着替えを済ませると、レストラン前のホールに集合した。
* * *
その夜の趣向は、少々変わっていた。フィナは一昨日、昨日同様、ルイーザと二人で夕飯を楽しむものとばかり思っていたが、なんとルイーザはテーブルに、ルシアン、アベル、ダミアンの三人を同席させたのだ。かの一件以降、彼らは、すっかりルイーザに頭が上がらなくなっていた。その日はやはり地元特産の魚料理であったが、思いがけず、しかも食事という相当にプライベートな場面に無理やりに同席させられたことから、3人の少年たちは、正直食べ物の味などまるで分らない心持だった。

その異様ともいえる光景に、少し離れた教員たちのテーブルからマリクトーンが心配そうな視線を送っていたことは言うまでもないだろう。流れ作業のようにして、食器と料理だけが次々に入れ替えられていく。
やがて、その一連が一段落して、デザートの段になったとき、ルイーザがおもむろに少年たちに話し始めた。
「今晩はみんなで肝試しをしましょう!」
その脈絡ない提案に、フィナも含めてみなぽかんとしている。
「肝試しって、なんで俺たちを誘うんだよ。やりたきゃお前らだけやればいいだろうが。」
ルシアンが悪態をつくが、それをルイーザは視線で諫める。
「あら、私にそんなこと言っていいの、ダミアン?あの日のことを忘れたのかしら?」
「いや、そう言うわけじゃないけど、俺たちとお前らが馴れ合う道理がないだろう?」
「馴れ合うだなんて、そんなんじゃないわ。せっかくマリクトーン先生の取り計らいで『仲直り』ができたのに、仲良くしましょうよ。」
意外なことを口走るルイーザ。正直フィナは、そのときのルイーザの様子に少なからぬ違和感と恐怖を感じていた。
「あんたに逆らう気はないよ。あの時の約束だしな。でもどうしようっていうんだ?」
そう訊いたのはアベルだ。その言葉を待っていたかのようにしてルイーザが言う。
「今夜、みんなが、そう、先生も含めてね。みんなが寝静まった時間を見計らって、『聖天使の墓標』を探検しようと思うの。」
その提案に一同ぎょっとする。
「でも、あそこには学徒だけで赴いてはいけないという魔法学部長先生のきつい言いつけがある。それを破ろうっていうのか?」
ルシアンが訊いた。
「ええ、そうよ。こんなに面白い機会を不意にするなんてありえないわ。昨日ガイドさんから聞いた通り、あそこにはきっと公式には知られていない大きな秘密があるはず。それを探し出してみたいと思わない?」
普段のルイーザとは思えない口調で、そのルイーザは言った。
「あんなのただの作り話だろう。魔法学の教科書の記述に照らせばてんででたらめだ!そんなのに取り合ったっていいことはなんにもないぜ。」
そう言うダミアンに、アベルも続く。
「百歩譲って、あのガイドが言ったことに真実味があるとしてだ。そこに隠されているのは邪神『セト』って恐ろしい存在の封印の地なんだろう?そんな厄介に巻き込まれるのは正直ごめんだ。」
手元のお茶を一口傾けてから、ルイーザが言った。
「男のくせにだらしないのね。マリクトーンの後ろ盾がないと、何もできないってことなのかしら?」
その瞳がルシアンを一瞥すると、彼は複雑な表情を浮かべた。
「マリクトーン先生を悪く言うな。」
「じゃあ、マリクトーンなしでも何かできるってことを証明してみたらどう?」
ルイーザは明らかにルシアンを挑発する。
「い、いいぜ。そこまでいうならついて行ってやる。どうせあんな墓標、入り口も何も無いんだ。行って帰ってそれで終わり。それくらいの肝試し、やれと言うならやってやる。」
ルシアンはルイーザに絡めとられてしまった。
「そう、ルシアンには勇敢さがあるようね。で、あなたたちはどう?あなたたちは腰抜けかしら?」
聞こえてくるのはルイーザの声だが、同席するフィナはまるで別人といるかのような錯覚を起こしていた。
「ルイーザ、やめようよ。危なすぎるわ。」
そう言ってはみたものの、ルイーザに聞く耳はない。
「大丈夫よ、フィナ。約束したでしょ。どんなときにもあなたは私が守ってあげる。今大切なのは、こいつらに勇気があるかのか、それともただの腰抜けなのか、それを見極めることよ。」
なおも挑発するルイーザ。フィナに対して複雑な感情を抱くダミアンがそれに応じる。
「いいだろう。そこまで言うなら行こうじゃないか。なぁ、アベル。」
アベルは全く乗り気ではないが、腰抜けと言われるのには大いに抵抗があるようだ。
「わかったよ。ルシアンが言うように、行って帰って来るだけだ。そんな簡単なことはない。俺たちが腰抜けかどうか、みせてやるよ。」
ついに、3人の少年たちの意見が巧にまとめられてしまった。ルイーザは見たことのない笑みを口元にたたえ、その目を細めている。
「男たるものそうじゃなくちゃね。それじゃあ深夜1時、こっそり部屋を抜け出して、ホテルのエントランス脇に集合よ。いいわね。もし来なければ、臆病者としてみんなの前でつるし上げてやるからそのつもりでね?」
フィナは、ルイーザを思いとどまらせようとあたふたするが、深夜1時に、創生の地への暗夜行路を決行するということで、結局そのまま話が決まってしまった。ほくそ笑むサファイアと不安に揺れるエメラルドが、奇妙なコントラストを描いていた。
「絶対に来なさいよ!」
「ああ、二言はない。」
そう言って、ルイーザと少年たちはテーブルを離れる。その間で、フィナだけが立ち尽くしていた。
「大丈夫よ、フィナ。あなたは私が守るもの。何の心配もないわ。ただ、一緒に来て欲しい、それだけのことだから。」
「うん…。」
奇妙な説得の後で、二人は部屋に戻っていった。地平の裏を駆けるせっかちな太陽に変わって、真っ白い月が夜の時間を静かに刻んでいる。10時、11時…、日付が変わってついにその約束の時間が到来した。
息を殺し、身をひそめるようにしてエントランス脇の影に向かうと、少年たちは既にそこで待っていた。
入り口も出口もないただの石塊、そこに行って帰るだけ、その儚い見通しが、かろうじてフィナの心の支えとなっていた。少年たちの内心もおそらく同じであろう。ただ、その儚さと違う、何か決意とも確信ともつかない色がサファイアの瞳にだけ宿っていた。
* * *
一昨日の全体歴史学習の折に辿ったのと同じ道を進んで行く5人。南国のこの地では、夜風が冷たいということはなかったが、その生暖かさとそこに含まれる潮の湿度が、不穏で安心できない心地をもたらしていた。
途中、フィナは、自分たちとは違うもう一つ別の足音がするように感じて振り向いたが、闇の中には遺跡に続く一本道の他には何も見つけることができなかった。
ルイーザに先導されて一行はどんどんと丘を登っていく。やがて巨大なパンケーキのような丘の上に出る。そこには邪神を封じるために『聖天使』で蓋をしたという古い石造りの墓標が、静かに佇んでいた。
「ルイーザ、約束は果たしたぜ。もう満足だろう。時間もずいぶん遅い。急いで帰ろうぜ。」
ダミアンがそう促したが、ルイーザはその巨大な立方体上の墓標の周りをせわしなく移動しながら、なにかを懸命に探していた。
「あったわ!ダミアン、肝試しの本番はこれからよ。その勇気を見せてちょうだいね。」
そう不敵に笑うと、ルイーザは詠唱を始めた。
『153478889102233…』
はじめそれは古典語か古代魔術語による術式の詠唱に思えたが、よくよく聞いていみると、ルイーザは何らかの数字の羅列を唱えていた。どうやら数秘術のようだ。彼女の声が数字を刻むたびに、立方体の壁面に魔法光が少しずつ灯っていく。
やがて、その声は2と6だけを交互にしたり、続けたりし始めたが、それに伴って壁面を彩る魔法光はいよいよ大きくなり、遂にその無機質な一面に真っ黒い影のような口を開けた。一同を極度の緊張が襲う。ごくりと息を飲む音が聞こえた。

「さあ、行きましょう。」
そうルイーザが言うと、
「い、いやだ。もうこれ以上無理だ。俺は帰る。」
ダミアンが明らかなおびえを見せた。ルシアンとアベルも震えている。
「何を言ってるの、肝試しはここからじゃない?」
「冗談じゃない。こんな恐ろしい場所に入るなんて俺はいやだ!」
なおもダミアンが拒絶の意思を示すと、ルイーザは、剥き身の『フォールン・モア』を取り出して、それをダミアンの喉元に突き付けて言った。
「それはそれで別にいいのよダミアン。あなたの役目は到達のための1つなんだから。中に入るのが嫌なら、ここで息絶えてもらうわ。」
ルイーザの瞳は従前と何ら変わらぬ透き通る青色だったが、しかしその様相は狂気の色に染まっていた。
「わ、わかった。わかったよ。一緒に行く。一緒に行くから…。」
「そう、最初からそう言ってくれればいいのに。じゃあ、あなたからね。」
そう言うや、ルイーザはダミアンの身体を前に押し出して、その入り口らしき黒い空間へと進むように促した。
おそるおそる入り口をくぐろうとするダミアン。その一瞬だった!何か水平に魔法光か金属のひらめきのようなものが走ったかと思うと、ダミアンの身体はその場に崩れ落ち、そのまま動かなくなってしまった。
「ル、ルイーザ。よしましょう。ダミアンが、ダミアンが…。」
涙にぬれた震える声でフィナが言うと、
「何を言っているの、フィナ。こいつがあなたにしたことを考えれば当然の報いよ。悪が断罪された、ただそれだけのこと、気にする必要なんてないわ。まずはひとつ。さあ、行きましょう。」
そうとだけ答えて、ルイーザは残る三人を連れてその脅威の空間へと足を踏み入れて行った。ルシアンとアベルは、恐怖にすっかり絡めとられている。
白い大きな月が、妖しく口を開くその立方体の墓標を虚空の中に描き出していた。ダミアンはもう、帰らない。
to be continued.
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚最終集その9『束の間、そして…』完
