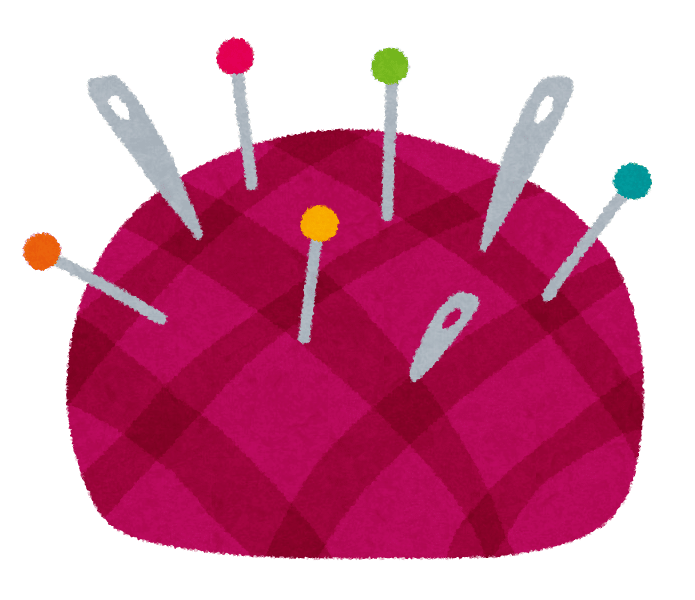「鑽笥」って何? 調べもののちょっとした技法
昨日、つばつばさんという方が「鑽笥」という言葉についての情報を求めるツイートをしていらしたので、調べてお答えしてみました。
「鑽笥」って何かわかる方いますか……?嚢床子というクッション付きの椅子のようなものの説明に「其の體面圓く鑽笥の如し」とあったそうです
— つばつば🤍 (@tubatuubaa) September 30, 2024
『江家次第秘抄』によれば、「ハリサシ」のようなものだそうです。https://t.co/gVVbeQuLaE https://t.co/dX2Q46fUHU pic.twitter.com/TWYerrp0VY
— *iwo (@iwoghoti) September 30, 2024
おそらく多くの方にとっては「鑽笥」とは何かという情報よりは、それをどうやって調べたのかの情報の方が役に立つでしょうから、以下にそのことを書いておきたいと思います。
1. あらかじめ色々と読んでおく
情報化社会と言われる今日、知識を持っていることよりも、必要な時に調べて取り出せることの方が大切だ、という言説は人口に膾炙しています。しかし、それはある面では正しいけれども、ある面では正しくないでしょう。情報が書かれているものを探して読むためにも、そこに書かれていることを理解するための知識が必要だからです。
今回私が調べてお答えしてみようと思ったのは、「嚢床子」という語やそれに対する「其体面円如鑽笥」という注釈の字面に見覚えがあり、「調べられそうだ」という印象を持ったためでした。調べている途中で判明したのですが、『江次第抄』にあるこの文言が引用されている書物を読んだことがあり、それが頭の片隅に残っていたようです。
2. ジャパンナレッジで調べる
さて、私はジャパンナレッジPersonal(年額16,500円)を契約しています。
『日本国語大辞典』(第二版)が入っており、これに「鑽笥」という項目があればいいのですが、残念ながらありません。そこで全文検索をしてみると、「のう‐しょうじ[ナウシャウジ] 【嚢床子】」に次のように『江家次第』が引かれており、文脈が分かります。
*江家次第〔1111頃〕一・元日節会「立嚢床子二脚〈嚢床子、其体、面円如鑽笥、長三尺広一尺五寸高一尺許、有三疋〉」
ところで、こういう調べものではそれが何という文献のどこに出てきたのかというコンテクストが重要です。今回は『日本国語大辞典』(第二版)にちょうどこの部分が引かれていたのですぐに出典が分かりましたが、そうでなければすぐには分かりません。人に尋ねる場合、何という文献のどこに出てきたのか、ということまで合わせて聞くのが望ましいでしょう。
3. 次世代デジタルライブラリーで調べる
次に、国立国会図書館の「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)で「鑽笥」と検索してみます。出てきたのは9件だけなので目視で全部見るのが容易な量です。
目ぼしいものを物色していると、『江家次第』の写本が出てきました。「サンケ」と振り仮名があります。
「サン」は朱、「ケ」は墨で書かれていますが、おそらく元の本にあったのが「ケ」で、「サン」は後から加えたのではないでしょうか。重箱読みなので本当に「サンケ」と読むべきなのかはよく分かりません。
また、ここで色々見ているうちに、『日本国語大辞典』に引かれていた「立嚢床子二脚〈嚢床子、其体、面円如鑽笥、長三尺広一尺五寸高一尺許、有三疋〉」のうち、「立嚢床子二脚」の部分は『江家次第』の本文で、〈…〉内はどうやらそれの注釈書である『江次第抄』に由来するものであるらしいことが分かってきました。
4. ウィキペディアで調べる
さて、出典が『江家次第』『江次第抄』だと分かったところで、ウィキペディアで『江家次第』について調べて、周辺情報を少し集めます。
有職故実書として高い評価を得ており、これに対する注釈書として、一条兼良の『江次第抄』、尾崎積興の『江家次第秘抄』がある。現在伝わる本文は、『江次第抄』の一部が竄入したものもある。
「鑽笥」という言葉が出てくるのは『江次第抄』だったのでした。すると、もう一つの注釈書『江家次第秘抄』の方に「鑽笥」に対する注釈があるのではないでしょうか?
5. 国会図書館サーチで調べる
というわけで「国会図書館サーチ」(https://ndlsearch.ndl.go.jp/)で『江家次第秘抄』を探すと、『故実叢書 第17 増訂版』が出てきました。閲覧には国立国会図書館の利用登録が必要ですが、登録していれば自宅でも見ることができます。
そして全文検索機能で「鑽笥」と入れてみます。
すると、ビンゴ!

「鑽笥ハリサシ也」という注釈がでてきました。めでたしめでたし。