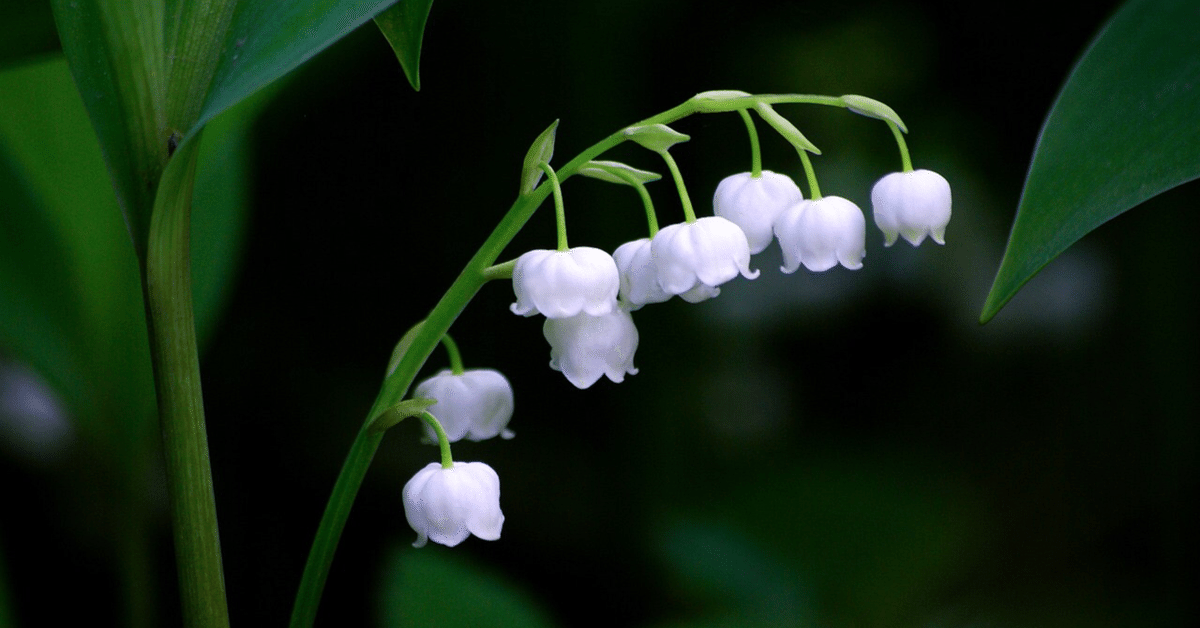
Nameless
ーーー鈴の音、ひとつ。
微かに響いたその音が君と俺を繋いだ。
Nameless
ひやりと肌を撫でられたような気がして目が覚めた。ぼんやりとする意識に気怠い身体、その内側は熱を持っているように火照っている。きっと久々に飲み過ぎたアルコールのせいだ。
重たい瞼をうっすら開ければ、薄暗いオレンジ色の光の下、ベッドの脇にぐしゃぐしゃになって置かれているシャツが目に入った。熱くなった身体に纏わりつくのが居心地悪くて、それを投げ捨てたのを何となく覚えている。所々冷たさを取り戻している冷感シーツに寝返りを打った時、ふと違和感を覚え、身を起こした。
するりと落ちる肩紐なんかより、隣にあるはずの温度が消えてしまっていることに心がざわりと波立つ。
おかしいな。まだ夜中なのに。どこか行っちゃったの。
肌にそよ風が当たる。産毛がそわそわするようなこの感覚は、私が起きるきっかけになったものと同じものだ。
風が吹いた方向を見れば、ベランダの窓が半分ほど開いている。入ってくる夜風にカーテンがゆらゆらと揺れていて、ひらりと捲れた先に見慣れた大きな背中を見付けた。
なんだ。そこにいたんだ。いつの間に外に出ていたんだろう。
束の間の安心感に満たされていると、カラカラと窓を開けて、ベランダから戻ってくる彼と目が合った。
お家の時にしかかけない眼鏡。飲んでいた時に着ていたのと同じ黒のTシャツ。片手にはタバコのカートリッジ。
気怠い感じで部屋に入ってきて、睫毛の長い垂れ目と暫し見つめ合う。
「あっごめん。起こした」
「んーん」
生返事のような気の抜けた声に、「もう少し寝てな」とやんわりとした低音が被さってくる。
彼が隣に腰掛けた瞬間、肺に悪そうなスモーキーな匂いがふわっと香る。不快に感じる灰色の香りにさえ安心感を覚えるのはきっと彼の香りだから。
またゆっくりと近づいてきた眠気に、身を任せるようにベッドに寝そべる。同じように彼も隣に横になる。シーツの程良い冷たさと彼の体温。別々の温度が何とも心地良い。
彼の方を向くと、彼もまたこちらを向いていた。眼鏡を外さないのはまだ起きているつもりなんだろう。
落ちたままのインナーの肩紐を、私よりも一回り大きい彼の指が肩に掛け直す。細かな気遣いが嬉しくて幸せだなって感じる。申し訳程度にお腹にもタオルケットがかかる。そんな優しさがとても愛おしい。
「おやすみ。ゆーくん」
「おやすみ。キミちゃん」
ゆーくん。キミちゃん。
私たちの呼び名。
でもこの名前で呼ぶのは私たちだけ。
本名にも掠らない、お互いを呼ぶだけの単なる愛称。
名前の無い関係が彼と私を結び付けている。
「……それでもう同棲して一年くらい?」
「そうだね。去年の秋くらいに始めたから、もうちょっとでそのくらいになるかな」
「おー順調順調」
「しーちゃんのところほどじゃないよ」
土曜日。仕事の休みがたまたま合致したしーちゃんとランチ。
ドラマとかで描かれるようなお洒落なカフェテラスではなく、一部の地域でチェーン展開しているパスタ専門店だが、気兼ねなく食べられるから割と好きだ。ドリンクバーがセットで注文できて、値段もリーズナブル。長居したい時は重宝しているお店でもある。ちなみにここで食べられるティラミスがなかなか美味しいのも選ぶ理由の一つだったりもする。
お互いの近況を交えつつ、ランチもデザートも食べ終えたあたりで、この前の夜にあったことをしーちゃんに早速ご報告。と言っても、ベランダから戻ってくる気怠げな感じが格好良かったという思いの丈をただつらつらと一方的に語っただけだけど。
そんな身内の惚気に、嫌がったり、逆に興味ある感じで聞きたがったりせず、うんうんと頷いて聞いてくれるしーちゃんの割とドライな性格が好きだ。ごめんねしーちゃん。話せるのしーちゃんしかいないんだ。
「私のことはいいから。特に何も進展ないし。なあなあできているだけだから」
と、照れくさそうに笑うしーちゃん。ストローをひとかき回して「久々に飲むと甘いね」と、メロンソーダの小さな泡に繁々と視線を遣っていた。
緩く巻いたラベンダーアッシュとメロンソーダ。大人な雰囲気と子供っぽい飲み物の組み合わせが珍しくて、照れ笑いするしーちゃんも可愛くて、ついつい私の頬が緩む。
しーちゃんとは昔から、遊ぶ時には必ずと言っていいほどドリンクバーがあるところに行っていた。学校終わりのカラオケも、小腹が空いた時のレストランも、ちょっと遠出した先の場所でも、ドリンクバーがあれば頼んで、グラスが空になるのにも気付かないくらい喋りっぱなしだった。
その頃のしーちゃんが持ってくるドリンクは、炭酸ジュースか何を配合したかわからないオリジナルが主だった。「何でもミックスできるのが醍醐味でしょ」と言った矢先、カルピスとココアとオレンジジュースを混ぜた何とも言えない味を生み出したことは生涯忘れられない出来事だ。それを本当に美味しいと思って作ったのか、はたまた、とんでもないひらめきに流されて作ったのかはその時のしーちゃんしかわからない。
今ではコーヒー片手にオフィスワークを熟すような大人びた雰囲気で、もうアレコレとミックスしたりはしないんだろうけれど、中身は私の知っているしーちゃんのままなんだと思うと少し安心する。
「早瀬くんがそこまで優しいっていうイメージ、なかなか無かったわ。捨てられた子犬に傘とか置いていく印象はあったけど」
「すごいわかる。魚も綺麗に食べるし、ご飯粒も一粒も残さないで食べるんだよ」
「えっウチの人と全然違う。真逆なタイプなのにどうして友達になれたんだろう」
「ひーさん細かいの苦手そうだもんね」
「美味しそうに食べてくれるのはいいんだけどね。せめて飲食店で働いているんだからもう少し自覚を持ってって思う……最近も変なこと始めるし」
「変なこと?」
「最近ね……」
『早瀬くん』はゆーくんの名字。『ひーさん』はしーちゃんの彼のあだ名。段々と積み重なっていく会話に、噂の本人たちは二、三回では済まないくらいのくしゃみをしているかもしれない。でもそんなことは一切気に留めることなく、学生に戻ったようにぺちゃくちゃと話す。
ひーさんが最近色んなレトルトをミックスして食べていること。ゆーくんの有り合わせで作った炒飯が美味しかったこと。しーちゃんが見つけた餃子が美味しいお店のこと。私がレンジでできるズボラ飯にハマったこと。数珠繋ぎでどんどん話が膨らんで、この放課後のような楽しい時間がもっと長く続けばいいのになって思った。
きっともう一時間すれば、隣には薄くなったメロンソーダと空になったグラスが並んでいるんだろう。
「またご飯行こうね」と、名残惜しくもしーちゃんとお別れした帰り道。
ランチの後は少しだけ買い物に付き合ってもらい、別れた後には駅前のスーパーで夕飯の買い出しを済ませて、もう時刻は夕方六時を回ったところだ。でもオレンジ色の空と生温い風がそれを全く感じさせず、まだ今夏は終わらないことを告げている。
家に着いたらまずは軽くシャワーを浴びよう。
スーパーを出る時に、ゆーくんに帰る旨を連絡したけれど、返信がないからまだ帰ってきていないのだろう。
無人の我が家は今日の暑さで温度も湿度も凄まじいことになっているだろうから、クーラーで部屋が涼しくなるまでの間、シャワーでベタついた身体をスッキリさせておきたい。今日はスーパーで安くなっていたお刺身を晩ご飯にする予定。ゆーくんの帰宅時間がわかってから準備を始めても充分間に合う。あっ、ご飯も炊いておかないといけなかったっけ。
そんなこんなでスーパーから歩いて約十分。坂道を登り切れば、もう少しで我が家が見えてくる。引っ越してもうすぐ一年経つ、メゾネットタイプの賃貸。ちょっとばかし家賃はお高いけれど、角部屋であることと駅近なところが決め手になった愛しの我が家。
その我が家の二階の窓。ゆーくんの自室があるところ。見上げた先で普段は閉め切っているはずのカーテンが開いているのが目に入った。
その向こうには、ゆーくんが頬杖をつきながらこちらを見下ろしていた。その片手にはタバコではなく。
「!」
私が冷凍庫の奥に隠していたアイス。
滑らかなチョコレートの口どけで有名なアイスだ。仕事で疲れた日のために、自分へのご褒美として買っておいた秘密のデザート。
甘い物があまり得意でないはずなのに、そのアイスの袋をゆーくんは見せびらかすように横に振っている。
その光景に固まっていると、彼はにんまりと笑いながら「おかえり」と大袈裟に口パクして部屋の奥に戻って行った。
ちょっと待て!!
早足で家へと向かう。
じわっと肌を滑る汗。脱げかけるパンプス。肩にかけたエコバッグがガサゴソ揺れる。
言いたいことや聞きたいことがいっぱいあるけど、まずはアイスが優先!
帰ってきているのなら鍵は掛けていないと踏んで、鍵は差さずに、ドアノブに手を掛けて勢いよく引く。案の定開くドア。
そして開けた先には。
「おかえり。楽しかった?」
階段をぱたぱたと降りてきたゆーくんのお出迎え。その手のアイスはまだ封を切られていない。ギリギリセーフ。
「たっ、ただいま。あの、その手のアイスは……?」
ほんのちょっとの全速力と安堵感で息が絶え絶え。見つかってしまったアイスについて聞くと、ゆーくんはさっきと同じ猫みたいな笑顔を作る。細くなる目に被さる睫毛が長いなこの野郎。
「すぐそこのコンビニで買ってきた」
「……はい?」
「今日かなり暑かったでしょ。前にCM観て食べたいって言ってたの思い出して。ほら早く手洗っておいで。買ってきた物こっちでしまっとくから」
「早くしないと溶けちゃうよー」と家内に入るよう急かされる。手に持っていたカバンやショッパー、肩にかけていたエコバッグを、ゆーくんは空いている方の手で一纏めに持つと、そのまま室内の奥へと行ってしまった。
そう言えば一週間くらい前。リビングで晩ご飯を食べた後。ゆーくんがパソコンで仕事している傍ら、テレビを観ながらぼそりと呟いたような気がする。まさか聞かれていたとは。しかも買ってくるとは予想すらできなかった。
聞かれていたことと疑ってしまったことがかなり恥ずかしい。それに焦って帰ってきたこの状況がまるで食い意地張っているようで居た堪れない。あながち間違いではないところが何とも言えない。
手を洗いに洗面台へと向かう。ちらりと鏡に映った自分の顔が暑さとは別に顔が赤くなっている。ああもう恥ずかしい。パシャパシャと忙しく手を洗って、熱を冷ますように手首を水で冷やす。このままこの羞恥心も流れてしまえばいいのに。
嗽も済ませてリビングに入るとゆーくんがソファーに座っていた。渡したバッグ等はソファー横にまとめられていて、エコバッグも綺麗に畳まれている。室内の涼しさからして、だいぶ前に帰ってきていたみたいだ。
「こっち座って」と手招きするゆーくんの隣に座る。その手には袋から出されたチョコレートアイスが握られている。
「はい、どーぞ」
優しい声と一緒に、唇に押しつけられるアイス。「……いただきます」と一口齧るとゆーくんは満足気に笑う。
ひんやりとした感触から、じわりと広がる二種類のチョコの味わい。コーティングのビターな苦味とミルクチョコのまろやかな甘さ、同じチョコレートでも別々の味と口どけに、口の中に幸せが溢れる。クーラーの効いた部屋の中で食べさせてもらうアイス。なんてすごく贅沢な時間だ。
「もう一つの方はまた今度ね」
やっぱりバレていたか。
鈴の音、ひとつ
ある夏の日のトロイメライ
ストレスが溜まっていた彼女の宅飲みに付き合って、酔い潰れてしまった彼女をベッドに運ぶ。酔うまでは飲まない彼女の新たな一面を垣間見えて嬉しい反面、急に「暑い!」と言い放ってシャツを脱ぎ捨てたところは多少心配になる。まさか自分の知らない飲みの場でもこんなことやらかしたりしてないだろうか。
そんな思いを露知らず、シーツの冷たい感触にお気を召したのか、ほんの少しだけ顔を綻ばせて背中を丸めた体勢で寝息を立てている。何となく猫みたいだなーと眺めつつ、その身体にタオルケットをかけてやる。かけた瞬間、暑苦しそうに身を捩るのを見て、ますます猫だなーって思う。
さてと。
俺が口付けていた缶もまだ中身が半分以上残っている。明日の仕事に響かないようにノンアルを飲んでいたけど、このまま冷蔵庫に戻して気が抜けていくのも勿体無い。
時計を見ると十一時を周ったところで、夜もまだそこまで深くない。リビングに戻って撮り溜めていたテレビでも観ようか。それとも後回しにしていたデータの整理でもしようか。眠る前に何かしら片付けておきたい。でもその前に。
部屋の電気を常夜灯のみにして、タバコのカートリッジを手に取る。彼女にまでタバコの匂いが染み付いてほしくなくて、同棲をし始めたのをきっかけに紙製の物から加熱式タバコに切り替えた。単純に止めればいいだけの話だが、長年の習慣から抜け出すのはなかなか難しい。
サンダルを履いてベランダに出る。専用のスティックをカートリッジに差し込み、スイッチを押す。起動したのを確認し、吸い口に口を付ければ、身体の中に蒸気が充ちていく。紙タバコと比べると多少の物足りなさはあるが、この夜更けには丁度いい具合だ。生温い微風が吐き出した煙を燻らせてかき消す。
坂の頂上にある家のため、このベランダからは遠くの街の夜景もよく見える。夜景を見ながら吸うタバコも乙なものだ。この前はここから花火も見えたようで、すごく綺麗だったのだと彼女が興奮気味に教えてくれた。出会った頃と変わらないそのあどけなさにはいつも心が洗われる。
思えば、彼女と過ごした時間はもうそこそこ長い。
彼女と出会って約七年。まだ彼女は高校生で、俺は大学生だった。
彼女と付き合って約三年。柄でもないのに彼女にアプローチして、付き合えることになった時は内心ガッツポーズした。
彼女とこの家に住み始めて約一年。今後のことを見据えた同棲生活。もうすぐで一年経つがまだその先をどうするか見通しが経っていない。
彼女が納得するーー幸せになる未来が俺にはまだ見えていないのだ。
彼女と俺にはルールがある。
それは本名やそれに関連するようなあだ名で呼ばないこと。
この世界で何よりも自分自身の名前を嫌っている彼女。
一生消えることのない傷跡。心の深いところまで根付いてしまった呪い。度重なる偶然と不運な展開に呑み込まれてしまった結果、彼女は生涯共にしてきた名前を嫌悪するようになった。
それは奇しくも俺が抱えていた苦悩と似たようなもの。彼女の名前が後天性のトラウマ由来なら、俺の名前は先天性のコンプレックスだ。名前によって苦しめられる辛さはそれなりに理解しているから、皮肉にもその繋がりで今の関係が成り立っている。
お互いに本名は知っているが、お互いを前にして名前を呼んだことは一度も無い。それが付き合う時の条件でもあった。
けれど、この関係が今後も継続できるかと言われれば怪しいところもある。
この状況が果たして彼女にとってプラスなのかと常々考えている。彼女と出会って、彼女を『キミちゃん』と呼んで、彼女と一緒に歩んできた時間の中で間違いを犯していないだろうか。嬉しかった出来事も楽しかった思い出も勿論沢山あるが、その中で見過ごしてしまったサインもあったのではないだろうか。出会ってから今までの間、彼女に不安な思いや後悔をさせたりしていないだろうか。彼女の人生に横槍を入れてしまっていないだろうか。色んな『もしも』が日頃から溢れてくるのだ。
ーー駄目だ。俺が弱気になってどうする。
鬱々とした気持ちを払拭するように煙を吸い込む。一時の充足感を得るのと共に、彼女と出会った頃に思いを馳せる。
大丈夫。もう彼女にあんな辛い表情はさせないと決めたのだ。彼女の声が届いている限り、俺はまだ必要な存在であり続けられている。
カートリッジが僅かに振動する。もうそろそろ終わりの合図だ。
スイッチが切れたのを見届けると、外に広がる夜景にもう一度目を遣る。変わり映えのない景色。だが、いつも安心感がある。
ベランダから室内に戻ると、寝ていた筈の彼女が身体を起こして、ベッドの上に座っていた。起きたてなのかぼんやりとした表情でじーっとこちらを見ている。恐らく俺を探していたのかな。
「あっごめん。起こした」
「んーん」
掠れた吐息の返答に思わず口元が緩む。
まだ眠いだろうに。
「もう少し寝てな」
ベッドの脇に腰掛けると彼女はゆっくりとまた横になり始めた。無意識なのだろう、ちらちらとこちらを見ている。よほど心配させてしまったようだ。
隣に添い寝すれば彼女が俺の方に身体を向けた。リラックスできているようで、一度伸びをした後にまた身を丸める姿勢に変わる。その仕草一つ一つが可愛らしい。
ただあまり見ないようにしていたが、肩の紐にも気を配ってくれたら良かった。横になって目に入ってしまう谷間にも思わずドキッとしてしまう。恐る恐る紐をかけ直して、ベッドの隅に追いやられたタオルケットを彼女に被せる。その一連の流れに彼女は嬉しそうに頬を緩ませている。
頑張れ俺。ここで手を出したら負けだ。気をしっかり持て。
「おやすみ。ゆーくん」
彼女の一言で、己の煩悩と戦っていた思考も瞬時に冷静になる。
ゆーくん。そう、俺は『ゆーくん』だ。
「おやすみ。キミちゃん」
俺も彼女の名前を呼ぶ。
そう、君は『キミちゃん』。
その名前で呼ぶのは俺だけ。
その名前で安心して眠りに就けるのもきっと君だけだ。
数分後。
また彼女は穏やかに寝息を立てている。この感じなら朝までは起きないだろう。
勿体ないが飲み残してしまった缶は明日の晩酌に持ち越して、俺も今日は寝てしまおう。ただ、空き缶とつまみを乗せていた皿の片付けだけはしておきたい。あのまま放置していたら翌朝酷いことになる。
起こさないよう慎重にベッドから降りて、階下のリビングに向かう。点けっぱなしになっていたテレビでは深夜バラエティーが放映されていた。若手芸人が何組か身体を張っているようだが、丁度山場を迎えるタイミングだったのか、すぐにCMに切り替わってしまった。
『チョコレートが織りなす、とろけるような夢のひとときーー』
あ。この前彼女が食べたいと言っていたアイスはこれか。
何かの作業中だったからCM自体はよく観ていなかったが、このフレーズには聞き覚えがある。彼女が珍しくぽつりと独り言を溢すくらいだったから気にはなっていたのだ。
あまり甘い物には詳しくないが、彼女好みのビター寄りのチョコアイスらしい。CMが流れているならまだ販売されているだろう。今度探してみるか。
テレビの電源を落とし、テーブルに転がった空き缶を集める。さて、早く片付けてしまおう。
「じゃあこの段取りで当日も宜しくね、早瀬君」
「はい。こちらこそお願いします」
土曜日。月末に控えているオープンキャンパスの打ち合わせで午前中のみの出勤。
卒業した大学で教鞭を取っていることを聞き付けた事務のお偉いさんに頼まれ、着任した年からオープンキャンパスや説明会に駆り出されるようになった。また、在学時からゼミ等でお世話になっている教授が今年の模擬授業の担当になり、その授業の補佐役も頼まれたのだ。大役のような役割に聞こえるが、レジュメの配付と音響や空調設備の調整などの謂わば雑用係である。
教授の専門分野は民俗学。納涼に相応しい怪談話をテーマに授業を行うらしく、リアリティーを出したいという要望で音響や空調も弄らさせてもらう算段になった。事務員さんが補助にあたる話にもなっていたが、買って知ったる間柄ゆえ、教授の直々のご指名をいただいてしまったのだ。
事務員の方々と当日のタイムスケジュールを確認しあい、教授との打ち合わせで授業構成を把握させてもらった後、研究室に戻って帰り支度を済ませる。
今は夏休みの最中。本来は後期の講義に必要な資料の収集や研究調査にあたってもいい時期だが、今日に関しては用事があるため帰らせてもらう。
時刻はもう少しで十一時になるところ。校舎から少し離れたところにある駐車場に向かうが、今日の気温も三十度を優に超えるらしく、少し歩いただけでも汗をかいてしまう。背中にツーっと滴り落ちる汗の感触が気持ち悪い。ベストを一刻も早く脱ぎ捨ててしまって、ワイシャツからラフなTシャツに着替えてしまいたい。
日陰のない道中を歩き、ようやく停めていた車に辿り着く。愛車のボディーもこの暑さで相当熱を帯びていて、車内に入ればサウナに入ったくらい暑苦しい。窓を全開にしてクーラーをフル稼働させ、一気に熱気を吹き飛ばす。涼しくなるまでの間、スマホにきていた通知を確認する。彼女からの連絡は無し。どうやら楽しく過ごせているようだ。
前々から椎奈とご飯を食べに出掛けるのだと嬉しそうに話していた彼女。「明日はしーちゃんとパスタ食べるんだ」と、昨晩も同じことをこれまた楽しそうに話してくれた。高校時代から仲が良いことはよく知っているから、思う存分楽しんできてほしい。
『今から向かう。20分くらいで着く』
今日会う予定の相手に一応連絡。すると直ぐに既読が付く。
『お待ちしてまーす♡』という返事に合わせて、モデル体型の熊がぐにゃぐにゃ踊っている奇妙なスタンプが返される。
どこで仕入れたんだそんなスタンプ。語尾のハートマークよりも謎のスタンプの方が気になる。本当に昔からふざけた奴だ。
車内もだいぶ涼しくなったのを見計らい、窓を閉め切り、クーラーの風量も抑え目にして車を発進させる。
キャンパスから目的地まで車を走らせること約十五分。道が空いていたのもあり、予定よりも早く到着できた。駅前の駐車場に停めて、徒歩数分の三階建てのビルの中に入っていく。
階段を数段昇った先、ニ階にある『Eine Kleine』というお店。此処が目的地である。『CLOSED』の看板がドアに引っ提げられているが、それを無視して入店する。チリンとドアの上部に掛けられていた呼び鈴が鳴る。
「いらっさーい」
店の中に入れば、入ってすぐのカウンターで頬杖をつきながら座っているマスターのお出迎え。まだ営業時間前のため、だらだらと過ごしていたようだ。その証拠に普段束ねている髪をまだ結んでいない。前に会った時よりも少し長くなっている気がする。どれだけ面倒くさがりなんだ。
「結構早かったんじゃない?そんなにオレに会いたかった?」
「いや道空いてただけだから。それより腹減ったんだけど、新しいの今から作るの?」
「オッケー。ちょっと待ってて」
「ああ。お願い」
マスターはのそりと立ち上がって、店の奥にある厨房へと入っていった。中を覗き込むと冷蔵庫からラップで包まれた皿を出して、それを備え付けの電子レンジで温め出している。その間約十秒。「後三分でできるよー」と、開けていた冷蔵庫を閉めているが、他に出された食材も調理器具もない。あれ、もしかしてあの皿はまかないの余りとかだったりしないか?
昨晩、『できたてほやほやの試作できたから味見に来ない?』という誘いがあったから来たのだが、まさか試作のメニューじゃなくてまかないの間違いだったのだろうか。
いや、午後一時からの開店前にご馳走してくれるだけ有難いと思おう。あいつが座っていたカウンターチェアに腰を掛けて、出来上がりを待つ。
昼は純喫茶、夜はバーといういわゆるカフェバーのお店『Eine Kleine』。その経営を任されているのがマスターの日下である。飄々とした雰囲気と口角が上がっているのが通常運転な優男だ。高校の時からの腐れ縁で、今も時々この店に呼ばれて顔を出しに行ったり、日下の自宅に呼ばれて飲んだりしたりする仲だ。
ちなみに名字の読み方だが、『ひした』でも『ひもと』でもなく、『くさか』と呼べば「すごく惜しいー!お兄さん女の子にウンチクとか語っちゃうタイプでしょ?もう口説かんといてー!!」と茶化してくる『ひのもと』だ。
「今温め中でーす。……ねえ、その格好暑くないの?黒シャツインのベスト付きスーツは見てるこっち暑いんだけど」
「めっちゃ暑い」
「もう着替えてから来いよー!なに、大学の先生ってスーツじゃないといけないの?どんな時もかっちり決めなきゃいけない感じ?」
「決まりとかないけど色々とあんの。周りの目とか、そういうの気にしてかなきゃいけない時もあるんだよ」
「周り気にするならもっと涼しい格好して」
ああ言えばこう言う。これが日下である。
口はよく回るが何も悪い奴ではない。歯に衣着せぬ言動や行動力に振り回されることがあるものの、自分のみならず他人の為なら率先して動ける頼り甲斐のある男だったりする。
本人には言わないが、我が道を行くこの真っ直ぐな性格は羨ましいと感じることがある。言ったら調子に乗るから絶対に言わないが。
「皆がみな良い奴ばかりじゃないんだよ。若いっていうだけで下に見てくる教授はいるし、下心で近寄ってくる学生はいるし……いわゆる線引きみたいなモン」
「なめられないための予防線?」
「そうそう」
「女子大生よりハチとか虫とか惹きつけてるのはいいの?」
「簡単に追い払えるからマシ」
「うーわ。女子大生に言い寄られたことあんだこの人。彼女ちゃん心配し」
「させるわけないだろ」
「ねーえー最後まで聞いてー。まだ喋ってたよオレー。……ホント、彼女ちゃんのことになると重いよね〜。愛が重すぎる」
「ほれお冷。それ飲んで頭も身体も冷やしてね」と、一言多いが出されるお水。からん、と氷が鳴る。
お前も椎奈のことになれば大概だぞ、とは言わない。一を言えば十を返されるのだ。浮かんだ言葉を水と一緒に流し込む。五臓六腑に沁み渡るなんて言葉があるが、まさしく水が通る感触で内臓の形が薄らとわかる。
「オレもさ、人のこと言えるような立場じゃないけどさ、今後どうしていく感じ?いつまでもこのままってわけにはいかないよね」
突然の問いかけに喉がきゅっと締まり、水の冷たさに咽せそうになる。一を言わずとも突き立てられた言葉に胸が痛くて重い。日下から連絡がきた時に、何となくこの話が出そうな気がしたが、このタイミングで振ってくるとは思わなかった。
手元のグラスから日下に視線を遣ると、顔を覗き込むように視線を合わせられる。この男は真剣な話をする時、人の目を見て話すから、その目に捕まると息が止まりそうになる。
「今後のこと?」
「わかってるのに聞くのは野暮だよ、野暮。彼女ちゃんとのことに決まってるじゃん。ちなみにオレの方は何がきてもいつでもウェルカムなんだけどね……向こうの出方待ち状態です」
「知ってるでしょー。椎奈が結婚とか家族に躊躇してるワケ。昔からの付き合いなんだし」と、いつもの軟らかい笑みで牽制される。向こうが先に話せば次は俺が口を割るのだとわかってやっているのだ。
「ここで振ったら店長に埋められるモンな」
「やめて。オーナー引き合いに出されるとオレ何も言えない」
元・店長。現・オーナー。
この『Eine Kleine』には先代のマスターがいて、それが椎奈の父親だ。日下の弱みはこの親子である。
「口出すことじゃないのはわかるけど、オレは心配なんだよ。お前も彼女ちゃんも。二人ともどっちかって言うと受け身な方だし、ウチみたいにぶつかって喧嘩して前に進むタイプじゃ」
チーン。
「あっちょい待ち」
電子レンジの軽快な音に、日下はぱたぱたとまた厨房へと入って行った。その様子を見送って深呼吸を一つ。
最近まで悩んで見ないフリしていたものを目の前に差し出され、あの夏の夜の不安が過ぎりかけた。吐いて出た軽口ではぐらかしてしまったが、戻ってきたらまた話の続きをされるのだろう。
「ほい。カツ丼代わりにこれ食べて早く楽になろうぜ」
「取り調べか何かか」
目の前に置かれたトレイには、スプーンと楕円形の器。先程レンジで温めていた皿とは別の物で、どうやら中身を移し替えたようだ。
その中には。
「……麻婆豆腐?」
「ノンノン。麻婆豆腐とカレーを合わせた麻婆カレーでーす。スパイスを上手く掛け合わせてみました」
見た目は麻婆豆腐。その横にはカレーライスのようにご飯がたんまりと添えられている。「冷めないうちにどうぞー」と、マスターはにんまり笑う。話の続きよりもこっちを優先して食べてほしいようだ。
「いただきます」
スプーンで一口掬い、口に運ぶ前に匂いを嗅ぐ。辛そうな匂いの中にカレーの香ばしいスパイスのそれも確かにある。恐る恐る食べてみると、ピリッとくる唐辛子や山椒の刺激と味をまろやかにする豆腐は麻婆豆腐なのだが後から迫って来るのはカレー。不思議な味だ。
「……うん、美味い。アリかも」
「おーし!どんどん食べてー!」
良い具合にお腹が空いていたから、早いペースで食べ進める。食べれば食べるほど辛さが増してくるが、その味と刺激が堪らなく欲しくてまた口に運ぶ。熱くなる身体を冷ますように途中で水を挟んで小休憩。その水のおかわりも日下がタイミング良く出してくれる。麻婆豆腐とカレーが合うとは思わなかった。後でレシピ聞いておこう。
気付けば完食。「ごちそうさま」と伝えると、「お粗末さまでしたー」と、満足そうなマスターの表情と食後のコーヒーが目の前に出される。おかわりのタイミングや知らぬ間にコーヒーも準備していたその手際の良さは、長年接客業を勤め上げてきたプロなんだと実感させられる。上から目線になるが、店長が日下にマスターを任せたのも納得がいく。
「さっきの話だけど……子どもじみた考えかもしんないけど、そもそも何かの形に収めないといけないのかな」
「おっ」
お礼代わりにはならないが、聞きたがっていた話を俺から続けてみる。答えはまだまとまっていないものの、変わらない考えだけはある。
日下も興味津々でカウンターに前のめりになっている。そんなに食い付かれると話しづらい。
「一緒にいて落ち着ける関係だから、ここまで長くいられたわけだし」
「うん」
「一年暮らしてみたけど何も不満もないし、むしろ一緒にいて楽しいし、このまま穏やかに過ごすのも良いなとは思うんだ」
「うん」
「ただ、結婚して夫婦になって、子どもを作って家族になっていくのは……そういうのはまだ考えられない」
「うんうん」
「世間体や今まで育ててくれた親の為ってあるけど……やっぱり、俺にはその有り様にはついていけないんだよね。そのレールに沿っていくのが幸せっていう感覚が未だにピンとこない」
彼女と結婚して、子どもができて、一つの家族になる。それはすごく幸せなことだと感じる。
だけど、『結婚』、『子ども』、『家族』で辛い思いをしてきた人を目の当たりにしてきたから、その形式に則るのなら相当の覚悟がいる。恐らく日下が言っていた椎奈が結婚を躊躇う理由もここにあるのだろう。
決して古い仕来りが嫌いな訳ではない。新しい形式を望んでいる訳でもない。その名称に求められる期待に不安を抱いている。
「まあね……難しい問題だよな。人様の事情はそれぞれだけど、色々と知ってるこっちの身としては、そこには安易に口は挟めないわ」
「別に誰かに押し付けられてるわけじゃないけど、その形に収まらなきゃいけない流れが嫌なのかも」
「いや、わかるわかる。『いつ結婚するの?』とか『子どもはどうするの』とか、そんなのこっちの勝手だから触れないでってオレも思うもん。……あっ、オレも今同じことやっちゃってる?気に障ったらごめん」
「別にいいよ。色々と心配かけてるのは事実だし。今の関係を続けていくのが性に合っているんだと思う。……でも、もしも彼女の幸せがそこにあるなら、俺はそれを叶えたいとも思うんだよ」
日下と話していて見えてきた。あの夜の俺は根本を見失い兼ねていたのだ。
彼女との未来はまだはっきりと見えない。でも、彼女が笑顔でいられる優しい日々を紡いでいきたい。その気持ちだけは出会った時から変わらない。俺の世界の中心には何時だって彼女がいる。俺一人で考えていても意味がない。
「俺も日下と同じかもな。彼女のペースに合わせるよ。俺一人の考えや思いだけじゃ答えは出ない」
「……あー、お熱いこって。そんな顔見せられちゃったらもう突っつけないわ」
今、自分がどんな顔をしているのかはわからない。でも日下が呆れるくらいならよっぽど『ひどい』顔だったのだろう。食後に出してくれたコーヒーをいただいて、この話はもう終わりだと暗に伝える。
「オレもごちそうさまでした!」と日下は両手をパチンと叩いて頭を垂れると、「これだけは言わせて」と人差し指を向けてきた。人を指差すな。
「オレからのアドバイス。もうね、当たって砕けるのも一つよ。言いたいことや思ってることお互いに言い合って、上手く丸く収まることもあるしさ。ベストエンドじゃなくてグッドエンドでも良いわけ」
俺に向けられていた指が下を差し、カレーが入っていた皿に向く。
「カレー美味しかった?」
「えっ、……おう美味かった」
「お前の食べたそれ、本当は市販の素を掛け合わせただけ」
「は?」
「昨日、適当にレトルト混ぜてたらめっちゃ美味いのできたんだよね。それを今日お裾分けしたかったんよ。意外とイケたでしょ?……それと同じで、案外やってみることに意味があると思うんだよね。これから何年何十年もの単位で考えるなら、遠慮なんてしてちゃあ苦しいだけじゃん」
日下の指がまた俺に向けられる。
「世の中のベストエンドが合わなくても別にいいんだよ。お前の考えるグッドがもしかしたら誰かにとっては最高のベストなのかもしれないし。それを確かめるのは実践あるのみ話し合いあるのみじゃない?」
ベストエンドとグッドエンド。
スパイスを一から調合して出来上がった至高の逸品と、既存品の掛け合わせで出来上がった偶然の一品。俺が満足感を得たのは後者の方だった。最高なのはベストに違いないが、何もグッドが劣っているという訳でもない。
俺の求めるものがベストな結果でも、グッドの方に納得がいくならば、選ぶべきなのはグッドなのだ。これは彼女との問題だけじゃない。俺自身が抱える問題全てに対するアドバイス。
いただいたものがお手製のものではなかった衝撃よりも日下の話す内容に聞き入ってしまった。
案ずるより産むが易し。俺の悪い癖に対する忠告。今日呼ばれた理由は試作品の味見ではなく、この言葉を伝えたかったのかもしれない。
「……やられた」
「オレが手の込んだ料理を一から作れるワケないじゃん。オーナーのレシピと指導があってようやくよ」
「試作って言うから新しいメニューだと思った」
「素直に言ったら来てくれた?」
「いや行かないな」
顔をお互いに見合わせてほんの少しの間。どちらとも耐え切れなくて同じタイミングで笑う。日下が茶化して俺が呆れるなんて昔からのやり取りだ。こんな馬鹿な日常を十何年も前からやっているのだから、俺が日下の手の内を知るようにこいつにも俺の内面は見透かされていたようだ。
「話して少し楽になった?」
「うん。だいぶ楽になった」
「でしょ。こっちから振らないと話さないなーって思ったんだよね。これでも十何年友達やってるし、進捗状況は気になるのよ。こっちが今までどんだけお膳立てしてきたかわかるかい?」
「はいはいおかげさまで順調です。……本当、なんでわかるの?」
「いやなんとなく。強いて言うなら勘よ、勘。オレの内なる声がそうお告げになるのです」
「なんだよそれ」
思えば、彼女との七年間を日下も椎奈も見守ってきてくれていた。二人の助けが無かったら立ち直れないくらい危うかった状況だって何度もあったし、その度に俺の背中を押してくれていた。
それに加えて、俺の名前も彼女の名前も知っているのに絶対に呼ばないのだ。呼ばれたくないこと、呼ばせたくないことをわかって、そんな俺の我儘に何年も付き合ってくれている。
いい加減なところもあれば義理堅いところもある。日下の掴み所の無さには一生かかっても敵わないし頭が上がらないと思う。
ちらっと日下の後ろにある時計が視界に入る。此処を訪れてからまあまあの時間が経っていた。開店準備や他のスタッフの出勤もあるだろうし、そろそろお暇しよう。
「そろそろ行こうと思うけど、食器片付けた方いい?」
「いや、そのまんまにしてて。おべべにシミ付けられたら困るし」
「じゃあお言葉に甘えて。今日はごちそうさま。何かあれば連絡する」
「おう、何もなくても連絡待ってるから報連相大事にしてね。次はオーナーも呼んどくから」
「やめろ。……気遣ってくれてありがとう」
「はいはーい。彼女ちゃんにも宜しくね」
食器はそのままに席を立つ。「じゃあねー」と間伸びした別れの挨拶を背に聞きながらドアを開けた。チリンと鈴が鳴る。
外に出た瞬間、また湿気のある暑さが肌を撫でる。駐車場に置いてある車もこの熱でサウナ状態に逆戻りしているだろう。億劫ではあるが、心はどこか清々しい。
階段を降り切ると、先程よりも強い日差しが容赦なく照り付けてくる。その眩しい日差しを手で遮りながら、今出てきたビルを見上げる。
『Eine Kleine』。俺に変わるきっかけを与えてくれた元バイト先。俺の原点は此処にある。
早く帰ろう。
早く君に会いたい。
「ありがとうございましたー」
帰る前に。
自宅近くのコンビニに寄って、彼女が食べたがっていたアイスを買っていく。何時も買って帰ろうと思うのだけど、ついつい忘れてしまう。
コンビニから自宅まではそんなに距離もなく、車だったらほんの一、二分で着く。アイスが溶ける心配もない。
駐車場に車を停め、無人の我が家へ帰る。ドアを開ければ予想通りの蒸し風呂状態。早くアイスを閉まってシャワーを浴びよう。
リビングの冷房を着けて、真横にあるキッチンの冷凍庫を開ける。開けた瞬間のヒヤリとした冷気が心地良い。
中はお弁当用に買い置きしている冷凍食品と保存食として冷凍したご飯でいっぱいになっているが、整理すれば買ってきたアイスはギリギリ入りそうだ。手前にある使いかけの唐揚げの袋を取り、奥にある冷凍ご飯の山を崩していく。このご飯をきちんと入れ直せば入るはずだ。
「あ」
最奥にあるご飯を手に取った時、現れた見覚えのあるパッケージ。ちょうど今買ってきたアイスと同じそれが冷凍庫の奥に既に眠っていた。
なんだ、もう買っていたのか。この隠すような入れ方からするとどうやら気を遣わせてしまったようだ。
『これが食べたい』とか『これが欲しい』とか、あまり口に出さずに自分で済ませる彼女。このアイスみたいに、気付いた時には自分で買っていたり、時には我慢してしまったりする癖がある。素直に教えてくれたのはこの前の宅飲みの時くらいだ。もう少し甘えてくれてもいいのにって思ってしまうのは俺のエゴかな。
片付いた冷凍庫にアイスを閉まう。今回も一足遅かった。でも、もう一本あるとわかったら喜ぶかもしれない。そうポジティブに考えよう。
気持ちを切り替えるようにシャワーを浴び、冷房の効いたリビングで溜まっていた映画を消化して、気づけばもう午後六時。夕焼けが窓から差し込んでいて、きっとベランダに出れば綺麗な景色が目の前に広がっていることだろう。
机の端に置いていたスマホを見ると、彼女から『スーパーで買い物終わりました。今から帰るよ』と通知が来ていた。最寄りのスーパーは自宅前の坂を下った先、駅の近くにある。自宅から歩いてだいたい十分程度だから、連絡がきた時間を考えると後もう少しで帰ってくる。
見るかどうかわからないが、念のため返信しようとアプリを開こうとした。が、指を止める。
さっき見つけたアイス。その存在に気付いているのを知ったら、彼女はどんな反応をするのだろうか。
ほんのちょっと好奇心が芽生えたのだ。
冷凍庫を開け、買ってきたアイスを取り出して、二階の自室へ向かう。
思い付いた悪戯を決行するのに打ってつけの場所がこの自室。この部屋の窓からは自宅前の坂道を眺めることができる。それに加えて、彼女は帰ってくる時、この部屋を見る習慣がある。その癖に準えるならアイスを持った俺に必ず気付いてくれるはず。
カーテンを開き、外の様子を伺う。夕暮れのアスファルトを見覚えのある緑色のワンピースが歩いているのを見つけた。アイス片手にその姿を目で追う。俺のことに気付いたら彼女はどんな反応をするだろう。後もう少しで彼女はこの部屋を見上げる。後少し。
そして、見上げる視線とかち合う。ビー玉みたいな丸い目がキョトンとしていたが、俺の持つアイスに気付くとより大きく目を見開いた。その様子が面白くて、つい笑いが溢れてしまう。
「おかえり」
窓越しで聞こえる訳ないのはわかっている。ちょっと悪戯心に火が着いたのだ。
階段を降りる時、忙しくドアが開く音がした。慌てて帰ってきたのがあからさまで、彼女の新鮮な一面にまた笑ってしまう。
さあ、お出迎えしよう。
「おかえり。楽しかった?」
「たっ、ただいま。あの、その手のアイスは……?」
荒い呼吸混じりで律儀に返される挨拶。帰ってきて早々、アイスについて触れてくるあたり、よほど知られたくない秘密だったのかもしれない。小さな子どもが必死に隠していた宝物を大の大人が暴いてしまったようなものか。
ここでバラすのも何となく惜しい。もう少しだけ泳がせてみたい。
「すぐそこのコンビニで買ってきた」
「……はい?」
焦りから一変、瞬きの数が多くなる。漫画みたいなすごくわかりやすいリアクション。
「今日かなり暑かったでしょ。前にCM観て食べたいって言ってたの思い出して。ほら早く手洗っておいで。買ってきた物こっちでしまっとくから。早くしないと溶けちゃうよー」
多分、彼女の中では今「何で?」とか「どうして?」とか色んな疑問が浮かんでいるはず。それを言葉にされる前に、彼女の手からバッグや袋を受け取り、室内に入るように促した。
もうちょっとだけこの気紛れに付き合ってもらおう。
ソファーの脇にバッグを置いて、エコバッグに入っている物を冷蔵庫に閉まう。入っている量もそんなに多くないのですぐに片付くだろう。
一番上にあったお刺身のパックに、今日は魚かと少し嬉しくなる。豆腐も買ってきたみたいだから、冷や奴か味噌汁を作って一緒に食べるのもいいな。折角だし、炊き立てのご飯と食べたいから、後でもご飯炊かないと。
あっ、そうだ。持っていたアイスを冷凍庫の奥で眠っていたアイスと摺り替える。出してからそんなに時間も経っていないし、さして変わりはないだろうけど、少しでも冷たい方を食べてほしい。
リビングのソファーに腰掛けて、アイスの袋を開ける。艶やかな焦茶色のチョコレート。違いがよくわからないが、茶色の色合いが濃いからきっと苦めなのだろう。
ちょうど手洗いを済ませた彼女も部屋に入ってきたので、隣に座るように手招きする。僅かに顔が赤くなっているのが初々しい。
「はい、どーぞ」
アイスを口先にわざとくっ付ける。少しでも距離を離すと自分の手で食べようとするから、このまま食べるよう仕向けてみた。恥ずかしいから面と向かっては言えないので、ちょっとでも甘えてほしいというこの気持ちが一緒に伝わってくれたらいい。
「……いただきます」
おずおずとアイスを口に入れる彼女。唇の先にはコーティングのチョコレートが薄ら付いている。ぱきぱきと表面にヒビが入り、別のチョコレートが顔を出す。
食べた瞬間、その言葉通り幸せを噛み締めるような表情を浮かべた。チョコレート好きには堪らないアイスだったのだろう。冷たくて甘くて、今日の暑さにはちょうど良い癒やしになったのかもしれない。
唇にチョコを付けたままのこの嬉しそうな表情をもっと見ていたい。けど、そろそろ種明かししよう。
「もう一つはまた今度ね」
彼女ははにかみながら微笑んだ。
今日も幸せな日だ。
鈴の音、ひとつ
(貴方とのひとときが夢でありませんように)
