
【私こそがマイノリティだった】
私は勧められるがまま、シリアルボウルにミルクを注いだ。
マンションの窓から見える青空は、朝日で柔らかく霞んでいた。
今日から数日間、私はバンクーバー市内の中学校に体験入学する。
なんの変哲もない、シュガータイプのシリアル。
私はそれを何気なく口に運び、ザクッザクッと噛み始めた。
私はあからさまに戸惑った。
こんなに美味しいシリアルを私は知らない。
∇∇∇
[バンクーバー・ノンフィクション──中学時代の海外研修よりホームステイ体験]
そのイラン人一家は、建築を大学で学ぶ父と、絵描きの母と、中学生の娘で構成されていた。
そしてそこへ、日本人の中学生女子が加わった。
朝起きて、シリアルを食べ、学校へ向かう。
『今日は何の授業があるの?』
『数学、歴史…、あ、あと体育も!』
母と娘の会話に父が入り込む。
『あっ!僕も今日、体育あるんだった!』
慌ててリュックを開け、体操着の確認をしている。
その姿に私は思わず笑い、皆も笑った。
モジャモジャ髭の40代半ばの父親が学校で体操着に着替えて体育に参加するのを想像したら、なんだかとても笑えたのだ。
そのテンションとジェスチャーから、それが冗談なのがよく分かった。
そんな冗談をよく言う父親だった。
そんな冗談によく笑う娘だった。
そんな冗談に微笑む母親だった。
私達は笑いながら別れた。
母親はマンションの小さな部屋で鳥の絵を描き、私達は父親の車で中学校に行き、父親はその後大学へ向かう。
シリアルは美味しくて、車の窓は朝日に霞んで、父親の鼻歌は少し音痴で面白い。
私は車に揺られながら笑いながら、心の中で謝った。
なんで私だけイラン人のホストファミリーなんだと失望したこと。
私も白人の家が良かったと他を羨んだこと。
世の中をマジョリティとマイノリティにきっかり分けて、私は絶対マイノリティに入りたくないと思っていたこと。
バックシートから、父親の後頭部を見て、自分は酷い人間だと思った。
隣で屈託なく笑う娘を見て、後悔した。
∇∇∇
マイノリティに偏見的なのは、それを怖がっているからだと気づいた。
自分に自信がなくて、一旦少数派に属してしまったら最期、そこから這い上がれないと思っている。
だからマジョリティにしがみつく。
だから多数派にどうにか混ざろうとする。
しかし、それは私の考えが幼稚で乏しいからであって、周りがそうとは限らない。
少なくともこの家族は、カナダに住むイラン人であることに何の不満も無いし幸せだ。
私は車を降りて、中学校に足を踏み入れた。
多くの学生の波に流されながら、やっと教室にたどり着く。
落ち着いて周りを見渡してハッとした。
マイノリティに属したくないとかマジョリティにしがみつくとかそんな問題ではない。
ここでは、私こそがマイノリティだ。
私自身がマイノリティだった。
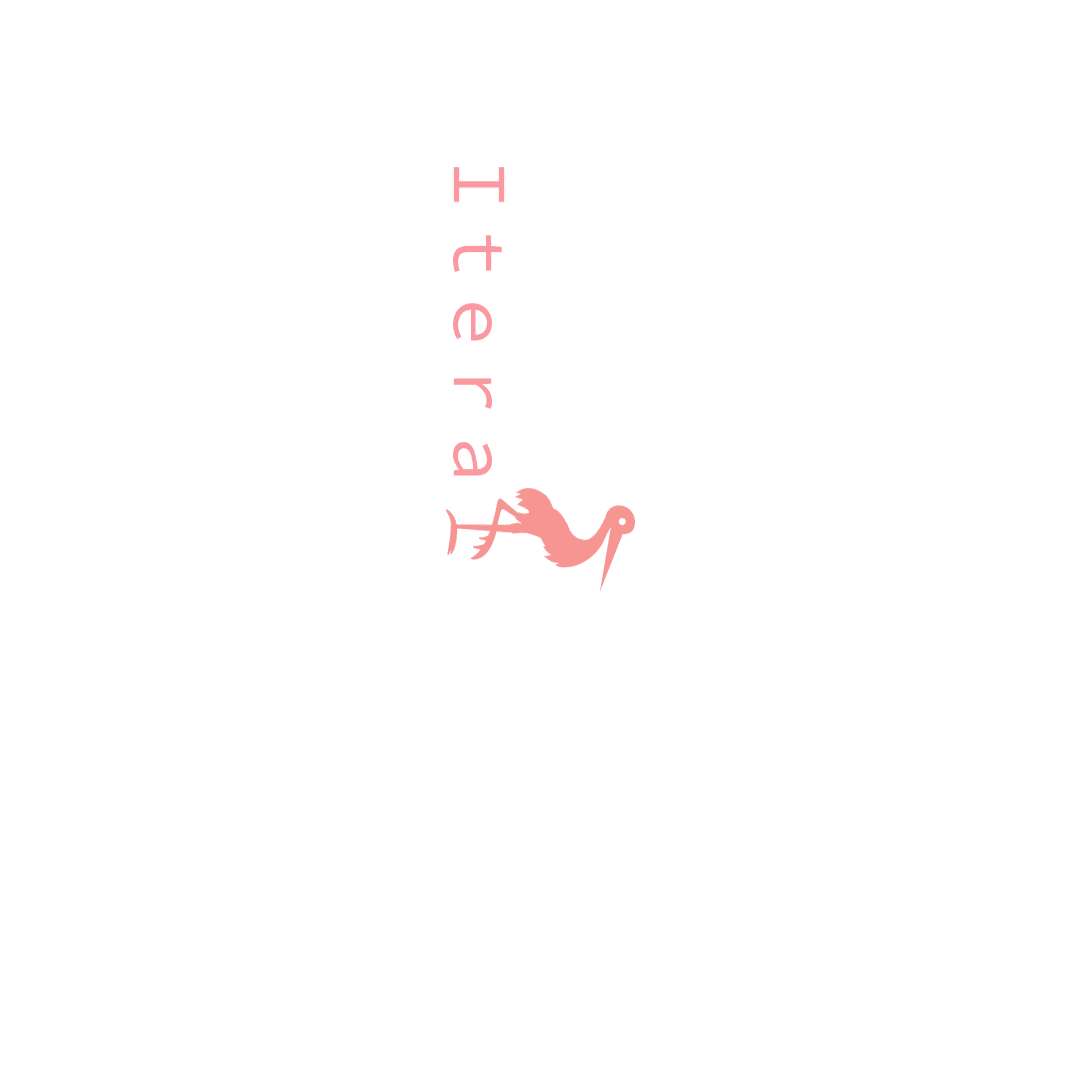
いいなと思ったら応援しよう!

