
カレーを食べながら、ウェルビーイングをかたる会Event Report 〈Well-being PJ〉
去る2024年4月24日(土)、
意識研では、ウェルビーイングプロジェクトの一環として、
「カレーを食べながら、ウェルビーイングをかたる会」を開催しました。
登壇したのは信原幸弘、渡邊淳司、七沢智樹。
ファシリテーターは発酵×ウェルビーイングをテーマに活動している田中菜月さんにお願いし、
当日は20名の方にご参加いただきました。
本リポートでは、第1部のトークセッションを中心にその内容をお伝えします。
・第1部:トークセッション
・第2部:カレーを食べながらフリートーク
技術哲学の七沢智樹、
心の哲学の信原幸弘、触覚研究の渡邊淳司、
本日はよろしくお願いします
七沢 こんにちは。意識研を運営しています七沢です。僕は普段はテクノロジーとは何かを哲学的観点から研究していて、デザインに応用することもしています。いま僕たちはテクノロジーどっぷりの世界で生きていて、スマホは身体の一部、脳の拡張として使っていますよね。そうした生き方でよいのか?と問い直すための実践として「現代人にジャングルを処方する」というスローガンのもと年に3回、西表島のジャングルでサバイバル的な滞在をするイベントもしています。この試みは、人間と自然とテクノロジーの関係を問い直すだけでなく、人間にとってのウェルビーイング、つまりより良く生きるとはどういうことかも問い直す試みになっています。あと、WIREDにテクノロジーをデザインする人のための技術哲学入門を連載中です。

信原 心の哲学を専門としてきました。4年前に東大を定年退職して、いまは名誉教授の肩書です。毎日、駒場の研究室でアクセクと働いてきたので、定年後は時間に追われるような生活からは脱却したい。悠々自適な生活を目指したい…と思いつつも、長年染みついた在り方はなかなか抜けきらないものですね。それでも、いまは、午前中は家で読書をして、午後は公園の芝生やベンチで寝転んだりしていまして、その瞬間がいまのわたしの最大のウェルビーイングです。こんな瞬間をたくさん感じられる人間になりたいと思っています。あと、綾瀬はるかが大好きで、「義母と娘のブルース」は最高です。

渡邊 NTTの研究所で、触れる感覚が人の気持ちに与える影響について研究をしています。早速ですが、自分が取り組んできた「心臓ピクニック」*という体験のデモンストレーションをしてみたいと思います。僕の胸に聴診器を当てたときに、丸い球が光って震えているのがわかると思います。これ、僕の心臓に同期して光ったり震えたりしているんです。いまちょっと緊張しているのでドキドキ速く動いているのが感じられると思います。技術によって情報が伝わるだけでなく、心と心が伝わる、そんなことを目指しています。さらに、この球が叩かれたら、嫌な気分になったり、優しく撫でられたらホッとしたりもします。どんな技術であろうとも、そのあり方や使われ方によって、良いものにも悪いものにもなる。ウェルビーイングに資するものに、損なうものにもなる。そんな観点からウェルビーイングを考えています。どうぞよろしくお願いします。
*https://socialwellbeing.ilab.ntt.co.jp/tool_connect_heartbeatpicnic.html

意識研の目的は
科学的な探究をしても答えが出ないような
究極の問いを考える文化を広めること
田中 テクノロジーの七沢さん、心の哲学の信原先生、触覚の淳司さんと、異なるジャンルを専門にされているみなさんが一緒に活動されるようになった経緯からお聞かせいただけますか?

七沢 3人の共通の関心がウェルビーイングで、3年前くらいから研究会をしていました。ウェルビーイングは世に言われている主観的幸福だけではない。一般的にはWHOの定義が広まっていますが、それだけではない。本質的な哲学的な探究の観点から議論してきました。その活動がじつは意識研の「ウェルビーイングプロジェクト」に発展したんです。あるとき信原先生のお知り合いの方から声がかかりまして。意識や価値、宇宙と言った究極の問題を問う文化を日本に広めたいと言われて。アメリカに『Closer to truth』という番組があるのですが、それの日本版みたいな感じで、スポンサーをするからやってくれと。すごいですよね。そのお話を受けて、それで設立されたのが意識研です。
田中 そもそも究極の問いとは何なのか、もう少し説明してもらえるとうれしいです。
七沢 例えば意識とは何か。意識はどこからくるのか。人間はなぜ生まれたのか。科学的に探究しても答えが出ないような問いのことです。それを問うことで、科学もより発展するし、科学を超えたことにも気付けるようになるような問いのことを究極の問いと言っています。

田中 きょうはどうしてイベントを開催することになったんですか?
七沢 今年度はほかにも、マインドアップローディングの研究、マインドフルネスの研究をするチームもあって、どちらも書籍化が決定したり予定されているんですが、ウェルビーイングチームはどうしよう?となって、インフルエンサーと組んでイベントしようか?となって菜月さんにお声がけしました。難しい話をまとめて活字にしても読む人は限られるので、きょうここでみなさんと時間を共有して、それをレポートにすることが1年間の研究会の区切りになればと思って。
肉体的、精神的、社会的に満たされた状態だけが
ウェルビーイングだと思っているなら
それちょっと待ってください!
田中 きょうは3つの質問をご用意しています。初めは、肉体的、精神的、社会的に満たされた状態とよく聞くけど…?ウェルビーイングってなぁに?という質問です。このフレーズはもはや教科書のように刷り込まれているように感じますが、意識研のみなさんはどう考えていますか?
信原 肉体的、精神的、社会的に満たされているというのは不可欠なことだとは思います。痛みに耐えながらとか、食べるにも困るような状態などであれば、なかなかウェルビーイングとはいかないでしょう。ただ衣食住さえ整っていればいいわけでもないんですね。わたしが公園で寝転がって青い空に雲がたなびくのを見ている瞬間、何の役にも立ってないこの瞬間にこそウェルビーイングを感じるということが人間にとって難しいことであり、同時に生きることの大いなる喜びだと捉えています。
渡邊 何かに喩えるとするならば、ウェルビーイングは天気みたいな側面があるのかなと。天気は、誰もが感じたり、考えたりすることができます。しかし、“よい”天気と言うと、ピカピカに晴れた日が好きな人もいれば、雨が落ち着く人もいる。春のうららかさが最高によいと感じる人もいれば、花粉がひどくて最悪という人もいますよね。“よい”は人それぞれに違う。ウェルビーイングも天気と同じように、誰もが持っているものだけど、人によって全然違う。それぞれが見つけていくものだというのが大前提だし、その“よい”には正解がないと思っています。

七沢 そう、いま広がっているウェルビーイングは、正解があるイメージなんですよね。肉体的、精神的、社会的に満たされた…と書かれるとこれが1つの正解であり、何か人類全体が目指すゴールのように見えます。でもそうじゃない。全員に共通の目的は存在しないと気づくこと、各自が実践することが重要なんです。そもそも肉体的、精神的、社会的にというフレーズは、WHOが健康の定義としていたものがいつの間にかウェルビーイングの定義にすり替わってしまったものなんですよ。もともとはベネッセレ=よく生きるというイタリア語が語源になっているのですが、よく生きる=必ずしもハッピーに生きるということでもないですし。
ウェルビーイングがgood for meなら
そのme、過去のmeも未来のmeも?
そのme、家族や友人、同僚なども?
信原 ウェルビーイングは直訳したら“よいあり方”ですが、この「よい」は英語だとgood for meと言われます。あくまでわたしにとってよいことであり、あなたには違うかもしれない。
渡邊 good for meの、meには、過去の自分や未来の自分も含まれると思われますか?例えば、目の前にケーキがあったとして欲望のままにたくさん食べたら、その瞬間は満たされるかもしれない。でももしダイエット中ならば、明日のわたし、1ヶ月後のわたしは、体重計に乗って後悔するということがありますよね。
信原 そうですね。ウェルビーイングは短期的にも長期的にも評価できるし、必ずしも短期的なよさは長期的なよさにはつながらないですね。
渡邊 短期的にいま食べたい自分と、長期的にダイエットをしている自分。両方の声を聞きながら行ったり来たりのバランスを取ることが大切なんじゃないかなと思います。もう1つ言うとgood for meの、meは、どこまでがmeか?もありますね。家族は含まれるか。あるいは自分がしたことが隣の人に嫌な思いをさせていたら、はたしてそれはウェルビーイングなのかな?とも思います。
信原 わたしはあくまでもmeは自分だと捉えていますね。

渡邊 結局ウェルビーイングって何ですか?を考えると、みんなのことまで考えるのは必要なのか?という問いが生まれます。それぞれが自分のmeのために好きなことをすればいい。でも同じ場所にいて、何も知らずに相手の嫌がることをしたら喧嘩になるかもしれない。だったら相手のことを知ったほうが、結果的にはそれぞれのmeにとっていいんじゃないか。広くいろんな人がウェルビーイングであるにはそれぞれのmeを大事にするのが大事なのかなと。
七沢 淳司さんは「わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために」という書籍も書かれていますが、人間は社会的な存在だから、自分を構成しているものには、他者も含めていろんな要素がある。これは単純にその瞬間にしあわせを感じているかという次元の話ではないですよね。非常に多くのことを考慮する必要があるし、ウェルビーイングとはなにか?は哲学的な問いです。ここ数年、ウェルビーイングはどこでも使われている言葉ですけど、実は考えることも多く、自分の人生を大切にすることにつながる究極的な問いだと思いますね。
学ぶ場でのウェルビーイングって?
働く場でのウェルビーイングって?
三者三様の見解をここに
田中 次の質問は、学ぶ場でのウェルビーイングって?働く場でのウェルビーイングって?これからどうなっていくと思いますか?です!
田中 ちょっと前に主人公が昭和と令和をタイムスリップする「不適切にもほどがある」っていうドラマを観てて、時代によってもウェルビーイングは全然違うなと感じました。これからはどんなふうになっていくと思いますか?
渡邊 先ほど、ウェルビーイングを天気に喩えてお話ししましたが、大きな違いもあります。天気は変えられないけど、ウェルビーイングは自分で変えられる。具体的には、ウェルビーイングを状態として考えるだけでなく、“あり方”、つまりその人の資質や能力としても捉えることができるのではないかということです。例えば、何かが起こったときに落ち込みすぎないとか、人と関わりながらお互いのウェルビーイングを保ったまま問題を解決することができるとか。そして、それは学べるものであると思います。身体を鍛えるように、心の筋トレもできる。いま文部科学省も、ウェルビーイングを重要なコンセプトの一つに掲げていますし、さらに、ウェルビーイングを学んで成長した子どもたちは、それが考慮されている働く場を自然に選ぶようになるでしょう。
田中 淳司さんが働く場で実践されていることはありますか?
渡邊 人の話をよく聞くことですかね。それぞれの人は、何かを大事にしているから意見を言うわけで、意見の内容に賛成・反対するだけでは仕方がない。その人は何を大事にして働く場にいるのか、そもそもの価値観を知ることが大切だと思います。協調することが大事な人と自己成長が大事な人では、同じ局面にいても取る行動は違いますし、その人の言動や行動の背景を知るのは一緒に働く上でも効果的だと思います。具体的には、「わたしたちのウェルビーイングカード」*を使って価値観をシェアしてからプロジェクトを始めたりしています。
*https://www.amazon.co.jp/dp/4757170513

七沢 学ぶ場はこうあるべき、これが正解という管理がされがちです。わかりやすく言うと受験が目的になったり。その設定された目的は、往々にして個人の目的よりも優先されてしまう。正直、鬱や不登校が生まれやすいシステムだと思います。いまはウェルビーイングを掲げたいろんな学校や職場が出てきていますが、一方でウェルビーイングを目的にしてしまうのも違う。ウェルビーイングじゃないとNGというのも怖いです。自分自身のウェルビーイングに気づくのは大事だけど、わざわざ大上段に掲げなくてもいいんじゃないかな。そもそも人間は自分らしい人生、よりよい人生を目指すものではないでしょうか。
信原 いや、むしろ人間が自然にウェルビーイングを目指すのは難しいと考えるべきかもしれません。必ずしもよりよい人生にむかっているとは限らないし、そう思っていても勘違いだったりもする。嫌でも受験勉強はするし、ノルマを課せられたら盲目的に働きもする。
七沢 人生の目的なんて意識しないで生活している人も多いですよね。でも生きてる限り、こうしたい、こうありたいという感情はある。
渡邊 敢えて言い切りますけど、僕は「自分のやりたいことをやっている感覚」は全然ありません。自分から流れを作っているというよりは、どちらかというと流れている水にのせてもらっていて、その流れに流される中でどういう姿勢を取るとスムーズに流れるのか、流れがぶつからないのかを考えている感じですね。ウェルビーイングを研究している人がすべて、一般的にイメージされるようなウェルビーイングであるわけでは全然ないです。
七沢 そうですね(笑)。僕は淳司さんの本もよく読んでて、考え方にはとても共感しているんですけど、実際に会うと「自分なんて全然ウェルビーイングじゃないです」とか言うので面白いです(笑)。
学ぶも、働くも、遊ぶに置き換える?
あるいは遊ぶように学ぶ、働く?
自由はどこにあるのでしょう?
信原 学ぶ場、働く場のウェルビーイングを問うならば、その場自体をなくさないといけない。いまの学びの場は国や企業に役立つ人材の育成にすぎない。働く場も企業の利益を追求するところにすぎない。根本的にはウェルビーイングとは正反対です。すべての場を遊び場にする。それで初めてウェルビーイングが可能になるとわたしは答えたいですね。AIを活用してベーシックインカムを実現して、人生を遊びにしていく。
渡邊 遊ぶには、内からの動機に基づいて、さまざまな行動ができる余白がありますよね。だから、遊ぶように学ぶ、遊ぶように働くということができるはずです。でも何にもないと普通は遊べない。何かしらの目的やルール、型が必要じゃないかなと思うんです。例えば、茶道は作法の手順があるから動ける。お茶を点てたり、お菓子を出す順序は決まっていますが、そのタイミングはある程度調整ができる。自由は不自由があるからこそ生まれる。

信原 淳司さんは、喜ばしい学び、喜ばしい働きがあると思っているけど、わたしはやっぱりそれらは人材育成という目的から離れられないと思う。学ぶ、働くという言葉自体を失くす方向にむかわないといけないとわたしは思います。
渡邊 働くということには、利益を出すことと社会に貢献することと、どちらも起きてるはずなのに、結局決算書で判断されてしまうといったところに問題があるかもしれないですよね。
どうしたら
ウェルビーイングでいられるでしょうか?
もし何かヒントがあれば…
田中 最後の質問は、どうしたらウェルビーイングでいられるでしょうか?です!
七沢 「いま自分はウェルビーイングだな」と思ったことは一度もないんですよね。こういうのがウェルビーイングと言うんだろうなとあとから振り返ってる。だからウェルビーイングでいたこともないし、その予定もないです…という答えになっちゃう(笑)。振り返ってみたときに時間性や関係性など全体性をふまえた上で、自分がよりよく生きるあり方が実現できてればウェルビーイングでいたんだろうなと。
田中 そうなんですね〜。わたしは常にいまというか、きょうはウェルビーイングで行くぞ!っていう感じなので面白いです。あとでカレー食べながら話しましょう!
信原 わたしはこれまでの70年、全然ウェルビーイングではなかった。この人生を今からどうやってウェルビーイングに転換できるのだろうかと考えています。これから5年、10年、何歳まで生きるかはわからないけれども、辛いことの多かった人生でも何かひとつのきっかけで一瞬にして物語全体がイルビーイングからウェルビーイングにチェンジできると信じています。

渡邊 どうしたらウェルビーイングでいられるか。具体的に回答すると、目標を3勝7敗ぐらいにすること。そうしたら気持ちがラクになります。good for meのmeが10勝や9勝をめざしていたらしんどいですよね。人から奪わないと勝てないし、恨みだって買いやすい。一方で、0勝や1勝もちょっと辛いですよね。だから3勝7敗ぐらい。でもここで重要なのは3勝のほうじゃなくて、7敗をどのように負けられるか。相手が輝けるような負け方。結果として楽しい負け方。あと、負けても人に恩を着せないことも大事。「こうしてあげたんだから、応えてよ」とか思わないこと。自分の感覚で言うと、お地蔵さんというか、公共財としてどのように使ってもらうかということを意識しています。
信原 3勝7敗…というのは、ウェルビーイングのラインを安易に下げすぎているのではないかと疑問ですね。
渡邊 自分はプロレスが好きなのですが、プロレスの場面で言うと、お互いどちらも勝ちたいけど、試合自体も盛り上げたい。そのバランスですよね。勝ったり、負けたりしながら、お客さまがどう楽しめるかを考える。目の前の相手と競争しながら、お客さまに向けて相手と一緒に共創する、そんな感じです。
みなさまと過ごした時間こそが
ウェルビーイングだったと思います
ありがとうございました!
本日の会場は永田町にあるMIDORI荘。
おしゃれなカフェみたいな席から、家のリビングのようにくつろげるソファまで、
思い思いの場所に座った参加者たちからはたびたび笑い声があがり
始終和やかな雰囲気のトークセッションでした。
そして第2部は、3つのテーブルにわかれてのフリートーク。
東京パーマカルチャーランチの提供による美味しいカレーを食べながら
ウェルビーイングにまつわることからそうでないことまで、各テーブルで話が弾みました。




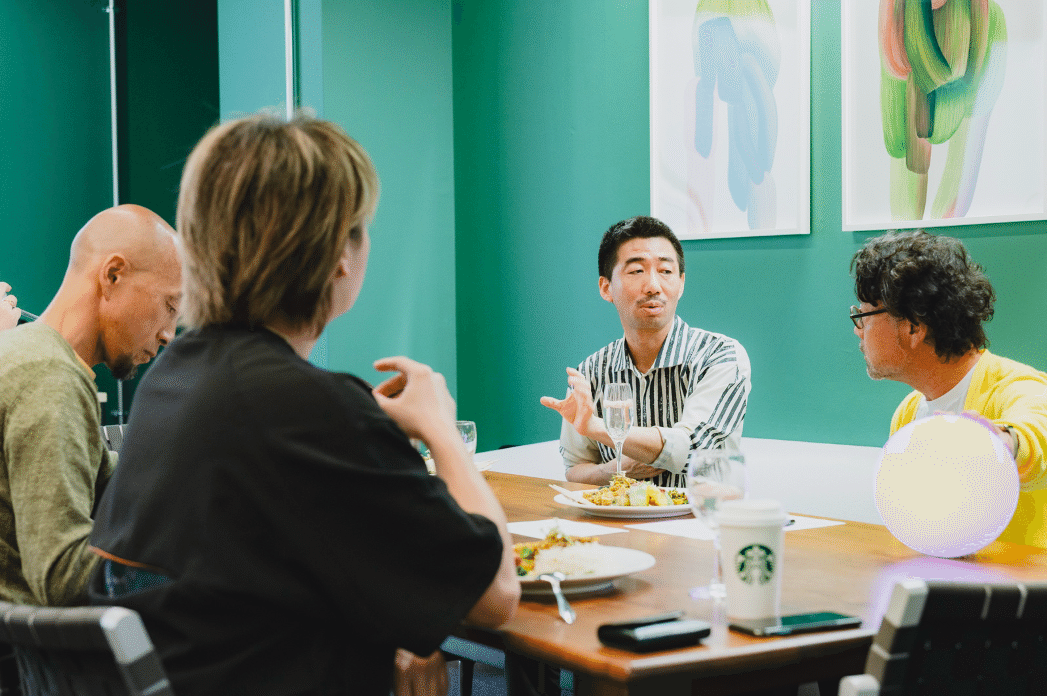
最後に参加者の方から
「ウェルビーイングがますますわからなくなった。謎が深まった」というナイスな感想があり、
まさにウェルビーイングが究極の問いであることを感じていただけたと思いました。やってよかった。
ウェルビーイング。考えるほどに気軽に使えない言葉だという気もしてくるのですが
きょうみなさまと過ごした時間こそはウェルビーイングだった!と、
ここに感謝とともにお伝えしたいです。
みなさま、ご参加どうもありがとうございました。
今後とも意識研をどうぞよろしくお願いいたします。
またお会いしましょう!
