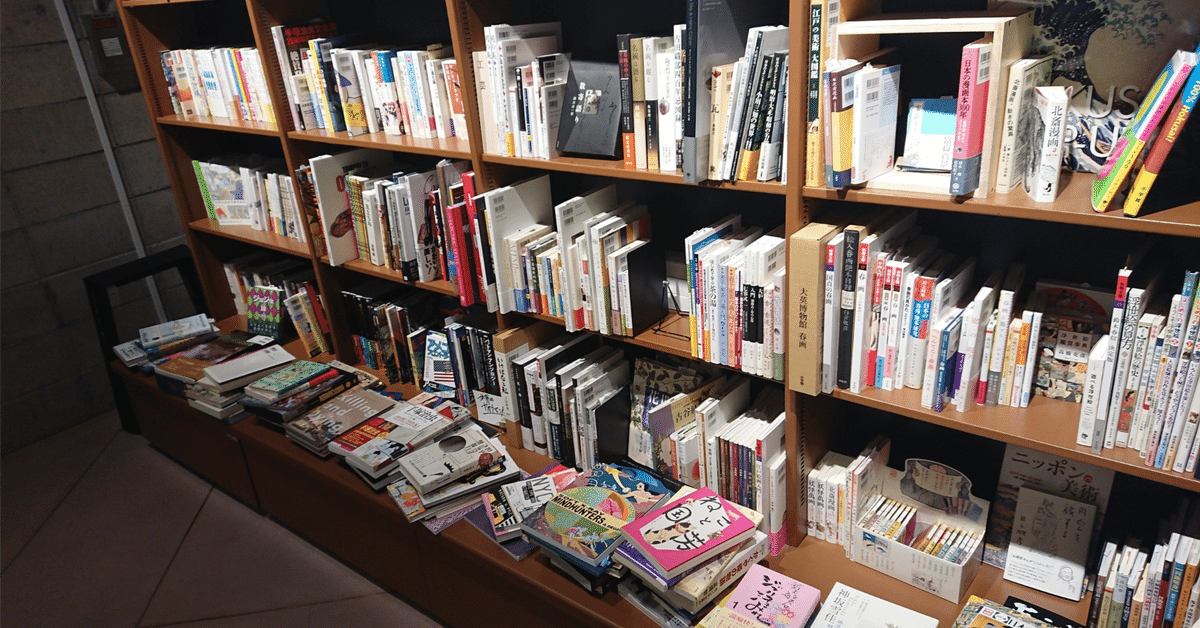
今年読んだSF短編・中編 オススメ5選
前書き
9月ぐらいからSFにハマってちょこちょこ読んでいる。
今年の振り返りとして読んだSF短編・中編の中からオススメ5選を選んでみる。確認してみたら読んだのは以下の21冊(長編含む)
https://bookmeter.com/users/1364544/bookcases/11857955?sort=book_count&order=desc
あなたのための物語 (長谷 敏司)
アステリズムに花束を (アンソロジー)
ウは宇宙船のウ (レイ・ブラットベリ)
生まれ変わり (ケン・リュウ)
祈りの海 (グレッグ・イーガン)
夏への扉 (ロバート・A・ハインライン)
たんぽぽ娘 (ロバート・F・ヤング)
SF的な宇宙で安全に暮らすっていうこと (チャールズ・ユウ)
アメリカン・ブッダ (柴田 勝家)
たったひとつの冴えたやりかた (ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア)
なめらかな世界と、その敵 (伴名 練)
折りたたみ北京 (アンソロジー)
ハーモニー (伊藤計劃)
きまぐれロボット (星 新一)
紙の動物園 (ケン・リュウ)
まず牛を球とします。 (柞刈湯葉)
幼年期の終り (アーサー C.クラーク)
あなたの人生の物語 (テッド・チャン)
タイタン (野崎 まど)
息吹 (テッド・チャン)
しあわせの理由 (グレッグ イーガン)
注意
単に僕が今年読んだ本の中でオススメを上げるだけなので、出版年が古い本もあれば、新しい本もある。
『サイエンスやテクノロジーをバックボーンとしたハードSFのほうが好き。哲学・人文学的考察が作品の核になっているとなお良し。』という嗜好の持ち主。
出来る限りネタバレをしない方向で感想を述べるが、それでも、初見の感想に影響を与えてしまう可能性は否めない。
オススメ5選
偽りのない事実、偽りのない気持ち テッド・チャン
『息吹』収録作品。息吹は僕がSFにハマったきっかけともいえる作品だ。テッド・チャンは作品数は少ないが、そのどれも完成度が異常に高く、どれをとっても名作といえる作家。その待望の新作が息吹(Exhalation)だ。
テッド・チャンといえば、物理や数学をモチーフとしたもの(ゼロで割る、あなたの人生の物語)や、宗教・神学をテーマとしたもの(バビロンの塔、商人と錬金術師の門、地獄とは神の不在なり)が多い中、この作品はこれらとは異なるテーマを選択している。2つのストーリーがパラレルに展開し意外な形で結びつく構成の上手さもさることながら、様々な学問分野への造形の深さも感じ取ることができる作品。完全に好み。
この中編以外にも面白い作品が盛りだくさんなので、息吹はぜひ読むことをオススメする。テッド・チャン天才すぎるだろ…
紙の動物園 ケン・リュウ
『紙の動物園』の表題作。
この作品は、ネビュラ賞、ヒューゴー賞、世界幻想文学大賞の三大賞をトリプル受賞した史上初の作品となる。
ケン・リュウは中国系アメリカ人1世であり、自らのバックグラウンドを存分に活用した作品も多い。本短編はその代表作の一つだろう。中国文化をモチーフとして細やかな情感を描写する。同短編集収録作品「もののあわれ」の本文中の言葉を借りれば”仔猫の舌が心の内側をちろちろと舐める”ような感情を揺さぶられる傑作だ。
ケン・リュウの作品の多くは新☆ハヤカワ・SF・シリーズで読むことができるが、短編集ごとに受ける印象が微妙に変わるおもしろい作家だ。(といっても神の動物園と生まれ変わりの2冊しか読んでいないのだが) 短編集は手っ取り早く作家の色々な側面を見せてくれる試金石のような存在だ。『生まれ変わり』では、また別の側面が見られるだろう。
祈りの海 グレッグ・イーガン
『祈りの海』表題作。
ヒューゴー賞・ローカス賞のW受賞を果たしている中長編。
グレッグ・イーガンはナノテクノロジーやバイオテクノロジー、量子論など多岐に渡る分野をモチーフとしたハードSF作家として知られているが、本中長編でも存分に持ち味が発揮している。
しかし、「祈りの海」の持ち味はハードSFであることではない。信仰という個人のアイデンティティに大きく踏み込み解体したことこそが、この作品の持ち味だ。
印象的な兄弟による「浸礼」の儀式から始まるストーリーは、最初から全く予想がつかない結末へとドリフトしていく。読了後の足元がおぼつかなくなるような感覚こそがセンスオブワンダーだと確信できる。
表題作以外にも形而上学的テーマを扱った作品が多く、自分と好みが同じあれば楽しめる作品が多く収録されていると思う。
美亜羽へ贈る拳銃 伴名 練
『なめらかな世界と、その敵』収録作。
タイトルからわかるようにハーモニーのオマージュ作品であり、もともともは『伊藤計劃トリビュート』に掲載された作品らしい。
作者の名前は明らかにハンナ・アーレントのもじりであることからわかるように、作中に様々なオマージュが埋め込まれている。表題作『なめらかな世界と、その敵』も『なめらかな世界とその敵』という社会学の本が元ネタだ。
作中では”聖書”として「しあわせの理由(グレッグ・イーガン)」「顔の美醜について-ドキュメンタリー-(テッド・チャン)」などが出てくる。作者の膨大なSF知識には目を見張るものがある。
雲南省スー族におけるVR技術の使用例 柴田勝家
『アメリカン・ブッダ』収録作。
論文のようなタイトルのSF。本文も架空の民族に関する学術調査誌のような文体で展開される。
はじめはVRを使う少数民族という突飛な設定に驚くが、文化・食事・宗教・風俗に対して詳細な設定が用意されており、あってもおかしくないと思わされてしまう説得力がある。それぞれもディティールも文化人類学的に見たことがあるような構造を有しており、著者のバックボーンが遺憾なく発揮されている。
最後のオチに関してもまさに文化人類学のコンテクストに即したものでニヤリとさせられる。SFも文化人類学も意外と近い共通項によって結ばれるものなのかもしれないと感じた。
おわりに
1作家1作品という縛りで紹介してみたが、ほかにも紹介しきれなかったよい作品が多くある。気になったらぜひ他の作品も読んでみてほしい。
