
科学的に証明!難関国家資格でも使えたドラゴン桜の暗記方法
お受験、受験、国家資格、TOEIC、TOEFLなど学ぶというのは学生時代から社会人になっても続く。
「昔から勉強が苦手で、特に暗記物が大の苦手です。頭のいい人は一回聞いただけで覚えられるけど、私は全然覚えられないです。どうしたらいいんでしょうか?」
大学受験、就職活動は工夫と忍耐で乗り切れたが、国家資格は並大抵の工夫では無理だった。色々試したが、気合と根性だけではどうにもならず、中小企業診断士試験は結果7回も受験することになった。
しかし7回目は余裕合格だったのだ。
6回目までは非常に苦しんでいたのにも関わらずだ。
しかも7回目受験の経験はビジネススクール首席卒業にも大きく影響を与えた。
その経験とは勉強法を変えて得た体系化された知識だった。
そこで、今回は“ほへと”が7回目の試験をうける上で大きく変更した「本当に使える暗記方法」を教えます。
「もう勉強しないから私には関係ないよ」という人でも、料理のレシピ、子育て教育、病気の知識、恋愛、友人関係に至るまで生きていく上では勉強とは違う形でも学ぶという事はずっと続くと思うので、ぜひ参考までに読んでもらえればと思う。
■本記事のテーマ
暗記が苦手な人の為の記憶術を大学論文と実体験を使って解説
■科学的に証明!難関国家資格でも使えたドラゴン桜の暗記方法
勉強法を勉強していないという致命的な損失

勉強が苦手、暗記が苦手という人はこんな勉強法をしていないだろうか?
・授業では先生が黒板に書いたものをひたすら写し、ノートに隙間を作らず、びっしり埋めていく。
・参考書で勉強するときは重要だと感じたところをマーカーで色付けする。
・一つの科目を1時間以上もずっと勉強科目を変更せず勉強する。
といったような感じだろう。
結論から言うと、これらはすべて効率が悪い。
2013年ケント州立大学が様々勉強の効果について評価している。
10個で比較した勉強法の中で、学習効率が低かった方法の1位は「ハイライト、アンダーライン」2位に「キーワードメモニック」3位に「要約」という順番であった。
ハイライト、アンダーラインはマーカーを使ったり、印をつけたりする方法だ。
キーワードメモニックとは重要単語を抜き出して書き留めておくという方法。
そして要約は言葉のままで、テキストに書いていること、先生が言ったことを短くまとめるという方法である。
見覚えのあるこれら勉強法は学校で正しいとされてきた勉強法ではないか!?
私も6回試験を受けるまではこの勉強法を多用していた。
しかし、結果は残酷で、それらは非常に効率の悪い勉強法だったこともあり、一年で1000時間勉強したのにも関わらず不合格が続いた。
なぜ、その効率の悪い勉強法を使っていたのか?
なぜ小中高とこの勉強方法で学校授業は進んでいたのだろうか。
おそらくそれは、学校の先生が勉強法を勉強したことがなかったからだろう。
脈々と日本の教育において、これらの勉強法が正しいと疑いも持たず行われきた。
先生もこの方法で勉強してきたのだろう。
となればもちろん、この方法しか知らなくて当然だろう。
つまり、暗記が苦手、勉強ができないというのはあなただけが悪いということではないのではないか。
悪いのはあなたの頭ではなく、やり方なのではないか。
僕はこの事実を知った時、すぐに勉強法を変更した。
そして、7回目の中小企業診断士試験を余裕で突破できたのだ。
更に、会社に多くいる、東京大学、京都大学、大阪大学の友人に話を聞いてみたところ、これら勉強ができると言われている人は軒並み、僕がやっていた間違った勉強はやっておらず、アクティブラーニングを中心に勉強をしていたのだ。
改めて、勉強法を勉強し、勉強の生産性を高められるヒントになればと思い記事を書き進める。
ドラゴン桜の勉強法はオークランド大学とケント州立大学で実証されていた

ドラゴン桜 63限目 「東大医学部生のノート」(三田紀房 、出版:講談社)で記憶に大切な要因は「関連付け」と「強調」にあるとしている。
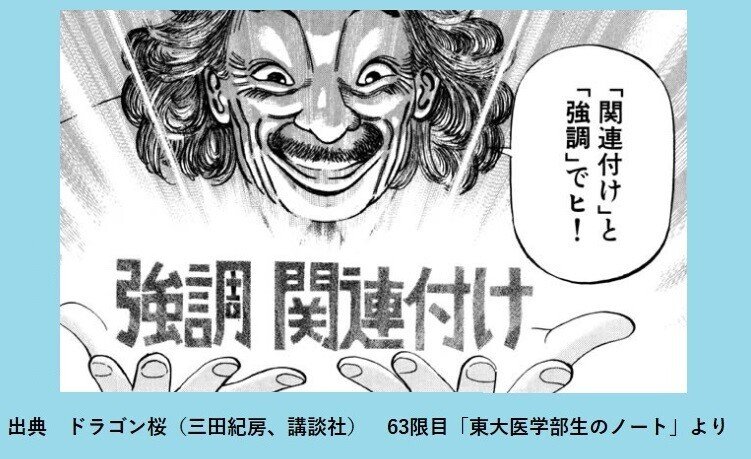
これはどういうことなのか。
2014年オークランド大学のバーバラ=オークレイが行った、「学習における先行研究の文献レビュー」のなかで有効とされた記憶法に「チャンク化」がある。
チャンクとは「意味のある塊」のことだ。
例えば“森”という単語を聞いたときに、“ウサギ”“川”“原生林”“山火事”といったすぐに連想されまとめられているモノ(言葉、記憶、ストリー等)を指す。
このチャンク化がドラゴン桜で言う「関連付け」というところに該当する。
そして、ケント州立大学が行ったレビューの中に、効果的な勉強法に「テキストイメージング」が含まれていた。
このテキストイメージングが「強調」に当てはまるのだ。
つまり、ドラゴン桜で使っている暗記方法は大学の発表でも効果を検証しているものであり、非常に効果的なものであることが分かる。
暗記のポイント①は「関連付け」

関連付けは非常に簡単である。無意味な言葉の羅列があった時、それを覚えることが難しいのだが、それをストーリーでつなげることで「チャンク化」することができるのだ。
試しにやってみる。
下記の言葉の羅列を30秒で覚えてほしい
・りんご
・時計
・ランニング
・おじさん
・本
・傘
・電車
・パン
・5番
9個の非関連的な言葉を覚えることは難しいだろう。
しかし「チャンク化」するための工夫をすれば一瞬で覚えられるようになる。
例えば
「りんご型の時計を持ってランニングしているおじさんが、本に傘を挟み電車に乗ろうとしたがパンを5番のりばで落としたみたいだ」
とストーリー建てにしてみたらすぐ思い出せるようになる。
いかがだろうか。
つまり、無関連の言葉に「ストーリー」という文脈でつなぐことで記憶に定着しやすくなるという事だ。
これが「関連付け」である。
暗記のポイント②は「強調」

強調とは印象に残るように自分で考え、能動的に印象付けることをいう。
強調と聞くとマークラインを引いたり、重要ワードを書き出すことだと勘違いするかもしれないが、違う。
それは前述した効果のない勉強法の1位の「ハイライト、アンダーライン」、2位の「キーワードメモニック」のことである。
ここで言う強調とはあくまでも能動的に自身で考え作った「強調」である。
先ほどの例文を使って説明する。
「りんご型の時計を持ってランニングしているおじさんが、本に傘を挟み電車に乗ろうとしたがパンを5番のりばで落としたみたいだ」
この例文自体をイメージしてほしいが、文全体がそもそも強調されいる為忘れにくくなっている。
さらに細かく見ると「本に傘を挟み」という部分はなかなか独特な世界観である。
変な表現、変な事というのは記憶に残りやすい。
つまり、協調とは自身の経験と比較した中でも印象的になるようなことだったりする。
日本史の年号を覚える時の「いい国創ろう鎌倉幕府」や「一杯で酔っちゃうおえー。アヘン戦争」などがそうだろう(少し古いが・・・)。
つまり、自身が印象的になるようにイメージできるものを「強調」と呼ぶのだ(エロ、グロ、意味不明系で作られた語呂合わせは非常に忘れにくいと思うが、その根拠がこの「強調」という効果なのだ)。
メモリーツリーで「関連付け」と「強調」を作る
「関連付け」と「強調」を使った暗記方法でドラゴン桜はメモリーツリーを紹介している。
マインドマップといったほうが一般的なのかもしれない。

何かキーになる言葉から、関連付けされた言葉が放射状に広がっていく。
それをイラストや語呂合わせ、色付けなどを使い強調する。
このマインドマップは「関連付け」でチャンク化し、「強調」も駆使された最強のノート術である。
更に有効なのが、マインドマップ同士が関連付けされることがあるという事だ。
例えばマインドマップを五つ作ったとする。
その五つのマインドマップすべてで「空の色」という文言が使われていたとしたら、五つのマインドマップが「空の色」という文言でつながり「チャンク化」される。
つまり、非常に大きな関連付けされた知識に広がるのだ。
これを勉強に置き換えた場合。
数学の知識と物理の知識が関数で繋がったり、日本史と世界史、現代社会、英語などがつながったりするのだ。
そうすることで記憶をたどる道がいくつもできる為、記憶が定着しやすくなる。
さらに思い出しやすくなるのだ。
1本のロープより、2本のロープで物を吊り上げるほうが安定するように。
是非、これからは「関連付け」と「強調」という力を信じ、暗記方法を変更してほしいが、小中高大、社会人までノートの取り方をあまり考えずにやってきた人にとって、あたらしい方法を試すのは不安だろうとは思う。
しかし、考えてみてほしい。
「今までの方法を変えたくない」というその考えが暗記を苦手にし、今の結果につながっているのではないだろうか。
僕はその考えを捨て、新しい方法に取組んだことで成功した。
なぜ、新しい方法に取組めたのか。
それは大学研究に裏付けされた方法だったから信じることができた(ハロー効果、権威性という効果だ)。
主観よりも客観的根拠を信じる。
常に自分が正しいと思うのではなく、謙虚に物事をとらえるほうが良いという事を私は知っているという事だ。
まとめ

ドラゴン桜のmemoryツリーを反映したノートの取り方。
そして記憶するときに「関連付け」と「強調」を駆使する。
相すれば記憶力が向上できると科学的証明されている。
モノは試し。
一回やってみることをお勧めする。
