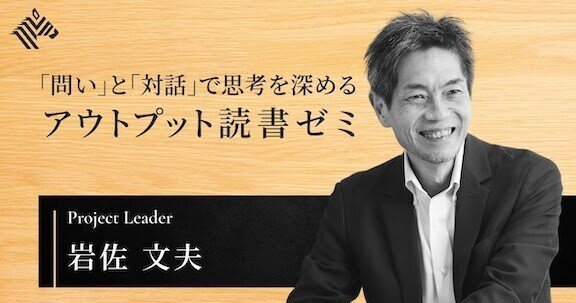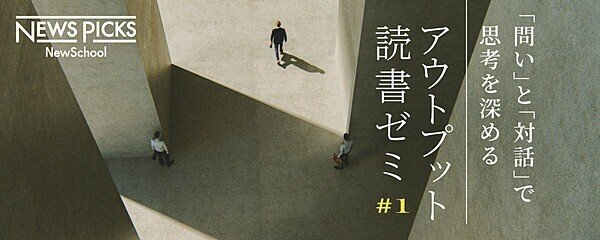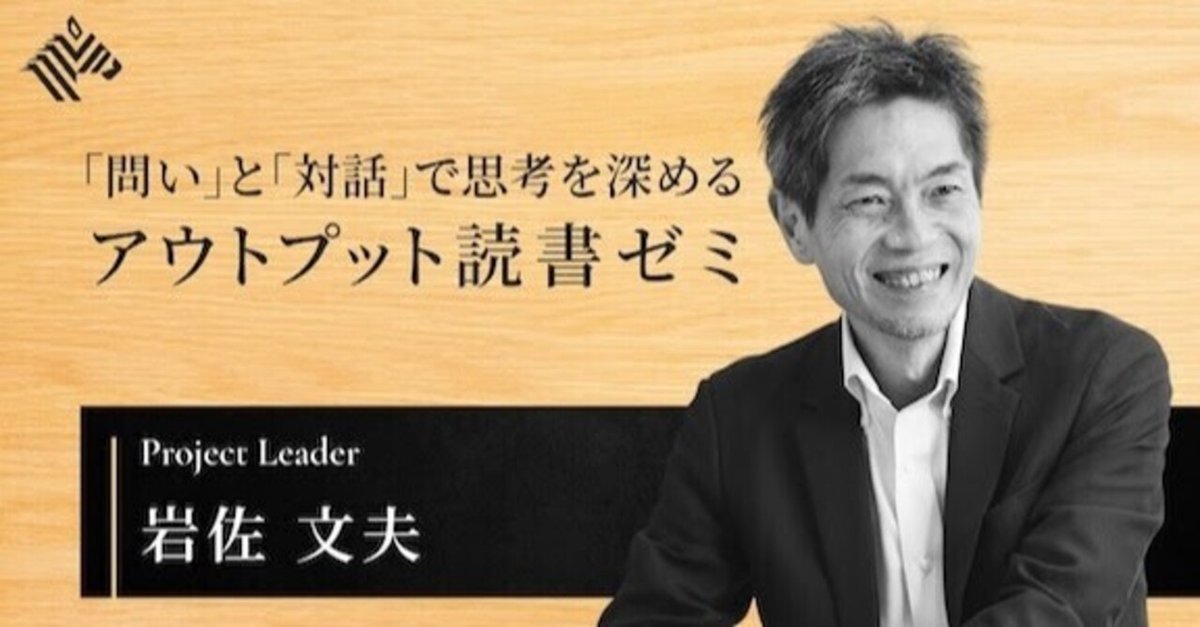
何かを学ぶとき、人は自分に驚いている
「人類は、まだ視覚と聴覚しか『転送』できていないんですよ。これだけオンライン会議が当たり前になっても」
ある会で、ある人がそう言った。
「最近、一軒の焼肉屋が、肉を自宅に配送して、複数人が同時に焼きながら『zoom飲み』ができる体験を売り始めたんですね。これは、とっても面白い。なぜなら、転送不可能な味覚を、肉そのものを物理的に送ることで、転送可能にしちゃったからです」
ははあ、そういうことか!と僕は思った。僕たちは今、本で同じことをしているわけだ。
「ある会」とは、NewsPicksパブリッシングで企画したアウトプット読書ゼミ。
「ある人」とは、ゼミにゲストでいらしていただいた暦本純一さんだ(記憶があやふやなので、多少言葉は不正確かもしれない)。
「本来一人で焼くはずだった肉」をみんなで焼き、思い思いに言葉を交わす。
僕たちは、読書ゼミで「本来一人で読むはずだった本」をみんなで読み、交わされなかったはずの「思考」を交わした。
その体験に、少し大げさな言葉を使うと、僕は感動してしまった。
これから、僕はアウトプット読書ゼミで見た学びの形について書く。
なんだ広告か、と思われるかもしれない。
たしかにそうなんだが、心から素晴らしいと信じられるものの「広告」だ。
よかったら読んでみてほしい。きっとこれからの学びのヒントがある。
コラボレーションには「一人の時間」がいる
もう一つ、人の言葉を引用したい。
「全員でブレストするより、一人で考える時間を設けるほうが、いいアイデアが出るんですよ」
ビジネスデザイナーとして世界中で活躍する、濱口秀司さんの言葉だ。
詳しくは、このほぼ日の記事をぜひ読んでいただきたいのだが、濱口さんによるとブレストの中でもっともアイデアの質が低いのは、参加者全員がずっと喋り続ける形式。逆に優れたアイデアが出るのはそれぞれが一人だけで静かに考える時間を設けたときらしい。
一人で黙々と考える時間が、いいコラボレーションには重要なのだ。
当初は意図していなかったのだが、アウトプット読書ゼミでも、これに近しいことが起こっている。
この読書ゼミは、
❶インプット
❷アウトプット
❸ダイアローグ
の3つのパートで成り立っている。
毎週指定された箇所を読み(❶インプット)、自分の考えをslackに書き(❷アウトプット)し、そして、zoomで集まり対話を交わす(❸ダイアローグ)。
課題図書に選ばれるのは、ふだん一人ではなかなか手を出さないような骨太の名著だ。
毎週、明確な正解のない「問い」が出され、受講者は思い思いに「ああでもない、こうでもない」「いや、待てよこういう可能性もあるぞ」などと自分の頭で考える。
一人で黙々と考える時間があるからこそ、zoomでのダイアローグはとても深いものとなる。
濱口さんの言う通り、「話さない時間」を設けることが「話す時間」の質をあげている実感が、確かにあるのだ。
読めば読むほど、わからない
名著と呼ばれる本には、ある共通点がある。
それは、「読めば読むほどわからなくなること」だ。
信じていた常識は揺さぶられ、答えより多くの量の問いが与えられ、何かがわかる以上に、自分がいかに「わかったつもり」だったのかを思い知らされる。
読み終わった後の頭の中は、まとまらない思考でごちゃごちゃだ。
一人だと、そのごちゃごちゃは言葉にならないまま沈殿していく。
でも、対話の場があれば、思考は不完全ながらも言葉として形になる。そして、他者を触発するための「一石」となる。
問いは人を仲間にしてしまう
先日、読書ゼミの参加者と「飲み会」をした。
そこで参加者の方が口々に「こんないい仲間に出会えるとは思わなかった」と語ってくださった。
読書ゼミは「いい仲間をつくること」は目的にしていない。むしろ、仲間づくりを求めて来る人は、明確にお断りしたい。
ただ、結果的に、一冊の名著を読み終えた人同士はとても気心の知れた仲間となる。
そこに、問いの持つ不思議な力がある。
「こういう正解のないことを話す場って、なかなか日常にはないんですよね」
参加した方は、そう口を揃える。
日常、特に仕事の場では忙しくて、明確な意思決定につながらないような話ができない、というのもあるだろう。
しかし、本質的には、時間がないからではなくフラットな関係性がないからこそ、対話が生まれないのだと思う。
正解のある問いは人を序列化するが(知っている人が偉い。知らない人は偉くない)、正解のない問いは人をフラットにする。
そしてフラットになったとき、人は自分の考えに固執することなく、容易に変わることができる。これがまた抜群に気持ちいいのだ(なんだかヤバい人に見えていると思うが、ままよ!)。
議論において自分の意見を変えられるのは敗北だが、対話ではむしろ自らが変わること、それ自体がゴールとなる。
対話対話・・・と言うとなんだか説教くささが漂う。僕がとても好きな文章を一つだけ紹介して、いったんこのあたりにしておこう。
対話は、強制的な統合も、集団からの排除もなく、人と人とを異なったままに結びつける。差異がなければ対話する必要は生じず、結びついていなければ対話することはできない。ーー『人は語り続けるとき、考えていない』(河野哲也著)
もはや「読書」を超えている
焼肉屋は、肉を送ることで味覚を共有した。
僕たちは、本を通じて人を結びつけ、沈んでいくはずの思考を共有した。
語られるはずのなかった自分の思考を聞いていちばん驚くのは自分だ。ああ、自分はこんなことを感じる、考える人間だったのか。
そして、自分の話に他人が触発され、その他人の言葉によってまた自分も触発され、意見が更新されていく。
最終的にたどりついた答えは、その場にいた誰のものでもないが、同時に全員のものだ。
「感動とは、知らなかったことを知ることだ」
昔、恩師に言われた言葉だ。
そのときは正直意味がまったくわからなかったが、今なら少しわかる気がする。
自分なりの言葉を補えば、「感動とは、知らなかったことを知ることで、変わった自分を見ること」なのかもしれない。
人は本当に深く学んだとき、必ず自分に驚いている。
第二回目のアウトプット読書ゼミがもうすぐ始まる。今回は、前回よりさらに問いと対話の設計をパワーアップしていくつもりだ。
4/7(水)が締切予定だが、もうすぐ満員となりそうなので、興味のある方はぜひこの週末にエントリーしてほしい。
今回扱う課題図書について書いたゼミ全体のモデレーター、岩佐さんのnoteはこちら。
第一回読書ゼミ参加者による鼎談はこちら。
ほんと感動するんですよ。こんな場があるのかって。