
やってみてよかった情報43「変身する助詞の見つけ方」
変身する助詞をどう教えるといいか、悩んでいた時に作った教材です(⌒▽⌒)
先日、旧twitterを見てたら、
「わ・は」「お・を」「え・へ」の使い分けがなかなか入らなくて、
学年が上がっても苦労しているという呟きが流れていました。
あー、めっちゃわかる(T ^ T)
通常級担任時代から、これって結構鬼門でした。
「ここは下の『を』でしょ!」と声をかけたり直したりはするものの、
混乱している子達は、言われたところは直せるけど、
また次の時には、間違いを繰り返してしまうことが多かったです。
学年が上がると、「すごく気をつけていると、正解率が上がるけど、
急いで書くとほぼ全部「わ・お・え」になってしまう子も何人もいました。
「違うでしょ!」と言いながら、
・どう違うのか
・どう説明すればルールが腑に落ちるのか
をうまく説明できていない自分にもモヤモヤとしていました。
で、まず作ったのがこれ
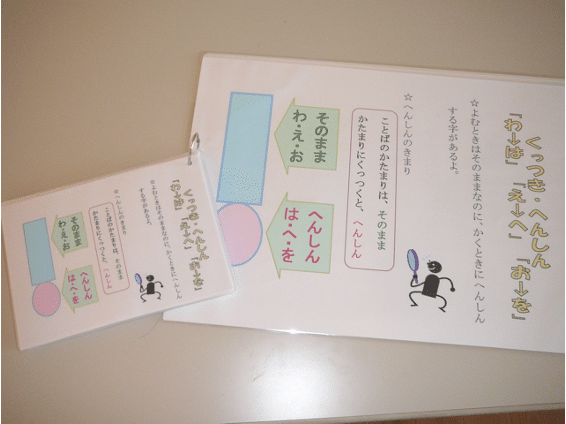
・音は同じ
・書くときだけ変身
・「言葉のかたまり」はそのまま
・かたまりに「くっつく」と変身
というのを短い言葉と図で示してみました。
これを作ってる時のことはよく覚えてます。
・「えんそくえいった」
という音なのに
・「えんそくへいった」
と書かなくてはいけないから混乱するんだよなぁ。
とぶつぶつ考えてて、
本当に当たり前のことなんだけど、
「変身させなくても音としてはあっている」
ということに、初めて気がついたんですよねぇ。
なんというか、いつの間にか覚えていて、
「どっちだったっけ?」と考えたことすらなかったので、
「音はあっているから混乱する」
ということに考えが全く及ばなかったんですよね。
「ああ、そりゃあ混乱するよなあ」
と、相当遅ればせながら腑に落ちて、
わかりやすくルールを見せないといけないなと思ったんですよ。
で、さっきの図を作りました。
あと、自分の考えてることも図にしてみました。

でも、ここでさらに問題が、
「言葉のかたまりとは」という疑問が(^◇^;)
「遠足は、言葉の塊でしょ?だから上のえを書いて
えんそく。
遠足えの「え」は「遠足」にくっついてるからへんしんして
「へ」になるんだよ」
と言っても、スタートの「遠足は言葉の塊」というのがイメージできないと
難しい。
うーん、今書いてても「こりゃあわかんないよなあ」と反省。
で、「言葉の塊」とそれ以外って、どうすればわかりやすく区別できるかなと考えて、
・言葉のかたまりは、絵になる
というのを手掛かりにしてみました。
こんな感じ。

これだと、「そういうことか」が割とわかってもらいやすかったです。
で、そういう練習問題を作ってやってみたり
ルールカードを作って、見せて確認したり

ここで大事なのが、「間違った時だけやらない」こと。
だって、「変身するかしないか」は2択ですから、
間違えたときだけこれを出すと、
「あっ、違うんだ。じゃあこっち」
と、ルールを意識せずに直してしまいかねません。
そうすると、また間違いが続くんですよね。
だから、「どれどれ、確認するよー」と言って
「おっ、ここは言葉の塊だね。絵にかける。だからそのままで正解!」
「こっちはくっついてて、絵にならないやつだから変身だね正解!」
と、合ってる時もカードを見せながら確認していくことを、
しばらくはやってました(⌒▽⌒)
もう10年以上前に作った教材なんですが、
今でもよく使います。
上の画像は私が元々作ったデータですが、
きれいにリデザインされたデータが、
国語のじかんにはついていますので、
よかったらそちらもご覧ください(⌒▽⌒)
