
大学生メンターとは? / 2年間やった僕の最後の問い(なるる)#Season2
大学生メンターのなるるです。
このnoteは、これから「大学生メンターになってみたい人向けに」書いていますが、そうでない人も読み応えのある文章を心がけています。
タイトルが「大学生メンターとは」なんていう大仰なものですが、そんなに立派なことを書くつもりはないです。ただ、Season1,2と大学生メンターを経験したからこそ、「(innovationGOの)大学生メンターとは(何だろう)」ということを書けるのではないかなと思います。
どうぞ、お付き合いください。
■大学生メンターの立ち位置
大学生メンターは、innovationGOに参加するU-18をサポートをします。これまで20名近くの全国の大学生に参加してもらいました。もちろん、僕もその一人です。

大学生メンターは、U-18の入っている「ゼミ」を任されます。ゼミは全国各地を冒険していくときのホームチームのようなものです。
大学生メンターはゼミ生同士が好きやワクワクを応援できる仲間になれるように一人ひとりをつなげたり、毎回の冒険後の学びを整理したりする活動をします。
こういう活動をしているので、「大学生メンターの立ち位置ってなんですか?」って聞かれたら、「大学生メンターはクラス担任のような立ち位置です」と答えるかもしれません。
担任の先生がクラスの様子を見渡して生徒同士の仲を深めたり、授業をして学びを整理したりするのと、同じようなことをしているのではないかと思います。
■僕が大学生メンターとして、今までやってきたこと
innovationGOには、FINDコースとMAKEコースというコースがあります。この画像はinnovationGOのwebサイトです。

U-18の「やってみたいかも?」をみつけるFINDコースと、U-18の「やってみたい!」をかたちにするMAKEコースです。
僕たち大学生メンターも、これらのコースをU-18と共に走ります。
では、具体的に大学生メンターは何をするのか。ここからは、大きく二つの活動内容を紹介していきたいと思います。
キーワードは「問いをわたす」ということです。
- 内容① 初めまして、では未来をつくろうか。
innovationGOのFINDコースでは全国を巡ります。Season1では全10地域を、Season2では全6地域を巡りました。

各冒険先では、地域を案内してくれる人(以下、ナビゲーター)が地域で事業を営む人(以下、ローカル・プレイヤー)を紹介して、インタビューをしてくれます。
このインタビューを通して、U-18は自分が知らなかった世界を知り、興味の裾野が広がっていきます。興味の裾野が広がった先の「やってみたいかも?」をみつける、これがとても重要なことです。
U-18の日常生活の中で「やってみたいかも?」を考えても、どうしても選択肢が少なくなるような気がします。できる限り、日常を延ばして、選択肢を増やしつつ、その中で「やってみたいかも?」をみつけることがU-18の成長につながっていくと思います。
では、そのU-18の「やってみたいかも?」をみつけることに、大学生メンターはどのように寄与していくことができるのでしょうか。
FINDコースでは、ナビゲーターとローカル・プレイヤーのインタビューの時間の後に、ワークショップの時間があります。
このワークショップの時間では、インタビューを経てU-18が「気づいたこと」をもとに、未来をつくるアイデア(=イノベーション)を考えていきます。
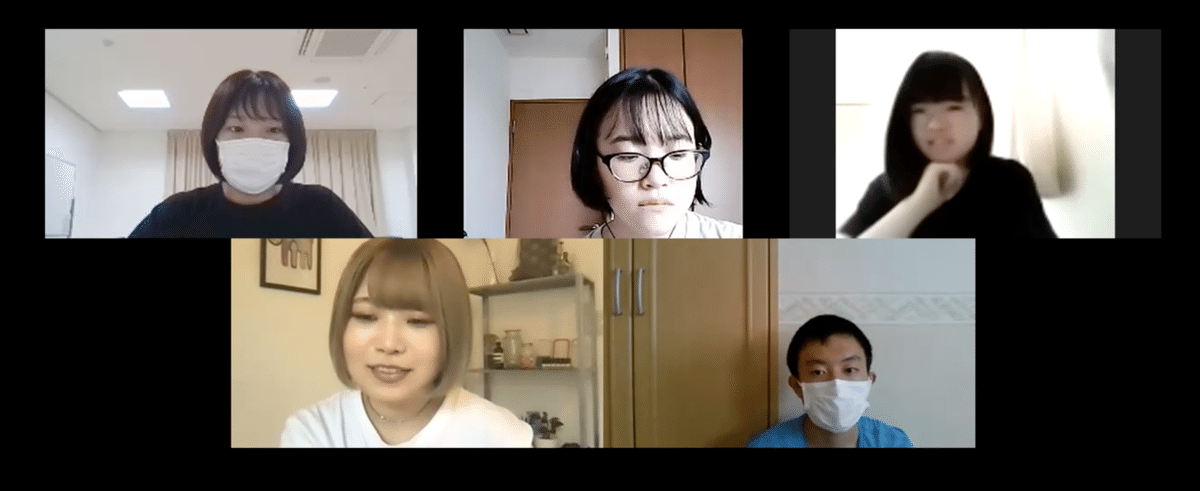
このワークショップは、ゼミ生同士でチームを組んで行います。プログラムが進むにつれ、U-18もリラックスした雰囲気で進められるようになります。
ですが、プログラムが始まったばかりの頃はちょっと大変です。U-18同士は、お互い初めましての状態。その状態で、ワークショップ開始「じゃあ、未来をつくろう!イノベーションを起こそう!」となるわけです。
つまり緊張をどうほぐしていけるかが、大学生メンターの最初の役割。なので、毎回のプログラムで緊張をほぐすためのアイスブレイクをしてからワークショップに入ります。緊張が少しほぐれてきたら、次の課題が立ち上がってきます。
U-18がインタビューの中で気づいたこと、興味を持ったことを話してくれるのですが、みんなちょっとしか話さないんです。
「OOがすごいなと思いました」
「OOということを初めて知って驚きました」
おそらくみんな恥ずかしがっているのか、そこまで深掘りできていないかの状態です。
こんなときこそ、大学生メンターの出番。
「すごいと思った理由はなんだろう」
「OOのことを初めて知った、なんで今まで出会わなかったんだろう」
みたいに「問い」をわたしていきます。
大学生メンターが「新しい世界との出会いを通したU-18の内面の気づきを、問いをわたすことで促す」。そしてこうしたU-18の内面の気づきを得ることは、自身の未来をつくる火が灯ることに今後つながっていくわけです。
初めまして、では未来をつくろうか。
これは地域の未来でもあり、U-18自身の未来でもあるわけです。
-内容② 「やってみたい!」のきっかけを教えて!
innovationGOのMAKEコースでは、FINDコースで冒険した地域の中から一つ地域を選び、U-18の「やってみたい!」をかたちにするための冒険をします!

MAKEコースがFINDコースと違うことは、つくりたい未来を実現するためのアイデアを実際に「やってみる」ことだと思います。
やってみる(チャレンジ)の行動量はU-18によって違いが出ます。アイデアを実行するためのアンケートを取る人、プロトタイプをつくってみる人。大学生メンターは、それぞれのU-18に向かい合いって、モチベーションを高めつつ、チャレンジを後押しできるようにメンタリングをしていきます。
そのメンタリングをSeason1,2とやってみて必ず出会う瞬間があります。それは「やってみたい!」のきっかけを聞く、問いをわたしたとき。
最初は流暢に話していたU-18が、大学生メンターの問いに答えているうちに、ふとこんなことを聞いてきます。
「エントリーのときのつくりたい未来、アイデアから、変わってもいいんですか?」
こうした声は、U-18の心に火が灯り始めた瞬間だと僕は思っています。
というのも、このU-18の問いかけの真意は「(メンタリングの中で)自分が何にワクワクしているのか、何を『やってみたい!』のかやっと腑に落ちました」ということを表しているように思うのです。
全てのU-18が当てはまるわけではないですが、エントリーフォームにはU-18がその瞬間に思いついたことを書いている場合があります。
そうなるとプログラムが始まってみると「正直そんなにやってみたくないかも?」と思い始める状態があります。もし、そういう状態にあるなら相談してくれれば早いのですが、なかなかU-18は言い出してくれません。
だから、メンタリングでまず「やってみたい!」のきっかけを聞く問いをわたす。U-18がその問いに答える中で、彼らの中にある真の「やってみたい!」に気づくわけです。
「やってみたい!」のきっかけを教えてくれない?
それは、U-18が自分の中にあるワクワクに気づくための問いであり、U-18が心の底からの「やってみたい!」をかたちにするために必要な問いなわけです。
■結局のところ、大学生メンターとはなんなのか
大学生メンターの活動内容は、上の2つのセクションで書きました。僕は今まで、U-18に問いをわたしてきました。そして、今僕は一筋縄ではいかない問いを自分自身にも、わたしています。
「(innovationGOの)大学生メンターとは(何だろう)」
パソコンの前に向かいながら、ドラフトや構成を書いていた紙と睨めっこしながら、ずっと悩んでました。そこで気づかされたのは、大学生メンターを語る上で「信頼関係」という言葉を抜きには語れないということです。
大学生メンターは、U-18の友人でもない家族でもない、何だか不思議な信頼関係を構築します。U-18を信頼してるから、問いを1人で考えさせます。また、U-18も大学生メンターを信頼しているから、この人に自分の考えをぶつけてみようと思える。
もし、信頼関係がうまく構築できていなかったら、「U-18も言いたいことが言えなかったり、メンターに答えを求めるようになる」のだと思います。そして、それ以上に「U-18自身がワクワクを深めていくことにモチベーションを維持できなくなっていく」と思います。
だから、U-18との信頼関係があって初めて「メンター」になれるのだと思います。ですが、信頼関係は一朝一夕では構築できません。
信頼関係を構築するには一方的にU-18のことを知るだけではダメで、大学生メンター自身も自分のことを積極的に知ってもらおうとする姿勢が求められると思います。
それは詰まるところ、大学生メンターは大学生である自分としっかり向き合う必要があるということです。そうすることで、U-18と大学生メンターはお互いを信頼し合いながら活動をしていくことができます。
先日、Season2 大学生メンターのお疲れ様会を行いました。その会では、大学生メンター活動のあれやこれを振り返り、学びを共有するという時間です。figmaというホワイトボードツールを使って、学びを深めました。

この中で、大学生メンターの楽しかったことを共有したときにも、信頼関係的に関連する付箋が出てきました。
「U-18に頼られていると感じたときが嬉しかった」そんな言葉が上がったのです。初めましての状態で、お互いのことをよく知らない状態からスタートして、大学生メンターである自分を頼ってくれたとき。それは、大学生メンター冥利につきるのではないかと思うのです。
他にも、「参加してよかったと言われたとき」という付箋も上がりました。大学生メンターとU-18との信頼関係があるからこそ、こういう言葉がU-18から自然と出てきたのではないかと思います。
「大学生メンターというのは、特別このスキルが必要です」ということではない。
U-18のことを知ろうとし、自分を知ってもらおうとする、そうやって信頼関係を構築する。アイデアをどうしていきたいかは、その後でU-18と一緒に考えていけばいいんです。
ということで、ここまでのことをシンプルにまとめてみたいと思います。

『大学生メンターは、U-18と信頼関係を構築し、対話を深めるパートナーである。必要なのは、目の前のU-18にとことん向き合うこと』
この答えはあくまでも僕なりの答えです。
これが正解ではないと思います。
ただ、これから大学生メンターを「やってみたいかも?」と思う人は、ぜひこのことを頭の片隅におきながら活動をしてもらえればと思います。
■大学生メンターを「やってみたいかも?」
ここまで読んで、大学生メンターを「やってみたいかも?」と思った方は、ぜひ、応募してみてください。
大学生メンター特設WEBはこちら!
大学生メンターの活動を通して、きっと大きな学びを得て、成長することができると思います。
何よりも、この活動を「楽しそう、面白そう」と思ってくれたその気持ちは間違いではないので、その最初の気持ちを大切にしてこれから活動してほしいです!
innovationGOの大学生メンターチームは、いつでもみなさんのことを温かくお待ちしています!
なるる
追伸
これまでたくさんのinnovationGO noteを書いてきましたが、これがぼくが執筆する最後のinnovationGO noteとなります。
(ぼくが執筆した記事はこちらにまとまっています!)
このnoteを読んで、「大学生メンターって面白そう!」とか、「innovationGOって大学生にも意味がある取り組みなんだ!」とかそういうことを感じていただければ、とても嬉しいです。
改めてですが、innovationGO noteを愛読していただいた皆様、本当にありがとうございました!
また、どこかで。
なるる
<この記事を書いた人>
なるる。武蔵野美術大学造形構想学部に在学中。innovationGOの運営をするi.clubでインターンをしており、大学生メンターとしてinnovationGOに関わる。普段は、社会とデザインをどう結びつけるか、を考えている。森や川、海、山など自然の創り出す空気が好き。実は・・・なるるが本名ではない。
