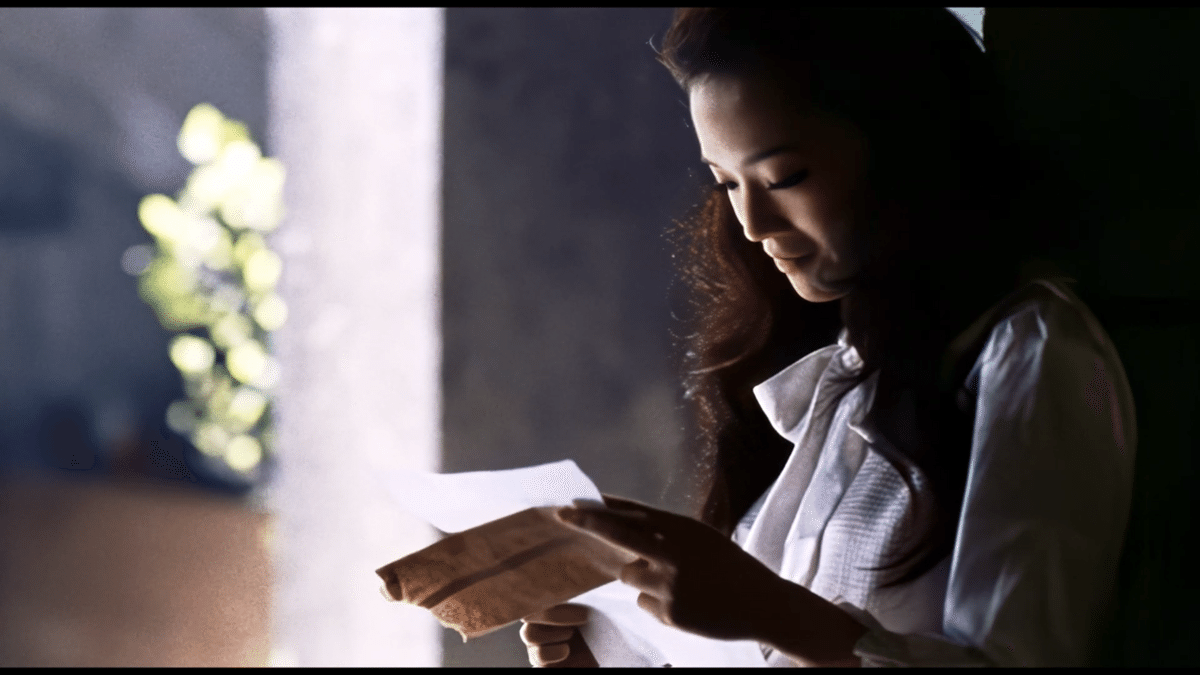時間は滅多に進まない
優れた映画作家はいとも簡単に優れたシーンを撮る。同じように優れた作家は、「なんてことのない場面」さえ、それが人の人生の忘れられない一瞬であるかの如く劇的に撮ってしまう。
例えば侯孝賢、『百年恋歌』の冒頭。青年(張震)が春子という女性に会うためにビリヤード屋へ行くが、彼女はすでに店を去っている。春子の代わりに秀美(スー・チー)という女性が新しく店の娘として入ってくる。そこで青年は秀美と夜までビリヤードをする。青年が帰った後、店じまいをしている秀美のところに、店のシャッター(のようなもの)が閉まるすんでのところで青年が帰ってくる。青年は秀美に「手紙を書くよ」とだけ伝えてまた去っていく。

ただ二人の人間が喋ったり喋らなかったりするだけのこのシーンが、一体どうしてここまで美しい時間を形作るのだろうか。似たような例をもう一つ挙げたい。マノエル・ド・オリヴェイラの『クレーヴの奥方』である。
医師のクレーヴ氏と結婚したカトリーヌ(キアラ・マストロヤンニ)は、世界的に高名な歌手であるペドロ・アブルニョーザ(本人)に密かに恋心を抱いている。かつて死際の母に、「お前が不倫をしないかだけが心配よ」と言われた彼女は、本心を隠しアブルニョーザを避けるようになる。ある日、カトリーヌは一人でアブルニョーザの写真展に行く。展示される写真に夢中になっていた彼女がふと振り返ると、そこにはアブルニョーザ本人がいる。驚いて立ち去ろうとした彼女を、アブルニョーザは呼び止める。しかしカトリーヌは自らの欲望を恐れるように、「夫が待っている」と言って去っていく。

上に挙げた二つのシーンはどちらも2人しか登場人物が出てきていないのにも関わらず、どこまでもサスペンスフルで美しいシークエンスとなっている。こう言ったシーンを見てしまうと、素晴らしい映画を撮るということがあまりにも簡単なものに思えてくる。2人の人間の会話だけで映画はつくれるのだと。しかし決してそうではないということ、2人の人間の会話だけで映画を作るということがとても簡単ではないということを示す証拠もまた同時にある。竹内梨沙監督の短編、『再見』である。オープニング、朝、同居している2人の若い女性が会話をしている。「今夜オーロラが見えるらしい」「デマでしょ」「いってらっしゃい」「行ってきます」そんななんの変哲もない会話である。

この会話には『百年恋歌』のロマンチシズムも『クレーヴの奥方』のサスペンスも含まれていない。ただのんびりとしたどこにでもある雰囲気が描写されるだけである。この差異は一体どのように生まれるのか。侯孝賢の方は確かに美しい映像が叙情を誘発したと言って説明できるかもしれない。店の外と内の光量の差がもたらす見事な逆光と、店の奥の方に置かれて一切出てこようとはしないカメラ、それから然るべき瞬間に挿入されるクロースアップが「なんてことのない場面」を特別なものにしたと。しかしオリヴェイラの方は、たとえエマニュエル・マシュエルの確かな画調選択とカメラポジションの設定があるとはいえ、フルショットの画面をパンさせ2人の動きをただ追うだけである。
傑作とは決まって、人に「時間は進んでいる」ということを知覚させる映画のことだ。時間は滅多に進まない。人が時間が進んでいることを知覚するのは、何か忙しく作業をしていてそれが終わった後だったり、自らの、あるいは他者・外部の変化を振り返った時のみであって、時計を見て時間を知るという行為は記号としての時間を認識しているだけに過ぎない。人は時間を滅多に知覚できない。そして人は、時間を「変容」を見ることによってでしか知覚できないのである。「シネマ」とは、「変化」の意味である。ある状態から別の状態へ変容する様を見ることによって人は時間が進んだということを知る。
『百年恋歌』に、『クレーヴの奥方』にあったのは、「変容」の表象による時間の存在に他ならない。そして『再見』の冒頭になかったのもその時間の存在なのである。侯孝賢において、2者の会見シーンは今にも関係が変容しようとしている。ある男女が見知らぬ他者同士から恋人たちへと変容していくプロセスを、絶妙な沈黙の中で繊細に捉えようとしている。このシーンがどこまでも美しいのは、会話もほとんどないなかで二人の男女の決定的な関係の変容を、作家が巧妙に描き出しているからである。この「変容」が見る者に時間が進んでいることを知覚させる。オリヴェイラにあっても事態は同様だ。今にも関係が変容してしまいそうなその場からカトリーヌは断固として立ち去ろうとする。しかしその時にはすでに関係は決定的に変容してしまっている。
その関係が変容する様、その場が明らかに変容しようとしている様を見るとき、我々は時間が刻一刻と刻まれていくのを生々しく感じる。時間は滅多に進まない。だからこそ時間が進んでいるということを知覚させてくれる映画は傑作なのである。侯孝賢とオリヴェイラがしていることとは単に「時間を進める」ということに過ぎない。それゆえに彼らの映画はいとも簡単に感動的なシーンを撮ってしまっているように見えるのだ。そして「時間が進んだ」映画の最後に残るのは、「全てが変わってしまった」という諦念と「色んなことがあった」という過去への憧憬とがもたらす感動なのである。