
第7話 対外政策(授業第2回)
対外政策論はそれだけで一つの科目になる。意義も、内容もある。アメリカはこうだ、中国はそうだ、ロシアはああだ、日本はどうだ、と素人がやる。多くは的を射ている。
プロがそれをやったらどうなるか?、というのがハロルド・ニコルソンの『外交』だ。ニコルソンはイギリスの外交官だが、紳士服のモデルのように見かけのよい人だ。まぁ外交官というものは見かけで説得するものだ。
イギリス、ドイツ、フランス、そしてイタリアの外交についてニコルソンがイメージしたことをスライドにした。

イギリスは自分の国だけに、スマートなイメージが前面に出ている。

つぎにドイツは「敬して遠ざく」といったところ。信用できないし、少し危ない。

恐いドイツのことで頭がいっぱい、という当時のフランスの様子が表現されている。意外にも、太陽がいっぱい、とか、デモがいっぱい、というイメージは当時なかった。

イタリアにいたっては、軽蔑を吐露した以外の何物でもない。
要するに、ニコルソンが表現した各国対外政策のイメージは帝国主義と両次大戦間期の歴史を観察して得た感想そのものなのだ。AIに表現させても同じような結果が得られるかもしれない。個々のケースについてのイメージを答えて、頻繁に出てきた概念を抜き出したものが対象国についてのニコルソンのイメージというわけだ。未来が過去に似ていれば、その国がこれからどう出てくるか、を予想するのに役立つが、新機軸や革命的変化には対応できない。
ニコルソンの例のように、対外政策をイメージや印象に基づいて論じることはたやすい。しかし、科学的、体系的に教えようとすると、これほど難しいものはない。体系的な枠組みを示したものとしては、花井等ほかが整理したものがある。
一. 外交政策の諸要因
二. 政策決定過程
三. 外交政策スタイルの特徴
私なりの理解を書くと、一つ目の「外交政策の諸要因」は環境要因であり、特に「国力」や「地政学」として論じられるものだ。いわゆる現実主義がこれを主な分析対象にする。国力のテーマも授業1回分になるので、ここでは扱わない。
他方、三つ目の「外交政策スタイルの特徴」は上で見たニコルソンのイメージに近いものと考えられる。アウトプットから支配的な印象を抜き出したものだ。日本外交にはどういう傾向があるか?、は学生さんたちに考えていただくことにして、ここでは割愛する。
そこで、二つ目の「政策決定過程」ということになる。Decision-makingは意思決定、Policy-makingは政策形成や政策策定と訳される。「政策決定」とは、両者の意味を合わせたものだろう。
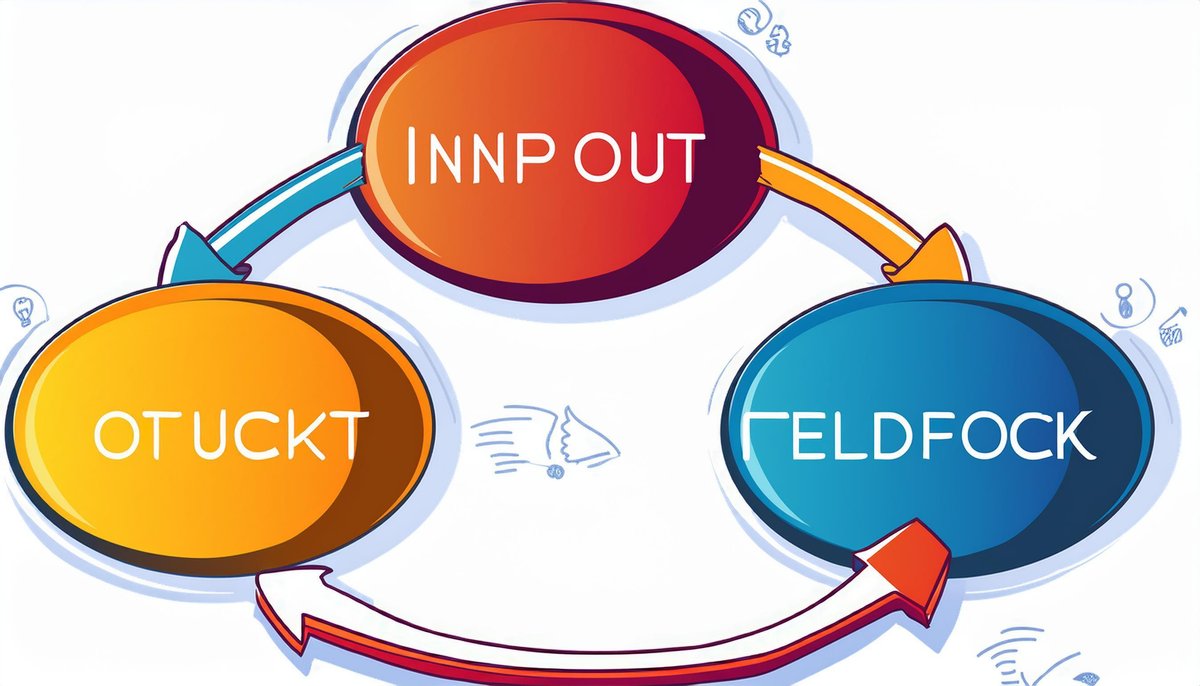
システム理論やサイバネティクスと政策決定過程は相性が良い。環境からのインプットを情報処理し、政策としてアウトプットする。政策がうまくいったか否かを判断し、次の政策へとフィードバックする。こうしたフローが政策決定過程だ。(ただし、花井ほかの著作ではシステム理論は採用されていない。)
つまり、政策決定過程は諸アクターが所与の制度のもとでいかに政策に影響を与えるか?、というゲームだ。研究の方法としては、アクターと制度を分析することが中心だ。
システム理論を政策決定過程に応用するメリットは、独裁国、民主国、共産国、前近代国家など、政治体制を選ぶことなく記述できる点にある。蒙古襲来を調伏する祈祷も、国連安保理への訴えも、等しく対外政策であり、機能的等価物ということになる。
システム理論は比較には役立つものの、一国だけを分析する場合は、皮肉にも、ほぼ必要ない。一国の政策形成を説明するのが上手か下手かは、各国の政治制度をいかに熟知しているかに大きく依存する。
ということで、日本外交を分析するには、その政治制度がいかに変化し、その枠組みの中で諸アクターがいかに行動したか、を細かく論じることが重要だ。
時代区分を日本外交の政策決定過程に施せば、幕末、明治憲法以前、明治憲法下、そして現行憲法下に分けられよう。明治憲法下までは制度・慣行は激しく変化した。

外務大臣が外交を主導するのが大日本帝国憲法のもとではふつうだった。総理大臣、軍部、議会、あるいは枢密院が大きな役割を果たした時期もあったものの、天皇に直接、外務大臣は外政の責任を負った。実務でも、在外公館や部局からの報告を外相が読み、それに対して返事を書く、というのが基本的な流れで、他国でも大同小異だった。
第二次世界大戦後、総理大臣が外交も事実上、ワンマンで責任を負うようになった。大臣の人事権も「彼」が握った。このあたりは下の記事に書いてある(授業では無料)。
アクターの分析も制度の分析と同様、掘り下げがいがある。吉田茂など総理大臣がどのようなパーソナリティだったか、は単に物語として面白いだけでなく、対外政策アクターの研究として意義深い。
こうした政府内の政策決定過程は、どう概念化できるのか?
世界一、有名なのはグレアム・アリソンの対外政策モデルだろう。
合理的行為者(古典)モデル
統一的な国家・政府による価値の極大化官僚政治モデル
立場のことなる閣僚プレイヤー間の駆け引き組織過程モデル
政府を構成する巨大組織のルーティンな過程・手続き
合理的行為者モデルは、どちらかというと政府内の過程に左右されない。意思決定はこうあるべし、という理念として捉えられる。
アリソンのものの真骨頂は残りの2モデルだ。閣議室での高官間の駆け引きが官僚政治モデルでは描かれる。他方、それぞれの省庁での立案が下からの圧力で上がってくることをイメージさせるのが組織過程モデルだ。
日本の政策形成は、組織過程モデルに近いのでないか、という印象を私は持っている。なぜなら、丸山真男が指摘したタコツボ型の「巨大な組織体が昔の藩のように割拠する」というイメージが日本社会の特徴としてしみついているからだ。総理大臣が国益を第一に沈思黙考して日本の未来を決断する、というのは劇画的な世界観に感じるし、閣議で合理的で冷静な議論が行われ、その結果として最適解が出されているとも想像しがたい。最近は丸山真男を読む人はあまりいないと思うので、『日本の思想』から引用しておく。
ただ日本の特殊性はどこにあるかというと、ヨーロッパですとこういう機能集団の多元的な文化が起っても、他方においてはそれと別のダイメンジョン、それと別の次元で人間をつなぐ伝統的な集団や組織というものがございます。たとえば教会、あるいはクラブとかサロンとかいったものが伝統的に大きな力をもっていて、これが異った職能に従事する人々を横断的に結びつけ、その間のコミュニケーションの通路になっているわけです。ところが日本では教会あるいはサロンといったような役割をするものが乏しく、したがって民間の自主的なコミュニケーションのルートがはなはだ貧しい。明治以後、近代化が進むにつれて、封建時代の伝統的なギルド、講、寄合といったものに代って、近代的な機能集団が発達しますが、そういう組織体は会社であれ、官庁であれ、教育機関であれ、産業組合であれ、程度の差はありますが、それぞれ一個の閉鎖的なタコツボになってしまう傾向がある。巨大な組織体が昔の藩のように割拠するということになるわけです。
日本の歴史で最も猛威を振るったタコツボが軍部だった。「関東軍」というと、満洲事変を強行して国全体を世界のつまはじきにした組織だが、内部の論理だけで動き、外部の声を聞かない人々を指す普通名詞でもある。
稟議制については、下僚が起案した稟議書が上司の同意を得ながら最終的には大臣の決裁を経て法令となるさまを辻清明の『新版日本官僚制の研究』が描いた。こうしたやり方は集団主義につながり、対外政策でもタコツボ化をもたらしていることだろう。以上、20年以上前に勉強した内容なので、今でもこれでよいのか心もとなくもない。
さらに、政治制度内での政策決定過程を「システム」と呼ぶならば、世論や外国といった外部からのインプットも考慮に入れる必要がある。
日本はタコツボの集合体だ。すべてが「関東軍」のように暴れまわったら、内部崩壊してしまう。そこで、それぞれのタコツボからの要求を集約することが必要になる。このゲートキーパーの役割、つまり集約機能、を果たすのが政党だ。日本では自民党が長期政権を握り、固定客を優遇する政策を続けている。そうしたお客さんの対応をしているのが族議員たちだ。
「鉄の三角形」という言葉がある。政・官・財というように、政界・官界・財界の特殊利益がタッグを組み、自分たちの利益になる政府政策を支持しているという分析だ。対外政策ならば、「軍産複合体」による軍拡や日本のコメ農家を守るための通商政策に見られる。
だんだん、対外政策から離れてきたような気がする。対外政策というと、平和政策と武力行使といった政策手段のテーマもある。ローレン、クレイグ、ジョージのこの本はもう古いのか?
ここまで書いて、対外政策を講義することは大洋に乗り出すがごとき事業だ、と悟った。それに比し、我が身は水面にただよう落ち葉のようになんと頼りないことか!
と考え、筆を止めることにした。
課題
戦後における日本外交の傾向またはイメージを20字程度でまとめて鍵括弧にくくって示し、どうしてそのような傾向またはイメージとして表現されるのか、できれば具体例をあげながら300字以内で説明しなさい。
13デイズの会議シーンにおける文民と軍人の発言内容や身振りを比較し、それぞれの特徴を述べなさい。
対外政策でなくてもよいので、「鉄の三角形」の具体例を、それを構成する①政策、②政界の特殊利益、③官界の特殊利益、そして④財界の特殊利益(財界でなくても民間の利益集団ならばよい)のすべてを挙げて解説しなさい。
