
2024年で変化したメディアの新しい地図―新旧メディアの興亡からコンテンツビジネス大転換を数字から読み解いてみた
テレビ局の視聴率が歴史的な下降線をたどった昨年から、2024年一旦は下げ止まったように見えましたが、都知事選や兵庫県知事選ではYouTubeがテレビ報道を超える選挙行動への影響を発揮しました。これは単なるプラットフォームの交代劇でしょうか。もっと本質的な「メディアの価値」の変容が決定的になった年なのかと思います。
新旧メディアの興亡から、情報時代の転換点。それは「規模の経済」から「希少性の経済」へのパラダイムシフトに見えます。というわけで「共感」を通じた価値創造について数字から読み解いてみました。約5,000字。興味の在る方はお付き合いください。
池松潤/Jun Ikematsu
コミュニケーションデザイン/事業計画/エクイティストーリー/エンタープライズ営業コンテンツ/マーケティング/コンテンツなど。スタートアップCEOの壁打ち相手。慶応義塾大学卒/博報堂を経てスタートアップの若手と世代間常識を埋める現役58歳。ときどき婦人公論.jpにコラムなど。 ⇒ https://lit.link/junikematsu
第一章:「メディアの構造」の変化を数字で辿る
2024年は「視聴者、広告費、報道」3つのポイントからメディア構造が変化しました。テレビからyoutubeへ、プラットフォームがシフトした象徴的な年なのではないでしょうか。数字で追ってみましょう。

◆「メディアの構造」/視聴者の変化
テレビとYouTubeの視聴動向(2014-2024)

2010年から2024年にかけてのテレビとYouTubeの視聴動向は、特に若年層を中心に大きな変化を見せています。
※コネクテッドTV白書2024より作図
◆YouTube視聴動向
視聴時間の増加:
YouTubeは特にスマートフォンでの視聴が多く、コネクテッドTVでの視聴時間も増加。2024年にはYouTubeがコネクテッドTVでの視聴時間で地上波放送に次ぐ位置を占めています。
◆テレビ視聴動向
視聴時間の減少:
近年、特に若年層(10代・20代)のテレビ視聴時間が大幅に減少しています。例えば、10代では2009年の140分から2021年には83分に減少し、20代でも同様の傾向が見られます。

◆「メディアの構造」/広告費の変化
◆テレビ広告費の推移
・2014年:1兆9,564億円
・2019年:1兆7,880億円
・2024年:1兆4,750億円

◆インターネット広告費
・2014年:1兆519億円
・2019年:2兆1,048億円
・2024年:3兆5,000億円
※YouTubeの広告収入は全体の約20%を占める

◆「メディアの構造」/報道・ニュースの変化
兵庫県知事選が象徴的でしたがSNSのPR活用を記したnoteに是非が報道されました。公職選挙法違反の可能性や、「マスメディアvs SNS」から生まれる拒否反応を予測しなかったのはどうかと思いますが、「法的」な問題は司法の判断を待つこととして、2024年は、SNSが選挙戦ニュースの主役に躍り出た象徴的な出来事として記憶に残るのではないでしょうか。
これを期に「選挙報道・ニュースのあり方」が考え直されたのは事実です。テレビは依然として主要なニュース源ですが、SNS利用が急増して、2024年には42.9%の人々が、SNSを通じてニュース情報を得ています。特に10代から30代のユーザーの約6割がX(旧Twitter)でニュースを収集しています。

※ニュースを得ているメディア利用/2024年・モバイル社会研究所調べ
すでに視聴者は、ネットにある大量のコンテンツにアクセスしつつ、なおかつ「ネットメディアからの情報リテラシーを得る機会」を急増したのだと言えます。これは情報の接種スタイルが、全世代にわたり急速にネット空間にシフトしているのは間違いありません。
◆テレビ報道の変化
2024年の選挙では、SNSの影響力が顕著で、テレビ報道は選挙後の疑惑や問題点を十分に取り上げられず、「報道の穴」が指摘されています。放送法や公職選挙法による制約がある中で、テレビは公平な報道が求められますが、新たな情報や疑惑を取り上げることが難しくなっています

◆YouTubeとSNSの影響
YoutubeやSNSは、特に若年層において重要な情報源となっています。2024年の選挙では、SNSを参考にした有権者が30%に達し、これは新聞やテレビを上回りました。斎藤県知事の公式YouTubeチャンネルは約119万回以上再生され、SNSでの情報発信が支持基盤を広げる要因となりました。
兵庫県知事選における「マスメディアがYouTubeに負けた」というのは、メディア構造の変化をこのような「数字」が表しているのではないでしょうか。

第2章:ネットメディアの考察
PIVOT /ReHacQ /NewsPicks 3つのYouTubeチャンネル分析

では、ネットメディアを深堀りしてみましょう。2022年9月〜2024年9月のデータ分析から見えてくるものが、検索しても出てこないので書いてみました。
◆登録者数(2024/12現在)
・PIVOT 226万人
・NewsPicks 148万人
・ReHacQ 121万人

◆直近の登録者数増加(差分)の比較
毎月何人純増しているかをグラフにしました
①:PIVOTが2023年5月前と比べ、2023年9月以降の上昇率が増えている
②:2023年5月から2023年9月まで急上昇。この期間はチャンネル登録を目的として、広告プロモーションを強化していた様子。PIVOTがNewsPicksを追い抜こうとしていたのがわかる。
③:各チャンネルを分析すると、ライブ放映はユーザーが即時性が高く感じるので、チャンネル登録させやすいという傾向があり、編集が不要なので制作コストを抑えやすいというメリットがあります。

◆誰が見ているのか
「検索データ」から逆引きして「興味ユーザー」の年齢層をみました。
各メディア共に40代50代が中心であることが分かります。

◆経済メディア読者層も高齢化
経済メディアは30代・40代をターゲットとしたメディアが中心だった印象ですが、30・40・50代が中心読者層です。この10年で40歳代が50歳代へなっているのがわかります。

◆再生数・推移:累計視聴数の推移を比較
全体再生数はNewsPicksが圧倒的で差は広がっています。
そもそものアップ本数と、自社WEBメディア読者とのクロスメディア相乗効果と思われます。

◆動画1本あたりの視聴回数

・1本あたりの視聴回数はReHacQ
・1登録者あたりの視聴回数はNewspicks
・PROピッカーによるコミュニティ形成による視聴回数への効果が推測される。
・ReHacQが資本も少なく、人数も少数精鋭で、質を追求せざるを得ないのがわかる
第3章:PIVOT /ReHacQ /NewsPicks 3チャンネルの分析からわかること
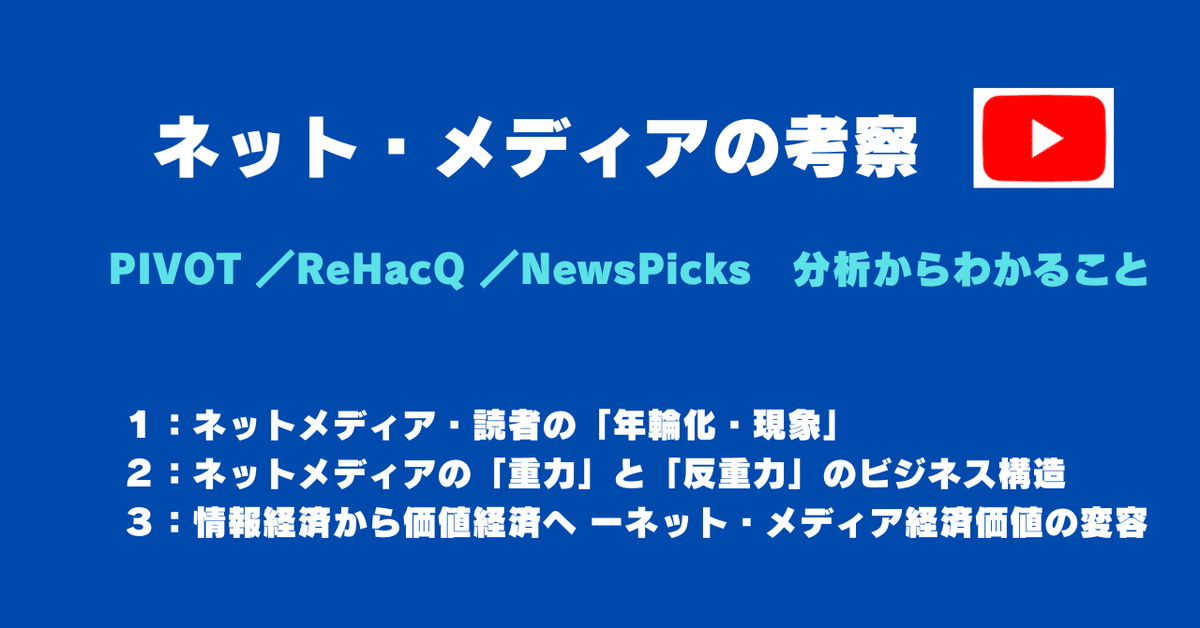
1:ネットメディア・読者の「年輪化・現象」
下記のデータ分析から考察できるのは、NewsPicks、PIVOT、ReHacQの読者層が40-50代中心になっていること。これは単なる高齢化ではありません。経済メディアと読者の「共に年を重ねる現象」です。
10年前に30代だった読者が、メディアと共に成長し、現在の40-50代コアユーザーとなっています。つまりネット・メディアには「年輪のように読者層が積み重なっていく」特性があります。
ここから学べるのは。より若い世代に「橋頭堡を構築」することがネットメディアのオーガニックな長期成長をもたらすことでしょう。
2:ネットメディアの「重力」と「反重力」のビジネス構造
ビジネス経済メディアの3社のうちリーダー的存在である「NewsPicksの事例」から考察できるのは、プラットフォームには二つの相反する力が働いていることです。
・「重力」:既存の収益モデルに引っ張られる力
(広告収入・課金など)
・「反重力」:成長と価値創造は比例しない
(伸び率が下がると収益性を求める)
「NewsPicks」から考察できるのは、メディア運営の効率性がテレビ時代に近い「集約労働」に偏っており、制作工程のAIなどによる自動化(効率化)が出来ていない点です。このビジネスモデルだと成長の鈍化がさらに進むことが推測できます。
これはネットメディア界隈では、よく言われている「言説」ですが、ネットメディアにおける「イノベーションのジレンマ」が既に生じていると見て間違いないでしょう。
PIVOTもビジネスモデルにおいて同様な収益性の鈍化が指摘されています。その点、ReHacQは髙橋さんの個人能力に依存しているので、この点をよく把握していると思われます。それが「1本あたりの視聴回数」にあらわれています。下記の考察に続きます。
3:情報経済から価値経済へ
―ネット・メディア経済価値の変容
興味深いのは、動画視聴データにおいて最も新しいReHacQが「1本あたりの視聴回数」で最も高い数字を示していることです。
これは従来の「情報の経済価値」(規模の経済)が「共感という価値経済」(希少性の経済)に反転している可能性を示唆しています。

つまり、視聴者(読者)との関係性の距離が近いことが重要です。その方向性にシフトしているネットメディア「ReHacQ」の方が「収益性」と「成長性」が高い点が興味深いです。これは「ReHacQ」の番組内容が優れているわけではなく、ほぼ高橋さんの個人が全部を見ている「個人商店」要素が「吉」と出ているようにも見えます。
上記3社は、コンテンツの「量より質」のせめぎ合いの時期になっているのが2024年の傾向だっったと総括できます。「規模」より「関係性の深さ」が価値を生むネットメディアの新しい形が見えつつあるのではないでしょうか。

これは8月に行った、婦人公論.jp「メーテレ・メモ少年・篠田プロデューサー」へのインタビューからも兆候が見えています。これに気がついているヒトはまだ少ないのではないでしょうか。
手短に言うと、これらの「コンテンツ価値の再定義」とは、実は「メディアの本質的価値」の再定義を意味してます。
ひも解くと、AI時代のネットメディアとは、一周回って実は「人間の「問い」の価値が重要になっている」ことを示しています。AIによる人間力の拡張によって格差が一層広がっているとも言えるのではないでしょうか。
第4章:「共感する」経済効果の指数化が今後の鍵を握る
今後は、「共感する」部分の経済効果の指数を開発していくことが大事です。新しい指標を開発して「見える化」させていくと、ステークホルダーへの説得力が増していくと思われます。
1:「共感」がもたらす経済価値の数値
・チャンネル登録者の継続率(定着率)
・コメント数やエンゲージメント率の利益との相関関係
・「推し」共感コンテンツの視聴時間と広告収入の関係性
2:収益構造の変化を示す数値・比較
・従来型の広告収入 vs コミュニティ収入との比率
(メンバーシップ課金など)
・「単発・視聴者」 vs 「コアファン」による収益貢献度の比較
・コンテンツ1本あたりの制作コストと、収益率の推移
(何が収益率に影響が大きいのか)
3:視聴者行動の変化と経済効果の指標
・視聴時間とコンバージョン率の関係
・コミュニティ参加度と、ファングッズなど購買行動の相関性
・横のファン同士のつながりや、相互作用がもたらす収益性との関係性
おわりに:「ミサイル空中戦」から「ドローン空中戦」へ
これらは、単にメディア・ビジネスの「お作法」が変わったのではなく、戦争の仕方が劇的に変化したと言えます。
例えて言うならば、ウクライナ戦争で「AIの戦術活用」(過去の戦術の自動比較で最適な戦術がサジェストされる)と、「安価なドローンの大量生産」による「現場の戦闘が激変した」ように、ネットメディアの競争環境が「ミサイル空中戦」から「ドローン空中戦」へ、劇的な競争環境が変化したのだと言い例えられるのではないでしょうか。
この変化の本質を「戦略レベル」から理解して「戦術」「作戦」に落とし込む必要があります。その「知識」と「具体的なスキル」(※SaaSメトリクスの数値指標の設定力)が必要になっているのです。
これらは、単なる「ネット・メディアの変化」ではありません。デジタル時代における「価値創造の新しいパラダイム」を示唆しているのではないでしょうか。
特に興味深いのは「規模の経済」が必ずしも優位性をもたらさない状況が生まれていることです。「規模の経済から希少性の経済へ」パラダイムシフトしているのではないでしょうか。

さて2025年はどんな年になるのでしょうか。皆さんと一緒に注意深くみていきたいと思います。
またnoteでお会いしましょう。
◆最新情報はXで
振り返れば💫 #メモ少年 との一年でした
— 池松潤 / Jun Ikematsu (@jun_ikematsu) November 26, 2024
名古屋🚄楽しみ
4月・秋山音楽祭のTLからおっ!となる
5月・長崎行きを決める
6月・長崎総科大✈️メモ少年講義・訪問
8月・対談インタビュー
9月・記事掲載
11月・氷のないスケートリンク豊田合成・オープニングセレモニー#左端に写るロバート秋山さんに注目 https://t.co/ulE5rlHyMv pic.twitter.com/UvyV9suCXx
いいなと思ったら応援しよう!

