
『象は鼻が長い』入門を読んで思うこと
『象は鼻が長い』入門
庵功雄(著)
コテンラジオをほぼ2周聞いてしまったので、他のも聞こうと思い、ゆる言語学ラジオを聞き始めました。歴史や言語などの文系コンテンツは極力避けて通ってきましたが、どちらも面白く聞けてありがたいです。今更ながら人文学を義務教育以来に学び直しています。
そのラジオでタイトルが気になって最初に聞いた回の本を読んでみることにしました。ただ、三上章さんの『象は鼻が長い』そのものを読んでも多分理解できないので、入門から読むことにしました。
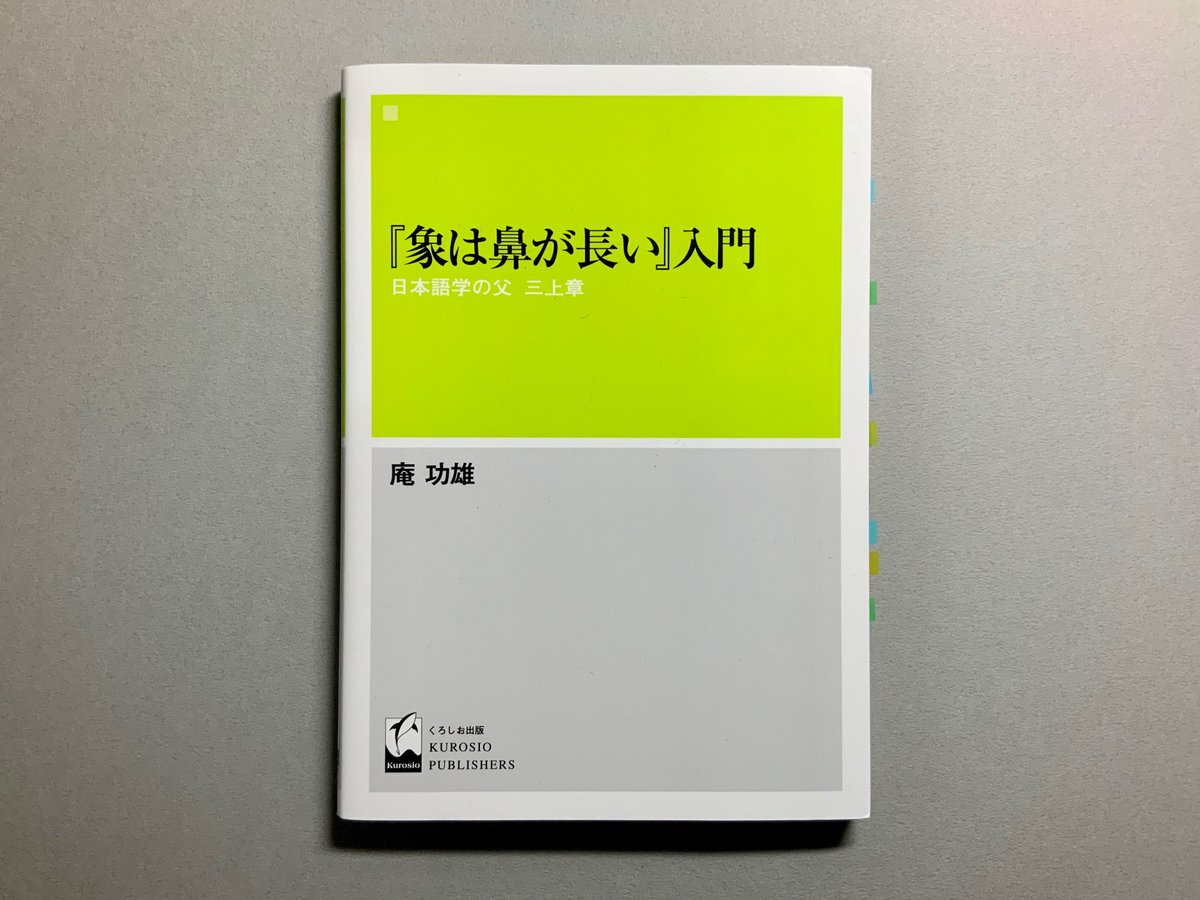
どんな本か
三上章さんの8冊の著書を整理して、三上文法の理念と構成がまとめられていて、その後、主語廃止論について書かれています。『象は鼻が長い』も説明されています。説明方法が、(15)a、b、cの変換で(16)a、b、cと(17)a、b、cで比較されていたりして、え〜っと(15)bってなんだったっけ?となるため、行ったり来たりしてしまいました。そしてベースとなる知識がまったくないこともあり、理解するのに時間がかかりました。
本当に理解できているかはおいておきますが、この本を読むことで三上文法のほんのちょっと端っこに触れれた気がします。ラジオも聞いてるし、入門書だし意外とサッと読めるだろうと思ってましたが、こうした予測の全てが途方もなく間違っていました。休みの間に読もうと思って買った本が机に何冊も積まれてGWが終わりを迎えそうです。
著者の思い
現在の時点で三上の業績を振り返る必要性を感じたのは、「日本語学」が目指したものを再確認しておきたいという気持ちからである。三上の業績を振り返ることによって、日本語学の今後の進むべき方向性を考えてみたい。これが本書の最大の執筆動機である。
本書は、三上さんの文法論への道案内です。本書を読まれた方はどうか三上さんの世界をご自分で体験なさってください。文法論の専門でない方にとっても、このようにオリジナリティにあふれた思想家が日本にいたのだという形での感動が得られるものと思います。
読んでのまとめスケッチ

読んでの感想
ちなみに庵さんは、"三上さんの本は必ずしも簡単に読めるものではありません。私自身、学部生のときから、何度も『序説』に挑んできましたが、未だに完全に理解できたという自信はありません“と書かれています。そのため、入門書もやっぱり難しいです。できることならば、困った時に頼りになる100de名著で是非とも取り上げていただきたいです。
どういう本なのか?をスケッチでまとめるだけでなく、どういう理論なのか?ということも今回スケッチにまとめてみました。内容をまとめないと理解できなかったのと、文章で説明できる自信もないので、おおよそどういうことなのか知りたい方は下のスケッチをご確認ください。

とはいえ、象が主語なのか鼻が主語なのかを知りたい人は正直、ゆる言語学ラジオを聞いたほうが良いと思ってたりします。(ちょっと間違えもあるので、訂正動画も併せてご確認ください。)
義務教育で国語も文法も習っているし、そもそも喋っているので、日本語は文法が決まっているものだと思っていましたが、今回学んでみてそうではないことがわかりました。そのなかで学校では橋本さんの理論が国語の文法として使われているそうです。
最近では、ChatGPTなどAIでの文章生成がめちゃくちゃ進んでいるので、文法もその技術に利用されているものだと考えてもいたので、さらに驚きました。スケッチにもほかの先生たちの考えた論を記載してありますが、日本語文法には諸説あり、象は鼻が長いに関してはこれで決まり!とはまだなっていないそうです。結構意外です。
三上さんの論は、一部の人は取り上げたり、似たような理論を説明している人もいたそうですが、当時思っていたほど取り上げられなかったそうです。聞いたり、読んだりしていると三上論の方が納得しやすいので、尚更意外です。
ここからはよく聞く2つのラジオで話されていた内容を取り上げながら思ったことを書いていきます。その2つはCOTEN RADIOとゆる言語学ラジオです。
話はズレますが、
・人を社会の歴史から学ぶことで、外面的構造から人を理解する。
(COTEN RADIO)
・人を言語の歴史から学ぶことで、内面的構造から人を理解する。
(ゆる言語学ラジオ)
そんなイメージで聞いてます。
それぞれのラジオの目的とズレていて、その上表現そのものが間違えていそうですが。。
話をもどしまして、ゆる言語学ラジオの堀元さんが話していましたが、三上さんの論は天動説よりも綺麗に説明できているの地動説のようだと言われていて、「なるほど」と感じました。
そしてコテンラジオの樋口さんは地動説と天動説ともどこから見るか、切り取るかで異なっていて、その時代に説明しやすく便利な方がとられているのではないかと話されていました。これも「確かに」と思いました。
(どちらも私の感想が貧弱ですみません。)
大航海時代がはじまって航海では地動説の方が便利で、日付も地動説の方が説明しやすいそうなので、利用されるようになったとの話でした。実は古代ギリシャですでに天動説に考えられているけれど中々世の中に出てこなかったのが、天動説の方が人の感覚と合っていて、多少説明できないことがあっても、特段不便でもなかったので地動説に変える意味があまりなかったということだと思います。その変更により、世の中のシステム(歴、宗教など)も変わっちゃうので大変そうです。
そうすると言語の場合は、言語学を学んでいなくても話せているし、理解できているので日常生活上全く不便はありません。そして、三上さん論の方がたとえ綺麗であっても、今までの言語学で積み上げてきたものが一部否定されたり、世の教育システムを転換させたりとなって、そこに不便さがあるので、これで決まりとはならないのかなと思いました。
AIによる文章作成で主語抹殺理論が活用されれば、変わるかと思いましたが現状ではあまり関係なさそうで、AIの文章力あがっているので、今後も技術進歩の要因でどれか一つに決まることはなさそうで、技術的な視点からはその必要性もないのかもしれません。
コテンのヤンヤンさんがいっていたのですが、天動説と地動説とを調べている中で、一番魅力的だったことは、天動説が間違っていたとか、無駄だったというわけではなく、そこで培われた技術や理論があったからこそ、地動説への転換につながっていったことだと話していました。そしてコテンの深井さんの言うように遠回りのように見えるけど実は最短距離で進んでいたようにも思えます。
言語学も二重主語文までの研究があって、学校教育を受けたからこそ、三上さんの論があり、日本語文法を説明する研究が続いていき、今後進むべき方向性を日々考えながら進んでいるのだと思います。そこには間違いも無駄もないのかもと思えました。
ラジオで聞いた話をまとめただけですが、多くの人がヤンヤンさんのいうように考えられると物事を素直に見れるようになるのではないかと思いました。
この前はコテンラジオの本『歴史思考』を読んだので、今度はゆる言語学ラジオの本『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』を読んでみようと思います。
積まれた本が読まれる前に次の本が来てしまうのですが、ゆる言語学ラジオの水野さんがいっていた積読は発酵するという言葉を信じてこのGWを過ごそうと思います。
