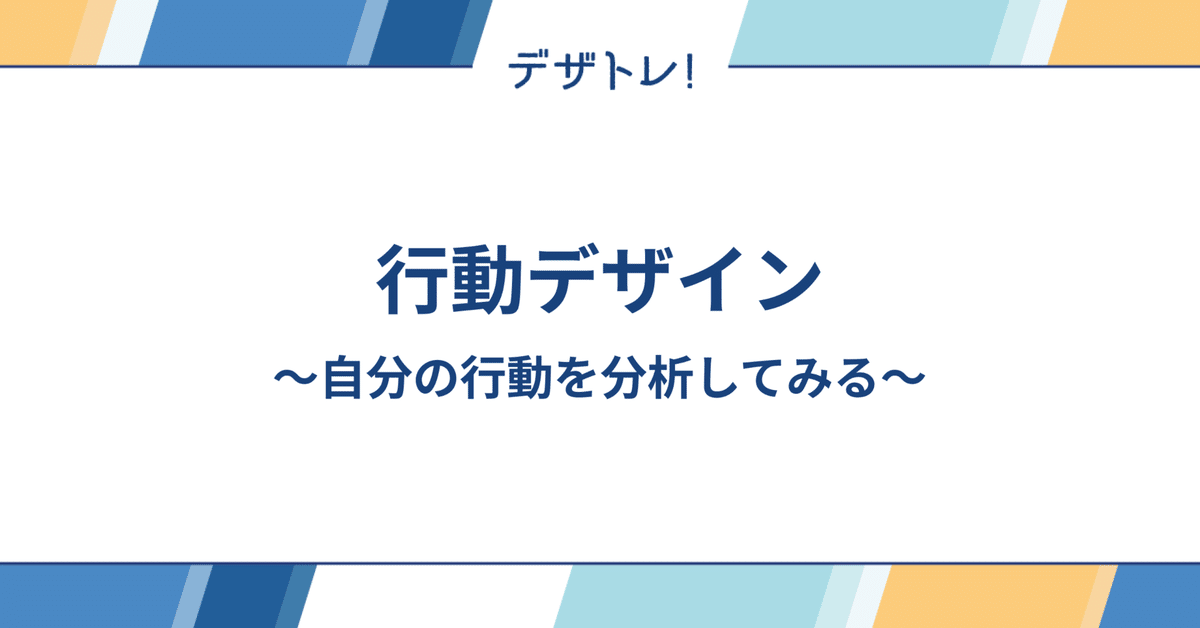
行動デザイン、はじめの一歩〜自分の行動について分析してみる〜
こんにちは、UIデザイナーのマスダです。
私の所属するゴーリストのデザイン部では、毎週1時間デザトレ!を開催しています。デザトレとは、デザイントレーニングの略。毎回チームメンバーの1人がトピックを用意して、ナレッジの共有を行っています。
今回、私が用意したトピックは「行動デザイン」。
人が行動するときのメカニズムの紹介と、自分の行動を分解してみるワークを行いました。
どうして行動デザインをトピックに選んだのか
このトピックを選んだ理由は、私がUIデザイナーとしてユーザーの心を動かすデザインをすることを大切にしているからです。
心を動かすというのは、「なぜか気になる…」「ちょっと使ってみようかな?」「もっと使ってみたい!」など、ユーザーの行動を促すという意味があります。
ユーザーの心を動かすデザインをする。
言葉にするのは簡単だけど、じゃあ実際ユーザーの心を動かすにはどうしたらいい?というようなことを考えていた時期に出会ったのが、『行動を変えるデザイン』という本です。
この本では、人が行動を起こすメカニズムや、それを踏まえたプロダクト開発への応用法などが書かれており、とても勉強になりました。
これはデザイナーであれば知っておいて損はしないな〜と思ったので、トピックとして選択しました。
人が行動するときのメカニズム
この本の中でユーザーが行動を実行するときの心のイベントとして紹介されていたものがCREATEアクションファネルというものです。
C - Cue(キュー):行動を思い浮かべるきっかけ
R - Reaction(反応):思い浮かべた行動に対する直感的な感覚
E - Evaluation(評価):行動に対して費用対効果を考える
A - Ability(アビリティ):行動にうつるときの制約の有無
T - Timing(タイミング):いまやるべきかどうか
E - Execution(実行):行動を実行する
キュー、反応、評価、アビリティ、タイミングという5つの心のイベントを通過できた時に、行動が実行されます。
例えば献立アプリを使用する時だと、このようなイメージです。

ここからは、5つの心のイベント(キュー、反応、評価、アビリティ、タイミング)の詳細を紹介します。また、プロダクトデザインに活かすならこういうことを考えると良いのかなというポイントをまとめました。
一部、『行動を変えるデザイン』より抜粋しています。
Cue(キュー)とは
行動を思い浮かべるきっかけとなるもの。
キューの種類には、外部のキューと内部のキューがあります。
外部のキュー:メール、アプリ通知、広告、カップ麺、料理本など
内部のキュー:空腹状態、痛み、眠気
プロダクトデザインに活かすなら
👉 ユーザーの日常の中にプロダクトを設置する
→そもそもプロダクトに触れる機会がないと、行動のきっかけも作れない
👉 無視されないように、毎回ちょっと違うキューを用意する
→同じキューだと飽きてしまい、反応しなくなっていく
👉 ルーティンの一部から連想できるようにする
→すでに習慣化された行動とセットにできれば、行動を促せる
Reaction(反応)とは
キューから思い浮かべた行動に対して引き起こされる直感的な感覚のこと。
反応の仕方には以下のようなものがあります。
行動の判定:楽しいか?危ないか?しんどいか?便利か?
→以前の経験で得たことをもとにした直感的な感覚他にできそうな行動や思いつき:自分で料理を作る?出前を頼む?
習慣化された行動:無意識のうちにアプリを開く
→すでに習慣となっており、キューがあれば自動的に引き起こされる
プロダクトデザインに活かすなら
👉 プロダクトへの第一印象をよくする
→広告などのプロダクトへの接点で与えるイメージが反応につながる
👉 信頼されるような体験を提供する
→プロダクトで得た経験をもとに反応が生み出される
Evaluation(評価)とは?
思い浮かべた行動や他の選択肢に対して費用対効果を考えること。
どのような評価がされるかは以下のとおり。
メリット:ネット検索よりも、早く食べたい料理が見つかる
コスト:出前よりも安く済ませられる
他の選択肢をけなす:出前は料理が冷めてしまうから、美味しくない
プロダクトデザインに活かすなら
👉 定量的な価値を明確に伝える
→価値が明確であればあるほど、特定の行動を選択する確率が上がる
Ability(アビリティ)とは?
実際に行動しようと思ったときの制約の有無のこと。
例えば、行動のステップ(アクションプラン)がわかっているかや、行動に必要なリソースがあるかなどです。
他にも以下のようなものが制約として挙げられます。
アクションプラン:スマホを持つ→アプリを開く→料理を決定する
リソース:スマホは手元にあるか?材料はあるか?
スキル:アプリでレシピを見つけられるか?料理の腕前はあるか?
うまくいく確信:簡単レシピなら自分も作れそう
プロダクトデザインに活かすなら
👉 アクションプランを簡単にする
→行動が簡単であればあるほど、行動しやすくなる
👉 自信をつけてあげる
→行動を実行して失敗する確率が低ければ、実行しやすくなる
Timing(タイミング)とは?
行動をいまやるべきかどうかという判断をすること。
タイミングの種類には、外からの緊急性とうちからの緊急性があります。
外からの緊急性:家族から夜ご飯を催促された
内からの緊急性:お腹が空いて耐えられない
プロダクトデザインに活かすなら
👉 いつやるのかを具体的に決める、約束する
→人を巻き込んで行動を約束する場合、効力はUPする
👉すでに生活の中にある急ぎのイベントにあわせる
→すでに習慣化された行動とセットにできれば、行動を促せる
自分の行動を分析してみる
プロダクトデザインでなにかユーザーの行動を促したい時は、CREATEアクションファネルを思い出して、障害となっている部分はないかと考える作業が有効になると思います。
ですが、さぁユーザーの行動を分析して!と言うのは簡単ですが、他人の行動や思考を考えるのは意外と難しいです。
ということで、まずは自分の行動を分析してみて、自分がどんなことを考えて行動しているのかという言語化から初めてみましょう。
自分の行動を分析してみると、意外と気づいていない一面が見つかったりして…!👀
ワークのやり方
自分が最近実際にやった/やめた行動をピックアップする
行動をキュー/反応/評価/アビリティ/タイミングに分解してみる
行動ができた理由/できなかった理由を書く
行動するための改善ポイントがあれば書く
このワークの目的は、自分の行動を分析し言語化することで、人の行動メカニズムを知ることにあります。
また、行動できた/できなかった理由や行動するための改善ポイントを書くというのもミソだったりします。
たぶんプロダクトデザインで人の行動をうながしたい時は、こういうことを考えるのではないかなと思っています。行動デザインの考え方を練習しよう!ということです。
以下の画像は行動分析の一例です。毎月1回開催されるチームランチで出前を頼んだときの自分の行動を分析してみました。

この時は一度Uber Eatsのアプリを開いたものの、注文しなかったパターンです。残念ながら、タイミングの部分で今じゃないとなって離脱してしまったのです…。
分析する行動は本当に些細なものでOKだと思います。
週末に本を読まなかった、こたつの電源を入れた、テレビでブラタモリを見た…などなど。
興味があればみなさんも自分の行動を分析してみてください。行動デザインへのはじめの一歩です!
👟 👣 👟 👣 👟 👣 👟 👣 👟 👣 👟
