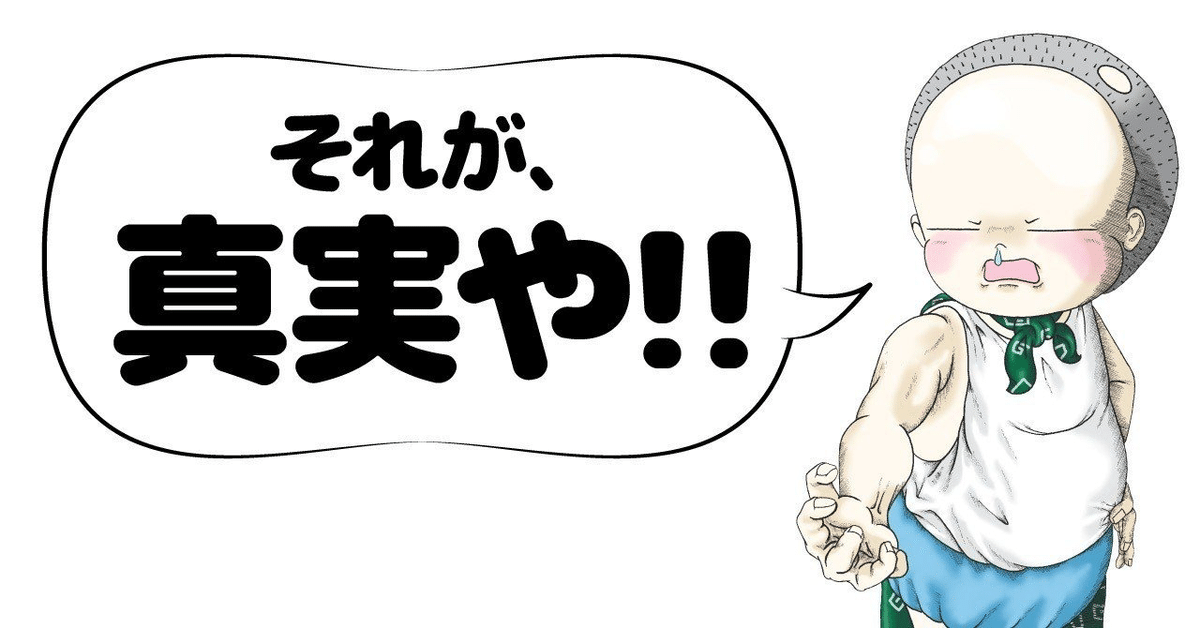
フィードバック制御の本質は発振動作
フィードバック制御は発振(振動)によって成立しています。
(以下、フィードバック⇨F/B)
※ここで説明するF/B制御とは、オペアンプ等を用いた電子制御の事を指します。
「F/B制御」と「発振回路」は同じものです。
F/B制御で発振が問題になる事がありますが、
それは、元々の発振が共振によって大きくなっているだけです。
元々の発振? F/B制御が正常に働いている時は発振などしていないと思われるかもしれません。 発振してない様に見える理由は、発振の振幅が0だからです。
通常「発振している・していない」の解釈は、現象だけを見ます。
ですから、F/B制御が正しく動いてる場合は「発振していない」と表現しますが、
それは発振振幅が0というだけの事で、発振動作はしているのです。
では、なぜ発振して(させて)いるのでしょうか。
それはF/B制御には「目標値で止める」という指令(動作)がないからです。
「目標値で止める」のではなく、
「目標値を超えたら下げる、目標値を下回ったら上げる」。 この二つの指令(動作)のみで目標値に擬似的に静止させているのです。
ですから、うまく制御できていないと、目標値を大きく超えてから下げる(上げる)動作になり、結果的に上下に振動し「発振した」となるのです。
目標値に載っている時は何も指令せず、ずれた時だけ修正指令が入るようなイメージを持つと、F/B制御の本質は理解できないのです。目標値上にあろうがずれようが関係なく、目標値を中心に常に上下に動いているイメージを持つ事が大切です。
この原理は、定電圧源、定電流源などにも適用されており、制御を理解する上で非常に重要なものです。
実際の回路がどんな動きをしているかを知らないと、深い理解は出来ません。
伝達関数の理解もいいですが、このF/B制御の本質を知らないと現実世界ではすぐ限界が来ます。 どんなものも理論と同時に現実を考えましょう。
