
私が『ゆるキャン△』を好きになった変な理由
今年2024年、TVアニメSeason3が放送されたあfろ氏原作漫画『ゆるキャン△』。以前から作品名自体は知っていたのですが、恥ずかしながら今般の放送をきっかけにして今更本作に触れました。
本記事では私がゆるキャン△に触れた際に感動した少し変わったところを綴っています。
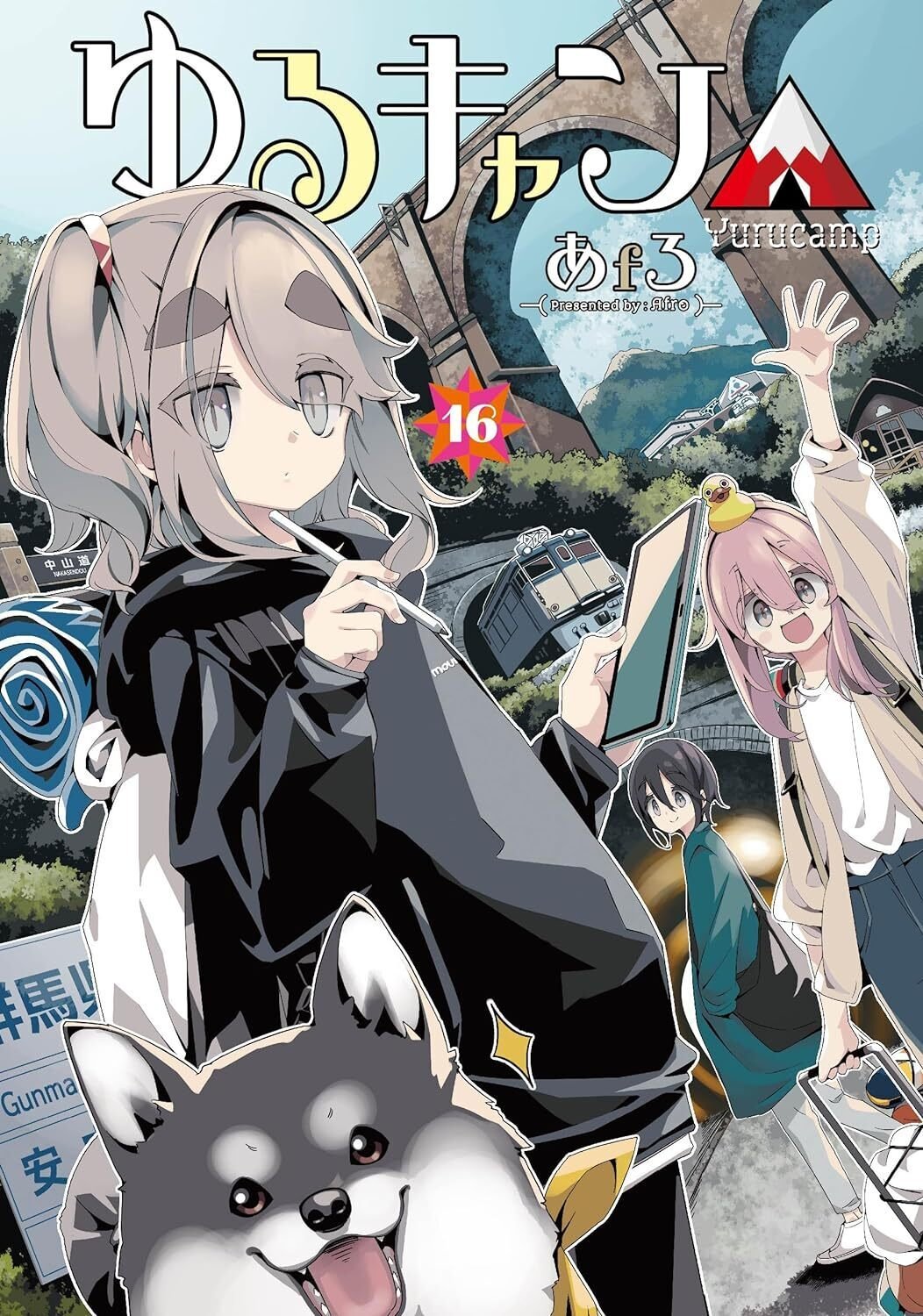
当世風ではない言葉選び
主要登場人物の大半が高校生であるゆるキャン△。同時代に連載されている他の漫画には所謂『若者言葉』やもう少し広い世代で共有される『流行り言葉』が多用されるものもありますが、ゆるキャン△の場合そうした言葉の使用は限定的です。
こうした時代を象徴する言葉を盛り込むことには今この瞬間の読者に強く訴求する効果がある訳ですが、同時に言葉の流行り廃りは予想が難しくほんの数年経過しただけで作品全体から古臭さを感じるようになってしまうデメリットも含んでいます。内容が素晴らしくあっても流行が去った言葉が頻繁に飛び出せば作者の意図しない別な笑いが発生する漫画になってしまったりするものです。
また、そもそもそうした流行り言葉を嫌う人や特定の世代の言葉が多用される漫画に疎外感を感じる方もいらっしゃる可能性を考えれば多くの読者を掴む為の商業的な合理性に合致した選択でもあります。
ゆるキャン△は流行り廃りと適度に距離を取っている印象で、『mono』などあfろ氏作の他作品を読んでもそうした傾向は共通している為、恐らく特別に意識しての戦略などではないことと推察されますが、結果的に幅広い読者を掴みやすく永く愛される要素として機能していると言えます。
こうした時代との適度な距離感は私がゆるキャン△を読んで最初に気に入ったポイントです。
極めて肯定的に描かれる山梨・静岡ロケーション
ゆるキャン△の主な舞台になっているのは山梨県及び静岡県ですが、作中で主人公達が居住地域に不満を述べたり自虐をしたりすることはありません。
きらら系雑誌掲載漫画ではゆるキャン△に限らず特定の地域に根ざし実在する場所を積極的に描写する作品が複数見受けられますが、ゆるキャン△はその中でも特別こうした特徴を活かすことに秀でています。
日本を舞台とした漫画の場合、東京或いは周辺三県を舞台に設定する場合が多い中、ゆるキャン△は本州の中でも山梨県を舞台に物語が始まり、そこから静岡・長野・埼玉・群馬と物語の進行に合わせて描かれる範囲が広がっていきます。しかしそこで登場人物に「田舎だ」や「何も無いな」などといった"ありふれた地方への罵詈雑言"を言わせるようなことはありません。
作者のあfろ氏自身の馴染み深い地域や経験から山梨県という選定となっているのだと推測されますが、罵倒も自虐もないのはある意味不自然に感じる程我々の社会にはそうした言葉が溢れています。
日本に於いて東京都以外では福岡福岡市・大阪大阪市・愛知名古屋市などの人口が200万人を超える様な大都市であるか北海道・沖縄の様な特別な自然環境を有している観光地など、田舎罵倒を受けずに済む場所は限られています。それ故、多くの人々は生まれ育った地域を嘲笑され(それらは"イジリ"とも言い換えられます)場合によっては中傷されたりすることを甘受しなければならない現実があるわけです。
都市部居住者と地方居住者のこうしたやり取りはお互いに"戯れて"いることを自覚して所謂プロレス的に行われるものもあれば、本当に相手を見下した都市部に居住し優位に立っている側から見ても不快に感じるものもあります。
そうした外からの言葉がある一方で地方居住側は「電車が1時間に1本しか来ないから、乗り遅れたら次の電車まで人生を考え直す時間が生まれる。」「ショッピングモールって言ってもコンビニとドラッグストアと100均くらい。」などと自虐して辺鄙な環境を笑いにすることが増えました。長年住んだ結果生まれる愛憎から自発的に発する例、外部からの嘲笑の常態化に対する防御反応、理由は様々かと考えられますが余りに増えてしまっている為に自虐笑い自体にも辟易としてしまうところがあります。

ゆるキャン△は山梨県の中でも甲府市の様な都市ではない地域を主な舞台としていながら辺鄙な環境を罵倒することも自虐することもありません。それは”当たり前の風景”であり、そうした景色の中でポジティブに学生生活を送りキャンプを楽しむ登場人物達の日常が生き生きと描かれています。読んでいると「この場所に行ってみたい」という思いや「他の地域にもこんな素晴らしい場所があるのでは…?」と現代の田舎罵倒に慣れすぎた思考を転換するきっかけにもなりうる肯定的な考え方を提供してくれるのです。
あfろ氏がゆるキャン△と同時に連載しているmono内の登場人物である秋山春乃は”その場所に行きたくなる漫画”を描くことを志すわけですが、ゆるキャン△は正しくそうした意志を体現している漫画と言えます。
描かれていない余白で持続する"読書後のゆるキャン△世界"
ゆるキャン△には作中で描かれていない登場人物同士の交流や関係の深化が推測出来る余白が度々見られます。
本作は主要登場人物の一人である各務原なでしこが山梨県南巨摩郡南部町へ引っ越して来るところから始まり、彼女が野外活動サークルの大垣千明及び犬山あおいと初対面である様子も描かれますが、伊豆キャンプ出発時には犬山あおいの妹である犬山あかりと既に顔見知りである様に会話が進行します。思わず「何処か読み飛ばしたかな?」や「そんなシーンあったかな?」と自身の間違いを疑って読み返してみてもそうした描写は存在しません。

他にも、当初「大垣」「犬山さん」と呼んでいた志摩リンがいつの間にか彼女らを「千明」「あおい」と呼ぶようになっていたり、反対に大垣千明と犬山あおいも「しまりん」から「リン」に「志摩さん」から「リンちゃん」に呼称が変化します。

『ゆるキャン△アンソロジーコミック』のマシーナリーとも子氏作『ファーストネーム』にもあるような形で"その瞬間"を描くことも可能でしょうが、私は寧ろ読者の見えないところで登場人物同士が仲を深めている様子が想像出来るという造りが読後もゆるキャン△を考え続ける重要要素になっていると考えます。
「なでしこはある日の放課後あおいの家に招かれそこであかりと会ったのではないか」や「リンが千明を直接下の名前で呼んだ瞬間はお互いに照れがあったのではないか」など想像の余地があるからこそ読書後も頭の中にゆるキャン△が留まり続ける訳です。
他には、作中で登場人物達がキャンプ用品を購入する印象的なアウトドア用品店として登場する『カリブー』と登場人物それぞれの関わり方が異なるというのもそうです。なでしこは千明とあおいに連れられて身延駅近くのカリブーを訪れることから二人がこの店舗を普段から訪れていることが伺えますが、なでしこからカリブー訪問の連絡を受けたリンはしばらく考えた末「かりぶー?かりぶー…」「あ 駅前の用品店」(第14話)と思い出す様子が描かれています。この描写から『リンはカリブー自体は知っているが訪れることは少ない、或いはこの時点では一度も中に入ったことはない。リンがキャンプ用品を購入するのは全く別の店に頼っているのかもしれない。もしかしたら通販のみで揃えているのかもしれない。』などと推測することが出来ます。
一昔前であれば作品の心惹かれる点として"余白があることがいい"などと挙げることありませんでした。それは程度の差こそあれどそれが当たり前であった為なのですが、現代的な消費者の傾向として心情的な面は説明口調で"わかり易く"伝える演出を求める人が目立っているという側面があるため敢えて特徴として書きました(これらは映像作品のみならず漫画読者にも見られる傾向だと感じます)。
"分かりにくさに怒る読者"にとってはゆるキャン△もまた理解が難しくすっきりしない漫画かもしれません(確かにこうした仕掛けはやり過ぎると「説明不足」や「読者置いてきぼり」などといった不満が無視できない程に目立つようになります)。しかし、私の感覚ではこうした『語らない部分』の加減は適度な塩梅と感じますし、これらの要素を上手に盛り込む巧みな手腕こそ読み終えた後も作品世界を考えさせ続ける効果的な仕掛けとなっているのではないでしょうか。
最後に
志摩リンらの花見キャンプで締めくくられた今年春放送のアニメSeason3。原作ではこの後新入部員獲得に奔走する野外活動サークルの様子が描かれ、その後片道70kmサイクリングキャンプと群馬県野反湖キャンプへと繋がっていきます。
連載自体は10周年が目前に迫っていながら、作中の時間経過は半年ほど。しかし、中津川メイや瑞浪絵真といった新たな登場人物を加えて更に面白くなりそうなゆるキャン△。まだまだ急ぐことなく丁寧に描かれることを願うばかりです。
