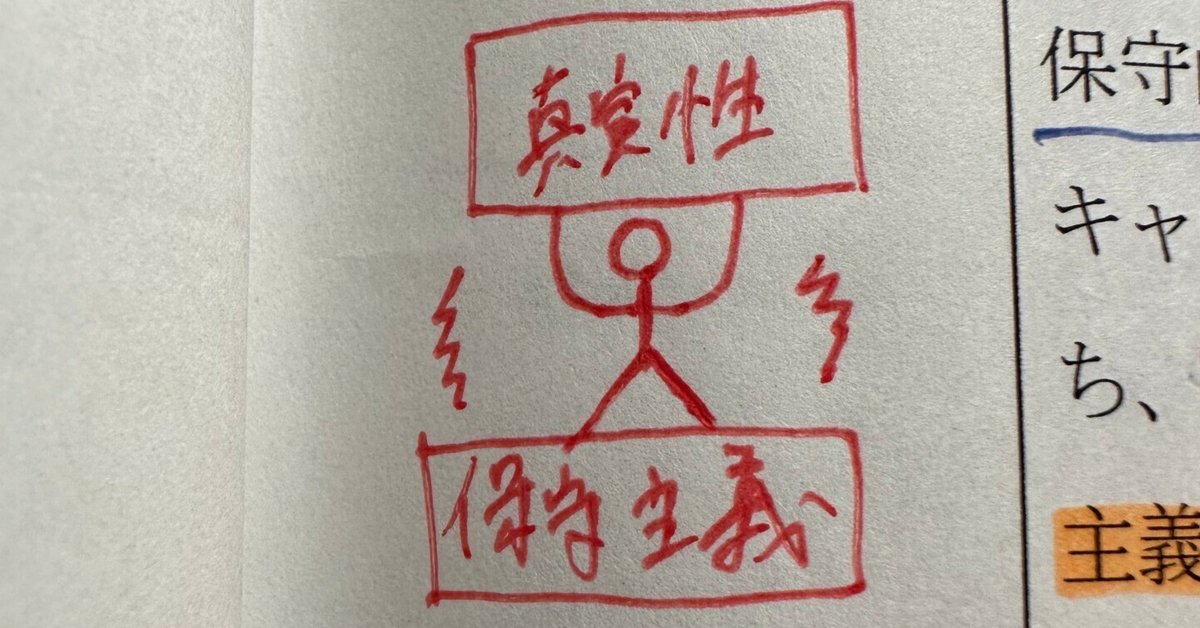
不動産鑑定士試験の会計学対策
不動産鑑定士試験における会計学の話なんですが、簿記をやってない人からすると講義聞いても本当に何言っているか分からないし、どうやって勉強したらいいのか分からないって人、たくさんいるのではないでしょうか。
実際に私も会計は初学者でしたし、周りの人でも会計学は苦手という人たくさんいました。
私の本試験の成績は、令和4年が36点、令和5年が39点、そして令和6年が84点でした。
令和5年までと令和6年とで大きな点数の乖離がありますが、何をしたらこんなに点数が変わったのか明確ですので、以下で使用教材と勉強法をご紹介します。会計学の勉強法に迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
会計学の勉強時間と使用教材
まず私の会計学の3年間のトータル勉強時間は336時間でした。うち最後の1年間は約200時間ほど勉強しましたので、勉強時間の半分以上は3年目の1年間に集中しています。
そして使用教材ですが、私はLEC生でしたので、
①こう書け会計学 ②重要用語定義集 ③総ざらい ④各種答練や摸試
の4つを周回していました。
その中で1.2年目と3年目での決定的な違いは、①こう書け会計学の周回の有無です。
2年目までは、重要用語定義集と各種答練等をある程度押さえるようにし、こう書けはほぼノータッチでした。
その理由として、こう書けの重要性が分かっていなかったこと、そして講師の先生も、こう書けよりも定義集や答練等を完璧にするようにとの教えだったからです。
会計学の講師の先生はとても優しい方でしたので、初学者でも心が折れないように最低限重要なところだけ押さえるように気を使ってくださってたのだと思います。従って、こう書けは概念フレームワークや企業結合会計など、深入りすると初学者には何言っているのか分からない単元もありますので、余裕がない方はやらなくていいスタンスだったのではないかと思います。
(決定的に実力不足だったのもありますが)個人的にはそこがちょっとした落とし穴だったかなーと思います。
本試験で出た問題とこう書けとの対応
令和4年度では負ののれんとその発生原因について、令和5年では後入先出法の意義とそれが削除された理由について、総ざらいや答練では出題されませんでした。というか重要度は低い論点と思いますので、ここを答練で押さえるのはほぼ無理ですよね。
しかも令和5年は、答練等で棚卸全般は確か押さえていませんでした。というのも、令和3年に棚卸が出題されていましたので、先生もまさか隔年で出題されるとは思わなかったと述べられていました。(実際に、試験委員対策講座で過去10年分くらいの本試験を分析されていましたが、隔年で同じ分野から出題されたのは確かなかったです)
本試験後、全然解けなかったので落ち込んで帰って、家でこう書け見てみると、負ののれんも後入先出法がなくなった理由も一つの論点としてしっかり書いてあるんですよね。
いずれもB論点でしたが、覚えられないほど分量が多いのかというと全然そんなことはないです。こう書けのあの1ページやっとけば点数とれたなって反省しました。
その反省を生かして、令和6年度はこう書けの周回に着手しました。
各種教材を用いた勉強法
こう書け会計学
私が1年間で50点近くも点数を伸ばせた理由はここにあります。
こう書けの周回です。
11月~8月の試験までの間に19周しました。
試験前日も、約4時間で1周しています。
勉強法は鑑定理論と被るのですが、
⑴問題を見て
⑵空を見て、頭の中で解答を暗唱し、
⑶答えを見る
の繰り返しです。
眺めるだけでは力はつきません。
そして、大変ですがB論点も含めて覚えるようにするのがいいと思います。
実際に、令和4年~6年まで全て一部の論点がBから出ていますので。
必修論点総ざらい
手早く重要論点を押さえるのに非常に効果的です。
特に、こう書けを周回する余裕や時間がない方は、最低限総ざらいを押さえることで本試験でも戦えるレベルになると思います。
時間がある方は、総ざらいを完璧にしつつ、こう書けも周回します。
ただ、総ざらいの内容はこう書けとほぼ被っていますので、こう書けにないところのみ総ざらいを使って押さえるというやり方で問題ないと思います。
重要用語定義集
寝る前に歯磨きしながら毎日暗記していました。
絶対に本試験までに全ての定義を完璧に覚えてください。
B論点もです。
令和6年の本試験ではCFの論点で直接法と間接法の定義と内容について聞かれました。
実はこの定義、何故かこう書けには載ってないんですよね。
特に間接法の定義、めちゃくちゃ長いしなかなか覚えられないから、覚えなくてもいいかな~なんて思ってました。
試験で出たとき、本当に本当にやっててよかったって思いました。
各種答練や摸試
全力で受けましょう。
ちなみに、LECの全国公開模試での成績は会場受験で、1回目が1位/143人(77点)、2回目が13位/153人(70点)でした。(普段の答練は、通信生ですので自宅受験でした。)
こう書け周回の成果です。
受験対策上の会計学の重要性
会計学は、民法や経済学、演習と違い、ほぼ暗記科目です。
理論と同じく、やった分だけ力になると思います。
経済など、理解が最重視される科目と違い、暗記でごり押しできます。
私みたいな経済学弱者にとって、会計学で稼ぐことがポイントになってくることを理解していましたので、特に気合を入れて対策しました。
確かに令和6年度は例年と比べて点数は取りやすかったのかと思いますが、CFについてはこう書けをやっていたからこそ解けた問題がありました。
そのおかげでライバルと差をつけられたと思っています。
臆せずこう書けと定義集を周回するようにしてみてください。
