
ドット絵メイキング『ヤツデ』
ひさしぶりのドット絵メイキング、今回は「天狗」について語った6月の記事のタイトルに使った『ヤツデ』の制作過程を振り返りますですよ。
1. 骨組みを描く
まずは、直線ツールでヤツデの骨(葉脈、葉柄)の線を引き、全体のバランスを決めます。

ヤツデは「八手」と書きますが、実際の葉は9枚にわかれていることが多いとのこと。"八"には「数が多い」という意味があるそうで、葉が8枚にわかれているわけではないそうです。なので、7枚にしてみました(9枚が多いという話はどこいった)。
なお、この時点で葉っぱの形状を考えてしまうと、狭いキャンバス(16x16ドット)に押し込むのはかなり難しくなるので、あえて骨だけで決めてしまいます。
ところで、ぼくは普段の習慣で直線ツールや塗り潰しツールなどの描画ツールの類いをあまり使いません。しかし今回のように、様々な角度の骨を手動でキレイな線として描くのはかなり厳しいので、珍しく直線ツールを使うことにしました。
描画ツールをあまり使わないのは、キャンバスから目を離したくないのと、かといってショートカットキーを覚えることはしたくないから。あと、ちまちまとドットを打ちながら「この先どうしようかな」と考えごとをしたいという理由もあります。あまりオススメはしません。
2. 葉の形状を考慮してシルエット化

ヤツデの葉はひとつの葉の先端がわかれていて、ちょうど手のひらのようになっています。まず"手のひら"部分をグチャっと丸くまとめたら、あとは葉の部分を肉付けしていき、全体のシルエットを整えます。
このとき、直線ツールで描いた骨は消しておきます。骨が残っていると不要な正確性を維持したくなり、形状の調整をしにくくなるからです。
なお、色はもちろん仮の色です。あとで置換するので、色数は少なめを心掛けて作業を進めます。
3. フチドリ線を描く

空白を埋めつつ、フチドリ線で全体を囲みます。手で言えば"指"の部分がわかれていることを重視しつつ、少し葉の形状を整えています。
ただ、手順2と比較するとわかるように、"指"の角度を変えるような大きな調整はしていません。これは最初に直線ツールでバランスを取っておいたおかげでしょう。ヤツデのような「微妙な角度」のものがモチーフでなくても、直線ツールで骨を描いて下描きにするのはいいかもしれませんね。
4. 骨を通しなおす

さて、今度は骨を通しなおします。葉、指の中央を通るようにつないでいくと、手順1で描いた骨とは異なる線になりました。なんだか不思議です。
結果的に少しクネっと曲がって葉の柔らかさが出ていますね。いやあこれはすばらしい。才能ある~! と自画自賛しておきますが、実際はただの偶然です。
5. 立体感を出すため増色

ヤツデの"指"の部分は波打っているため、平坦な葉に立体感をもたらします。その表現のために"指"の周囲、特に指同士が接していない部分に明色を1色加えます。
6. 色を調整して「生ヤツデ」完成

葉のメインカラーを生き生きとした明るい緑色にし、葉脈は白さを出すため少し青めの色に置き換えます。また、中央部分ほど葉脈がクッキリしているものなので、葉脈の色は先端に行くほど薄くなるようにしています。
これにて「生ヤツデ」は完成ですが、さらにこれを「ヤツデの団扇」にしていきます。
7. 団扇化準備
手順3(ベタ塗り&フチドリ状態)に戻り、これをベースに生ヤツデを団扇化していきます。
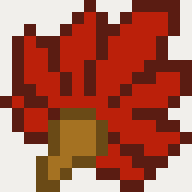
まずは、葉柄(ようへい)の部分を団扇の柄(持ち手)に変えます。
また、全体の色を紅葉したものに変えました。生ヤツデで試行錯誤は済んでいて迷いなく作業を進められるので、今回は初めから「本気色」にします。
8. 葉の色を調整

黄寄りの茶色で葉脈を少し描き加えたうえで、葉全体と葉脈の中央付近を明るくします。
なお、これはリアリティの追求ではなく、デザイン的な都合です。ちょっと炎っぽくすることで絵に「味」を加えたいのです。
9. 柄(持ち手)を整えて完成

最後に柄(持ち手)の部分に人工的なツヤを出します。
よく見直しつつ出来を自画自賛して「どや!」と天狗になれば、「ヤツデの団扇」の完成です。
