
エンジンがかかったおかげで、更に充実した海外生活
はじめに
私の両耳には、合計4つ、
ピアスホール(ピアスの芯を通す穴)が開いている。
左と右、どちらも耳たぶに2つずつ。
初めて開けたのは、新卒二年目の冬。
職場で親しくしてもらっていた先輩で
かなり歳上にもかかわらず
カッコいいお姉さまがいた。
お姉さまの行きつけである
某ジュエリーショップに併設する皮膚科、
そこでピアスホールを開けてもらった。
やがてピアス生活に慣れてくると、
また2つは開けたいなと思うようになる。
なぜなら、ピアスを少しずつ集めているうちに、
これとこれを組み合わせて着けたらおしゃれだな、とか想像してみたり。
この組み合わせで着けてみたいな、などと思っていたのだ。
その数年後。
その思い は思わぬ形で実現する。
日本の真裏、遠く離れた南米の地で
親しくなった友人と 一緒にピアスホールを開けることになるとは。
当時の私は全く想像もしていなかった。
その友人は、ある方の紹介のような形で出逢うことになる。
私と同じ立場(駐在員の妻)であり、
偶然なのか必然なのか、
日本人があまりいない、私たちの住んでいた地区に住む人だった。
ピアスを開けて喜んでいる彼女の笑顔も、
初対面では想像することなんてできない。
それくらい、初対面での彼女の印象は
最悪だったからだ。

マエヤマ先生からのお願いごと
日本が夏を迎える頃、南米には冬が訪れた。
ジャケットやコートが手放せなくなり、
外で吐く息も白くなる。
その日は、私たち夫婦が着任した時から
公私共にお世話になっていた 日系人医師 、
マエヤマ先生の往診の日だった。
マエヤマ先生は、ちょっとした風邪でもすぐ来てくれる。
時間をかけて話をすることで、
ちょっとしたカウンセリングに近い往診をしていた。
私たちのように日本から駐在員、
その家族として生活している場合、
本人は自覚しなくても
ちょっとしたストレスが体に変化を起こすことはよくある。
実際、マエヤマ先生に診てもらって
意外な症状が見つかることもよくあった。
マエヤマ先生は、いつからか他の患者さんの往診の帰りなど、
私の家に立ち寄ることもあった。
そういう時、私はあくまでも 年の離れた友人として接する。
マエヤマ先生も食べることが好き。
私の家の周辺のお店は、
いつの間にかマエヤマ先生の行きつけになっていたこともよくあった。
私たちのマンションの並びにファストフードに近いお店があったのだが。
ステーキサンドイッチが美味しいというのを私たちがかなり後から知ると、
すでにマエヤマ先生のお気に入りのお店だ、と言われたときには、大笑いした。
さすがマエヤマ先生だと納得もした。

マエヤマ先生の診療が終わると
いつも私はお茶やコーヒーを淹れて
クッキーやビスケットを食べながら
マエヤマ先生とおしゃべりした。
「お願いがあるの」
「えっ、私にですか?」
「そう、あなたに助けてもらいたい患者さんがいる」
聞けば、この国に来てから 一歩も外に出たことがない方なのだという。
旦那さんも 困ってしまい、
奥様を日本に返した方がいいのかどうか、
悩んでいるのだそうだ。
「私はね、あなたが、色んな苦労や、
悲しいことを乗り越えて、
ここで笑顔で暮らしてること、
とても素晴らしいと思っているの。
あなたなら、彼女を救えるかもと思ったのよ」
「...」
「一度会ってもらえないかしら」
迷いながらも私は頷いた。
マエヤマ先生はほっと明るい笑顔になる。
けれど、実際この段階では気が重かったのは確かだ。
私が関わることで、
彼女のメンタルが、ぶれたりしないか、不安だった。
メンタルの調子を崩しているということだけ、やんわりと先生から聞いていたからだ。

接し方がわからない、「彼女」との対面
マエヤマ先生が付き添ってくれた、
彼女の家での初対面は忘れられない。
髪の毛も乱れ、ボサボサの頭。
化粧どころか洗顔もしてないような顔。
よれよれの毛玉だらけのスウェット。
メイドを雇っていらしたご家庭なので
家の中も少しはきれいだ。
しかしすぐに汚くなるのだろう、
あちこちにモノたちが散乱している。
彼女は私を一目見た後は、背を向けて
日本から持ってきたテレビゲームをやり続けていた。
「あの、はじめまして。これ、よかったら。
この近くの通りで美味しいお店のクッキーを...」
私が言い終わらないうちに、彼女は立ち上がり、こちらに向かってきた。
クッキーの包みごと私から奪い、床に叩きつける。
彼女は私を睨んでいた。
正確に言うと、不安で震えながら、
目の奥は泣きそうになっていた。
人を寄せ付けない防衛本能だったのかもしれない。
それが彼女との初対面。
「とりあえず一週間、彼女に会いに行ってみます」
医師でもカウンセラーでもない私を受け入れるはずがないだろう。
でも、私にはなぜか彼女を助けなきゃという気持ちがあった。

まだスペイン語を話せない時でも、
アジア人である私を温かく受け入れてくれた、
恩師マリアから習っていたフラメンコ。
ゼロから始めて、慣れてきてからは
大学で勉強していたスペイン語。
日本語教師のボランティア。
この他に接待やお茶会など駐在員の妻としての務めがあった。
そうした数々の合間を縫って
「外から一歩も出たことがない」という、
そんなナオさんに ほぼ毎日会いに行った。
あまり食べられないと聞いていたので
消化のよく、食べやすいものを作って容器に入れて持っていったり。
飲み物と一緒に食べられるようなお菓子を持っていったり。
開けて、そのまま食べずにキッチンの流しに捨てられたこともある。
メイドと私が一緒におしゃべりしながら
日本食デリバリーを食べていても、
彼女はなかなか 心が開かない。
どうしたらいいのか、全くわからなかった。

春の訪れとカウントダウン
季節は春の訪れを告げていた。
木々がだんだんと紫づいている。
それは、日本の桜のようなハカランダ(ジャカランダ)という花のため。
(見出し画像はハカランダの並木通り)
ちょうど その頃 、夫の任期終了と日本へ戻る時期が決定し、私にも知らされた。
この南米にいられるのもあと数ヵ月。
とにかく、ここでの生活を今まで以上に満喫しようと思った。
スペイン語の目標のクラスを必ず修了すること。
フラメンコの発表会を頑張ること。
そして、ここで得た現地の友人や
同じ立場である駐在員の奥様の友人と
思い出を作ること。
ナオさんを、外に連れ出すこと。
この時は、とにかく その一心だったかもしれない。
何がそこまで突き動かしたのだろう。
振り返るとやはり 「○月には日本へ帰る」という、本来なら嬉しいはずのことが、
私にはたまらなく寂しかったせいかもしれない。
それくらい、南米でのラテン生活は私の気質に合っていた。

ナオさんは少しずつ話を交わすことはできても、
それでも相変わらずだ。
いくら来たくなかった国にいるから
といってもなめすぎだ。
私が訪ねる日もいつも だらだらしている。
ある日、あまりにもだらけて甘えた
ナオさんの態度に対して、
頭に来た私は、ナオさんを一喝した。
「お前、甘えてんじゃねぇよ!」
敢えて汚い言葉遣いのまま
私は思いの丈をナオさんにぶちまけた。
ナオさんはとにかく甘えきっていると思った。
ここ南米で、ナオさんを心配して、
診察以外でも毎日通ってくれるマエヤマ先生のような存在にも甘えている。
頼れる人、みんなに甘えている。
あなたより辛いのは私だ。
ナオさんのように実家から日本食が届くなんてことはない。
ナオさんのように、ご両親が電話してきたりもしない。
なぜなら私は南米にいる時に
日本で暮らしていた両親と妹を一度に失ったからだ。
そのために帰国して喪主もした。
相続の手続きにも追われた。
それなのに、そうしたアクシデントなど
とは無縁なのに、あなたは
なんでこんなに周りに甘えていられるのか、
と。
「あんた、さっさと日本へ帰れば?」
思いの丈を言ってもスッキリせぬまま、
私はメイドにだけ挨拶をして帰った。

「ごめんなさい」
泣きながらその日ナオさんは私に電話をくれた。
「強くなりたい。ほしまるさん、助けて」
やっとその言葉を聞けた。
本人からの言葉を聞かなきゃ、動けないと思っていたからだ。
そこからの彼女はどんどん回復を見せた。
近くのスーパーへの買い物に一緒に行ったり。
全て私に頼っていたスペイン語を勉強し始めたり。
カフェやレストランにも行ったし
彼女の旦那さまと、私の夫の会社のフットサル試合にも
私と一緒に観に行くことができた。
彼女が旦那さまを目で追う嬉しそうな姿も、
ハカランダの木を見つける度に喜んでいたこと、全て記憶に焼き付いている。
そして、ナオさんは私に最後の願いをしてきた。
「ねぇ、一緒に記念にピアス(ホール)開けようよ」
記念に、なんて彼女から言われるとは思わなかった。
それくらい、彼女にとって私は大切な存在でいられたのだと思うと
泣きそうだった。

帰国。そして第二の故郷となった理由
帰国の日。
夫と私は相談して、
最後に滞在していた市内のホテルのラウンジを借りた。
お世話になっていた人たちを招待し、最後にこちらからお別れの挨拶をひとりひとりに伝えたかったのだ。。
第一部に招待したのは
夫の仕事関係や、私もあくまでも公式でのお付き合いの 人たち。
第二部は プライベートでお世話になっていた人たち。
マエヤマ先生も、恩師マリアも、友人もみんな来てくれた。
その時 恩師マリアから渡された手紙代わりのカセットテープに語られていたことがある。
マリアは私に Estrella スペイン語で星、という名前をくれた。
その由来を彼女はこう話していた。
「貴女はこの国での生活でも、スタジオでも
とても輝いていたね。
そんな貴女の優しい輝きは皆を癒し、笑顔にしてくれるものでした。
星は夜にしか見えないように思えるけど
貴女の国(日本)が朝でも昼でも、
他の国では夜だから、必ずどこかで絶えず輝いているの。
離れるのは寂しいけれど。
でも貴女はいつでもどこかで輝いていると信じて応援しているからね」
彼女にそんな風に私は映っているなんて思えなかったのと、
彼女の気持ちが嬉しくて私は泣いた。

そして日本に帰国してからしばらくすると
ナオさんは、南米から私に手紙をくれた。
私と親しくしていた友人たちと一緒に
みんなで撮った写真と共に。
ナオさんのことは その友人たちにもお願いしてきたのだった。
安心したのと、ナオさんが笑顔で
心から嬉しかった。
あんなにも色んなことを住んでいた間に頑張れた国。
沢山の人たち出会えて、かけがえのない体験をできた国。
私にとって第二の故郷だ。

そう思えるのは、何よりも
私にとってエンジンがかかった瞬間があったからだろう。
南米での生活にやっと慣れてきた頃、
私は 両親と妹を一度に亡くした。
悲しみにくれながらも、
一度は葬儀や相続のために、数ヵ月の一時帰国をする。
普通なら慣れ親しんだ日本で、ゆっくりと心の傷を癒すことができたのかもしれない。
でも、私は日本には居場所なんてないと思った。
異邦人だとしても、南米で歯をくいしばって生活することを選んだ。
とにかくここで悔いなく暮らそう。
その一心で過ごしてきたことがエンジンかもしれない。
また、夫の任期終了で日本帰国という目標ができたことも 、エンジンのかかる瞬間だったかもしれない。
本当なら嬉しいはずなのに、
南米を離れる寂しさから、それまで以上に生活を楽しもうと思えた。
国内外どこでも、住み慣れた場所から離れて新たな地で一時的にでも暮らす場合、
充実する日々になるかどうかは
もしかしたら、自分のエンジン次第なのかもしれない。
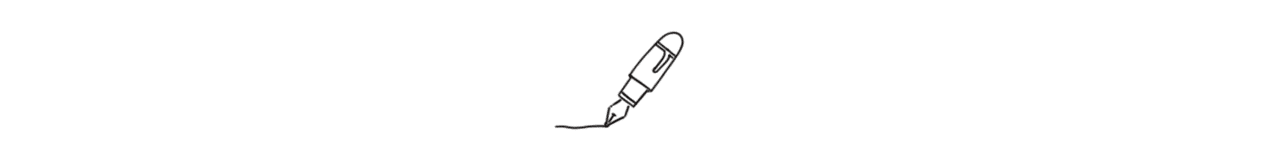
いいなと思ったら応援しよう!

