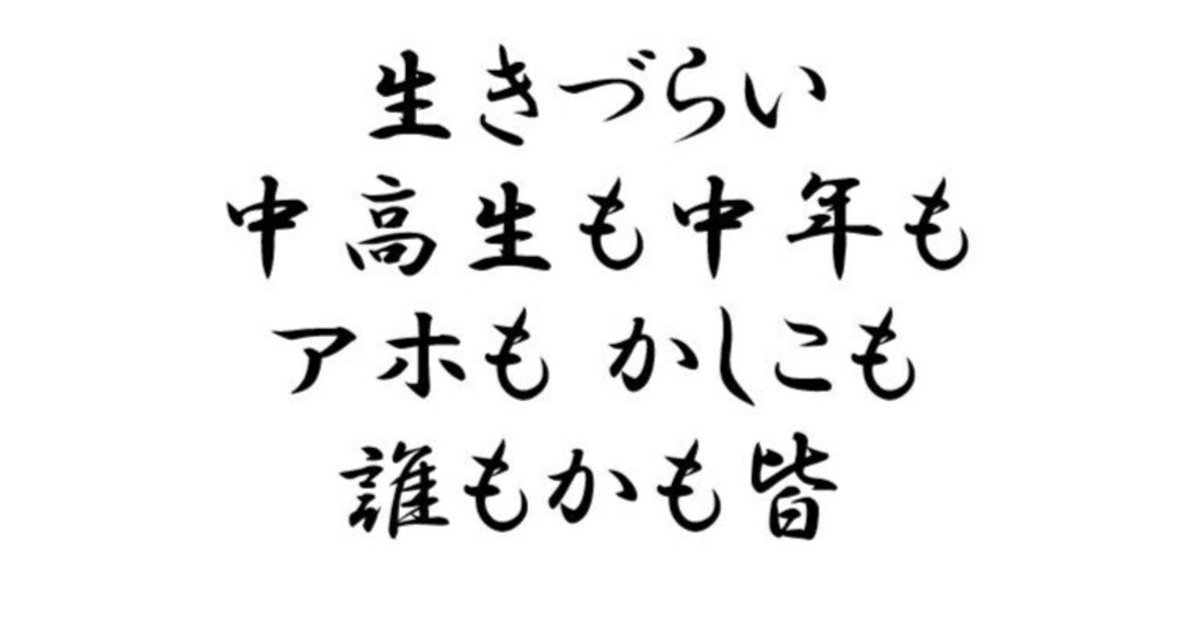
【現代文】咲いたまま 千代に散らずに 続く春
真夜中に小便で目を覚まし、再び床に入って眠りにつきかけたその時、玄関から鍵の回る金属音が響き、勢いよく母が帰ってきた。どうやらご近所さんと飲んでいたらしい。――是、親子であるが故、互いに赦し合えるのだろう。同じ同居人でも、夫婦となれば、何ら連絡も寄越さず“午前様”など、互いに不快の火種としかならないであろう。我が独身の自由な生活環境に妙な感謝をする。――それにしても随分と長い間、家を留守にしていたものだ。もう私は、このまま母に二度と会えないしれないと覚悟していた程である。
飛び起きざまに台所で水をコップに汲んだものの、それを居間に腰掛けているだろう母へ渡そうとする足取りが実に恐る恐る。そりゃそうだ。失踪した母が何年か振りに戻ってきたのだ。親子だというのに、緊張感をもって遠慮気味に「おかえり」を言う、否、言おうとするも、声が出ない。あれだけ会いたかった母が目の前に居る。にも関わらず、声を失った息子。母は私の姿にまだ気付いていない。そうなると、大声でも構わないと腹に力を入れる。が、いくら大きく口を開こうとて、私の耳は自分の発する音の一切を拾わない。・・・漸く私は「様子がおかしい」と思い始めた。まず母は酔っ払うほど酒を飲まない人である。それに今夜この布団に潜り込む直前にも、私は位牌に掌を合わせたところなのだから。
夢から覚めた私は人目も憚らずに嗚咽していた。否、声こそ殺しても、人目を憚る必要は無い。最愛の母の束の間の老後の休息と晩年の自宅介護のためだけに買ったと言って過言でないこのマンションの部屋。遺された私と此処に同居する者は、今、誰一人としていないのだから。自分自身が髪に白髪の目立つ齢になっても、涙を流してまで恋しくなってしまう。男にとって母親とは、そういう存在なのである。
すっかり眠れなくなってしまった私は、テレビを点ける。どうせ土曜の未明だ。このまま起きてしまえ。眠くなったら昼寝をすればいい。そんな気持ちで視始めたのが古い白黒映画の再放送。数秒ボーっと眺めていたが、1分も経たぬうちに『浪曲子守唄』だと分かった。私にとって「任侠」と「親子」の掛け算は最強の鉄板なり。やっと泣き止んだところなのに、再び嗚咽する。私の父は社会のレールから外れた人だったが、その子煩悩ぶりも常軌を逸していた。映像の向こう側に生前の父が偲ばれ、涙腺は予定通り決壊したのだった。
大原麗子と当時5才の真田広之(当時は下沢広之)が駆けっこする。迫りくる宿命を人情で乗り切る二人の後ろ姿を葉陰から垣間見る千葉真一。一節太郎の名曲に乗せたあのラストシーンの余韻に浸りつつ、チャンネルを早朝のニュースを切り替えると、国会議員の面々が仰々しく少子化対策について弁舌を振るっていたため、急に白けた。高校・大学の教育まで無償化すれば、本当に本当に少子化に歯止めがかかるのだろうか。男性の育児休業を推進すれば、本当に本当に出生率が上昇するのだろうか。すでに1人目を産んだ実績を有する夫婦に2人目にも意欲を持ってもらおうという狙いだとしても、やはり疑問を禁じ得ない。一体いつまでこうした不毛な議論と不発の対策を続けるのだろうか。悲し過ぎて涙も出やしない。
根底に立ち返るが、少子化だと何が困るのか。年金制度が破綻するから困るのか。経済成長が停滞するから困るのか。いや、私は困っていないし、隣人もそのまた隣人も「困ったもんだ」と騒いでいるだけで、実はさほど困っていないし、本気で事態を打開しようとはしていない。それは事態を「問題」だとは受け止めていないからだ。少子化とは「問題」では無く「現象」なのである。結局、全員が他人事になってしまうのは仕方ないのだ。大衆の意見なるもの所詮他人事の塊。「街の声」ほど怪しいものは無い。どんな街のどんな人の声なのか。まさか私の声まで街の声に含有されてしまっては、是、甚だ迷惑というものだ。
私の場合、子孫を世に残すという「通常の人にしてみると比較的簡単な人生」から脱落した理由は、高額な教育費でも取得困難な育休でもなく、もっと酷なものである。そりゃ、私とて愛する人と共に子を授かりたかった。私自身が、両親から、そして社会から、愛情をもって育てられたことに感謝しているからである。ところが相手が居ない。どんなに練習しても、一人では試合が成立しない。則ち、私には「生産能力」が無いのだ。生殖不能ではない。けれど、それに等しい。だって、私の精子を受け入れてくれる卵子が見つからないわけであるから、これを以て男性機能障害も同然と云われても、返す言葉がない。子を設ける前提となる舞台にすら立てない。私の生涯とは、是、マスターベーションなり。
国家権力が「産めよ増やせよ」を強制することは民主主義に相反するものの、少なくとも出産の手前にある結婚たるものに社会的な強制力が作用していた過去については、現在より不自由ながらも合理的だったのだとつくづく納得する。「親戚の決めた人はイヤ」だなんて我儘なのだ。親戚が決めてくれるのだから楽ではないか。親戚が決めてくれるのだから、お相手の人物像は折り紙付きなわけだし、世の中にはお相手を自分で探そうにも見つからないという人が居るのだ。ただでさえ慌ただしき人生――「世話焼きによる見合い」とは、不要な苦労や挫折を味わわずに済む装置だった筈なのだ。まあ、見合いでも無理だった男がここに孤独な桑年を迎えているわけだが、政府の少子化対策に冷笑を浮かべることにも徐々に疲れてきた。
女性にも外で稼ぐことを促すのなら、男性にも専業主夫になる権利があることを社会的に許容させるべきであり、それが本来の同権というものだ。両方が“お父さん”だったら子供が生まれなくなるのは至極当然の結果なのである。「働いてほしいし、産んでほしいし、育ててほしい」ってのは、些か虫の良い話ではないか。私は財力のある女性と結婚して、家の内を守ることに専念したい。でも、妻が外で働いて欲しいと望むなら働くし、妻が専業主婦を望むなら尚更の事である。が、その相手が居ない。就職するまでは貧乏に苛まれた私だが、今はカネも家もある。が、カネがあっても家があっても結婚できないオトコも居るという事実を証明しただけで、我が人生は終局へ向かっている。男性の結婚条件に財力を求める女性は多いけれど、財力以外のものまで求めている事実を証明しただけで、我が人生は終局へ向かっている。従って、政府には非婚化や少子化が「カネさえ手当すれば解決できる」かの如き現象では無いという事実に気づいて欲しい。ちゃんとここで私が身をもって証明しているではないか。私という国民には、男女共同参画社会に貢献する権利も意思もあるけれど、能力までは付与されなかったようである。まあ、高校生くらいの頃から薄々勘付いてはいたけれどね。
鬼教師の現代文は、そのテスト内容も「鬼」だった。ヤマを張り、当てれば100点も狙えるが、外せば0点の可能性すら覚悟せねばならない程、テーマが限定的で、兎に角しつこい。2学期の中間は徹底的に短歌だった。神無月の風がレースのカーテンを柔らかく揺らす窓際で、千春さんの鉛筆の先は堅い机の上でカタカタと音を立て続け、全く動きを止める気配を感じさせない。この愛しい人の辞書には「ヤマを張る」などといった文字は無い。一方、そのすぐ風下で彼女の髪の優しい香りに鼻先を撫でられていた私は、あまり集中できずに度々答案用紙と見合っていた。八百万の神々も、ついに私を見放したか。彼女の頭脳だけが神在月の出雲大社の如く賑わっているようだった。
「のど赤き玄鳥(つばくらめ)ふたつ屋梁(はり)にゐて足乳根(たらちね)の母は死にたまふなり」――斎藤茂吉か。「<問1>『母』への敬意はどの語に示されているか」――これには即座に「たまふ」と答える。「<問2>下の句の末にある助動詞『なり』の文法的意味を答えよ」――これはまあ「断定」だ。「<問3>『なり』に込めた作者の心情を答えよ」――だっ、だから、これは「死んじゃった」という断定的な寂しさなんじゃないの?――後で千春さんに訊けば「母の死という逃れられない現実に対する限りなく悲痛な思い」が模範解答とのことだった。
「<問4>宮柊二の作品のうち、『父』と『雨』の入る短歌を2首出しなさい」――これは丸暗記していれば済む、或る意味“サービス問題”である。化学式に比べれば短歌の丸暗記は楽なもの。だいたい百人一首は何度も繰り返すうちに凡人の頭にも殆ど入るものだが、化学式は誰もがそう容易くマスター出来るものでは無い。「春の夜も雨とどろけり部屋にゐぬ父は何処(いづこ)に行きしかと思ふ」「ふるさとの石の唐櫃(からと)に白骨(しらほね)の父を納めて青き梅雨来ぬ」――千春さんと同じペースで筆を走らせたのはこの部分だけだった。
「金亀子(こがねむし)擲(なげう)つ闇の深さかな」――おっと、今度は俳句か。高浜虚子だな。「<問5>『擲つ闇の深さ』とあるが、作者は何によって深さを捉え、擲った先に何を感じたと思われるか」――「家に飛び込んできたコガネムシを外へ力いっぱい投げつけたが、そのコガネムシが物に当たる音もなく、どこまでも闇の中へ吸い込まれていった。その手ごたえのなさに無限の夏の闇の底深さを感じた」――まあ、答えはこんなところだろう。
「冬菊のまとふはおのがひかりのみ」――これは水原秋桜子か。「<問6>『冬菊』ではなく、他の花であれば、どんなものを『まとふ』のか」――これは深い。野に咲く花たるや、いずれも自然の中に晒されて、ありのままの姿かと思いきや、決してみな同じ装いでは無い。事実、私のすぐ横で眩しき光を放つ千春さんたるや、これ程までに紺のブレザーと胸のリボンの似合う人に私は出会ったことが無い。その“春”のあまりの目映さに頬を紅潮させつつ、答案用紙に「例えば季節が春であれば、蝶や鳥、傍で同じように咲く色鮮やかな花や暖かい陽射しをまとふ」と書いている私。彼女は用紙をさらりと裏返し、余裕綽々で後半の問いに進んでいる。「<問7>作者の視線が注がれている『おのがひかり』とは何だと思われるか」――千春さんにしか注げない私の視線を、このテスト中だけは冬の花に移し「冬菊自らの内面から発する美しく清楚な色・光沢・輝き」と答える。そして、この答えを記しながら、千春さんは冬の美しさをも内包していることを発見する。私にとって彼女とは、枯れることを知らない花なのだ。
秋桜子は医学博士でもある。帝大医学部を卒業し、「東大俳句会」の再興にも励んでいる。医者が趣味の俳句でも名を残すことはあっても、俳人が趣味で医療行為をするわけにはいかぬ。化学式をすらすら読んじゃう生徒が、百人一首も得意だったりする話は珍しくないけれど、逆のパターンはなかなか聞かない。これぞ、私が昔から理系の人間の才能に尊敬と憧憬の念を抱いて止まない根拠の1つである。なお、オトナになった千春さんはメガバンクで活躍している。文理双方の知識とセンスを併せ持つ彼女らしい選択だ。銀行員という職業の可能性が微塵も無かった私とはハナから「格」が違う。幻想の域を出ない“たられば”の話にはなるが、もし青春の恋が実り、千春さんと私が結ばれ、二人の間に子が授かったならば、私はこの上無き幸せだったに違いないけれど、生まれた子は母と父の「格」の違いにきっと戸惑ったに違いなかろう。
与謝野晶子は女性だが、高浜虚子と水原秋桜子は男性。これは小野妹子の「子」と同じ理屈か。その点、杉田久女と中村草田男はズバリ判りやすい。「咲き切つて薔薇の容(かたち)を超えけるも」――最後の問いは草田男だった。「<問20>『容を超え』には作者のどんな驚きが表れているか。『けるも』の文法的な特徴と合わせて説明せよ。」――だからさあ、千春さんは枯れない華なんだってば、と胸の奥で唱える私。でも、このテスト中だけは咲き切ったバラを想像し、「散華する直前のバラの姿に、今までの整った美しさを超越した新たな美しさを見出した驚きについて、詠嘆の『ける』に終助詞の『も』を付けて強調している。」と解答した。
これにて全問終了。やっとの思いで答えの見直し時間を5分ばかりは余らせることが出来た。得点源の「現代文」でもこの調子では、この後の「化学」はどうなってしまうことか、先が思いやられて仕方ない。私の散り際は薔薇のような美しさを伴うものでは決して無かろうな・・・つづく
