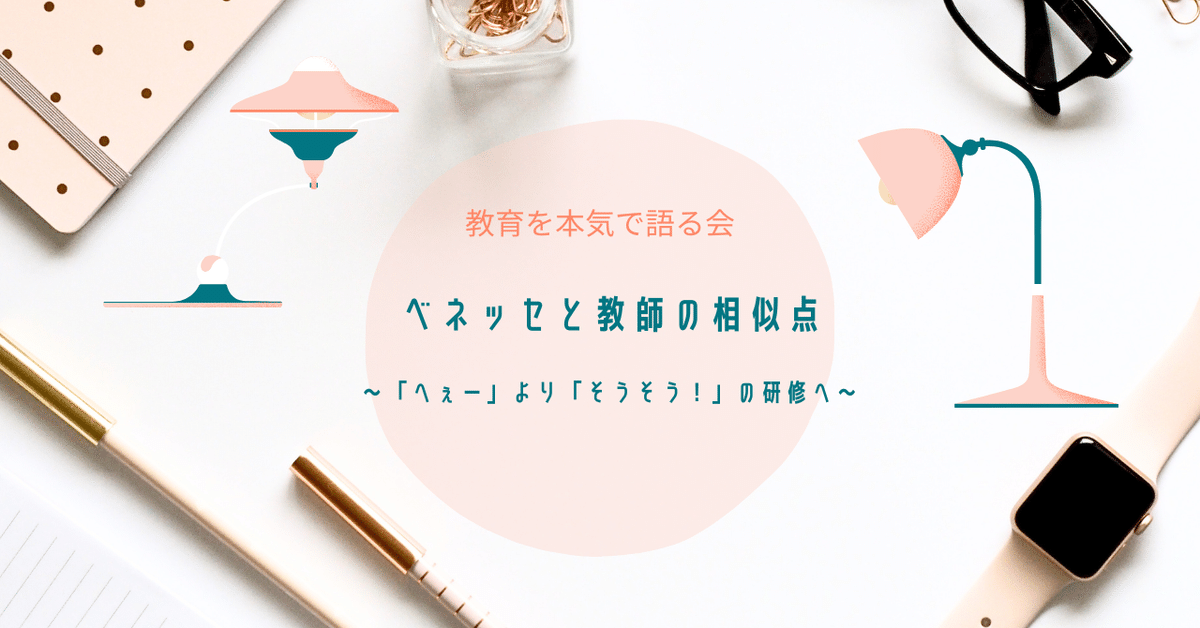
ベネッセと教師の相似点 〜「へぇー」より「そうそう」の研修へ〜
教育を本気で語る会…本の影響を受けやすいJOYです!
前回、ベネッセの研修でお世話になった庄子さんの研修を振り返っていたら、
たくさんの書籍の内容と結びつきました。
前回は「記憶術」だけのご紹介で終わりましたが、
今回はもっと掘り下げていきます!
エビデンスが詰まりまくりの庄子さんの講演です!

1 人を動かす
以前の投稿でご説明したように
アイスブレイクの段階で参加者の名前を覚えるアクティビティが多いです。
こんなにも名前を呼ぶことや覚えることを大切にする講演を聞いていると、
デール・カーネギーさんの名著「人を動かす」の内容が彷彿と蘇りました。

“人間は他人の名前などいっこうに気にとめないが、自分の名前になると大いに関心を持つものだということを、ジム・ファーレーは早くから知っていた。自分の名前を覚えていて、それを呼んでくれるということは、まことに気分のいいもので、つまらぬお世辞よりもよほど効果がある。逆に、相手の名を忘れたり、間違えて書いたりすると、厄介なことが起こる。”
生徒を名前で呼ばずに「次、後ろの人」のように言っている先生もいます。
職員室でも名前をつけずに「先生」とだけ言う人もいます。
これもこれで無難ではありますが、
名前を呼ぶことをきっかけに様々なコミュニケーションが生まれます!
相手の名前の由来を聞いたり、
名前を間違えられた事例を教えてもらったり、
自分の名前に興味を持ってもらったり。
名前を呼ぶだけでこんなにも会話が広がります。
間違えてでも名前を呼んでみて、
そのミスを記憶と結びつけて、
1人でも多くの人の名前を覚えたいです!
“相手と話しているうちに、何回となく相手の名を繰り返し、相手の顔や表情、姿などと一緒に、頭の中に入れてしまうように努める。もし、相手が重要な人物なら、さらに苦心を重ねる。自分一人になると、早速紙に相手の名を書き、それを見つめて精神を集中し、しっかり覚え込んでしまうと、その紙を破り捨てる。こうして目と耳と、両方を動員して覚え込むのである。”
2 HAPPY STRESS
名前の次に印象的だったことは
「ポジティブなことに焦点をあてる」ことです。
給与や休暇などの不満は目につきやすいですが、
環境や待遇などの優遇な面はありませんか?
苦手な同僚や上司の嫌いなことは見つけやすいですが、
その人たちの良いところにも目を向けて見ませんか?
庄子さんのこのお話を聞いた時に、
青砥瑞人さんのHAPPY STRESSが頭を過ぎりました!

批判ばかりしていれば、あなたの脳のフィルターはそんな粗探しが得意になり、自分とは関係のない世界にまでストレスをためることになってしまいます。 何度もいうようですが、どんな情報を、あなたの貴重な注意の対象に向かわせたいのかということを、改めて見つめ直す機会があってもいいと思うのです。ネガティビティバイアスがダメだなどと悲観する必要もなく、むしろそれが自然な反応であり、かつ自分を改善するための学び、成長の機会であると認識をする。
他人のあら捜しばかりしてしまう習慣が
無意識のうちに身についているかもしれません。
しかしそれは悪いことではなく
人間の自然な習慣です。
だからこそ、意識的に他人の良いところに目を向ける練習を重ねていけば、
意外な発見がたくさんあり、
それが私たちの生活を豊かにしてくれます!
庄子さんのポジティブ探しは、
ネガティビティバイアスに基づいた
ハッピーアクティビティでした!
3 20歳のときに知っておきたかったこと
ポジティブ探しのなかのお話で、
「できないことよりもできることを探してみましょう!」
とありました。
主観的に考えると視野が狭くなるので、
自分たちの長所を客観的に考えるための
楽しいグループワークでした。
このアクティビティをやっているときに、
この書籍の内容を思い出しました。

この第8章に「矢の周りに的を描く」という内容があります。
特定の的をめがけて矢を放つより、
放った矢の周りに的を描けば百発百中で当たる。
そりゃそうだよ、と思いがちですが、
ここでは適材適所の大切さを学べました。
タスクのために人材を探すより、
人材にあったタスクを割り当てるほうが、
効果も効率も絶対に上がります!
自分の得手不得手を理解して、
タスクの取捨選択ができるようなコミュニケーションがチーム内に生まれれば、
きっと仕事が楽しくなります!
前例踏襲や自己流から脱け出して、
働く人たちが幸せになることが大切です。
「自分にできることを大切にする」
庄子さんのお言葉に強く同意します!
4 エンゼルバンク
このように、庄子さんの研修を受けていると
今までの自身の学びと結びつくことが多いです。
同じ教育者だからだと思いますが、
ここでもやはり、このエピソードと結びつきました。

庄子さんのお話を「そうそう」と聞いていると、
今までの自分の学びの方向は間違っていなかったと安心できます。
与えられた業務ばかりをこなしている毎日だと、
自分の存在意義に自信が持てませませんが、
職場以外の方々との交流が、
自信と安心につながります。
このようなサードプレイスをこれからも大切にしていきたいです!
「教育を本気で語る会」ではX(twitter)、 Facebook、 Threads、spotifyでも発信しておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。
