
Web3とロイヤリティ:新たなユースケースの可能性を探る(NIKE編)
先日ご紹介したスターバックスに続いて、本日はナイキの取り組みを紹介したいと思います。ナイキは、デジタル空間、仮想世界においても“NIKE”というブランドを確固たるものとすべく、デジタルファッションで人気を博したRTFKTを買収するなど、DXの次のフェーズ、新しいイノベーションへの挑戦としてWeb3領域にも積極的に取り組んでいます。
RTFKT買収に関するCEO(ジョン・ドナホー)のコメント
”DXを加速させる新たなステップ。我々の計画は、RTFKTブランドに投資し、彼らの革新的でクリエイティブなコミュニティに奉仕し、成長させ、ナイキのデジタルフットプリントと能力を拡張することです。”
今回の記事では、買収したRTFKTも合流したと言われる新設部門NIKE Virtual Studioが主導する新サービス / プラットフォーム「.Swoosh(ドットスウォッシュ」をご紹介します。
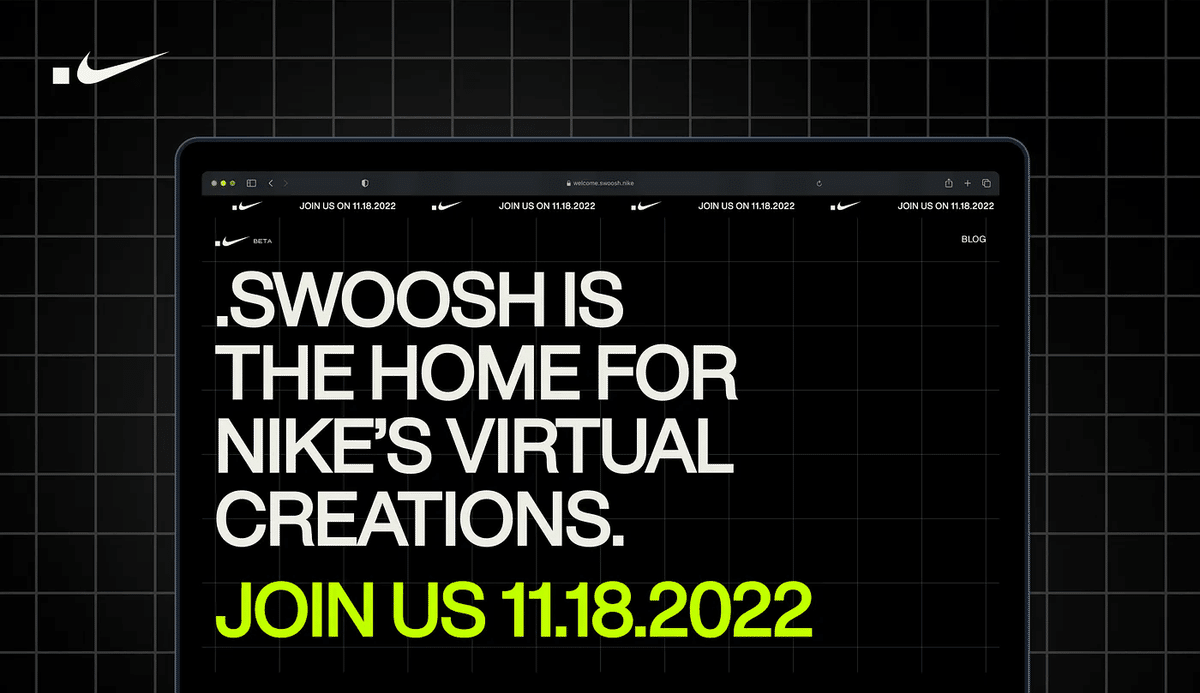
.Swooshとは?
.Swooshは、2022年11月に米国とヨーロッパの一部のユーザーを対象にリリースされました。ナイキは、.Swooshの立ち上げに際して、その目的や位置付けを以下のように表現しています。
現在ブランドに関わっている、またはこれから関わりたいと考えている全てのひと(アスリートやデジタルクリエイター、コレクターなども含む)が、「スポーツの未来をデザインし、所有する」ために集えるバーチャル空間
純粋な顧客向けのロイヤリティプログラムやNFTの販売だけではなく、ナイキがコミュニティと協力・共創するためのプラットフォームをつくることを目指していることが伺えます。
立ち上げ時に発表されていたコンセプトとしては以下の4点があり、現時点ではその中でも1.と3.の要素が強く、特に”スニーカー”にフォーカスして立ち上げを進めている印象です。
Create, Collect, Trade and Flex
Unlock Special Access
Build with Our Community
Pull Up to NIKE Events
それぞれについて簡単に補足します。
1. Create, Collect, Trade and Flex
自分だけのバーチャルコレクションの作成や収集、他のユーザーとの取引を可能にする。ここでつくられるNIKE Virtual Creationsは、ゲーム内でのウェアラブルアイテムなどとして機能することも目指す
2. Unlock Special Access
事前注文やエアドロップなど、様々なコンテンツや機会への特別なアクセスを提供する
3. Build with Our Community
他の.Swooshメンバーとのコラボレーションや、コミュニティ内でのチャレンジプログラムを通じた競争や共創
4. Pull Up to NIKE Events
オンラインや対面でのイベント、さらにはナイキの契約するアスリートやデザイナー、カルチャーを形作るナイキファンとのイベントの実施
リリースからの5ヶ月間を振り返る
ここからは昨年のリリースからこれまでの約5ヶ月間で発表されている取り組みをいくつかピッアップしてご紹介します。
オンボーディングセッション
Community Collective
Our Force 1
Your Force 1
1. オンボーディングセッション
Web3が何かわからない、Web3って仮想通貨?、そんなユーザーの戸惑いや疑問を払拭し、ナイキが目指すビジョンを共有すべく、各地域で.Swooshへのオンボーディングセッションを実施しています。公表されているだけでも週に1回〜2回は全米各地で開催しているようです。
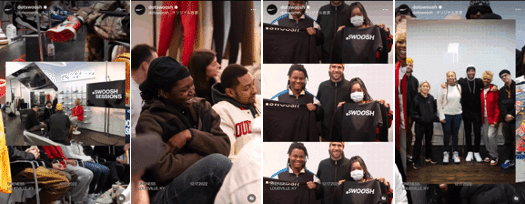
個人的にこのセッションで面白いと感じた部分は、どこか大規模なカンファレンスルームを借りて作り込んだ舞台で実施するのではなく、また、オンラインのみで実施したりするのではなく、各地のスニーカーショップなど、現地の店舗やコミュニティを利用して開催しているところです。
ナイキがローカルのコミュニティを重視している姿勢が伝わりますし、集客の点でも、エンゲージメントの高いファンをしっかり店舗が呼んでくれる、そんな相乗効果もあるのではないでしょうか。
ある日のセッションでは、①.Swooshのゴール、②.Swooshのユーティリティ、③.Swooshの概要(Web3や仮想通貨への特別な知識が不要であることなどの説明)が話されたと言われています。
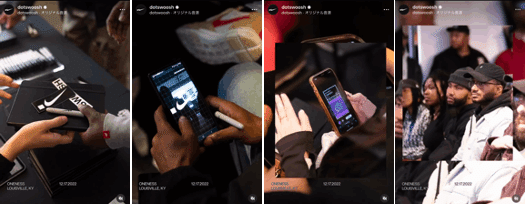
セッション終了時には、参加者全員に.Swooshに登録するための特別なアクセスパスが提供され、その場で登録までサポートすることもあるようです。(特別にアクセスパスがもらえる、なんて言われたらとりあえず登録しちゃいますよね)
.Swoosh IDの発行数はまだ32万を超えたところのようで、まずは検証も含めて、焦らずじっくりと増やしているのではないでしょうか。
3. Community Collective
Community Collectiveというイニシアチブを立ち上げ、スポーツやデジタル、若者などに関連する各地の団体とのコラボレーションを推進しています。
例えば、スポーツを通して若者や家族の人生を変え、希望を与え、文化を育むための取り組みを推進するシカゴのBeyond the Ballという団体とのコラボレーションなどを発表しています。

残りの2つは、共創の取り組みです
3. Our Force1
.Swooshの最初のコレクションとして、同社の誇る人気シリーズAir Force1(以下、AF)、その中の64種類を対象に、コミュニティでキュレーションに挑戦する取り組みです。
参加者は、インスタグラムやSNKRSアプリからお気に入りのAFを投票することができます。この投票によって.Swooshコミュニティとしてのデジタルコレクションが決まります。(このコレクションが今後どのように活用されていくのかは不明です)
ちなみに、投票においては「Regional(地域)」、「Herigtage(遺産)」、「Cultural(文化)」、「Innovation(イノベーション)」の4つのカテゴリが設けられています。

4. Your Force1
2023年1月、.Swoosh Studioの立ち上げとともに発表された取り組みです。.Swoosh Studioはこのコミュニティに参加するナイキのファンやクリエイターなどと直接コラボレーションするために立ち上げられました。
その第1弾としてアナウンスされた取り組みが、「Your Force1」です。
Your Force1は、ナイキから提示されたクリエイティブブリーフに基づいて、自身のアイディアを提案するものです。提案された様々なアイディアの中から優れたものに対してナイキが5,000ドルの賞金を提供するとともに、その内容に基づくデジタルアイテムの開発、そしてOur Force1コレクションへの追加の可能性が示唆されていました。
3月に受賞者の4名が発表され、提案されたコンセプトが実際にナイキのデザイナーとともに具体的なデザインプロセスに進んでいることが明らかとなっています。また、受賞者の発表以降に4名を招いたインスタライブなども実施しており、着々と制作が進んでいることが伺えます。

以上、この5ヶ月の取り組み内容はいかがでしたでしょうか。
ネット上で単に登録フォームを設けるのではなく、丁寧なオンボーディングプロセスと、コミュニティを重視する姿勢、また、コミュニティとの共創の強調など、急がずとも着実に、うまくマーケティングしながら進めているのはさすがナイキ、という印象です。
まだインスタグラムの.Swooshアカウントのフォロワーは21万ほどではありますが、Web3とは関係なく、ナイキというブランドが誰を重視しようとしているのか、その姿勢をうまく表現しているのではないでしょうか。
Web3的な要素は?
さて、ここまで.Swooshの概要やこれまでの取り組みをざっとみてきましたが、また、.SwooshはWeb3というキーワードをよく利用している取り組みですが、果たしてどのようなWeb3の要素があるのでしょうか。
まずは今一度、リリース日に遡ってみていきたいと思います。11/18に実施された、NIKE Virtual Studiosのディレクターたちによるオンラインセッション「.Swoosh Sessions」での発言をいくつかピックアップしてみます。
“Web3がNikeにとって何を意味するのかを考えてみてください。デジタルコレクタブルやWeb3テクノロジーを使って、スポーツと文化の全く新しい進化に拍車をかけることでどんなことができるのか”
“NFTは単なるアートワークではありません。それが最も重要な部分です。今、多くのメディアはNFTのアートの面を捉えています。今後の数年間で、目にみえるアートワークだけでなく、このアセットが何を開放してくれるのかが重要になります”
“ナイキといえば、フットウェア、アパレル、アクセサリー、アスリートなど、私たちが長い間築き上げてきたものを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。Web3が可能にするのは、私たちがより早くイノベーションを起こすためのプロセスを加速させ、コミュニティがそれに応えてくれるということです。”
あまり具体的な内容への言及はありませんが、大雑把に意訳すると、「Web3 ≒ NFT、コミュニティとの共創 」、「新たなイノベーションのための取り組み」といって捉えていると考えられるのではないでしょうか。
ナイキは2017年にトリプル・ダブル戦略を発表しており、その3つの中核要素の一つとして、「イノベーションの速度とインパクトを倍増(=ダブル)させること」を掲げていました。.Swooshの取り組みも、その延長線上にあるのかもしれません。
一方、スターバックスと同様、分散化といったような側面はあまり感じられず、コミュニティとの共創を謳っている一方で、DAOのように発展させていくことや、発生する収益をコミュニティで分かち合う、といったところまでは今のところ踏み込んではいないように見えます。
ちなみに、この.Swoosh上で利用されているNFTは、現在のところIDとして登録時に作成する.Swoosh IDのみだと思われます(私自身は登録できていないのでログイン後の詳細は確認できていません。この.Swoosh IDはOpenSea上で確認できますので、興味あればコチラへ。)

今後、上記のYour Force 1の取り組みなどを通じて、NFTコレクションなども発表されると予想されますが、ナイキとしてWeb3をどのように捉え、活用するのか、引き続き注目したいと思います。
おわりに
RTFKTとともにCryptokickの開発なども進めているナイキですが、今後はこの.Swooshの取り組みの中でうまれたアイディアも、NFTなどのデジタルスニーカーや、リアルライフで実際に履ける物理的な靴となってリリースされる日が来るかもしれないと思うと楽しみですね。
昨今のGenerative AIの盛り上がりの中で、単純にオシャレ、カッコいいスニーカーをデザインするだけであれば、AIにたくさん書かせたほうが効率が良い、となってしまう可能性が高い中、ナイキブランドとして各コミュニティとの共創によるストーリーやコンテクストをつくることは、今まで以上にブランドの意義が問われる中で、とても意味があるチャレンジなのではないでしょうか。
文字数がだいぶ多くなってしまったのでこちらで筆を擱こうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。
