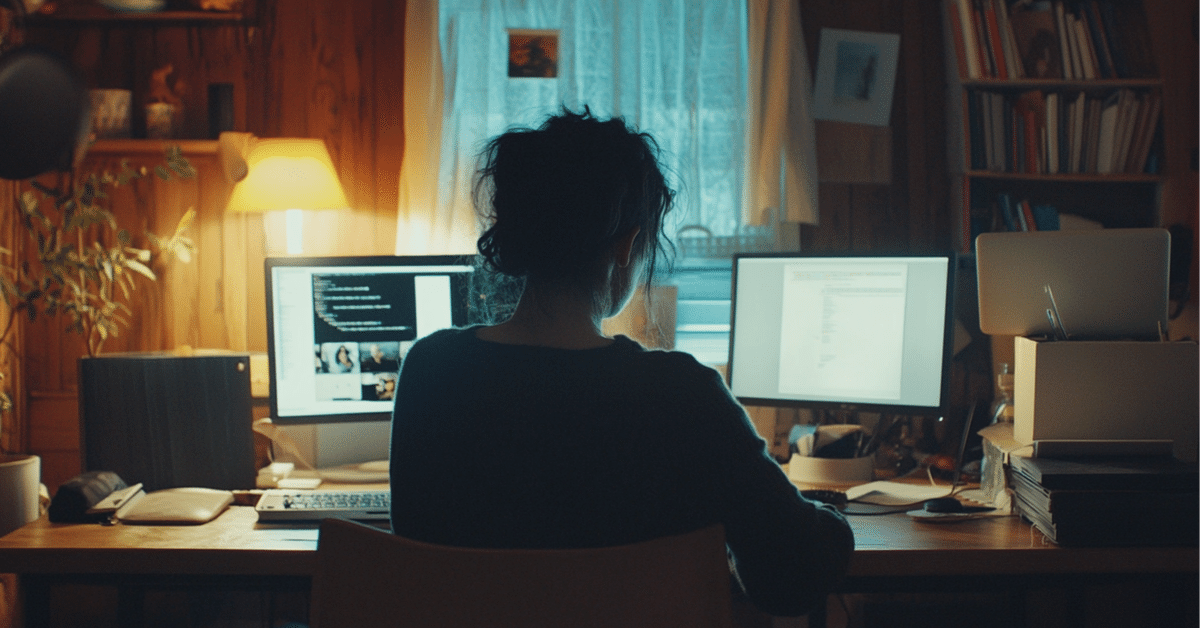
"良いデザイン"を生むディレクション術 2025年01月21日
ということで、
タグチマリコさんのウェビナーに参加してきました。
それにしてもマリコさんなんでもできるなー
尊敬
登壇資料を共有しようといない、
マッチボックスは糞。
▼今日のゴール
1.ディレクションを「プロジェクトデザイン」と捉える視点
2.不確実性や曖昧さを"チャンス"に変える方法
3.コンテクストと全体像を把握する力が"良いデザイン"に直結する
▼ディレクションとは何か
1.ディレクターは「進行管理+指示出し」だけをする存在ではない
2.“プロジェクト全体をデザインする”ことで、
チームやステークホルダーが同じビジョンを共有できるよう導く
3.良いデザインには 「目的背景・コンテクスト」 を理解し、
それを形にするプロセスが欠かせない
▼仕様が決まってない!というチャンス
「いっしょに整理しませんか?」
要件があいまいだからこそアイデアの自由度が高く
ユーザー分析や作るべき成果物の整理がおこないやすい
かけだし発注者さん
(という可能性)
依頼自体が適切でない可能性が高い
アサインしている人員は適切か? つくるものは適切か? ターゲットは適切か?
発注者のリテラシーが低いという言葉で片付けない
必要な向き合い方、取り組み方をかんがえる
▼曖昧さの向き合いかた
コンテクストを捉え、全体像をみる
制作(開発)背景、社会背景、ユーザー背景、チーム背景
社内の状況、ユーザーが置かれている状況、業界の動向、リソース、メンバーの立場など
▼ディレクションはディレクターだけのものじゃない
進行管理をみんなでしましょう!という話ではない
ディレクターに管理を依存させず
みんなでいつでも確認できる状態をつくる
全員参加型ディレクション
“いいデザイン”は組織から。
チームUXを高める組織マネジメント
ツール、ツールの使い方、管理のしかた、相談のしやすさ
意見をオープンに出せる文化・手法を整えれば多様な専門性が結集した価値創造がしやすい
▼具体手法
これまでの取り組み
※ここから実例のFigmaをみんなで見る会
▼まとめ
・すなわち、プロジェクトをデザインする
・“いいデザイン”は組織から。
・チームUXを高める組織マネジメント(ステークホルダー含む)
▼Q&A
Q.今デザイナーとしてディレクターとしてディレクションやってるんですけどペルソナ外の人などの具体例をもし可能でしたら見せていただきたいです。
A.共有画面が迷子になるマリコさん:ペルソナを見せていただきました。
Q.思考量や分析量が予想以上で圧倒されました
分析手法や論理的な思考などを学ぶにあたっておすすめの本があれば教えてください。
A.難しい本がいいわけじゃないですよね。私超器用貧乏できたんですよね。
とりあえず手を動かしてみる
Q.BtoBサービスなどではユーザーインタビューが難しい場面があると思いますが、どのように一次情報を得ていますか
A.BtoBサービスでも結局結局自社のサービスだと
クライアントさんを捕まえるのが
難しいケースは
当然関係値的にあると思うんですけど
全く別のプラットフォームでユーザーインタビュー
協力者を探す
インタビューだと
ユーザーインタビューのプラットフォーム
今非常にたくさん出ているので
例えばユニーリサーチさんとか
私は多分一番使っています
Q.ディレクションについてのご説明ありがとうございます
昨年UX UIデザイナーとして転職をして
現在社内初のデザイナーとして働いています
会社にも私自身にもノウハウがない中
手探りで業務を進めている状況です
またデザイナーとしての業務に加え
ディレクター的な役割も期待されています
ディレクションはみんなでやっていくものという考えには
大いに共感しています
しかし開発メンバーが少なく
私自身も経験が不足しているため
ディレクション業務だけではなく
デザイン業務に十分な時間を避けるかどうか
不安を感じています
もし田口さんがこのような環境を受けた場合
どのようにキャリアを構築し
これに対応されますか
アドバイスをいただけますと幸いです
A.私最初の会社はその状態でした
経験なくはないですけれど
制作に直接関係のあるポジションにいた
情緒がついてたわけじゃなかったので
結局デザインの正解みたいなのがなかったんですけど
やっぱり私の心の中にずっとコンテキストがあって
今でこそコンテキストという言葉で表せるんですけど
今こういう動きを求められている
求められている本当のデザインはこれであるとか
そういうのを考える癖がついている
多分、無
それはきっと生存戦略的な部分が強かったと思うんですけれど
ディレクションをみんなでやっていくものって
無理に捉えずに
これですね
何が言いたいかというと
私多分XD出始めかもっと前ぐらいの時代に
こういう資料はやっぱりずっと作っていて
こういう資料をいかに早く作れるかを
今AIの時代になってきているので
もっとやっていくと
全体像を見る力っていうのは
結局自分の得意なところを見つけられる能力にもなるので
例えば情報設計が
自分の中ですごく早いなって気づくのか
この後の
デザインもきっとされていらっしゃると思うので
あれかもしれないですけど
ちょっと難しいな
キャリアを構築し
課題に対応されますか
課題に対しては
どっちみちみんなが迷子になられないように
これは作りますっていうのだけは
これは私昔だと多分1日かけて作ってた
それでも1日で作れた自分を褒めてたんですけれど
今だとこのボリューム
私多分2時間ぐらいで出せます
AIに手伝ってもらいながら
このUIもAIに書かせてるので
これを出してみんなで
もうこれで作ってていいですよねって確認したら
もう一気にみんなで走れると思うので
そういう意味でスピードもアップできるし
みんなで合意するためのスピードを上げるためには
今自分が何をしたらいいのかっていう考え方で動くことで
多分自分のさくべきところにも時間を避けるし
チームのスピードも上がると思うので
ぜひAI時代の今だからこそ
投げちゃいけない情報はちゃんとマスクした状態で
作り方まで今回しゃべれないのであれなんですけど
こういうものをチャットGPTなり
いろいろ出てるものから一緒に作っていくのを
やったらいいんじゃないかなと思います
キャリアを構築するというか
いいものを作るために必要な情報は何だっけっていうのを考えていくと
多分今自分に必要な情報が見えてくると思います
Q.非常に分かりやすいセミナーをありがとうございます
ご紹介いただいた手法が非常に勉強になりました
私はアプリ開発のデザイナーをやっています
ディレクションの経験は浅いのですが
リリースまでの期間が短くスピーディーな開発をまとめられるときに
先ほどいただいた具体手法の中で比重を置く良い情報は何か
もしマリコさんが実践されているプロセスがあれば
お伺いしたいです
A.全部にユーザーの意見を挟めとは思ってないんですけど
たくさんユーザーを見てたらある程度最適解を見てくるので
プロセス
良い情報
なんだろう
いい答えがパッと出てこないです
具体手法の中で比重を置くと良い情報は何か
これを時間ないときにやれるなんて当然私も持ってないので
やっぱ
アプリのデザイナーをやってらっしゃるんですよね
スピーディーの開発
おすすめは一番最初だけ時間かけることですけど
つまり
そうですね
やっぱりこれですね
私は困ったときに立ち帰れる場所を
何らかの形で絶対作っておくっていうのは
なんとか法でもなんでもなく
今回作るものってなんだっけっていうのを
パッと見に帰れる場所を
別にFigjamじゃなくてもいいです
Googleスプレッドシートとか
Notionでもなんでもいいので
誰に作るんだっけっていう
ユーザーの情報をまとめておく場所と
今回絶対
この作ってる機能って正直作ってる間に
ブレてきたりするので
機能を書いておくというよりも
誰に作ってるんだっけっていう情報と
それに向けて
絶対
こういうフローとかも正直
なんかスピーディーな開発やってるとき
どんどんどんどん開発
ブレてくわけじゃないんですけど
いい意味でどんどんどんどん
アップデートされていくので
ユーザーの情報と
あと
ここだけはブラさないという
コンセプトだけ置いておくように
してますね
ちょっとコンセプト設計の話まではしてないので
今回ちょっとあれかもしれないんですけど
今回の場合
みんなで合意を取ったのは
例えばこの図の例だったら
ここにいる
最初からセールスフォースや
キントーンさんや
ヤプリさんのようなツールを使うと
まずいよねっていう合意だけは
みんなで取ってる
取ってた
なので今回みんな目指すのは
まずステップが
ここを目指して
ここを促進だけできるツールを
目指していこうねっていう
合意は取ってるんですよ
なのでそういった活動コンセプトだけは
みんなでいつでも
立ち返れる状態にしておくっていうのは
心がけてます
いいなと思ったら応援しよう!

