
ブラタモリ日記その17 「法隆寺 #161」 (2020.4.11放送)
高校の時の修学旅行が京都・奈良だった。奈良の大仏のある東大寺へ行ったのは覚えているが、法隆寺へ行ったかどうかはまったく覚えてない。行ったような気もするし、行ってないような気もする。
その法隆寺。なんと世界最古の木造建築だという。いやこれはもしかすると学生時代に習っているかもしれない。しかし残念ながら、まったく覚えてないのだ。いま初めて知ったような感覚。
これまではドラマや小説の影響で、戦国時代や幕末ばかりみてきた。ところがブラタモリをみるようになってから、古墳〜飛鳥〜平安〜鎌倉〜室町、このあたりの時代にとても興味が湧いてきた。ブラタモリはボクの知的好奇心を刺激してくれる、本当におもしろい番組なんだなッ。

「なぜ法隆寺は1400年愛され続けるのか?」
飛鳥時代 607年に創建される
世界最古の木造建築



法隆寺は日本で最初に世界文化遺産に登録されたお寺(1993年)
聖徳太子(574〜622)→ 飛鳥時代の皇族・摂政(せっしょう)、名は廐戸皇子(うまやどのみこ)→ 没後に聖徳太子とよばれる → 仏教を国の中心に置く、遣隋使など外交に尽力(607年)
西院伽藍(せいいんがらん)と東院伽藍(とういんがらん)



(ほうりゅうじこんどうしゃかさんぞんぞう)
金堂 釈迦三尊像(飛鳥時代)
飛鳥時代の特徴
・仏様の格好が三角形
・ヒダが左右対称
・アルカイックスマイル → 唇の両端が少し上向きで微笑をうかべたような表情
仏像13体のうち10体が国宝

(ほうりゅうじしてんのうりゅうぞう)
飛鳥時代の四天王立像は鬼が踏みつけられていない

釈迦三尊像のウラ → 光背銘文(釈迦三尊像がつくられた由来)→ 釈迦三尊像は聖徳太子の等身大につくられている(175cm前後)→ 聖徳太子の像でもある
今の五重塔や金堂は再建されたもの → よって今の法隆寺に聖徳太子をまつっても不思議ではない


最初の法隆寺 → 若草伽藍(わかくさがらん)
斑鳩宮(いかるがのみや)→ 聖徳太子の住まい
法隆寺創建から63年後の670年、火災で焼失
聖徳太子の建てた法隆寺と再建された法隆寺、1400年の歴史の中で2つの法隆寺の存在がある
再建された法隆寺は1300年 → 現存する世界最古の木造建築(ヒノキ)
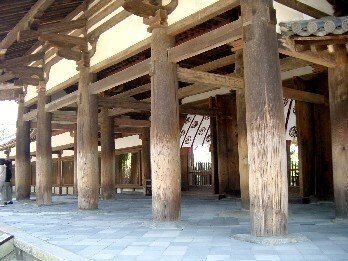

エンタシス → 古代建築にみられる上にいくほど細くなる柱の形状
中門の柱は上も細いが下も細い → 下から1/3くらいの高さのところが最も太い
埋め木 → 木材の傷んだ部分を他の木材で埋める修理法

廻廊(かいろう)→ 飛鳥時代のハリは少し湾曲、江戸時代につくり直されたハリは真っ直ぐ

金堂の四隅に支柱 → 金堂が建ってすぐに支柱が入った → 江戸時代につくり直した時に龍をまきつける
再建された法隆寺は聖徳太子を象徴
西院伽藍は高い場所 → 地盤が強い丘陵の尾根を削る
大和川を舟で飛鳥へ向かう時、斑鳩(いかるが)は必ず通る場所 → 斑鳩は交通や物資の中継地点の役目
交通の要衛だった斑鳩に法隆寺を建てる → 法隆寺を建てた翌年、随から使者がやってきて大和川を上り飛鳥の都へ
法隆寺は国際的に認められるシンボル
