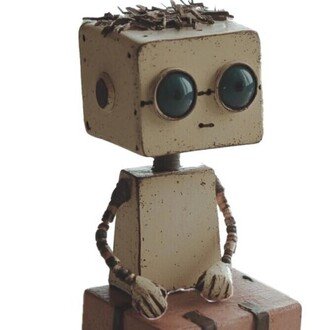著作権トラブルを回避!SOUNDRAWでYouTube BGMを作成してみた感想と注意点
最近、動画に合わせたBGM探しに苦労している人って多いんじゃないかなと思います。
YouTubeをはじめ、TikTokやInstagramのリールなど、短い動画コンテンツが盛り上がっている今、動画制作者にとって「サクッと手に入って、しかも自分がイメージした雰囲気の曲が欲しい!」というのは切実な願いですよね。
でも、音楽制作のスキルがあるわけじゃないし、フリー音源サイトを探しても著作権や使用条件がややこしかったり、クオリティがいまいちだったり…。
そこで注目したいのが、AIが自動で音源を生成してくれるサービス「SOUNDRAW」なんです。
「SOUNDRAW」をひと言で言うと、AIが自動作曲をしてくれる便利な音楽サービス。
ボタンひとつで色々なジャンルや雰囲気のBGMをパパッと作ってくれます。
私自身もYouTubeでちょこちょこ使っていて、「直感的に操作できるし、そこそこクオリティが良い音源が出てくる」ので、かなり重宝しています。
しかも商用利用に対応したプランが用意されていて、私がアップしたYouTube動画でも著作権の警告に一度も引っかかったことがないのは素晴らしいポイントだと感じています。
ただ、「SOUNDRAWさえあれば完璧!」というわけでもなく、やはり同じようなメロディが生成されがちだったり、細かい長さ調整が思った通りにいかなかったり…といった問題点があるのも正直なところ。
この記事では、SOUNDRAWの良いところ・悪いところ、実際の口コミを踏まえながら、「どんな人におすすめできるのか?」をわかりやすくまとめていきたいと思います。
知り合いに紹介するような感覚で、ザックリと本音を語っていくので、これから導入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
まずは動画で使用説明していますので、ご覧いただけたらと思います。
SOUNDRAWとは?
まずは「SOUNDRAWってそもそも何?」というところから簡単に解説します。
SOUNDRAWはAI(人工知能)を使って、ユーザーが希望する雰囲気のオリジナルBGMを自動生成するサービスです。
クラウド上で動くので、基本的にPCのブラウザからアクセスすればOK。
詳しい作曲の知識や、膨大なフリー音源サイトの検索も必要なく、「ジャンル」「ムード」「テンポ」などのパラメータを指定してボタンをクリックするだけで、パパッと数パターンの曲が提案されます。
生成された楽曲は、そのまま再生して確認できるだけじゃなく、「もうちょっと盛り上がり部分を作りたいな」とか「ギターの音が強すぎるな」といった編集も可能。
ブロック単位でエネルギーレベル(曲の強弱)を調整したり、楽器の数を変えたりできるので、自分がイメージするBGMにグッと近づけられるんです。
これは他のAI作曲サービスにはあまりない特徴で、初心者でも直感的なUIでサクサク操作できるのがかなり魅力的だと思います。
そして最大のメリットは、そうして作った音源を商用利用できるという点。
YouTubeにアップして収益化する動画のBGMにしても、たとえば企業の広告動画やテレビCMに使っても問題ない(※プランや規約の範囲内)ので、「権利関係どうなってるんだろ…?」と悩む必要が少ないのは大助かりだと感じます。
良いところ
それでは、まずはSOUNDRAWの良いところをザックリまとめてみます。
私自身が実際に使って感じた部分や、ネット上でのポジティブな口コミを踏まえつつお話ししますね。
1. 操作が直感的で簡単
AI作曲系のサービスって、なんだか難しそうに思えますよね。
でもSOUNDRAWのUIはわりとシンプルで、興味本位でポチポチ触っているうちに「こんな曲も作れるんだ!」という感じで理解できます。

とくにブロック単位で楽曲を区切って構成を変えられる仕組みは面白くて、たとえば「ここからサビに入りたいから盛り上がりを作ろう」と思ったら、そのブロックを“クライマックス”に変えたりして調整できるんです。
これが思いのほか直感的で、音楽制作の知識がなくても扱えるのが最高です。
2. 著作権に引っかからない(商用利用OK)
YouTubeでBGMを使おうとすると、一番怖いのが著作権やライセンスの問題です。

でもSOUNDRAWなら、有料プランに入っておけば基本的に商用利用がOKなので、YouTubeやブログのBGMとして使っても著作権警告を受けることはまずありません。
実際に私も何本かの動画で使いましたが、コンテンツIDに引っかかったことは一度もありませんでした。
これは地味にストレスを減らしてくれる大きなメリットだと思います。
3. クオリティがなかなか良い
AIが作る音楽って、正直「ちょっとしょぼいんじゃないの?」なんて想像するかもしれませんが、思ったより自然です。
もちろん、プロの作曲家が何時間もかけて作ったような芸術性あふれる曲とは違うかもしれませんが、YouTubeやSNS用のBGMにするには十分すぎるくらいのクオリティ。
ジャンルもポップやロック、エレクトロ、ジャズ、クラシック調などいろいろ選べるので、動画の雰囲気に合わせて使い分けられます。
4. ブロック単位でエネルギーレベルを調整できる
個人的にかなり気に入っているのが、このブロック単位でエネルギーレベル(強弱)をいじれる機能です。
「曲が盛り上がりすぎると、動画のBGMとしてはうるさく感じる」ことってありますよね。
そういうときはSOUNDRAW上でさくっとブロックの盛り上がりを抑えることで、BGM全体が前面に出すぎないように調整できます。
逆に「ここはしっかり印象付けたい!」という場面があれば盛り上がり部分を挿入するなど、使い分けがしやすいのは本当に助かります。
5. ブラウザで完結する
ソフトのインストールが不要で、ブラウザさえあればどこでも作業できるのは地味に便利です。
私はMacを使っているんですけど、普段からブラウザ中心で作業するタイプなので、この「クラウド完結型」はめちゃくちゃ相性が良いです。
デスクトップPCはもちろん、ノートPCやタブレットなどでもアクセスできるので、移動先でもパパッとBGMを作成・編集できるのは嬉しいところだと思います。
悪いところ
続いては、SOUNDRAWの悪いところや使っていて不満に感じた点、ネット上でもよく挙がる「微妙…」という意見をピックアップします。
どのサービスもメリットばかりではないので、ここは正直に語らせていただきますね。
1. 同じようなメロディが生成されやすい
AIが作曲するといっても、やはり元になっているデータやアルゴリズムのパターンがある程度決まっているせいか、「またこの進行か」「前にも似たようなのが出たな」ということが起こりがちです。
特に、自分がよく使うジャンルやテンポだと、「あれ、以前生成した曲と雰囲気が似てない?」と感じることがあります。
完全に同じ曲じゃないにしても、コード感やメロディラインに既視感がある場合があるんですよね。
2. 料金がかかる
サブスクで月額制または年額制になっていて、無料プランだとダウンロードに制限があったりします。
本格的に使おうと思うと、有料プラン(月額で1,650円くらい)に入る必要があるので、人によっては「ちょっと高いな」と感じるかもしれません。
特に「BGMをそんなに頻繁に使うわけじゃない人」にとっては、割高な印象になる可能性があります。
3. 細かい長さ調整が難しい
個人的に一番痛感しているのが、ブロック単位で曲を構成する都合上、どうしても自分の動画の長さにピッタリ合わせられないことが多いんです。
たとえば「2分16秒の曲が欲しいのに、ブロックを組み合わせると2分14秒か2分18秒になっちゃう…」という問題があるんですよね。
動画のエンディングに合わせてしっかり曲を終わらせたいときに、微妙に長さが合わなくてイライラしてしまうことがありました。
最終的には動画編集ソフトでクロスフェードやフェードアウトで誤魔化すんですが、ぴったり収めたい場合にはなかなか難しいのが正直なところです。
4. エディットの自由度はそこまで高くない
ブロック単位でエネルギーレベルを変えたり、楽器のオン・オフを切り替えたりはできるのですが、細かい演奏フレーズや音色をいじるとなると限界があります。
たとえば「このタイミングでギターのリフが入り、ピアノのソロをちょっと長めに…」みたいに、こだわった演出をしようとすると難しいですね。
本当にプロの作曲ソフト並みにいじりたい人には物足りないと思います。
5. 使わない時期がもったいない
これはサブスク全般に言えることですが、たとえば「今月は動画制作がほとんどないや…」という月でも、契約を続けていると料金が発生し続けます。
必要なときだけサクッと課金して使えるといいんですが、プラン的にすぐ解約してまた契約して…というのが面倒で、そのまま課金を続けてしまう人もいるんじゃないかなと思います。
コストパフォーマンスをよく考える必要がありますね。
良い口コミ
ここからはSOUNDRAWに対する「良い口コミ」をいくつか紹介しましょう。
私が実際に目にしたものや、ネットで見つけたユーザーの声をまとめてみました。
「YouTubeのBGMとして使いやすい」
これは本当に多くの人が言っていることで、特にYouTuberやVloggerに人気が高い印象です。
やはり商用利用OKで、直感的に曲を生成できるというのが好評なようです。「時間短縮になる」
フリー音源サイトを巡回する手間が減る、DAWを立ち上げて作曲する時間をカットできる、という点が評価されています。
数クリックで雰囲気の合う曲をいくつも試せるので、締切がタイトな仕事を抱えた映像クリエイターやマーケターには助かるみたいですね。「エフェクトやソロなどの編集が案外しやすい」
曲自体をゼロから大きく作り変えるのは難しいですが、SOUNDRAWのブロック編集機能は初心者にとっては革命的という声も。
ミックスや音量バランスをAIがそれなりにうまくやってくれるので、音割れや急激な音量変化などを気にしなくて済むのは便利だと感じる人が多いです。「英語がわからなくても使える」
日本語対応がしっかりしているので、英語が苦手でも大丈夫という口コミもありました。
海外製のAIサービスだと英語UIに苦労することがありますが、SOUNDRAWは公式サイトは日本語版があるので、操作で詰まることがあまりないようですね。
創設者は日本の方ですので・・・・
悪い口コミ
ここでは「悪い口コミ」や「ちょっと不満」という評価についてまとめます。
良い部分ばかり取り上げてしまうとリアルじゃないですし、実際に使っている人の生の声は導入前に知っておくと役立つはずです。
「料金が高い・プランが合わない」
やはり真っ先に出てくるのがコスト面。月額1,650円前後だと、頻繁にBGMを必要としない人にはハードルが高いという声があります。
年額プランのほうが割安ですが、それでも「どのくらい使うかわからないのに年額はなぁ…」と感じる人もいるようです。「思ったほど個性的な曲ができない」
AIが自動生成するという性質上、どうしてもパターンの枠が決まっているらしく、斬新なサウンドや尖ったメロディラインを求める人には向かないという意見もあります。
汎用性の高い“無難なBGM”を作る用途では良いけれど、曲そのものが独自の魅力を放つような作品にはなりづらい、という指摘がありました。「同じようなメロディが多い」
先ほども触れましたが、AIが使うデータベースやアルゴリズムの関係で、「何度か生成するとパターンが似通ってくる」と感じる人は少なくないようです。
背景音楽として使うならそこまで問題ないですが、頻繁に使う人だと変化に乏しく思えるかもしれません。「曲の長さ調整がイライラする」
これも私自身が感じている不満点ですが、やはりブロックを組み合わせて楽曲を構成する仕組みなので、秒単位での微調整が難しいという声が多いです。
ぴったりの長さに仕上げたい場合にちょっと融通が利かないのは、実務で使うときには意外にストレスになるかもしれません。
どんな人におすすめ?
じゃあ結局、「SOUNDRAWってどんな人が導入すると良いの?」という疑問に答えてみます。
私なりの意見ですが、以下に該当する人には割とハマりやすいんじゃないかと思います。
YouTube・SNS向けの動画を量産している人
やはり一番のターゲットはここでしょう。
毎回BGMを探すのが面倒なクリエイターや企業の動画担当者にとっては、手軽にそこそこのクオリティの曲を用意できるのは大きなアドバンテージです。作曲ソフトや音楽理論を使いこなすのが難しい人
「音楽制作にガッツリ時間を割けない。でもオリジナルBGMが欲しい」という人にはピッタリ。
DAWを使ってゼロから作曲するのは大変ですし、フリー音源を探すのも結構骨が折れます。
SOUNDRAWならクリック操作でOKなので、時間と労力をかなり節約できます。短い尺のBGMを大量に作りたい人
たとえばインスタのリールやTikTokなど、ショート動画をどんどん更新したい人にとっては、あっという間にBGMができるSOUNDRAWは便利です。
ショート動画向けの長さにブロックを調整して使うだけで、すぐに新作のBGMを生成できます。商用利用をガッツリ考えている人
企業PR動画や広告、収益化しているYouTubeチャンネルなど、「著作権的に安全な音源を確保したい」というニーズがある人にもおすすめです。
フリー音源サイトとは違い、商用利用で揉めるリスクが少ないのはかなり安心できます。
一方で、「音楽制作が趣味で自分で凝りたい人」や「めちゃくちゃ個性的な曲を求めている人」、「動画の音楽まで完璧にこだわりたい人」にはちょっと物足りないかもしれません。
大がかりなアレンジや秒単位での終わり方の調整が必要なときには、最終的には手動で編集しなければならないので、そこが許容範囲かどうかがポイントです。
まとめ
SOUNDRAWは、AIが自動で曲を作ってくれるという点で、とにかく「作曲のハードル」を大幅に下げてくれるサービスだなと感じています。
私自身もYouTubeのBGMとして何度か使いましたが、「著作権に引っかかる心配がほとんどない」「割といい感じの曲がすぐできる」「エネルギーレベルをブロックごとに調整できる」という点に大きな魅力を感じています。
ただし、「本格的なこだわりには対応しきれない」「同じようなメロディが増えがち」「曲の長さを微妙に合わせられない」などの弱点もあるのは事実です。
月額または年額でコストがかかるので、頻繁に利用する動画制作者や企業クリエイターでない限り、「金額に見合う価値があるのか?」をしっかり考える必要があるでしょう。
私としては、動画編集の仕事や趣味で一定の頻度でBGMを使いたい人には相当おすすめです。
フリー音源を探す手間やライセンス問題の不安が一気に減るので、「あ、じゃあもうSOUNDRAWで作っちゃおう」って気軽に考えられるんですよね。
一方、毎日使うわけでもない人は、ちょっと贅沢なサブスクになりがちなので、実際どれだけ曲を必要とするか、まずは無料プランやトライアルで試してみると良いんじゃないでしょうか。
いいなと思ったら応援しよう!