
【クトゥルフ神話03】残響の楽園に揺れるは忘却の旋律
この短編小説は2025年1月13日に遊んだ【新クトゥルフ神話TRPG】でのオフラインセッションのリプレイを元に作成したものです。
PLはボドゲゴーやつなげーと等のアプリで募集中していますので、ぜひよろしくお願いします。
<文庫本70ページ相当>
探索者紹介
夏目竜胆 (なつめりんどう)

34歳/ミステリ作家
身長170cm/体重68kg
STR50 CON55 SIZ60 DEX60
APP45 INT80 POW65 EDU85
耐久力12 正気度65 幸運70 回避70
芸術(文芸)90 心理学90 目星80 図書館80
言いくるめ80 応急手当50 オカルト50
信用40
心理描写が巧みなミステリ作家(出版社所属、山田風太郎賞受賞)で、犯人の思考まで共感を誘う作風が賛否を呼ぶ。常に和装で、金銭に無頓着。自身の作品制作を最優先し、取材と称して出版社に無断で失踪することも多く、編集とは折り合いが悪い。人付き合いは自分本位で、心理や隠し事を見抜く能力が反感を買うこともある。次回作ではオカルトの導入を検討中。和風の物を好み、フィジカルはそれなり。独身貴族を自称し、交渉や頭を下げることを苦手としている。
相馬天馬 (そうまてんま)

30歳/アルバイト(スーパー店員)
身長200cm/体重110kg
STR90 CON80 SIZ90 DEX50
APP40 EDU50 INT40 POW60
耐久力17 正気度60 幸運35 回避25
ビルド2 ダメージボーナス+2
近接戦闘(格闘) 90 精神分析86 応急手当
80目星80 投擲70 追跡60 登攀40 信用5
「筋肉は全てを解決する」という信念を持ち、自分の筋力とプライドを最優先に行動する。愚鈍で無神経ながらも神経質で気が小さく、短気で自己中心的。筋力を否定されたり笑われることを極端に嫌い、挑発に乗りやすい。怪異にも「筋肉で殴れば大丈夫」だろうと無謀に立ち向かおうと考えているが、通用しない現実に直面したときは混乱してしまう。冷静な判断が苦手で、無計画に突っ走りがちだが、稀にそれが事態を打開することもある。過去には、スーパーで冷蔵庫を壊し「全力を尽くした結果だ」と開き直ったことがあった。当然クビになった。
宇佐木未美 (うさぎみみ)

28歳/看護師身長162cm/体重50kg
STR50 CON60 SIZ55 DEX65
APP75 EDU80 INT75 POW60
耐久力12 正気度60 幸運75 回避82
医学90 応急手当90 図書館85 聞き耳85
心理学60 生物学51 跳躍20 信用20
愛嬌ある表情とくりくりした目を持つ看護師で、天真爛漫な性格と勉強熱心さで周囲から信頼されている。外科での経験を経て救急科に異動し、優秀な若手として地位を確立。趣味の縄跳びで鍛えた筋肉質な体格が特徴。彼女のモットーは「1日1つ新しい知識を得ること」。未知の領域に対する強い好奇心を持ち、学びのためなら睡眠や食事を忘れることもある。一方で退屈を極端に嫌い、何も得られない日には蕁麻疹が出るほどの恐怖を感じる。未知の生物や怪異にも興味を抱いており、危険があっても迷わず手を伸ばす可能性がある。勉強熱心で真面目ながら、その好奇心が予期せぬ波乱を引き起こすかもしれない。
一本道正直 (いっぽんみちまさなお)

24歳/無職(転職活動中)
身長168cm/体重57kg
STR40 CON50 SIZ50 DEX60
APP70 INT70 POW80 EDU60
耐久力10 正気度80 幸運75 回避30
目星65 説得60 心理学60 芸術(切り絵)55
心理学50 精神分析51 歴史25 自然20
信用5
ブラック企業(幼児向け教材営業職)を退職後、転職活動中。本音でしか話せない性格から、建前や社交辞令を嫌う人々に強く支持される一方、初対面では驚かれることも多い。友人には恵まれ、悪い人間に利用されかけた際も救われた経験がある。転職活動に疲れ、「雇ってくれるなら幽霊でも神でも構わない」と思うほど判断力が鈍っている。就職に繋がる特技を模索し、最近はテレビの影響で切り絵を始め、折り紙とハサミを持ち歩きながら練習を重ねている。
永瀬咲良 (ながせさくら)

24歳/会社員(営業職)
身長156cm/体重55kg
STR50 CON60 SIZ50 DEX70
APP65 INT50 POW60 EDU55
耐久力11 正気度60 幸運60 回避35
説得90 聞き耳90 心理学75 言いくるめ55
図書館50 手さばき50 応急手当40
精神分析21 信用15
新卒で入社して2年目、学習教材を対象にした新規開拓営業を担当。これまでに受賞歴や役職経験はない。突発的な行動が好きで好奇心旺盛な性格。上京して2年が経ち、日常生活に慣れたことで新しいことに挑戦したいという気持ちが強くなっている。基本的には常識的だが、自分が「これだ」と思ったことは必ず実行するタイプ。イケメンに目がなく自己愛が強い。反面、あまり頭の回転は速くない。また、一度裏切られると二度と相手を信じない。長所は好奇心旺盛、短所は頑固なところ。家族を何より大切に思っているが、自分自身も大事にする性格。
序章 夢
――闇の中、朧げな旋律が風に溶ける。そこは草木が生い茂る島の情景だった。
夏目竜胆は和装の裾を翻し、手に取ったペンを万華鏡のように揺れる空に向けていた。耳に届くのは、どこか懐かしい少女の笑い声。振り向くと、青い海を背に白いワンピースを纏う少女がいる。しかし、その顔がぼやけて認識できない。
「あなたはだれだ?」
夏目が問いかけるが、返事はない。ただ、優しく微笑む少女の姿が消え、代わりに島全体が崩れ去っていく。音を立てて崩れる木々、吹き荒れる風。最後に聞こえたのは「戻ってきて」という小さな囁きだった。
彼は目を醒ました。薄暗い執筆部屋で、無意識に書き留めた文字が目に入る。そこには「楽園」とだけ書かれていた。
相馬天馬は陽光の差す草原を走っていた。遥か先に、誰かが楽しそうに手を振っている。彼は笑い返そうとしたが、声が出ない。ふと足元を見ると、花々の間を白い猫が駆け抜けていく。その先には異様な光景が広がっていた。
黒い花が絡み合うようにして島を覆い、天空を飲み込んでいく。力強く進もうとする彼の足は、突然地面に埋まり動けなくなる。どこからか聞こえる少女の声。
「相馬さん、助けて――」
彼はハッとして目を醒ました。自分の体を確認し、額に浮かぶ汗を拭う。耳元には、自分でも知らない番号からの通知音が鳴り響いていた。メッセージは一言『また楽園に来て』と。
夢の中で宇佐木未美は病院の一室にいた。窓の外には青い海が広がり、波の音が静かに響く。
ベッドに座る少女が、どこか儚げな笑顔を向けてくる。
「ねえ、未美ちゃん。楽しかったよね」
その言葉に答えようとするが、声が出ない。代わりに、彼女の手には古い写真が握られている。そこには自分と知らない少女が写っていたが、なぜか涙が止まらなかった。
目が覚めると、部屋の中に漂う花の香りが鼻をくすぐった。枕元には見覚えのない封筒が置いてあり、その中には「楽園」と書かれた地図が入っていた。
一本道正直は、手に折り紙を握りしめて立っていた。目の前には巨大な滝が広がり、その水面には懐かしい情景が映し出されている。白いワンピースを纏う少女が自分に向かって何かを言っているが、その言葉は水音にかき消される。
「何を……伝えたいんだい?」
声を張り上げた瞬間、滝が割れて背後に巨大な異形の花が現れる。それは滝を覆い尽くし、すべてを飲み込もうとしていた。
目を覚ました彼は、手に何かを握っている感覚が残る。見れば、小さな折り鶴が手のひらにあった。その背には「楽園」と記されていた。
永瀬咲良は小さな草原に佇んでいた。柔らかな風に揺れる花々の香り、心地よい音楽。だが、その静けさは不安を煽るようでもあった。
「あなた……誰、だっけ?」
ぼんやりと浮かぶ少女の影に問いかけるが、答えはない。ただ微笑むだけのその姿が霞んでいき、代わりに足元に広がる大地がひび割れ始める。目の前の花々が黒く染まり、枯れていく光景に彼女は息を呑んだ。
目を覚ました咲良は、ふと枕元に置かれた小さな楽譜を見つけた。その端には「楽園でまた会おう」と書かれていた。
第1章 楽園

#1
それぞれ奇妙な夢と不思議なメッセージ、そしてそれに続いて届いた招待状に導かれるようにして瀬戸内海の小さな港からチャーター船に乗り込んでいた。
だれしもなぜこんな得体の知れない招待状に従ってしまっていたのかわからない。あの懐かしげな夢を見たからとしか言いようがないが、どこかふわふわとした気持ちは波のせいだけではないようだった。
そして招待状はいつの間にか手元から消えていた……。
船はどこか古びた木造の漁船のような趣があり、少し揺れるたびに軋む音が響く。甲板に並んだ数個の大きな荷物は、食糧や水の補給物資のようだった。
夏目は一番端の席に腰掛け、和装の袖を直しながら目を細めて周囲を見回していた。
「なるほど……これが落栄島――転じて《楽園》の島への道というわけか」と独り言のように呟いた。
相馬は甲板に立ち、広い背中を揺らしながら荷物を覗き込む。
「やけにたくさんの食い物だな。これ、無人島に持ってくのか?」
船員に聞くが、返答は曖昧だった。
未美は船の手すりに寄りかかり、潮風に顔を向けながら目を閉じていた。
「懐かしい気がする……ここ、来たことあるのかな?」ふと、顔を上げて誰にともなく問いかけた。
一本道は荷物の隙間に腰掛け、小さな折り鶴を手で弄りながら目を伏せていた。
「楽園か……いい名前だな。でも、本当にここで何があるんだ?」と独りごちた。
咲良は船の中央でスマートフォンをいじりながら落ち着かない様子だった。
「無人島なんて聞いたことないけど、本当に大丈夫なの?」
画面をタップしても電波が入らないことに気付き、舌打ちをした。
船が小さな波を越えるたびに、探索者たちの視線が交差する。
不思議なことに、どこかで会ったことがあるような気がしてならない――それぞれの顔には、微かな記憶の片鱗が浮かんでいた。
「なんだか、初めて会った気がしないんだよな……」
相馬がぽつりと呟いた。
「ええ、そうですね」
未美が続ける。
「わたしも、皆さんに何か覚えがあるような気がします。おかしいですね」
「こういうの、既視感ってやつか?」
一本道が折り鶴を閉じ、顔を上げた。
夏目は冷静に観察していたが、ふと口を開いた。
「既視感かどうかはわからないが……それぞれが楽園という言葉に導かれている。何かしらの縁がありそうだな」
「縁って……そんなスピリチュアルなもん、信じたくないけどな」
咲良が腕を組み、肩をすくめる。
「でも、ここにいるみんなが同じ夢を見たとかなら……なんか、あり得る気がする」
船は静かに波を切り進み、やがて遠くに小さな島影が見え始めた。
どこか懐かしく、それでいて異様な雰囲気を放つ島――そこが探索者たちの向かう《楽園》だった。
咲良は立ち上がり、船員がロープを巻き直しているところに近づいた。年配の船員で、日に焼けた顔に深いしわが刻まれている。潮風の中で手際よく作業を進める姿は、無駄のない動きが印象的だった。
「あの、ちょっといいですか?」と咲良は控えめに声をかけた。
「この船の行き先の島について、どんなところか教えてもらえませんか?」
船員は手を止め、帽子のつばを押さえながら咲良を見上げた。
「行き先の落栄島のことか? 今じゃ無人島だが昔は観光地でね」
「観光地?」
咲良は首を傾げた。
「じゃあ、何か施設とかあったんですか?」
「ああ、リゾート地だったのさ。落栄島は縁起がわるいってんで当時は楽園島なんて呼んでたな。バンガローや小さな遊歩道、それに滝やら展望台やらがあってな。十年くらい前までは若い連中がサマースクールとかで利用してたもんだよ」
船員は少し懐かしそうに語った。
「でも今じゃすっかり寂れちまってな。しかたない。このあたりの海流は複雑でな。そもそも水難事故が多発するんでレジャーには向かなかったのさ」
「じゃあ無人島なんですね……」
咲良は少し考え込んだ。
「それで、いまは何があるんですか?危険な動物とか、変わった噂とか?」
船員は微かに笑ったが、どこか含みのある表情だった。
「危険な動物? いてもネズミや野良猫ぐらいだろう。変わった噂ってのも、よくわからんが、でも……」
「――でも?」
咲良は問い詰めるように言葉を継いだ。
「たまに、不思議な話を聞いたな。船で通るとき、ここだけ妙に空気が重いってな。ま、そのくらいか」
船員は顔を曇らせた。
「気のせいかもしれねぇけど、おれも長居したくはねぇ島だな」
その言葉に、咲良は小さく頷いた。
ふと足元の波を見ると、さっきまで透明だった海水が、わずかに深い青へと変化している気がした。
彼女がその場を離れるとき、船員はぼそりと呟いた。
「まあ、あんたらも気をつけな。島には……何かあるかもしれねぇからな」
咲良が甲板に戻ると、他の探索者たちが彼女の方を見ていた。
「なんか、変わった話でも聞いたのか?」と相馬が尋ねる。
「うん、落栄島のこと。昔は観光地だったけど、今は廃れてるらしいわ。でも……船員さん、ちょっと不気味なこと言ってた。島の空気が重いとかなんとか」
その言葉に一同は何とも言えない沈黙を共有したが、船はさらに進み、目の前には徐々に島の全貌が現れ始めていた。
夏目は船の揺れに身を任せながら、遠くに浮かび上がる落栄島をじっと見つめた。島の輪郭が近づくにつれて、その起伏や形状、覆う緑の風景が次第にはっきりとしてくる。潮風に混じる香り、遠くに聞こえる波の砕ける音――すべてが妙に懐かしい。
「どこかで……この景色を見たことがあるな」
夏目は目を細め、記憶を遡るように島の全貌を観察した。その瞬間、脳裏に鮮明なフラッシュバックが蘇る。
――青い空の下、無邪気な笑い声が響く。木陰で談笑する仲間たち、そして白いワンピースを纏った少女が滝壺のそばで水を跳ね上げている。視線の先には、島の展望台らしき場所が見えた。その構造物の形や位置が、目の前の島と完全に一致していた。
「確かにここだ……昔、来たことがある」
夏目は低い声で確信したように呟いた。
他の者もその言葉に反応した。
「本当ですか?どんな島だったんです?」
未美が振り返る。
「詳しいことは思い出せないが、ここには確かに来たことがある。滝があるはずだ。そして……何か、特別な理由でここにいたような気がする」
夏目は言葉を選びながら続けた。
「ただ、その時の記憶が曖昧だ。何か大事なことが、この島に隠されている気がしてならない」
その言葉に船内の空気が一瞬重くなった。他の者も目の前の島を見つめながら自分の記憶を辿ろうとするが、はっきりとした答えは得られなかった。
船はさらに近づき、落栄島の波止場が姿を現した。古びた木製の桟橋と、その奥に続く緑の道が探索者たちを待ち構えているかのようだった。
船が島の桟橋に近づくにつれて、みなはそれぞれの心に湧き上がる奇妙な感覚を抑えられなかった。
桟橋は古びていて、木材の表面は潮風に削られ、苔が張り付いている。ところどころに野良猫がたむろし、じっと船を見つめている。
未美は船を降りるためのハシゴを慎重に下りながら風景を見渡していた。
「すごく静かですね……でも、どこか懐かしいな」
一本道は荷物を降ろす相馬の後ろでポケットから折り鶴を取り出しながら小声で呟いた。
「なんだか、この島自体がおれたちを待ってるみたいだな……」
咲良は桟橋に降り立ち、周囲の景色を確認した。
「確かに無人島っぽいけど……猫がこんなに多いなんて、ちょっと変じゃない?」
彼女が視線を向けると、黒い猫が一匹、鋭い目つきでじっとこちらを見ていることに気付いた。
みなが全員桟橋に立つと、船員が軽く帽子に手を当てて言った。
「まあ、気をつけな。あまり変なことには首を突っ込むなよ」
船は彼らを置いて波間へと戻り始めた。
桟橋に残された探索者たちは、眼前に広がる緑と静けさの中に足を踏み出した。古びた道が彼らを島の奥へと誘っている。
風が吹き抜けるたびに、どこからか囁き声のようなものが聞こえる。それが風音なのか、それとも何か別のものなのか、誰にも分からなかった。
#2
未美は桟橋から一歩踏み出し、周囲をじっくりと観察した。
潮風が静かに吹き抜ける中、聞こえるのは風音と波の音だけだ。だがどこか空気がざわついているような感覚が彼女の肌を刺す。
「……誰かいる?」
彼女は小声で問いかけるように呟きながら耳を澄ませた。
ふと、桟橋の近くに残された足跡が目に入る。それは新しく、確かに人が歩いた痕跡だった。だが、その向かう先は森の中へと消えている。
「ここ、わたしたち以外にも誰かいるかもしれないです。ここに足跡が――」
未美は微かに眉をひそめ、他の者に声をかけた。
「気にしすぎじゃないか? 無人島なんだろ?」
相馬が肩をすくめながら周囲を見渡した。
夏目は島の入口付近で古びた観光案内板を見つけていた。
塗料が剥がれ錆つき文字はところどころ消えかけているが、かろうじて読みとることができた。
「島の中心には記憶通り滝がある……遊歩道が通じていて、展望台とバンガローが点在する……なるほど」
夏目はその内容を他の者にも伝えた。
「どうやら、滝やバンガローが探索の拠点になりそうだ。もっと奥に進めば何か見つかるかもしれない」
その間、咲良は野良猫たちに近づき、しゃがみこんで手を差しだしていた。
黒い猫が一匹、警戒しつつも興味を持ったように彼女に近づいてくる。
「よしよし、大丈夫だよ。ほら、おいで」
咲良は優しく声をかけ、猫の視線をじっと見つめた。
やがて猫は少しずつ距離を縮め、彼女の手元で鼻をひくつかせる。

「お、なついてきたか?」
一本道がその様子を横目で見ながら口元を緩めた。
「ふふ、やっぱり猫って可愛いなあ。ねえ、あんた、この島に何か秘密があるなら教えてくれない?」
咲良が冗談めかして話しかけると、猫はまるでその言葉を理解したかのように首をかしげるだけだった。
そんな中、不意に一行の視線が集めるものがあった。そう、森の奥から透き通るほど白く見える人影が現れたのだ。
「……あれは?」
未美が目を凝らすと、それは白いワンピースを纏った少女だった。長い髪をなびかせながら、静かに歩いてくる。

「みんな……久しぶり」
十五、六歳くらいの幼さの残る少女は微笑みながら一同を見つめ、その場に立ち止まった。
誰もがその姿に見覚えがあるような気がしたが、記憶が曖昧で確信が持てない。
「君は……誰なんだい?」
夏目が最初に口を開いた。
「わたしはアリア。きのう、この島に来たときは独りで不安だったけど、みんなを見て安心した」
アリアは柔らかな声でそう告げると、一同に向けて微笑んだ。
その笑顔にはどこか懐かしさと切なさが混じっているようだった。
彼女の言葉と存在に触発されるように、探索者たちの中で微かな記憶が呼び覚まされようとしていた。
「あなたは誰? もしかしてわたしのこと知ってる?」
未美は一歩前に出て、目の前の少女に視線を合わせるようにして問いかけた。
アリアは少し首をかしげ、穏やかな笑みを浮かべたまま答えた。
「この島で皆さんに出会えるのを待っていたの。未美ちゃん……やっぱり、覚えていないのね」
「覚えてない? わたし、どこかで会ったことあったっけ?」
未美は眉をひそめた。
アリアは少し悲しげな表情を浮かべたが、それでも声は柔らかかった。
「ううん、無理に思い出さなくていいの。ただ、こうしてまた会えて嬉しい。それだけで十分」
その言葉に未美は戸惑いを隠せなかった。
心の奥底に何かが引っかかるような感覚がある。それはまるで忘れたはずの記憶が目の前に差し出されたかのような気分だった。
「みんな、ここまで長い旅お疲れさま。島を案内するわ。ついてきて」
その場に立っていた他の者たちもいきなり現れたアリアの言葉に少々困惑しながら、どこか懐かしさを覚えているようだ。
そして彼女の透き通るような白い肌に浮かんだ絢爛たる花模様はタトゥーなのかどうか、全員が気にはなったもののセンシティブなことでもあってか質問するタイミングを失って、だれも問いかけることはなかった。
夏目は袖を直しながら冷静な視線をアリアに向けた。
彼女の表情や仕草、言葉の端々を観察し、何か隠していることがないか見抜こうと試みようと、アリアをじっと見つめ続けた。
しかし、アリアの微笑みは揺らぐことなく、その澄んだ瞳には一切の嘘や疑念を感じ取ることができなかった。むしろ、その無垢さが余計に彼の心に引っかかる。
……この子は何も隠していないように見える。だが、それが逆に不自然だ。夏目は内心で自問した。
「アリアさんだったね」
彼は柔らかな声を装いながら言葉を投げかけた。
「君がこの島に来たのはきのうと言っていたけど、一人で来るには随分と不便な場所だ。どうやって来たのかな?」
アリアはその質問に一瞬だけ視線を泳がせたが、すぐに笑顔を戻した。
「船で送ってもらったの。みんなと同じ船だったかも」
その返答に夏目は微かに首を傾げたが、それ以上の追及はしなかった。
アリアの言葉には何の矛盾も感じられない。だが、その完璧な笑顔が妙に心に引っかかる――夏目はそんなもどかしい感覚を抱えたまま黙り込んだ。
「さあ、こちらへ。楽園の中心に案内するわ」
アリアは柔らかな笑みを浮かべたまま探索者たちを島の奥へと誘った。
白いワンピースの裾が風に揺れるたび、どこか現実離れした雰囲気を漂わせている。
「この楽園って……どんな場所なんですか? 昔、リゾートだったって聞きましたけど」
未美は足早にアリアの後を追って訊いた。
「ええ、昔は人がたくさん訪れて、みんな楽しそうに過ごしていたわ。でも今は静かになった……そのぶん自然の音や景色をもっと感じられる場所になったんじゃないかな」
アリアは軽く頷きながら答えた。
「素敵……なんだか、すごく落ち着く感じがするわ」
未美は目を輝かせながら周囲を見回していた。
森の中から聞こえる鳥のさえずりや、草木の擦れる音に心を奪われているようだった。
「自然がどうとかおれにはよくわかんねぇけど、こんなとこで人が住めるのか?」
対照的に相馬は少し怪訝そうに言った。
「住めるかどうかはともかく……なんだか、この場所には妙な気配がある気がするね」
一本道は手の中の折り鶴を弄びながらぼそりと呟いた。
「ねえ、この猫たち、ずっとついてきてるんだけど……なんか変じゃない?」
一方で咲良は猫たちがついてくる様子に目を向けていたのだった。
道がやがて開けると、目の前にはかつてのリゾート施設の名残と思われるバンガローが数棟並んでいた。そのうちの一棟は比較的保存状態が良く、まだ使用可能に見える。
「ここが休憩できる場所よ。もちろん宿泊も。少し休んだら、さらに奥を案内するわ」
アリアが振り返って言った。
「でもさ、この島、無人島なんだろ?誰がここを管理してるわけでもないのに、そんなにキレイに保たれてるもんかね?」
相馬は少し顔をしかめた。
アリアは視線を落とし、少し考え込むような素振りを見せた。
「確かに……でも、ここに来るたび、なぜかこの場所は綺麗なままよ。不思議だけど、それがこの島の魅力の一つだと思うの」
その言葉を聞いて、夏目は冷静に口を挟んだ。
「不思議というより……都合がよすぎる。普通ならこんな場所、すぐに荒れるはずだ」
未美がその場を和らげるように口を開いた。
「でも誰かが時々、島に来て掃除しているとか、そういうこともあるんじゃないですか? 島の雰囲気に合った優しい人がいるのかも」
「まあ、そうだといいけどな」
相馬は納得がいかない表情を浮かべながらも、それ以上深追いはせず肩をすくめた。
#3
一行はアリアに導かれるまま、比較的保存状態の良いバンガローの一棟に入った。
外観からは年月を経た趣が感じられたが、案外、内装は整っており、かつてのリゾート施設らしい雰囲気を残していた。
中にはリビングルームを中心に、簡易的なキッチンとテーブル、奥には大きめの寝室が二つあり、それぞれに簡素なベッドが並んでいる。トイレも清潔で使える状態だった。木材で作られた家具はどれもシンプルだが、どこか温かみがある。
「へえ、結構しっかりしてるな。無人島にしては手入れが行き届いてるじゃねえか」
相馬が部屋の中を観察するように見回した。
リビングのテーブルにはわずかな埃が積もっているが、妙に新しい傷跡がついている。さらにキッチンの棚には、最近使われたような形跡も。水道の蛇口も少し濡れているようだ。
「……誰かが最近ここを使ってたみたいだな」
相馬が低い声で呟いた。
「それはアリアがきのうから使ってたから当たり前なんじゃない」
未美が言った。
「だとしても、この傷とかは違うだろう。アリアだけじゃなく他にも誰かがいるのかもしれない」
相馬の言葉には警戒心がにじんでいた。
「さすがに考えすぎじゃない?」
未美の意見に他の者も賛同した。
その間、咲良は外で待機していた猫たちが気になり、窓際に近づいて観察していた。
バンガローの外には先ほどからついてきた猫が3匹ほどいた。黒猫、茶トラ、そして灰色の猫だ。
「入ってくる気はないみたいだけど……なんか、ずっとこっち見てる」
咲良は窓越しに猫たちと目を合わせた。
黒猫がじっと動かずにこちらを見つめているのに対し、茶トラと灰色の猫は時折あたりを見回しながら歩き回っている。
「黒猫がリーダーみたいに見える……変な感じ」
咲良は独り言のように呟きながら、さらに猫たちの動きを追った。
その瞬間、黒猫が一歩前に出て咲良をまっすぐ見つめた。まるで「早く外に来い」とでも言いたげな視線に思えて、彼女は思わず身体をこわばらせた。
「ねえ、この猫たち、なんか普通じゃないかも。まるで……こっちを誘ってるみたい」
咲良が振り返り、他の探索者たちに声をかけた。
#4
咲良と相馬は意を決してバンガローを出て、黒猫の元へ行ってみることにした。
ふたりが近寄っていっても黒猫はじっとふたりを見つめたまま動かず、まるでこちらを試すような態度だ。
「大丈夫だよ、怖くないからね」
咲良は笑顔で黒猫に近づき、バッグから持参したスナック菓子を取り出した。「これ、ご飯代わりにどうかな?」
「おい、それ猫にやるもんじゃねえだろ」
相馬が呆れた声を出すが、咲良は気にせず袋を開け、黒猫の前に小さく割ったスナックを差し出した。
黒猫は慎重に匂いを嗅ぎ、少し鼻をひくつかせたが、興味を失ったのかその場を動こうとはしなかった。
「……だめかあ。何か他に食べられるものがあればなあ」
咲良は困った顔をして相馬を見た。
「これならどうだ?」
相馬はポケットから干し肉を取り出し、無造作に黒猫の前に置いた。
黒猫は干し肉には少し興味を示したようで、慎重に一口だけ食べると、再び二人をじっと見つめた。その目には、どこか知性すら感じられるようだった。
「なんか変だな、この猫。普通の猫じゃねえ気がする」
相馬が眉をひそめながら呟くと、咲良は小声で返した。
「でも、なんか分かってるみたいだよね。この島になにか知ってるんじゃない?」
黒猫はそのまま何かを待つように前足を揃えて座り込んだ。
バンガローのなかでは未美がアリアに話しかけていた。
「アリアさん、すごく優しそうな人ですね。一緒にこの島を歩いてみたいな。また案内してくれないですか?」
「もちろんよ。未美ちゃんが楽しんでくれるなら、わたしもうれしいわ」
アリアは微笑みを浮かべ、優しく頷いた。
「それにしても、この島って不思議な雰囲気があるよね。なんていうか懐かしいような気もするし……」
未美は少し照れくさそうに笑った。
「そう感じるのはきっと、この島がみんなを歓迎しているからだと思う」
アリアはその言葉に目を細めた。
「ありがとう、アリアさん。これからよろしくお願いしますね!」
アリアの優しい声に未美は胸を打たれたのだった。
「君はぼくたちのことをどこまで知っているんだ?」
疑念を拭えない夏目はアリアに距離を保ちながら率直に問いを投げかけた。
「知っていると言えば知っているし、知らないとも言えるわ。……でも、みんなのことは、もっとたくさん教えてほしいな」
アリアはその問いに少し目を伏せてから柔らかく笑った。
その曖昧な答えに夏目は眉をひそめ、じっと彼女の表情を観察しようとした。
しかし、アリアの微笑みは揺らぐことなく、まるで真実を隠しているようには見えなかった。
『……またか。どうしてこうも読めないんだ、この少女は』
夏目は内心で舌打ちをしながらも、それ以上深く追及することはできなかった。
リビングでは一本道が折り紙を取り出し、手慰みに切り絵を始めていた。
「さて、こういうのは静かに集中してやるのが一番だな」
手際よくハサミを動かしながら、彼は徐々に複雑な模様を切り抜いていく。その音が静かなバンガローに響き、妙に心地よいリズムを刻んでいた。
やがて一枚の紙が美しい花の模様へと変わり、彼の手元に完成した。
「よし、悪くない」
一本道は自分の作品に満足げに頷いたが、どこからか微かに花の香りが漂ったような気がして顔を上げた。
「……ん? 気のせいか?」
それぞれが異なる時間を過ごしている中、バンガローの外から風に乗って小さな囁き声が聞こえたように思えた。それが風の音か、それとも別の何かか――五人は不思議な感覚に包まれていた。
#5
一時間後、アリアは微笑みながら「それでは、もう少し島の奥を案内するわね」と言い、未美と夏目を連れてバンガローを出ようとしたときだった。
その後ろから一本道が手元の切り絵を見せながら歩み寄った。
「これ、さっき作ったんだ。良かったら見てくれないか?」
一本道は花を模した繊細な切り絵をアリアに差し出した。
アリアは目を丸くし、その作品をじっと見つめた。
「まあ、素敵……こんなに綺麗な切り絵、もらってしまっていいの?」
その反応に一本道は満足げに頷き「気に入ってくれたなら、君にあげるよ」と切り絵を手渡した。
「ありがとう、大切にするわ」
アリアは嬉しそうに笑顔を浮かべ、その表情にはどこか懐かしさすら漂っていた。
一本道はその反応に少し照れくさそうにしながらも「じゃあ、ぼくも一緒に案内してもらおうかな」と言い、三人についていくことを決めた。
アリアは四人を連れ、草木が生い茂る小道を進んでいった。
風に揺れる葉の音と、時折聞こえる小鳥のさえずりが、島の静けさを際立たせていた。
その頃、バンガローの外で聞き耳を立てていた咲良は、小さな囁き声が風に混じるのを聞きとった。
「……ここ……早く……」
それは言葉としてはっきり聞き取れるわけではないが、不思議と何かを訴えかけているようだった。
咲良は耳を澄ませたまま、その声の方向を探るようにして自然と足が向いていた。
「これって、誰かが呼んでるのかな……?」
気づけば、彼女は茂みの中へと入り込み、小道を外れてしまっていた。
周囲はしだいに薄暗くなり、草木の隙間から見える空すらも覆い隠されている。
「え、ちょっと待って、ここどこ……?」
咲良は足を止め、不安げに周囲を見渡した。
そのとき、目の前の木の根元から小さな異形の影が動いた。
暗い茶色の体、細長い手足、ギラギラと光る小さな目。大きなネズミのようにも見えるが明らかにネズミではない。その口元には、まるでミミズのような触手がうねうねと蠢いているのだ。
「な、なにあれ……!」
咲良は声を上げそうになったが、恐怖に息を呑んだ。その見たことのない動物は彼女を見つめ、カタカタと小さな音を立てて近づいてくる。

「やばい、やばいって……!」
咲良は後ずさりしながら何か武器になりそうなものを探したが見つからない。
焦る最中、背後からも動くものの気配を感じ振り返る――
あの黒猫だ。
猫はネズミの怪物を威嚇するように低い唸り声を上げながら金色の目つきでにらみつけた。
怪物は黒猫の気迫に押されたように動きを止めると、逃げるようにして木陰に隠れて姿を消した。
「助けてくれたの……?」
咲良は黒猫に呟いた。
黒猫はくるりと振り返ると、まるで「ついてこい」と言わんばかりに先へ進み始めた。
咲良は猫の後を追い、ようやく見覚えのある小道に戻ることができた。
「ほんとに助かった……ありがとう」
咲良が感謝の言葉を口にする間もなく、黒猫は一声、にゃあと鳴いた。
その頃、そんなことがあったとは露知らず、相馬はバンガローのベッドに横たわり、大きな体をシーツの中に沈めていた。
「島とか猫とかどうでもいい……今は寝るのが一番だ」
彼は深い眠りに落ち、潮風に包まれながら静かな時間を過ごしていた。
アリアに案内されながら進む一行の前に小さな滝が姿を現した。
その澄んだ水面はまるで鏡のように光を反射し、そこには歪んだ記憶の断片が映るかのようだった。
「ここが楽園の滝よ。昔はみんなでここに来て遊んだよね」
アリアが懐かしそうに語る。
滝壺によって池のようになった水面は驚くほど澄んでおり、鏡のようにそれぞれの顔を映し出していた。
その水面に目を凝らすと、微かに揺れる波紋の中に何かが浮かび上がるような錯覚があった。
夏目が滝壺をじっと見つめると、そこに映る自身の姿がふと消え、別の光景が現れた。

――眩しい陽光の下、滝壺のそばで笑い声が響いていた。白いワンピースを纏った少女が水を跳ね上げ、楽しそうに笑っている。
「アリア……」
夏目は小さくその名前を口にした。
彼の記憶はさらに鮮明になる。
アリアが水辺で足を滑らせそうになった瞬間、自分が手を差し伸べて彼女を支えたこと。
彼女が嬉しそうに「ありがとう、夏目さん!」と微笑んだその表情――それがはっきりと蘇てきたのだ。
だが、その記憶の最後には、彼女の姿が海へと消えていく断片的な映像が入り混じっていた。
あの時……ぼくは何をしていた? 夏目は喉の奥が詰まるような感覚に襲われ、無意識に滝壺から目を背けてしまった。
一本道もまた揺れる波紋の中に、ぼんやりとした情景が浮かび上がるのを感じた。
――夕暮れの滝壺。咲良が切り絵を手にして「すごい、一本道君! こんなに綺麗な切り絵、初めて見た!」と嬉しそうに笑っている。その隣には、白いワンピースの少女――アリアが微笑んでいた。
「一本道君、もっと作ってみてよ!」
アリアの声が耳に残る。だが、その後の記憶が急に歪み、何かが切れるように途絶えた。
「……なんだ、この記憶は? あの時、何があったんだ?」
一本道は額に手を当て、頭の奥を探るように考え込むが、それ以上の記憶は出てこなかった。
しかし未美は水面に視線を落としたが、何も特別なものは見えなかった。
ただ、自分の顔が揺れる波紋に歪むだけである。
「何か……見えるんですか?」
彼女は隣の夏目や一本道に問いかけるが、二人は無言のまま水面を見つめていた。
「わたしには何も……」
未美は肩を落とし、少し居心地悪そうに立ち尽くすしかなった。
アリアは三人の様子を静かに見守っていた。その瞳にはどこか悲しげな色が混じっているようだった。
「記憶は……少しずつ、戻ってきたのね」
アリアの言葉は、どこか達観した響きを帯びていた。
「でも、無理に思い出さなくてもいい。きっと、必要なときにすべてが分かるから」
夏目はその言葉に鋭い視線を向けたが、アリアの微笑みからは何も引き出せなかった。
黒猫の案内でようやく咲良が滝壺に辿り着いたのは、そのときだった。
息を切らしながらも「みんな、ここにいたんだ!」と声を上げた。
黒猫は案内を終えてやれやれと言った態度で、少し離れた岩場に腰を下ろし、人間たちを見守るようにしていた。
「ねえ、聞いて! ついさっき変なネズミみたいな怪物に遭遇したの!」
合流した途端、咲良は息を整えながら皆の方に歩み寄り、興奮した様子で話し始めた。
「え?怪物って……どういうこと?」
未美が驚いたように声を上げた。
咲良は頷きながら続けた。
「本当に変な奴だったのよ!茶色っぽい体で、普通のネズミよりずっと大きくて、目がギラギラしてた……まるでこっちを狙ってるみたいに感じた」
「ネズミの怪物だと……?」
夏目は眉をひそめ、興味深そうに咲良の話を聞いた。
「どこでそれに遭遇したんだ?」
「バンガローから少し離れた茂みの中よ。道に迷っちゃって、どうしようかと思ったときに遭遇したの」
咲良は言葉を早めながら、黒猫に視線を向けた。
「でもね、この猫ちゃんが助けてくれたの! 威嚇して追い払ってくれたのよ」
黒猫は滝壺の岩場に座ったまま、じっと咲良を見上げていた。その視線にはどこか知性めいたものが感じられるほどだった。
「この猫が……助けてくれたって?」
一本道が目を細めて黒猫を見た。
「普通の猫がそんなことをするのかな?」
「普通の猫じゃないのよ、この子は! 本当にありがとうね。きみが助けてくれなかったら、どうなってたか……」
咲良は黒猫に歩み寄り、感謝を込めるように優しく声をかけた。
黒猫はまるで彼女の言葉を理解したかのように小さく喉を鳴らし、頭を少し傾けてみせた。
「怪物、ね……」
夏目は腕を組み、考え込むように滝壺を見下ろした。
「もしこの島にそんな存在がいるなら、何かもっと深い理由があるはずだ。偶然出会っただけじゃないだろう」
「この島には不思議なことがたくさんあるの。でも、きっとみんななら大丈夫。何かあっても、この島がみんなを守ってくれる。それが島の意思だから」
アリアは少し心配そうな表情を浮かべながら口を開いた。その言葉は安心を与えるように聞こえたが、同時にどこか意味深でもあった。
一本道はアリアに歩み寄り、遠慮がちに問いかけた。
「あのさ……昔、ぼくは前にもきみに切り絵をあげたことがあった? それに、そもそもぼくが切り絵をやってたなんて自分じゃ思い出せないんだけど。最近始めたばかりだと思ってたんだよね」
アリアは彼の言葉を聞いて少し考え込むように目を伏せた後、微笑みを浮かべて答えた。
「一本道君が切り絵を始めたのは、確かに最近のことかもしれない。でも、こうしてまた切り絵を作ってくれたってことは……きっと昔も同じようにだれかを喜ばせたことがあったんじゃないかしら?」
彼女の要領を得ない曖昧な返答に一本道は首をかしげた。
「そうかな……でも、君がそのだれかだったかどうかは思い出せそうにないな」
「無理に思い出さなくても大丈夫」
アリアは優しい声で続けた。
「一本道君の切り絵は、とても温かい気持ちを伝えてくれる。だからきっと、それが誰であっても、大切な思い出だったはず」
一本道は少し納得したように頷きつつも、どこか腑に落ちない様子でその場を離れた。
「君に聞きたいことがある。もしかして君は過去に海に落ちたことがあるか?」
夏目は鋭い視線をアリアに向け、低い声で問いかけた。
「……どうしてそんなことを?」
アリアの表情が一瞬だけ曇ったが、すぐに元の微笑みに戻った。
「この滝を見て思い出した。君が水辺に立っていた光景と……その後、何かが起きた記憶の断片がある」
夏目はあえて核心に触れようとするかのように続けた。
「ごめんなさい、夏目さん。でも、その記憶はきっと……まだ思い出すときではないのかもしれないわ」
アリアはその言葉に対して曖昧な笑みを浮かべるだけで、明確な答えを避けた。
「はぐらかすのか?」
夏目は少し苛立ちを覚えながらも、矢継ぎ早に次の質問を重ねた。
「それなら、この黒猫について何か知っているか? 咲良さんを助けたようだが、どうも普通の猫じゃない気がするんだが」
アリアは黒猫をちらりと見やり、小さく頷いた。
「そうね。わたしも詳しくは知らないけど……この子もわたしたちを守ってくれているのかもしれないわね」
未美は一歩前に出て、心配そうにアリアを見つめた。
「ねぇ、アリアさん。この島は何からわたしたちを守ろうとしているの? 咲良さんが言ってたネズミの怪物って何か知ってる?」
「この島は、皆さんを大切に思っているの。だから、危険なことから守ろうとしているんだと思う」
アリアは一瞬だけ微妙な表情を見せたが、すぐに穏やかな声で答えた。
「でも……そのネズミの怪物のことについては、わたしもよくわからないわ。ただ島を歩いていると、不思議な生き物に出遭いそうな気はしてたわ」
「でも、それが本当に危険なものだったら……どうしたらいいの?」
アリアの言葉はどこか曖昧で、未美は眉をひそめた。
「そのときは、この島を信じて」
アリアは微笑みながら答えた。
未美はその言葉に完全には納得できない様子だったが、それ以上は問い詰めなかった。
#8
滝壺を後にした一行はバンガローへと戻った。
正午を過ぎた頃には太陽が頭上に昇り、島全体を柔らかな陽光で照らしている。潮風に混じる草木の香りが漂うなか、それぞれ疲れた表情を見せていた。
バンガローに戻ると、既に休息を取っていた相馬が目をこすりながら出迎えた。「おい、随分遅かったな。なにかあったのか?」
「あったよ、すごいこと! ネズミみたいな怪物に遭遇して猫ちゃんに助けられたの」
咲良は真っ先に応えた。
「なんだそりゃ、夢でも見てたんじゃないのか?」
相馬は呆れたように笑ったが、他の者の表情が真剣なことに気づき、息を呑んで黙り込んだ。
「……で、昼飯はどうするよ?」
彼は気まずさを逸らそうと話題を変えた。
未美がキッチンの棚を調べると、船着き場に置いてきた食料を取りに戻る必要もなく、保存食や缶詰、乾パンなどが整理された状態で置かれていた。
相馬が近づき、「こんなのがちゃんと残ってるのも不思議だよな」と呟きながら缶詰を手に取った。
「まあ、食べられるならいいじゃない。とりあえずこれでランチにしようよ」
咲良がテーブルに缶詰と乾パンを並べた。
「簡単な食事だけど、こういう時にはありがたいもんだよね」
一本道はポケットから小さな折りたたみナイフを取り出し、缶詰のフタを開け始めた。
アリアはキッチンの片隅に座り、皆が準備を進める様子を微笑みながら見ていた。
「アリアさんも食べる?」
未美が声をかけると、彼女は小さく首を振った。
「ありがとう。でもわたしは大丈夫。皆さんで召し上がって」
「そっか……じゃあ、いただきます」
未美は軽く頭を下げてから、缶詰の中身をスプーンで取り分けはじめた。
ランチの間、一同はそれぞれに今日の出来事を振り返りながら会話を交わした。
咲良はネズミの怪物との遭遇と黒猫の活躍を熱心に語り、未美はアリアへの信頼を強めていた。
一方で、夏目と一本道はそれぞれの記憶に浮かび上がった断片について言葉少なに考えを巡らせていた。
「この島、何かが確実におかしいな。もっとよく調べないと、何も分からないまま終わりそうだ」
夏目がぽつりと呟く。
相馬は缶詰の中身を豪快に頬張りながら「まあ、どっちにしろ腹が減っちゃ何もできねえよな」と言って笑った。
#9
昼食後、再びアリアに案内され、未美、夏目、咲良の三人は再びバンガローを出発した。
柔らかな陽光の下、道は緑に覆われ、風に揺れる草木が島の静寂を際立たせている。
道中、夏目が一歩前に出て、険しい口調でアリアにまた問いかけてみた。
「アリア、君が何を望んでいるのか、そろそろはっきりと言ってくれないか。ぼくたちに何を思い出してほしいのか、はぐらかさないでほしいんだ」
アリアは足を止め、ふと立ち止まった。背中を向けたまましばらく無言で立ち尽くしていたが、やがて振り返り、夏目の目をまっすぐに見つめた。
「……わたしは、みんなに大切な思い出を取り戻してほしいだけ。それが、いまのみんなにとって必要なことだから」
「それだけじゃないだろう?」
夏目は鋭く詰め寄った。
「その思い出が、君自身にどう関わっているのかを教えてほしいんだ」
「それを話してしまうと……きっと、皆さんを傷つけてしまう。だから、いまはまだ……ごめんなさい」
アリアの微笑みが一瞬だけ揺らぎ、その目にどこか悲しみの色が浮かぶ。
夏目はその答えに納得がいかない様子だったが深追いできなかった。
反対に未美はアリアの隣に歩み寄って明るい声で尋ねた。
「ねぇ、アリアさん。この島で一番好きなところってどこ?」
アリアは少し考えるようにしてから、優しく微笑んだ。
「この島全体が大好きだけど……もし一番を選ぶなら、小さな丘の上にある展望台かな。そこから見る景色は、本当に綺麗なの」
「展望台……行ってみたいな!」
未美は目を輝かせた。
そこに咲良が歩きながら話に加わった。
「アリア、この島に花園ってある? わたし、夢に見たような気がするのよね。色とりどりの花が咲いてて、すごく綺麗な場所だったんだけど……あるなら、行ってみたいな」
アリアは少し驚いたように咲良を見たが、すぐに表情を整えた。
「花園……そうね、この島には不思議な花が咲く場所があるわ。でも、そこはとても特別な場所。慎重にしないといけないの」
「行けるの?」
咲良が期待に満ちた目で問うと、アリアは小さく頷いた。
「ええ。でもその前に、もう少しこの島を知ってほしい。だって花園は最後に行くべき場所だから」
「まぁ、最後でもいいわ。でもきっとよ、絶対に行きましょうね」
咲良はその言葉に少し不満そうだったが、渋々頷いた。
ちょうどその頃、バンガローに残った相馬は一本道が切り絵をしているのを横に武器になりそうなものを探していた。
「怪物がいるなんて聞いたら、手ぶらで歩けるわけねえだろ。しかし、何にもない小屋だな」
ぶつくさと文句を言いながら、それでもキッチンをで大振りの包丁を見つけることができた。
「これなら十分か」
相馬は包丁を持ちながら、手に馴染む感覚を確かめた。
「どんな奴が来たって、これで一発だぜ!」
相馬はようやく一息つけた気分になってリビングのソファーにどっかりと座ったのだった。
#10
アリアに導かれた未美、夏目、咲良の三人は丘の上にある展望台に到着していた。
古びた木造の展望台は年月を感じさせるが、まだ十分に利用できる状態を保っている。風が心地よく吹き抜け、丘の斜面に広がる緑と青い海が眼下に広がっていた。
咲良は展望台から周囲を注意深く見渡していた。
「本当にここ、何かがいるんじゃないかって気がするのよね……あの怪物とか、変な影とか」
「さっきの話が気になるのか?」
夏目が視線を海に向けながら問いかける。
「そうよ。さっきあのネズミみたいなやつに襲われそうになったから……もしかして他にも仲間がいるんじゃないかって思うと、気が抜けないわ」
咲良は周囲の木々や草むらまで目を凝らして警戒を続けていた。
一方で、未美は展望台の手すりに寄りかかり、景色を楽しんでいた。
「すごく綺麗……本当に、ここがアリアさんの言ってた場所なんですね」
「あの辺りに例の花園があるのかも」
アリアは微笑みながら、遠くを指さした。
咲良はその言葉にすぐに反応し、アリアが指さした方向を見つめた。
確かに木々の隙間からちらりと見える何かがあった。色とりどりの花が揺れているようにも見える。
「花園……あそこがそうなの?」
咲良はさらに目を凝らし、周囲を警戒しながらその場を離れようとはしなかった。
夏目は展望台から周囲を観察しているうちに、視界の片隅に懐かしさを感じる光景を捉えた。
――またもや昔の記憶がよぎる。滝から上がった後、仲間たちとともにこの展望台に立ったこと。白いワンピースの少女――アリアが、木々の向こうに広がる花園を指さして微笑んでいた。
その記憶の中、夏目はアリアに「花園には何があるんだ?」と問いかけていたが、その先の答えはどうしても思い出せない。ただ、当時の自分が強くその場所に惹かれていた感覚だけが鮮明だった。
「やはり……この場所には昔来たことがあるのか」
夏目は低い声で呟き、アリアの方を振り返った。
「思い出しましたか?」
アリアは優しく問いかける。
「いや、まだ断片的だ。ただ、君がそこにいたことは覚えている」
アリアは微笑んだまま何も言わなかったが、その表情にはどこか意味深なものが感じられた。
時を同じくしてバンガローでは相馬が一本道を強引に引き連れて外に出ていた。
「ちょっと待ってよ、ぼくは行きたくないんだけど!」
一本道は半ば無理やり腕を引かれながら抗議する。
「ネズミの怪物ってのがいるなら、そいつを探してやろうと思ってな。あんなの、おっかねえ顔してるだけでおれの敵じゃねえよ」
相馬は包丁を手に構え、自信満々に進んでいく。
「だからって、本当に危険だったらどうするんだよ」
一本道は半ば呆れたようにため息をついた。
二人が森の中を進むうち、茂みの中から奇妙な音が聞こえた。
「カタカタ……カタカタ……」
その音に気づいた瞬間、相馬が茂みを掻き分けると、話には聞いていた例の怪物がいた。しかし一匹ではなく見える限りでは数十匹という群れだった。
茶色の体、小さな手足、光る目――咲良が話していた怪物が、複数体まとまってこちらを睨んでいた。
「おい、いたぞ!」
相馬は包丁を構え、前に出る。
「かかってこい!」
だが怪物たちは襲いかかるどころか、じっと相馬を見つめたままだった。
その次の瞬間、相馬の頭に直接響くような声が届いた。
『……去れ……ここは我々のもの……侵すな……』
「なんだ、この声……!」
テレパシーとも言えるその声に、相馬は動揺し、手元の包丁を強く握りしめた。
「相馬さん、この声は!?」
一本道もその場に凍りついていた。
怪物たちは警告を発しただけで動きを見せず、ただじっとその場に立ち尽くしている。
「……わかったよ、去ればいいんだな。行くぞ、一本道」
「そ、相馬さん……」
威圧に怖気づいた相馬は悔しそうに吐き捨て、一本道の腕を掴んで引き返した。
「こんなの、どう考えても普通じゃねえぞ。一刻も早くこんな気持ち悪い島から逃げねぇと――」
相馬は帰り道で吐き捨てるように呟き、一本道も深く同意することしかできなかった。
未美は風に吹かれながら、展望台から見える景色をじっと見つめていた。
鮮やかな緑、青い海、そして遠くに見える花園。その風景が、何か遠い記憶を揺さぶる。
――高校生の頃、参加したサマースクールの記憶が蘇る。島に降り立ち、ワクワクしながら他の参加者と一緒に行動したこと。年上の指導員たちに優しく教えられながら、滝や展望台を巡ったこと。
「そうだ……わたし、この島に来たことがあったんだ……」
未美は呟くように言った。
「サマースクールに参加して……ここで色んな人たちと友達になった……」
彼女は懐かしさと共に、その記憶をたぐり寄せた。
だがどうしてもそこにいた《友達》の顔がぼやけて見え、明確に思い出せない。そのことに焦燥感を覚えつつも、確かにこの島に来たことがあるという感覚だけは鮮明だった。
夏目は展望台から景色を眺めながら、記憶の断片が次々に繋がっていくのを感じていた。
――そこにはアリアがいた。白いワンピースを纏い、天真爛漫に笑っていた彼女。だが、その隣にはもう一人、少し年上の男性がいた。
「アリア……君には兄がいたんだな」
夏目は自分でも驚くほど自然にその言葉を口にした。
「……はい。そんなことまで思い出せたんですね」
アリアはその言葉に微かに驚いた表情を見せたが、すぐに笑顔を作り直した。
「彼はどんな人だった?」
夏目がさらに問いかけると、アリアは少し視線を逸らした。
「優しい人でした。わたしをすごく大切にしてくれて。でも、それ以上のことは……思い出さない方がいいかもしれない」
その言葉に夏目はさらにアリアへの疑念を深めていた。
咲良は花園の方向を見つめながら、心の奥底に引っかかっていた感情が浮かび上がるのを感じた。
――そこには、泣きじゃくるアリアの姿があった。何かに傷つき、俯いて涙を流していた彼女。それを慰めようと近づこうとしたが、声をかけられず、ただ遠くから見ているしかなかった自分。
「アリアが……泣いていた。どうしてだろう」
咲良は呟く。
「何があったんだろう。何もしてあげられなかったのかな……」
彼女は拳を握りしめ、悔しげな表情を浮かべた。
アリアは三人の様子を静かに見守っていた。彼女の表情にはどこか悲しみと安心感が交じっているようだった。
「少しずつ、皆さんの記憶が戻ってきているのね」
「アリアさん、あなたのお兄さんって……いま、この島にいるの?」
未美はアリアの顔を見つめて思いきって問いかけてみた。
「いえ……もう……ずっと昔にいなくなってしまいました」
アリアは小さく微笑みながら首を横に振った。
「それって、どういう意味?」
咲良が鋭く追及しようとしたが、アリアはそれ以上何も語らなかった。
風が強く吹き抜け、展望台の木々がざわめく音が響いた。その音に混じり、どこか遠くからかすかな囁き声が聞こえたような気がした。
一本道と相馬は怪物の群れとの遭遇の後、バンガローへの帰路を急いでいた。
相馬は包丁を握りしめたまま、不機嫌そうに地面を蹴る。
「結局、逃げて帰ってきただけじゃねぇかっ!」
相馬が苛立たしげに言った。
「そりゃそうだよ。あんな奴ら、普通の手段じゃどうしようもないよ!」
一本道は肩をすくめて言い返す。
「でもよ……あいつらの声、どういうことなんだ?テレパシーみたいに頭に響いてきやがった。島を侵すなとか言いやがったが……どうするよ?」
相馬は眉をひそめ、足を止めた。
「あれが本当なら、これ以上島を探索するのは危険だよ。でも……なにかがあるのは確かだ」
一本道も同じく足を止め、真剣な表情を浮かべた。
#12
夏目は展望台の手すりに寄りかかりながら、じっとアリアを見つめ、低い声で問いかけた。
「アリア、君のお兄さんとぼくには、何か関係があったのか? 今度こそなにも隠さず教えてほしいんだ」
アリアはその質問に、少し躊躇したように目を伏せた。
風が彼女の白いワンピースを揺らし、微かな沈黙が場を包む。
「……夏目さんと兄は、とても似ているところがあったわ」
彼女はようやく口を開き、静かに語り始めた。
「二人とも、本当に優しくて……でも、時々少しだけ冷たいところもあって」
「冷たい?」
夏目は眉をひそめた。
アリアは淡い笑みを浮かべたまま答えた。
「兄は、わたしを守ろうとしてくれる人だった。でも、そのために誰にも心を開こうとしなかったの。夏目さんも……たぶんあの頃はなにか抱えていたんじゃないかしら」
「それが君とぼくの兄さんを結びつける理由だと?」
夏目は納得がいかない表情で尋ねるが、アリアはそれ以上は語らなかった。
未美はアリアが少し悲しげな表情をしているのを見て慰めたい気持ちで優しい声で尋ねた。
「ねぇ、アリアさん。今からなら花園のほかに行くべき場所ってあるかな?」
アリアはその言葉に小さく首を振った。
「今日はもう遅いから、これ以上はやめておいたほうがいいわ。この島の夜は少し……危険かもしれないから」
「そう……。わかったわ」
未美は少し残念そうに頷いたが、もう一つの疑問を投げかけた。
「でもさ、わたしたち全員、サマースクールで一緒だったんだよね?」
「ええ、そうよ。皆さんとわたし、そして兄も……あの夏を一緒に過ごしたの」
アリアはその質問には正直に頷いた。
「やっぱりそうなんだ。なんだか、少しずつ思い出せそうな気がする」
その言葉に未美は改めて深い懐かしさを覚えた。
「アリア……わたし、あなたが泣いている記憶を思い出したの。あなた、あの時どうして泣いていたの?」
咲良は、花園の方を見つめながら静かに口を開いた。
「……それは……ただ、皆さんとのことで……少し……」
その質問に、アリアの表情が一瞬で曇った。彼女は答えることを躊躇し、少し俯いてしまう。
「少し、じゃないよね。泣かせたのは、わたしたちなんでしょ?」
咲良はアリアの曖昧な態度に苛立ちを覚え、さらに追及する。
アリアは目を伏せたまま、何も言い返さなかった。
その沈黙の中で、咲良の記憶が急に鮮明になっていく。
――サマースクールで過ごしたある日、アリアに対して自分や未美、一本道が冷たく当たっていた場面。嫉妬や誤解から彼女を責め立て、その結果、アリアが耐えきれずに涙を流した光景。その結果、アリアを孤独な存在にしてしまったことを……
「わたしたち、最低だ……あのとき、わたしたちがあんなことしなければ……」
咲良は顔を覆い、震える声で呟いた。
そして、なぜか未美もまたその言葉に心を揺さぶられ、同じような罪悪感を覚えていた。
「アリアさん……本当にごめん……」
未美も小さく声を漏らした。
「大丈夫よ。あれは、わたしが弱かったから……。みんなのせいじゃない」
アリアは二人の言葉を聞き、かすかに微笑みを浮かべた。
だが、その微笑みはどこか儚く、彼女の言葉が真実かどうかはわからなかった。
展望台の上で風が再び吹き抜け、彼らの沈黙を包み込んだ。
#13
一本道と相馬は肩を落としながらバンガローに戻ってきた。
ネズミの怪物との遭遇による警告が二人の心に重くのしかかり、会話はほとんどなかった。
相馬がバンガローのドアを開けると、アリアと共に未美、夏目、咲良の三人がすでに帰宅していた。
「相馬さん、一本道君、おかえりなさい!何かあった?」
未美がすぐに声をかけた。
「おう、あったとも……変なネズミの怪物にな。しかもたくさん」
相馬が苛立たしげに言いながら椅子にどっかりと腰を下ろした。
「ネズミの怪物? たくさん……やっぱり他にもいたんだ!」
咲良が身を乗り出す。
「……それ、本当に危険じゃないの?」
未美は不安そうに声を震わせた。
「ああ、こいつはかなりヤバいかもな」
相馬は虚ろな目で言った。
そこで五人はきょうあったことを話しておくことにした。なにかこの島の謎についてのヒントが得られるかも知れないからと。
「わたしたちは展望台に行ったの。すごく綺麗な景色で、花園が少し見えたわ。でも、今日はそこまで行くのはやめておこうってアリアさんが言ったから」
まずは未美が話を切りだした。
「それに……わたし、思い出したの。高校生の頃、ここでサマースクールに参加してたことを。アリアさんも、みんなも一緒だったんだよね?」
「そうよ。わたしたちはあの夏、一緒に過ごしたの」
アリアは微笑みながら頷いた。
つぎに夏目は腕を組んだまま静かに話し始めた。
「展望台では、ぼくも記憶が蘇った。アリアには兄がいたことを思い出した。どうやらぼくと彼には何か共通点があったらしい」
咲良も俯きながら口を開いた。
「それから、わたし……アリアが泣いていた記憶を思い出したの。わたしたち、未美さんと一本道君と一緒になってアリアを責めてた……。本当にごめんね、アリア」
「そうだね……あの時のこと、わたしも反省してる。アリアさん、本当にごめん」
未美も小さく頷きながら言葉を添えた。
「気にしないで。あのときは、わたしも自分の気持ちをちゃんと伝えられなかっただけだから」
アリアはその言葉に微笑んで応えた。
そして相馬と一本道の話となった。
「おれたちはネズミの怪物に出くわしてさ……あいつらはおれたちに島を侵すなって警告してきた。普通じゃねぇよ」
相馬は包丁をちらりと見やりながら言った。
「そうなんだ。まるで頭の中に直接声が響くみたいで……危ない感じがした。でも、攻撃はされなかったのが幸運だったよ」
一本道も補足した。
全員の話が終わると、アリアが穏やかな声で語りかけた。
「皆さん、それぞれの記憶が少しずつ戻ってきているのね。この島には、きっと皆さんにとって大切な答えが隠されていると思うの」
彼女の言葉に探索者たちはそれぞれ複雑な表情を浮かべた。
#14
そうして夜は静かに更けていき、バンガローの中は月明かりに照らされていた。
バンガローのランタンが揺らめくなか一行はそれぞれの記憶を整理しようと静かな会話を続けていた。
「ねぇ、どうしてわたしたちがアリアさんを責めたのか、その理由を思い出せる?」
未美はアリアと咲良に向き直り、口を開いた。
その言葉に咲良は少し黙り込み、視線を落とした。まるで記憶の奥底に封じ込めていた感情を手繰り寄せるように、ゆっくりと答えた。
「……嫉妬……だったのかな」
咲良は小さな声で呟いた。
「なんでか分からないけど、アリアが夏目さんと仲良くしてるのが、すごく気に入らなかった。あの時は、自分でも訳が分からなくて……」
「そう……わたしも、なんとなくそんな感じだった気がする。アリアさんがとても楽しそうにしてるのが、なんか悔しかったのかも……」
未美もその言葉に少し表情を曇らせた。
「皆さん、あの頃はまだ子どもだったし……そんな気持ちになるのも無理はないわ」
アリアは優しい目で二人を見つめ、小さく微笑んだ。
一方で夏目はアリアの兄についての記憶をたどろうとしていた。瞼を閉じ、展望台で感じた断片的な記憶を思い返す。すると、ある光景が鮮明に浮かび上がる。
――夏目はサマースクールの指導員バイトとしてこの島に来ていた。そこでアリアの兄と相馬が同じ指導員仲間だったこと。三人で滝や展望台に参加者たちを案内し、和気あいあいと過ごした日々がよみがえる。
「そうだ……ぼくと相馬とアリアの兄、三人はサマースクールの指導員だったんだ」
夏目は静かに呟いた。
「おい、それ本当かよ?おれもバイト仲間だったのか?」
相馬が顔を上げる。
夏目は頷きながら記憶を整理するように話し続けた。
「ああ。君とぼく、それにアリアの兄で、参加者たちの面倒を見てた。……でも、どうしてその記憶が抜け落ちていたのか」
夏目の言葉を聞いていた未美は、ふと胸がざわつくのを感じた。彼の言葉が自分の記憶の扉を開けるきっかけとなったのだ。
――高校生だった未美は、サマースクールで指導員の夏目に憧れていた。彼の知的で冷静な態度に魅了され、少しでも近づきたいと願っていた。
しかしアリアが夏目と親しく話しているのを目にするたびに嫉妬の感情が湧き上がった。そしてその嫉妬が中傷めいたアリアを責める行動へと繋がってしまった。
「あの頃のわたしは……夏目さんに憧れてて……それでアリアさんを責めてたんだ……」
未美は顔を手で覆い、小さく呟いた。
その言葉に咲良も驚いた表情を見せたが、何も言わずに黙っていた。
「おい、おれは君を泣かせたことはないよな?」
相馬はアリアの方を見て空気を読まず唐突に尋ねた。
「ええ、相馬さんはいつも優しかったわ。……ただ、少し遠くから見守ってくれていただけだったけど」
アリアはその言葉に少し困ったような顔を見せたが、小さく頷いた。
「そりゃ良かった。少なくともおれは責められる理由はねえよな」
相馬は大きく安堵の息をつき、椅子にもたれかかった。
それぞれが記憶の断片を取り戻し、胸に複雑な感情を抱えたまま、バンガローのなかは静けさを取り戻していた。外では風が強くなり、窓越しに揺れる木々の影が不気味に映り込む。夜の気配が濃厚になていく。
#15
「アリアさん、ぼくはなぜ君を責めたんだい? 自分でも思い出せないんだ」
一本道は堪えかねたように静かにランタンの灯りに照らされるアリアを見つめ、低い声で問いかけた。
アリアはその言葉に反応せず、視線をそっと下げたまま沈黙を貫いた。
その微かな沈黙が、一本道の胸に妙な不安を募らせた。
その瞬間、記憶の断片が彼の頭をよぎった。
――咲良に密かに好意を抱いていた自分。その彼女がアリアを責めるのを見て、少しでも彼女の側に立ちたいと感じたこと。そして、その結果、アリアに冷たく当たってしまったこと――
「……そっか、ぼくはあのとき、自分の気持ちに振り回されてたんだね」
一本道は自分の中にある小さな後悔の感情を覚え、言葉を失った。
だれにともなく呟いたその声は静かなバンガローの中に吸い込まれていった。
「アリア、外で少し話さない? ふたりで」
重く沈鬱な空気が漂うなか咲良は席を立ち、アリアの方を振り返った。
アリアは少し驚いたように咲良を見つめたが、やがて微笑みを浮かべて小さく頷いた。
そのときちょうど未美は外の静かな夜を見つめ、ぼんやりとした頭を冷やそうとしていた。
過去の自分と今の自分が大きく乖離していることに、どうしても整理がつかなかったからだ。
しかし暗闇の中で何かが動く気配に気づいた。
目を凝らすと、無数の小さな光が木々の間からこちらを見つめている――それは、あのネズミの怪物たちのいやらしく光る目だった。
未美は息を呑み、すぐに皆に声をかけた。
「みんな!外を見て!あの目……たぶんネズミの怪物たちよ!」
その言葉に一同が窓辺に駆け寄り、外の様子を確認する。
確かに無数の光る目が、まるでバンガローを包囲するかのように潜んでいるのがわかった。
「いま外に出るのは危険だ……」
夏目が静かに言った。
「アリア……やっぱり外で話すのはやめた方がいいかも」
咲良も怯えた表情でアリアに言った。
「ええ、その方がよさそうね」
アリアも神妙な顔で答えた。
「仕方ねぇな。今夜はここに籠城するしかねえだろう。おれが寝ずの番をしてやるぜ。何かあったらすぐ起こしてやるよ」
相馬が包丁を握りしめ、椅子に腰を下ろした。
一本道はそれに安堵しながら「頼りになるね」と言い、小さなため息をついた。
普段はまったく図太く気ままな相馬が、このときばかりは頼もしく思えた瞬間だった。
第2章 花園
#16
夜が明け、バンガローの中に差し込む朝日が島の静けさを照らしていた。
窓の外を覗くと、夜中に無数の目が光っていた場所には、今は何の痕跡も残っていない。ただの草木が風に揺れているだけだった。
「ネズミの怪物たち、消えたみたいね」
未美が窓辺に立ちながら静かに呟いた。
他の者もそうだろうが、ほとんど一睡もしていない。
ひとまず脅威が去ったことに急に眠気と疲労がどっと押し寄せてきているのを感じていた。
「日の当たるところには出てこないのかもな。なら、今のうちに行動するしかねえだろ」
一方で相馬は元気溌剌、腕を組んで椅子に腰掛けながら言った。
それもそのはず不寝番をすると言っておきながら、深夜0時を過ぎた頃にはすっかり白河夜船だったのだから気楽なものだ。
「だったら花園に行きましょう。もうそうするときが来たんだと思うの。アリアさん、もちろん連れて行ってくれるわよね?」
未美は振り返り、みんなの顔を見渡した。
アリアは穏やかに微笑み、小さく頷いた。
他の者もめいめい肯いた。話は決まった。
「いまさらだけどアリア、いまの君はぼくのことをどう思っているんだ? 正直に答えてほしい」
道すがら夏目がアリアの隣に歩み寄り、少し躊躇いながらも低い声で問いかけた。
アリアは立ち止まり、少し考え込むように視線を伏せた。そして再び夏目を見上げ、はっきりとした声で答えた。
「以前の夏目さんは、わたしにとって頼れる年上の存在だったわ。尊敬してたし、いつも安心感をくれる人だった」
その言葉に夏目は少し表情を和らげたが、アリアは続けた。
「でも……恋愛感情はなかったわ、昔も今も……」
「そうか。いや、君が正直に答えてくれたことが嬉しいよ」
夏目はその答えに驚いた様子を見せることもなく、ただ静かに頷いた。
アリアは微笑み返し、再び歩き出した。
相馬もアリアの近くに歩み寄り、少し戸惑いながらも熱心に尋ねた。
「アリア、あの時のおれってどんな奴だった?」
アリアは歩みを緩め、相馬の方を振り返った。
「相馬さんは……とても信頼できる指導員だったわ。いつも一生懸命で頼りにされていたと思います」
相馬は少し得意気な表情を浮かべたが、アリアは続けた。
「でも、あまり個々の参加者には関心を持たない人だったかもしれません。みんなの安全を守ることに集中していて一人ひとりに深く関わろうとはしなかったように見えました」
「そっか……まぁ、確かにおれっぽいよな」
相馬は考え込むように顎に手を当てた。
道中の会話を経て、一行はついに花園の入口と思われる場所に辿り着いた。
木々の間 に広がる広大な空間には、色とりどりの花々が咲き誇り、鮮やかな光景が目に飛び込んでくる。
しかし、どこか不穏な空気も漂っていた。風が吹き抜けるたびに花が微かに震え、囁き声のような音を立てている。
「ここが……花園……?」
未美が目を輝かせながら足を止めた。
「確かに夢で見た通りだわ」
咲良が息を呑むように言った。
「でも、この場所……普通じゃないな」
夏目は慎重に辺りを見渡しながら、静かに言った。
アリアは皆を振り返り、少し緊張した表情で口を開いた。
「ここから先、気をつけて進んで。花園は、わたしにとっても特別な場所だから」
#17
色鮮やかな花々が咲き誇る花園に、一行は立ち尽くしていた。それぞれがこの場所の異様さに触れ、何かを感じ取っていた。
未美は周囲の様子を伺うために耳を澄ませた。
風が花々を揺らす音に混じって、微かに低い囁き声のような音が聞こえる。耳にまとわりつくようなその音は、人の声とも風の音ともつかない、不気味な響きを持っていた。
「何かいる……?」
未美は周囲を見回しながら、小声で呟いた。
「アリアさん、この場所が特別だって言ってたけど、それってどういうこと?」
さらにアリアの方に顔を向けて問いかけた。
アリアは少し表情を曇らせながら答えた。
「この花園は、わたしの記憶や存在そのものと深く結びついている場所なの。だから、皆さんがここにいることで……何かを感じるかもしれない」
その曖昧な言葉に、未美はさらに疑念を抱きつつも追及は控えた。
咲良と一本道は目の前の美しい花々にすっかり目を奪われていた。
「すごいわ……こんなに綺麗な場所があるなんて」
咲良はスマートフォンを取り出し、写真を撮り始める。
「本当にここ、夢みたいだな」
一本道も周囲を見渡しながら、深く息を吸い込んだ。
だがふたりとも次第に違和感を覚え始めた。
花々は確かに美しいが、何かが普通の花園とは異なっている――それは花の形が少し不自然に感じられること、色があまりに鮮やかで現実感がないこと。
そして時折、花々が微かに動いているように見えることだった。
「……これ、本当に普通の花なのかな?」
咲良は写真を撮る手を止め、小声で呟いた。
「アリア、君の姿はあの夏の記憶から成長していない。どうしてだ?君は本当に“生きた人間”なのか?」
夏目はアリアの隣に立ち、低い声で問いかけた。
その問いにアリアはしばらく黙り込んだ。
瞳を伏せ、何かを考え込むような仕草を見せる。
そしてゆっくりと顔を上げ、夏目を見つめながら答えた。
「……わたしは、皆さんと同じような存在ではないのです」
「君がそれを自覚しているなら、どうしてここにぼくたちを連れてきたんだ?」
夏目の表情が一瞬で険しくなった。
アリアは答えず、ただ静かにその場を動かず立ち尽くしていた。
相馬は周囲の花々を一心不乱に観察していた。
「普通じゃない部分があるはずだ……」
彼は目を細め、花の影や茂みの隙間まで注意深く見て回る。
そのとき、ある花の影に微かな動きを捉えた。
茶色い小さな生き物――それはまたあいつらの影だった。
光る目がこちらをじっと見ており、次の瞬間、花の間に潜り込むようにして姿を消した。
「おい……あのネズミの怪物が、ここにもいやがるぞ!」
相馬は包丁を握り直し、全員に警告を発した。
「またあの怪物?」
咲良が驚きの声を上げる。
未美も警戒しながら辺りを見回す。
「アリア、あの怪物の存在もこの場所と関係しているのか?」
夏目は険しい表情を浮かべ、アリアを睨むように問いかけた。
「彼らはこの花園の園丁、花を慈しみ育てているものたち……」
アリアは少し悲しそうな表情を浮かべながら答えた。
#18
一本道は花園に咲き誇る不気味な美しさを持つ花々をじっと見つめ、冷静に観察し始めた。彼の目は、自然界ではあり得ない違和感に気づき始める。
――花々は風に揺れるように見えるが、その動きは風と無関係だ。それどころか、まるで独自の意志を持っているかのように蠢き、形を変え続けているようだった。そして花びらの色は、現実世界では見たことのないほど不自然に鮮やかで、まるで幻影のようだ。
「これは……この世界の花じゃない。断言できる」
一本道は小さな声で呟いた。
「自然界ではこんな花は存在しないし、動いているのは絶対におかしい」
彼はその異様な光景に背筋を寒くしながらも、足が震えてその場を動けなくなっていた。
咲良は不安そうに辺りを見回しながら、ネズミの怪物に備えるため、武器になりそうなものを探し始めた。
「何か……何か役に立つものがあれば……!」
彼女は目星をつけた場所を掻き分けてみるが、手に取れるものはどれも頼りないものばかり。
「これじゃ……あまり役に立たないかも」
ようやく地面から大きめの小石を拾い上げると、握りしめながら深いため息をついた。
未美はアリアに向き直り、真剣な表情で声をかけた。
「アリアさん、この花園の先に進みましょう。きっとそこに答えがあるはず」
「でも、その先は……危険かもしれないわ」
アリアは少し怯えたような表情で首を振った。
「危険でも構わない」
未美は毅然とした態度で言い放った。
「もしアリアさんが行かないなら、わたし一人でも行くわ」
その強い意志に、アリアは動揺しながらも何も言えなかった。
そんな未美の言葉を聞きながら、夏目は一歩前に出て、アリアに手を差し出したのだった。
「アリア、君はここに留まる必要なんてない! こんな場所から逃げよう」
アリアは夏目の手を見つめ、表情を曇らせた。
「でも、わたしは……」
「ぼくは君を助けたいんだ」
夏目は真剣な目で彼女を見つめた。
「ここにいる限り、君は自由になれない気がする」
アリアは迷いを浮かべた表情で、夏目の手と未美の背中を交互に見つめていた。
「おれは何があってもアリアを守るからな。それがどっちの選択だろうが関係ねぇ」
相馬は包丁を握り直し、どっしりとした態度で皆を見渡した。
「ありがとう、相馬さん」
その言葉にアリアは少し微笑んだ。
アリアが進むべきか逃げるべきかで躊躇しているその時、不意に花々の間から黒いローブを纏った人物が現れた。
彼は長身で痩せた体格をしており、白髪交じりの髪と鋭い目つきが印象的だった。

「皆さん、ようやくここまで来てくれましたね」 低い声で話しかけてくる。
刹那、一同はその顔を見た瞬間、記憶の奥底に眠る感覚が呼び覚まされた。
「きみは……! サマースクールの時の指導員……アリアのお兄さんの――」
夏目が驚きの声を上げた。
「ついに記憶を取り戻したようだね、夏目くん。そうだ、わたしはアリアの兄、佐伯洋介。そしてみなさんがここに来るように運命づけたのも、このわたしだ」
男は微かに笑みを浮かべた。
「運命……?」
咲良が警戒した表情を浮かべる。
「みなさんには、ここである選択をしていただかなければならない」
洋介は冷静な口調で続けた。
「それがこの楽園の、そして我が愛しき妹の未来を決めることになるのですから」
#19
「選択ってなんなんですか!」
未美は一歩前に出て、アリアの兄・佐伯洋介を真っ直ぐに見つめる。
すると洋介はその問いに薄く微笑み、ゆっくりと口を開いた。
「わたしは、この楽園を守る者、そして花園の管理人。そして選択とは、あなたたちがこの場所で過去とどう向き合い、どんな未来を選ぶかということ」
彼の言葉には不気味な静けさが漂い、花園の囁き声が一層強まったように感じられる。
「過去と向き合う?」
未美は首を傾げながら聞き返す。
「それは……わたしたちがアリアさんとの記憶を取り戻すこと?」
「その通り。そして、その記憶が戻った時、あなたたちは自分自身の心に問いかけることになる。この楽園を守るか、それとも終わらせるかを」
洋介は微かに頷いた。
そんななか夏目は洋介とアリアの間に立ち、アリアの手を掴んだ。
「アリア、こんな話に付き合う必要はない。ぼくたちと一緒にここを離れよう」
夏目は低い声で言いながら、彼女を促した。
アリアは驚いた表情を見せたが、夏目の真剣な目に引き込まれ、ゆっくりと頷いた。
「……でも、本当にそれでいいの?」
「いいんだ!」
夏目はきっぱりと言い切り、洋介と対峙した。
「彼女をこんな場所に縛りつけるのは間違っている!」
洋介は微かに目を細めたが何も言い返さなかった。
「さあ、行こう」
夏目はアリアを連れて花園の外へ向かおうとした。
だが、その時だった。
花々の間から無数の小さな影が飛び出してきたのはネズミの怪物の群れだった。
「なんだ、またあいつらか!」
相馬が包丁を構え、即座に前に出た。
怪物たちは鋭い目で夏目とアリアを睨みつけ、花々の間を這い回りながら道を塞ぐように展開していく。まるで、アリアを花園から出させまいとしているようだった。
「これは……わたしのせいなの……」
アリアは怯えた声で呟いた。
「で、どうするの?」
咲良が手に持った小石を握りしめ、周囲を見渡す。
「このままじゃ出られないよ……」
一本道も怯えながら言葉を漏らした。
怪物たちは直接攻撃を仕掛けてくるわけではなく、テレパシーで頭に響く声を送りつけてきた。
『……侵すな……守れ……戻れ……』
その声は不快で、まるで頭を締め付けるように響く。
洋介はその光景を見ても慌てることなく、冷静に声を上げた。
「彼らはこの花園を守る忠実なる園丁ズーグ。彼らの爪と牙から逃れることはできないよ。それに妹をこの楽園の島から出すことは、この花園と妹の崩壊を意味することだぞ。妹は花園に生かされ、花園は妹を生かされている。この因果は断ち切れぬのだ」
その問いに、夏目はアリアを守るように前に出た。
「ぼくたちは彼女を縛るためにここに来たんじゃない。彼女を自由にするためにここに来たんだ」
「ならば、その覚悟を見せてもらおうか」
洋介は微かに笑みを浮かべ、頭を振った。
#20
ネズミの怪物――ズーグたちの群れに囲まれ、緊張が高まるなか未美は冷静さを保ちながら、洋介に向かって声を張り上げた。
「洋介さん、わたしたちにちゃんと説明して! いったいこの《楽園》ってなんなの? アリアさんはいったい……? それに、わたしたちになにがあったのかも――全部教えて!」
その言葉に、洋介は一瞬だけ視線を下げた。そして再び顔を上げると静かに語り始めた。
「この楽園は、アリアの存在を維持するために生まれた場所だ」
洋介はそう切り出し、手に持つ杖を軽く地面に突き立てた。
花園の周囲が微かに震え、囁き声が一層強まる。
「十年前、君たちがサマースクールでこの島に来たとき、アリアはここで……死んだ。海岸で溺れかけていた子どもを独りで助けようとして自分が海で溺れてしまった……」
その言葉に、一同は息を呑んだ。
だれしもがアリアを独りにしてしまったのが自分のせいであるという自責の念を拭えなかった。
あのとき、アリアを責めなければ……あるいはやさしい言葉のひとつでもかけてあげられていれば彼女は独りで行動することはなかっし、溺れている子を見ても助けを呼びに走ったかもしれないのだ。
しかしアリアにその選択を強いた責任は自分にあると思ってしまった。
「だが、わたしはアリアを失うことに堪えられなかった。だから君たち――彼女と深く関わった人々の記憶を糧にすることでアリアを蘇らせたのだ」
「記憶を糧に……?」
未美は驚きの声を上げた。
洋介は静かに頷いた。
「君たちの記憶が、この花園を通じて妹を支えている。だから君たちがこの場所に呼ばれたのだ。楽園はその記憶を循環させるための装置のようなもの。しかし十年の時を経て記憶の力はすっかり弱まってしまったのだ。だから再び君たちに協力してもらうために、ここにやって来てもらうことにしたのだよ。妹の持つ夢の力でな」
洋介は少しアリアを見つめた後、さらに続けた。
「そうだ、妹はもう完全な《生きた人間》ではない。その命はこの花園に依存している。この花園がなければ彼女は生きていられぬのだ」
アリアはその言葉に目を伏せ、何も言わなかった。
その沈黙が彼女自身の認識を肯定しているようだった。
「十年前、わたしたちになにがあったの?」
未美はさらに問い詰めた。
洋介は少しだけ目を細め、静かに答えた。
「十年前、少しばかりの後悔を伴って妹の死を悼んでくれた君たちは妹を救うために自分の記憶、つまり大切な思い出――贄として差し出すことに同意してくれたのだ。過去の後悔、喪失の痛み――それを全て封じ込めることで楽園を維持することに貢献してくれた」
「洋介、君はそれを勝手に利用したってことか? そんなのは許されないことだぞ!」
夏目が声を荒げた。
「勝手ではない。十年前の君たち自身がそれを心から望んだのだよ。妹との美しい思い出を失えば、心の痛みも失われる。なによりたいせつな友を再び取り戻せるとな」
洋介は冷静に反論した。
「つまり、わたしたちは過去の記憶を捧げる代わりに、アリアを《救った》つもりだった。それで……この花園が、楽園が生まれたのね」
未美はその説明を聞いて深く息をつき、複雑な表情を浮かべた。
洋介は微かに頷いた。
「そうだ、未美くん。わたしが魔術の心得があったからこその成果だけどね。そしていま君たちが再び選択を迫られているのだ。この楽園を維持するか、終わらせるかのね。そう、君たちの記憶を再び妹のために捧げてもらいたいのだ」
「わたしは……みんなの記憶を、かけがえのない思い出を奪ってまで生きていたくなんてなかった。でも……兄さんが……いえ、もう兄さんの形をした何かがそうさせているのです……」
アリアは視線を宙に彷徨わせながら微かにつぶやいた。
「おお、そんな哀しいことを言わないでおくれ、愛しき妹よ。おまえがここにいることが、わたしにとっての唯一の救いなのだから」
洋介は優しい目でアリアを見つめた。
#21
「……なんだよ、これ……どうすりゃいいんだ……」
ズーグたちの不気味な囁き声が響くなか相馬は呆然と立ち尽くし、額から汗が滲み出している。
その大柄な体躯からは想像もつかないほど怯えた様子がありありと見てとれた。
未美は洋介の語る未知の知識、そして彼が持つ力に強く心を引き寄せられているのを感じていた。
その落ち着いた態度、冷静な分析、全てを把握しているかのような振る舞い――それは彼女の探求心を激しく揺さぶっていた。
「……洋介さんは……本当にすごい人なんですね。どうして、こんなにも全てを知っているんですか?」
未美は思わず口にした。
洋介は少しだけ微笑み「必要があれば、どんな知識でも手に入れる覚悟があるからだ」と静かに答えた。
その言葉に、未美はさらに彼に惹かれる自分を感じていた。
一本道はというと、状況の緊迫感をまるで無視するように、唐突に洋介に向き直った。そして自分ですら信じられない言葉を口にしていた。
「……あの、もしぼくを高給の超ホワイト企業に就職させてくれるなら、あなたに従います!」
その場にいた全員が一瞬沈黙し、ズーグの囁きさえも止まったかのように思えた。
洋介は少し驚いた表情を見せたが、すぐに淡々と答えた。
「君の未来を変える力を与えることはできる。ただし、それがどのような結果を生むかは保証できないがね」
一本道はその言葉に小さく頷き、焦ったように言葉を続けた。
「いや、それでもいいです!ぼく、どうしてもまともな職場に就きたいんです!」
「なに言ってるんだ、一本道くん!」
夏目が叫んだ。
「ぼくは……ぼくはどうしても就職しなくちゃいけないんだよ!」
一本道の狂気にも似た就職の執念、それは花園の毒気にやられたとしか思えない発言だったが、それこそが彼の本心だったにちがいないのだと一同は理解できた。
「それで、この花園を維持するために、具体的にわたしたちにどうしろって言うの?」
咲良は冷静を保とうとしながらも、洋介に真剣な表情で問いかけた。
「簡単なことだ。楽園の維持には君たちの記憶が、存在が不可欠だ。かつては妹との美しい思い出が力の源となったが、いまやきみたちと妹の絆は弱く細い。そのためにこの島で妹との絆を保って暮らしてもらわねばならぬ。もし君たちがこのまま島を離れれば、遠からずこの花園は崩壊し妹も露と消えてしまう」
「……やっぱりね。そうなるのね」
咲良はその答えに顔を曇らせながら呟いた。
その沈黙を破るように、夏目がアリアの手をしっかりと握り締めた。そして深く息を吸い込みながら語りかけた。
「アリア、十年前……ぼくは君を助けられなかった。本当にすまない」
「夏目さん……」
アリアはその言葉に驚きながらも、微かに目を潤ませた。
「でも、今度こそは助ける!」
夏目は決意に満ちた声で言い切った。
そしてズーグの包囲を破るため、アリアを連れて突進を試みた。
「待て!」
洋介の静かな声が響くが、夏目は振り返らずに突き進んだ。
するとズーグたちは俊敏に一斉に動きだし、夏目たちの行く手を阻むように花々の間から飛び出してきた。小さな体で素早く動き、彼らを取り囲むように跳び回る。
「くそっ……!」
夏目は懸命にアリアを守りながら進もうとするがままならない。
『戻れ……花園を侵すな……』
ズーグたちの囁き声が再び頭に響く――
#22
「もし、わたしだけでも、この島に残ったら、わたしや洋介さん、そしてアリアはどうなるの?」
未美は洋介に真剣な眼差しを向け、静かに問いかけた。
洋介は一瞬ためらいを見せたが、やがて静かな声で答えた。
「君が残れば、ひとまずこの楽園は維持されるだろう。妹は万全とはいかないだろうが数十年はまた《かたち》を保つことができる。だが……君自身は、楽園の一部となり、外の世界での人生は失うことになるだろう。それがこの楽園の代償だ」
彼の目には、決意に満ちつつも悲しげな光が宿っていた。
そんな洋介に未美は唇を噛み、どうしようもなく心が揺れるのを感じていた。
「ま、待ってよ! 島に残らなきゃいけないってことは……就職なんて無理じゃないか……!」
一本道は洋介の言葉を聞いて顔を覆った。
その現実に打ちのめされ、呻くように言葉を漏らす。
「……無理だ、こんな人生、おれには耐えられない!」
彼は突然顔を上げ、夏目に駆け寄った。
「夏目さん!おれ、やっぱり洋介さんには従えない!一緒にネズミどもを突破しよう!」
「ありがとう、一本道くん。君の勇気はきっと未来を切り拓くぞ」
夏目は一本道の決意を聞いて、やや呆れながらも頷いた。
そして夏目は少し微笑みながら付け加えた。
「おれのコネで出版社の仕事を斡旋してあげようじゃないか!」
「マジですか!夏目さん、ありがとうございます! ぼく、死ぬ気でがんばりますっ!」
その言葉に一本道の目が輝きを取り戻し、力強く頷いたのだった。
そして夏目と一本道は力を合わせ、ズーグたちの包囲を突破しようと試みた。
しかし小さな体で素早く動くズーグたちは執拗に攻撃を仕掛けてくる。
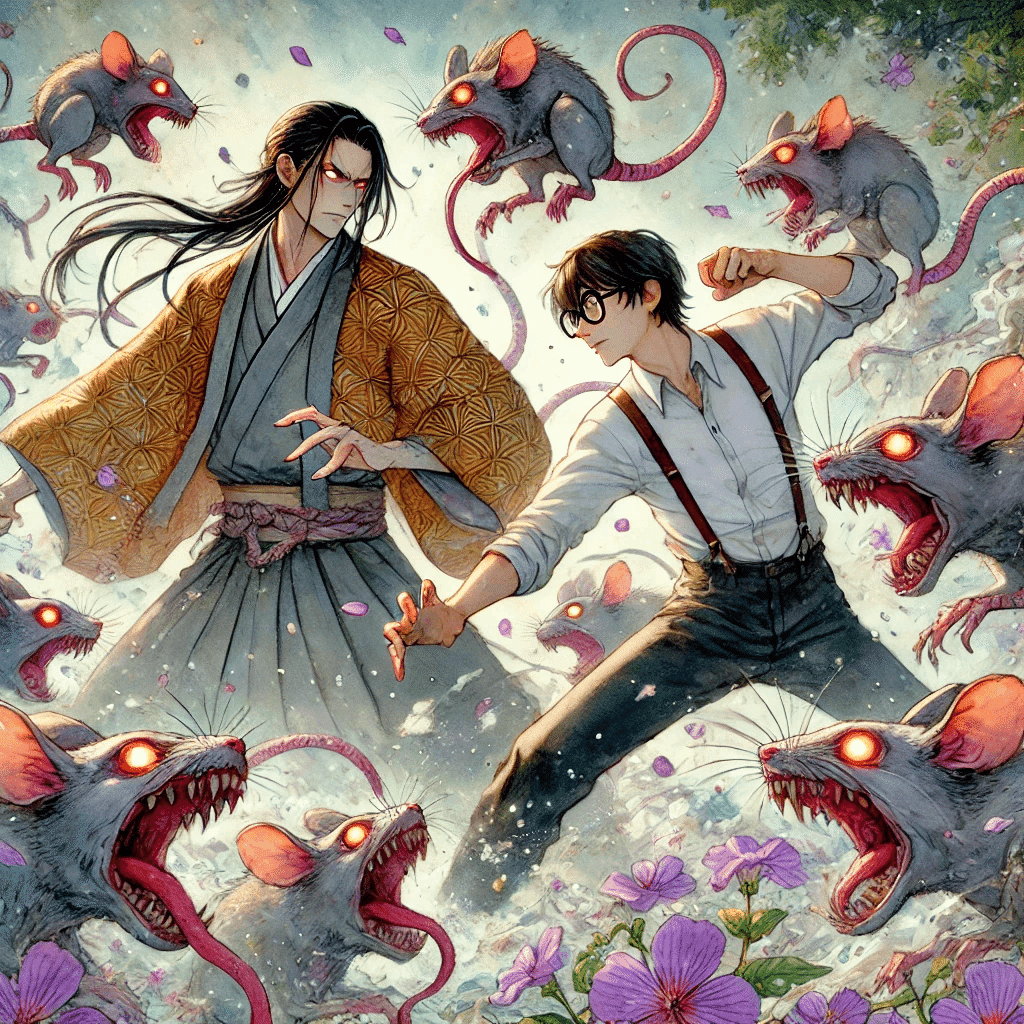
夏目は鋭い牙で足を噛まれ、呻き声を上げながらもアリアを守り抜いた。
一本道もまた爪で腕を切り裂かれ、血が滲むのを感じながら戦った。
ズーグたちの数をいくらか減らしたが、やつらの数はきりがない。数百……いやもっといるのかもしれない。
ズーグの数を減らす以上にふたりの体力も徐々に奪われていく。このままではジリ貧だ。
その時だった。
いきなり相馬が震える手で包丁を握りしめ洋介を鋭い目で睨みつけた。
「お前が全部の元凶なんだろう……!」
怒りの形相で相馬は全力で包丁を投げつけた。
包丁は洋介の腹部に突き刺さり、彼は短い呻き声を上げながらよろめいた。
「ぐっ……! よくも……しかしまだ……」
洋介は膝をつき、苦痛に顔を歪めながらも冷静さを失わなかった。
「洋介さん、しっかりして!」
洋介の負傷を目の当たりにした未美は、胸の中で渦巻く感情に突き動かされ、無意識のうちに彼の元に駆け寄っていた。
彼女は看護師として迅速に応急手当を施し、傷口を丁寧に処置していた。彼女自身も信じられない思いながら手は止まらない。
「ありがとう……未美さん……」
洋介は痛みに耐えながら静かに感謝を述べた。
「おい、宇佐木! なんで、そいつの味方なんてしてるんだよ?」
まったく信じがたいと言った表情で相馬が未美を睨みつけていた。
「わからない……わたし……どうしてこんなこと……」
未美は自らの行動にすっかり動揺してしまっていた。
今まで傍観していた、咲良は助けを求めるように外に向かって声を上げた。
「ねえ、黒猫さん!聞こえてたら、お願い! 助けて!」
それは一縷の望みを賭けた心の叫びだった。どうしてもこの場から助かりたい、その一心だったのだ。
花園に一陣の風が撫でていくも、なにも怒る気配はしなかった。
「だめか……そんな、都合よすぎるわよね、こんなときだけ……」
咲良が諦めかけたその刹那、草陰からのっそりと姿を表したのは黒猫だった。
「にゃあお」
黒猫は億劫そうに鳴いた。
「来てくれた……!」
咲良は歓喜して、希望を見出したように微笑んだ。
鋭い目でズーグたちを睨みつけた黒猫はゆっくりとズーグたちに向かって歩み寄り、しゃあっと唸り声を上げる。
それに反応するように、ズーグたちは次第に怯えた様子を見せ始めた。
#23
未美は洋介の隣に立ち、静かな声で問いかけた。
「わたし、アリアちゃんのために、この島に残ってもいいよ。でも自分の存在が消えてしまうのは嫌なの。もしあなたたちとこの島で静かに暮らせるなら、わたしはあなたに従うわ」
洋介はその言葉に少し驚いた表情を見せたが、すぐに真剣な顔に戻り、静かに答えた。
「心配ない。君の存在が消えるわけではない。ただ外の世界での君の人生は失われるだけだ。ここで妹と共にわたしと暮らそう」
未美はその答えにしばらく考え込んだが、迷いの色を隠せなかった。
「くそどもがっ! どいつもこいつもどうなってやがる! 勝手放題に! もう無理だって。こんなところで死にたくねぇっ!!」
いきなり顔を真赤にした相馬が突然声を荒げた。
彼は感情に任せるまま包丁を放り捨てるや、混乱した様子で花園から逃げ出そうと無我夢中で走り出したのだ。
「おい、相馬っ!」
夏目が驚いて叫んだが、相馬は振り返ることなかった。
ズーグたちは相馬を追おうとしたが、黒猫の鋭い威嚇に怯え、動きを封じられてしたため反応が遅れてしまったのだった。
一心不乱に脱兎のごとく走る相馬は一瞬の隙を突いて、まんまと花園を抜けて暗闇の中へと消えていったしまったのだった。
「お願い! ネズミの怪物を倒して!」
咲良は黒猫を見つめ、必死に頼み込んだ。
しかし黒猫は鋭い目でズーグを睨むだけで、直接的な攻撃には出なかった。
その代わりズーグたちは黒猫の威圧感に押されて動きを鈍らせていた。
咲良は地面から拾った石をズーグに向かって投げたが、緊張のあまり手元が狂い、ズーグたちに命中することはなかった。
夏目はアリアの手を引き、ズーグの動きが鈍くなっている黒猫の方へと導こうとした。
「アリア、さあ、ぼくたちと一緒に来るんだ。あの猫が出口への道を知っているかもしれない。走って!」
一本道もその後ろを追いかけながら、アリアに問いかけた。
「アリアさん、いったいどうやったらここから脱出できるんですか?」
アリアは苦しそうな顔で答えた。
「兄さんを……魔術師になってしまった兄さんを倒すしかないの」
その言葉に一本道は躊躇いを見せて一瞬、足を止めたが、夏目は「迷っている暇はない! 行くぞ!」と声を掛けたことで再び走り出した。
ズーグたちが黒猫の威圧で動けないことを悟った洋介は、静かに杖を構えた。
そして、その先端から青白い光が放たれ、夏目と一本道を狙って放たれた。
「君たちがここを離れることは許されない」
光は鋭い閃光となり、夏目の肩を掠めた。
呻き声を上げながらも夏目は立ち止まらず、アリアを引っ張り続けた。
一本道も必死に追いかけ、逃げ道を探していた。
#24
混乱の中、夏目は立ち止まり、アリアの肩を掴んで真剣な眼差しで問いかけた。
「アリア、君自身はどうしたいんだ? 本当にこの楽園に残りたいのか? それとも、この歪んだ世界を解消すべく消える道を選びたいのか?」
その問いにアリアは驚いた表情を浮かべたが、やがて視線を落とし、言葉を探すように沈黙した。
「……わたしは……」
アリアは震える声で言葉を紡ぎ始めた。
「楽園はわたしに命を与えてくれる場所。でも……みんなをここに縛りつけていることが正しいとは思えない……」
涙が彼女の頬を伝い落ちる。
「わたしは、この歪んだ世界を終わらせたい……」
その言葉に夏目は深く頷き、優しく彼女の肩を叩いた。
一本道はアリアの言葉を聞き、胸の中で迷いが渦巻いた。しかし彼はアリアの決断に寄り添うことを心に決めた。
「……アリアさんがそう思うなら、ぼくも協力するよ」
一本道は静かに答えた。
「たとえそれがどんな結果を生むとしても……ぼくたちで解決しなきゃいけないんだろう?」
その言葉には迷いを断ち切るような強さがあった。
咲良は黒猫のそばにしゃがみ込み、真剣な表情で話しかけた。
「ねえ、お願い。わたしを助けて。家族がいるの。たいせつな家族の元に戻りたいのよ」
黒猫はじっと咲良を見つめていたが、やがて小さく尻尾を振り、歩き始めた。
まるで「ついて来い」と言わんばかりの仕草だった。
「ありがとう……!」
咲良は立ち上がり、黒猫の後を追った。
一方で未美はその混乱の中で密かに包丁を拾い上げ、服の中に隠していた。
彼女の表情には、まだ決断しきれない迷いと不安が混在していたが、同時に何かを覚悟したような影もあった。
「何があっても、わたしは自分で選ぶ」
彼女はそう心に決め、誰にも気づかれないように包丁を握りしめた。
第3章 決意
#25
相馬は混乱と恐怖の中、花園を後にして一目散に走り続けていた。
「おれはここから逃げる……絶対に!」と呟きながら、汗だくの顔を拭いもせずに足を止めない。
島の海岸線に辿り着いた相馬は、辺りを見回しながらボートを探し始めた。
しかし運に見放された相馬はボートらしきものはどこにも見つけられない。
「……くそっ、なんで何もないんだよ!」
彼は拳を砂浜に叩きつけ、苛立ちを募らせた。
「……なら泳ぐしかねえ」相馬は立ち上がり、荒れる海を見据えながら自分に言い聞かせるように呟いた。
だが波立つ海は暗く深い色をしており、対岸すら見えない広がりに、相馬は一歩踏み出すのをためらった。
冷たい風が肌を刺し、海から漂う塩の匂いが彼の決意を揺るがす。
「本当に……泳いで行けるのか……?」
彼はその場に立ち尽くし、海の向こうを見つめたまま動けなくなった。
恐怖と現実感が彼の足を縛りつけているようだった。

相馬は深く息を吸い込み、振り返ることなく独りで声を漏らした。
「……おれは、ただ逃げたいだけなのに……」
その声は、広がる海の音にかき消され、だれの耳にも届くことはなかった。
未美は静かに一歩前へ出た。
そして隠し持っていた包丁を取り出し、しっかりと洋介の方へ向けた。
「洋介さん、お願いがあります」
その声は揺れながらも確かな意志を感じさせた。
「何を望む?」
洋介は微かに眉を上げ、包丁を向ける彼女を冷静に見つめた。
「わたしがこの島に残ります。わたしが楽園を支える存在になるから、他のみんなは見逃して!」
未美は少し息を吸い込み、声を張りあげた。
その言葉に洋介は静かに頷き、少し考えるように視線を落とした。
「君がここに残ることで、楽園を安定させることは可能だろう。だが、それだけでは十分ではない。妹のアリアも一緒に残ることが条件だ」
洋介ははっきりと告げた。
「彼女が楽園そのものであり、彼女がいなければ楽園そのものが成り立たない」
未美はその条件に一瞬躊躇したが、アリアを見つめながら頷いた。
「それでいいわ。わたしが残ってアリアと一緒にこの場所を守る。それでみんなを解放して」
洋介は未美の言葉にしばらく沈黙していたが、やがて杖を下ろし、低い声で答えた。
「わかった。君の覚悟を受け入れよう。他の者たちは見逃す」
彼は少し微笑みながら言葉を続けた。
「君がここに残ることで、楽園はこれまで以上に安定するだろう」
「ありがとう……」
未美は包丁を下ろし、深く息を吐き出した。
「未美さん、本当にそれでいいのか?」
そのやり取りを見守っていた夏目は、険しい表情で怒鳴った。
「大丈夫。これがわたしの選んだ道だから」
未美は少し微笑みながら彼に答えた。
「……ありがとう、未美さん……ぼく、絶対に忘れないよ」
一本道も迷いながら言葉を探していたが、やがて苦しげに呟いた。
「未美さん……本当にわたしのためにそんなことを……」
アリアは目を潤ませながら未美を見つめ、震える声で言った。
「アリアちゃん、これからは一緒にこの楽園を守りましょう。それがわたしたちにできることだから」
未美は優しく微笑みながら彼女に言った。
アリアは涙を拭いながら、静かに頷いた。
#27
アリアを花園から解放したい夏目は最初こそ猛烈に反対したが、魔術師の洋介とズーグたちに歯向かって適うわけがないと説得され、泣く泣く未美の提案に全員が最終的に同意するしかなかった。
「……これで皆さんが自由になれるなら、それでいいと思います」
アリアもその選択に静かに頷いた。
「それなら、おれもこの島に残る」
その場の空気が落ち着いた瞬間、夏目が突然言い出したのは全員が度肝を抜かれた。
一同が驚いたように夏目を見た。一本道が慌てて声を上げる。
「ちょっと待ってください、夏目さん!どうして……?」
夏目は少し笑いながら答えた。
「この楽園のために、おれもここに必要だと思う。それに未美さんだけに負担を背負わせるのは不公平だろ?」
「……夏目さんがそう言うなら」
未美は驚きつつも静かに頷いた。
「でも、ぼくの就職先の紹介は……どうなるんですか?」
一本道はまだ迷いが残る様子で、夏目におずおずと尋ねた。
「心配するな。ここに残る前に紹介状を書くから。それを持っていけ」
夏目は肩をすくめて笑った。
「ありがとうございます、本当に……!」
一本道はその言葉に安堵し、深く深く頭を下げるのだった。
「まったくゲンキンな人ね」
未美の一言に一同の緊張が解け、どっと笑いが起きた。
終章 残響
#28
島の桟橋に小さな船が波を切りながら近づいてきた。
一行は静かにそれを見つめ、様々な感情を抱きながら最後の別れを受け入れた。
船長が短く「乗るなら早くしな」と声を掛ける。
相馬と一本道が無言で乗船していく。
船の一番隅に座った相馬は、誰とも口を利かず、ただ一点を見つめていた。
仲間たちから距離を取り、まるで自分だけの世界に閉じこもるようだった。
「おれは間違ってないんだ……やるべきことを当然やっただけだ」
相馬は独りごちるように呟き、その言葉を波の音がかき消した。
一本道はというとポケットの中で大事そうに握りしめていた夏目の紹介状をそっと取り出し、しばらくそれを見つめていた。
「これで、本当に良かったのかな……」
彼は自分に問いかけるように呟いたが、答えは見つからなかった。
ただ少しだけ目を閉じると、自分の手が小さく震えているのを感じた。
「ねぇ、黒猫さん。一緒にこの島を出て、わたしと暮らさない? あなたをたいせつにするから」
桟橋のたもとで咲良は仲良くなった黒猫を抱き上げると、やさしく話しかけた。
黒猫はじっと咲良を見つめ、やがて人間の言葉で静かに答えた。
「吾輩はウルタールの猫である。本来ドリームランドにつながるこの島から出ることは許されにゃいが、たっての君の願いを聞き入れるとしようじゃにゃいか。この島には少々退屈になっていたところにゃ」
咲良の目が驚きで見開かれる。
「ありがとう……!本当にありがとう!」
船に乗り込むと黒猫はさっそく咲良の膝の上で丸くなった。さきほど人語を話した素振りなどおくびにもださない猫らしい猫に。
そんな黒猫の背を撫でると、咲良は少しだけ救われた気持ちになった。
島に残ることを選んだ未美は、出港準備に追われる船を眺めながら洋介に向き直った。
「先生、これから魔術やこの楽園のこと、わたしが知らないことをいろいろ教えてくださいね」
洋介は少しだけ照れくさそうな表情を見せたが、静かに微笑んだ。
「いいだろう。君には、その素養があるようだ」
未美は海を眺めている洋介の横顔に微笑み返し、心の中で新しい生活に向けた決意を固めたのだった。
そして夏目はアリアを花園の外へ誘い出し、ふたりきりで海辺に立っていた。
「夏目さん……どうしてここに?」
アリアは不安げに問いかけた。
夏目は静かに彼女の肩に手を置き、穏やかな目で見つめた。
「実は昔、言えなかったことがあるんだ」
アリアが目を瞬かせる中、夏目はそっと彼女を抱きしめた。
「本当は、君のことが好きだった」
その言葉にアリアは驚き、何かを言おうと口を開いた瞬間、夏目は彼女を抱きしめたまま海に飛び込んだ。
アリアをこの世の理から外れた歪んだ楽園から解放させる道は自らの命を犠牲にしても、それしかないのだと固く信じながら――
#29
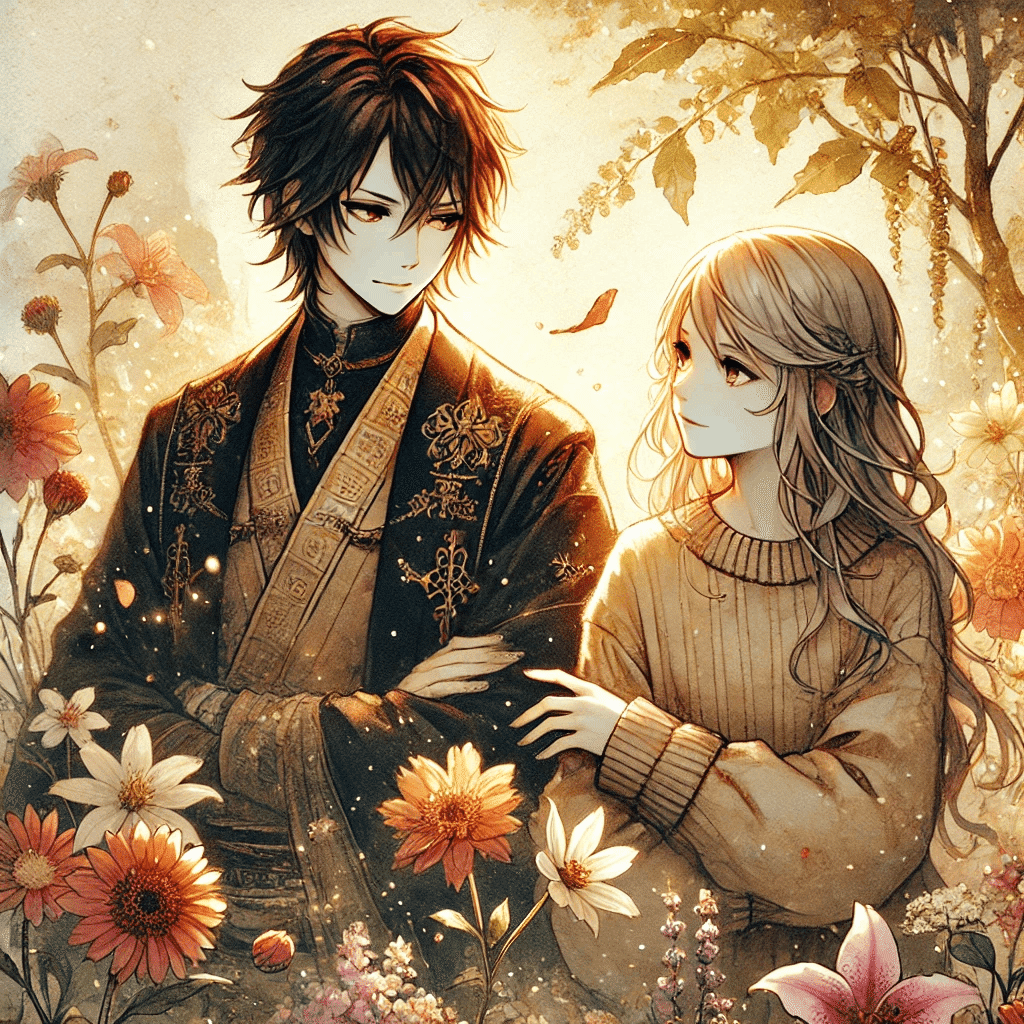
匂い立つように咲き誇る花園のなか、寄り添う洋介と未美に見守られながらアリアは風に揺れる花々に囲まれて微笑んでいた。
風に揺れる花々は一輪一輪のどれもが美しい記憶を秘める。遠い日の懐かしき名残りを花の香りに変えて。
そして穏やかな微笑みを浮かべるアリアの姿は時間から取り残された楽園のある限り、あの日の思い出のなかを朽ちることなく悠久にたゆたうのだろう。
残響の楽園に揺れるは忘却の旋律――終幕

KP後記
このシナリオは、とにかく〈エモい〉をキーワードにして創作してみました。当初は楽してAIに9割を生成してもらう目論見でしたが、なんだかんだで結局7割は自分で創作しています。
実際のセッション(約6時間)では、プレイヤーたちにはかなり好評価してもらえましたが、リプレイ小説でも再現できていたでしょうか?
今回はログの記録方法を工夫したので、今までより実際のセッション内容をより忠実に再現できています。
実はシナリオ構造的には最後の花園に行く以外は島内を自由に行動できるサンドボックス型だったのですが、やはり謎の少女アリアに探索者がついていく場面が多かったので、あまり脇道に逸れない進行でしたね。
展開しだいでは〈ウルタールの猫ルート〉や〈ゾーグ討伐ルート〉、果てはラヴクラフトの描いた〈ドリームランド〉に迷い込んでしまう可能性もありました!
反面、花園に到着してからは一致団結どころか各々の思惑がダダ漏れのロールプレイで、だれも協力プレイしないという展開に!
それはそれで愉しくプレイできたし、ストーリー的にもなんとか上手く収まってくれて一安心でした。
またイラスト関連ではアリアの体の花模様について、PL的にはみんな気にしながら、ついにPCとしてはだれも質問しなかったりとか、魔術師洋介のイラストが女性陣に大人気でロールプレイも乙女ゲーム風に流れていたような。
ちなみに想定では魔術師は倒されて楽園とアリアが崩壊する〈楽園の崩壊〉がメインエンディングでした。なので魔術師はわりと容易に倒せる(1人くらい道連れにするかもね)の強さ(下記参照)だったのですが、探索者たちは強敵と思いこんで直接対決を避けていましたね。看護師の未美も回復役として魔術師側についてしまいましたし。ゆえにより感傷的なエモいエンディングになったのではないかと思います。
それでは次回はもっと愉しく、また怖さを演出できるようがんばります!
佐伯洋介 (魔術師)のステータス
STR55 CON50 SIZ60 DEX65 INT85 POW80
耐久力11 MP16 正気度40
クトゥルフ神話45 オカルト80 心理学60 回避33
・杖(打擲) 40% ダメージ1D6 近接攻撃
・杖(電撃) 60% ダメージ1D6+3 射程15m 消費MP3
・ゾーグ召喚呪文 消費MP4

