
【カプラーとお友達】マイクロエース 南海2000系の加工
2両編成が発売されるのを契機に、4両編成も中古で購入した。
工事対象は以下の2品
・A-8054 6次車4両
・A-8055 5次車+6次車 2+2=4両
(A-8054のみ)動力車カプラーホルダー交換
カプラーに関するひとつ目の課題。
妻面をKATOカプラー密連型に交換したが、動力車で問題が発生した。

デフォルトのホルダーに取り付けると、カプラーが出過ぎてしまう。
短いカプラーホルダーを求め、ストックの中から小田急8000形をTN化した際に捻出されたモノに交換した。

車間も短縮され、色も良さそうである。

付随車よりも若干出ているが、全く気にならない程度である。
先頭車TNカプラー作製
カプラーに関するふたつ目の課題。
指摘されて久しい事だが、この製品シリーズの先頭車は、TNカプラーとの相性が悪い。
車体にポン付けした場合、黒色密連【品番:0339、カプラー爪が長い】が連結こそ可能だが、カプラーがボディに接触して首振りできない。
そもそも0339は、電連も無いし色も異なる。
今回は多種多様なTNカプラーのラインナップからパーツを寄せ集め、ポン付け&実用可能なカプラーを錬成した。

レシピは以下の通り
胴受け&上カバーは0337(密連グレー)からジャンパ栓モールドを切除
カプラー爪は0339
電連パーツは適当
組み上がったカプラーは、ガイアのマルチプライマーの上にクレオスのNo.32 軍艦色(2)をスプレーした。
カプラーを胴受けパーツに組み直す際は、復心バネを取り付けない。
バネがあるとカプラーが上に向いてしまい、首振りの際にボディと接触してしまうので、バネを外してカプラーを下垂させることで、首振りを可能とした。
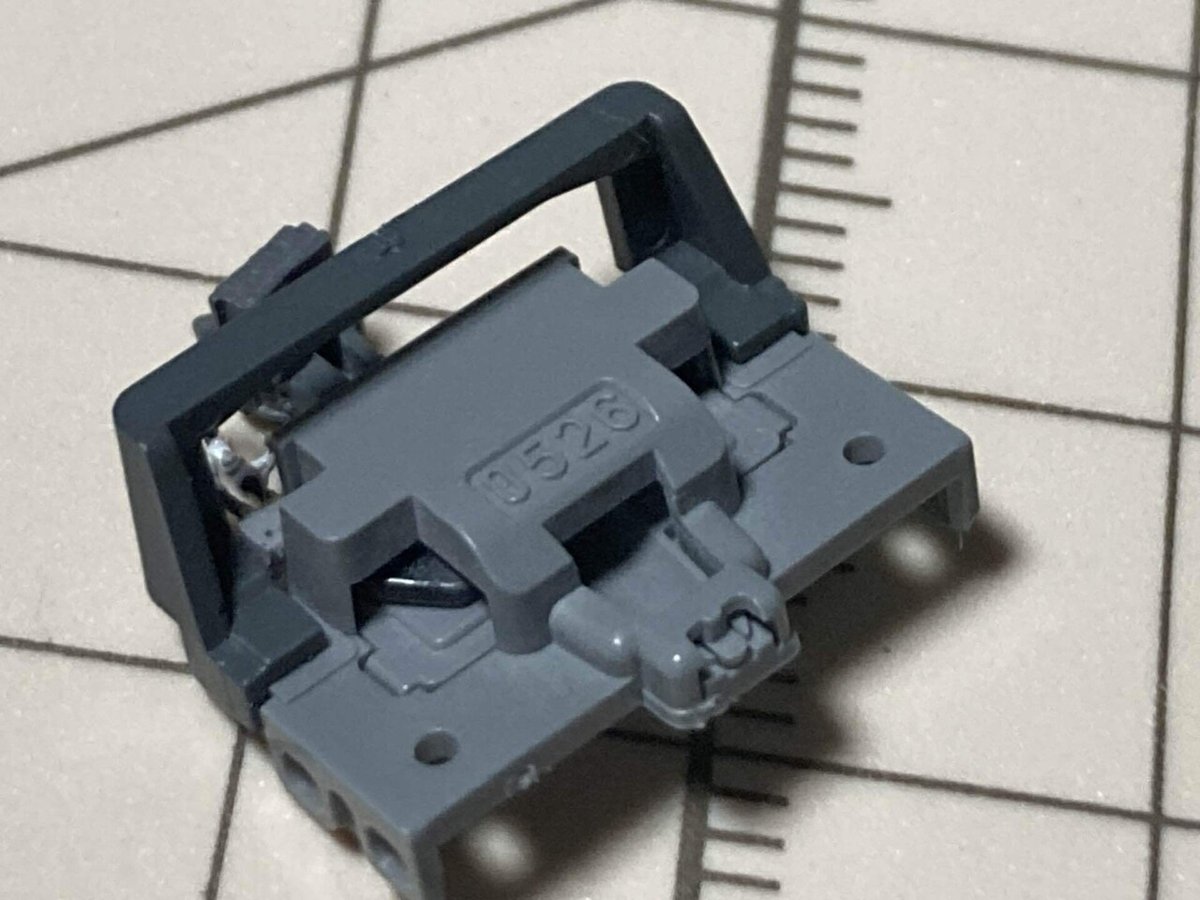

また、エアホース(阿波座製)も設置してある。
カプラーホルダーの脇に、ピンバイスで穴を開けたプラ棒を接着し、エアホースを挿入した。
スカートは取り付けが緩いため、ゴム系接着剤で胴受けパーツに固定した。


先頭車ダミーカプラー取り付け
課題という程ではないが、これもカプラーに関する事項。
連結を想定しない先頭車は、ディテール向上のためダミーカプラーを交換した。
いろいろ製作所の南海6000系パーツを、不要部分を切除のうえ使用する。
塗装には前述のTNカプラーと同じ、軍艦色を使用した。
高さ調整のため、カプラーパーツと床板の間に厚さ1.2mmのプラ板を挟んである。

本文記載と異なる塗料で仮塗装の状態
スカートは床板にゴム系接着剤で貼り付けた。
TORM室内灯加工・取り付け
先頭車は特別な加工なく取り付けた。
中間車は逆向きの長さが不足するので、切れ端を活用して延長した。
延長工程は以下の通り。
紙やすり(#400)で導体パターンを露出させる。
フラックスを盛り、仮半田付け
パーツ切れ端金属線で本番の半田付け
裏から接着剤で補強

最後にクリアパーツをゴム系接着剤で止めて完成。
余談だが、何故LED間はP, N共にパターンが2並列なのだろうか?
最も電流がキツくなる部分のパターンは1本なのだが…。
その他の加工&〆
白色前照灯の電球色化= 基板LED打ち替え
世田谷インレタを窓に張り付け
いろいろ製作所製排障器設置
など

直上写真とサムネ写真を比べると、前照灯の色味が全く異なる。
同じチップに打ち換えたが、プリズムに違いがあるのだろうか?
疑念は残るが、気が向いたら確認しよう。
