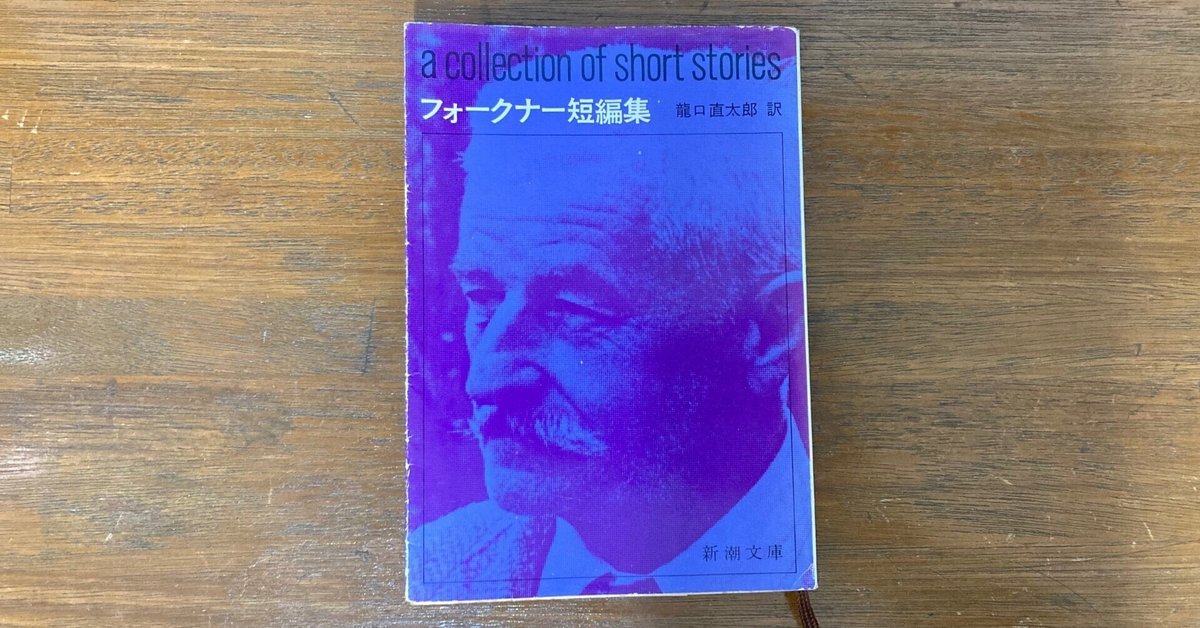
宿命的なフォークナー(ウィリアム・フォークナー雑記)
フォークナーの小説は宿命的だ。そして魔術的でもある。なぜか。彼の小説の主要人物はほとんどが自分の行く末を知っているからだ。
「クマツヅラの匂い」のベイアードは、父親の仇であるレッドモンドに銃口を向けられても絶対に当たらないことがわかっている。まるであらかじめ展開がわかっている演劇をやっているみたいだ。実際にフォークナーは芝居の一場面のような描写を書くことがある。
すると私の眼に、黄色い舞踏服を着て、芝居の一場面のように、開いた戸と窓から流れ出る光をあびながら、玄関正面の階段のいちばん上に立っているドルーシラの姿が見えた。
ヨクナパトーファ・サーガは閉じた箱庭世界であらゆる時代の物語を綴る。ゆえに、一度死んだ登場人物が後年の作品に登場することがある。例えば「響きと怒り」の主人公、クウェンティン・コンプソンは話の中で自殺するのだが、その2年後に書かれた「あの夕陽」はクウェンティンの幼少期の話だ。やがて自殺する人間の幼少期を書くことほど宿命的なことはない。
同じ書き方をする作家を二人あげることができる。J・D・サリンジャーと佐藤友哉だ。前者は宿命的だが同時に感傷的でもあり、後者はサリンジャーに影響を受けつつもフォークナー的な因縁深さを捨ててはいない。
今度は「あの夕陽」から、フォークナー作品の哲学を見てみよう。
この記事では「におい」について述べた。この作品にも同じく「におい」について述べている箇所がある。
ナンシーの家にはどことなくなにかにおうものが――ナンシーや家のほかになにかにおうものがあった。
なぜナンシーの家は「におう」のか。これが前の記事で述べたところの死臭、もしくは宿命的なものの象徴としてのかおりであるとすれば、なぜそれは嗅覚を通じて理解されるのか。
いや、それは理解されるのではなく直感されなければならない。自分の行く末、死に方、宿命、そういったものは常に理解を越えてあるものだ。
どうして私は死ななくてはならないのか、どうしてこの家に生まれついてしまったのか、どうして私は黒人なのか、それらを理解することはできない。ただ感覚で感じ取ることができるだけだ。自分の意志でどうにかできるものではなく、彼らはセンサーのように感じ取って反応することしかできない。この世界で自分が自分であることは誰の罪でもないのだ。
「あたしは黒人にすぎないのよ」とナンシーはいった。「これもあたしが悪いんじゃないけどね」
「やっこさんは靴をはくこともできないんだ。やっこさんとわしは両方とも、やっこさんのからだを包んでる、でぶっちょの肉のために挫折したんだ。やつにはそいつをはくこともできんのだ。しかし、それはわしの罪なのかな?」
最後は「納屋は燃える」のカーネル・サートリス・スノープス少年と、「アブサロム、アブサロム!」のサトペン少年には共通点があるという話。それはもちろん両者ともプアホワイト(貧困層の白人のこと。時に黒人より差別されることがある)であるという点だが、彼らを結びつける重要な繋がりがある。
サトペン少年は次のように考える。
もしそれが廐か屋敷が火事だというようなことを知らせるためだったとしても、あの黒人めはおれがやつにそのことを知らせ、警告することさえ許さなかっただろう。
カーネル・サートリス・スノープスは小説の最後で、大農場主のド・スペイン少佐の元へ納屋が燃えていると報告しに駆けつけるのだが、屋敷の戸口から出てきた黒人に彼は全く取り合ってもらえず、それどころか出てきた少佐が怒ってその少年を捕まえようとする。サトペン少年の考えていることが現実になるのである。
僕は「響きと怒り」を読んでおらず、また「納屋は燃える」のその後を書いたスノープス三部作も未読なのでこれ以上のことはわからないが、いつか読んでこれらのことに補足を加えたいと思う。
