
【まちづくり】スマートシティによる未来の生活。ロボと豊かさを体感〜藤沢市ロボテラス・SST〜
夜でもヒルタです。私は、「しあわせな+1時間を 岡崎市」をキーメッセージに、岡崎市を「子育て・福祉・産業・まちづくり」において「日本全国のモデルになるまち」目指して活動しています。
家族との時間・学び直し・まちづくり活動・趣味や休息等……つまり、自分自身が本当にやりたいことができる時間が、「しあわせ」につながると信じています。20年、30年先の岡崎市の未来をともにつくる。
私、ひるた浩一郎は、藤沢市(神奈川県)で取り組まれているスマートシティの先行事例を視察してきました。
藤沢市にあるロボテラスとFujisawa SST(Fujisawa サスティナブル・スマート タウン)にいってきました!

ロボテラス ROBO TERRACE
ロボテラス / ROBO TERRACEは藤沢市が運営し、「ちょっと先の未来に会える場所」として最先端ロボットなどを体感できる施設です。2023年10月14日にリニュアルオープンされたばかり!
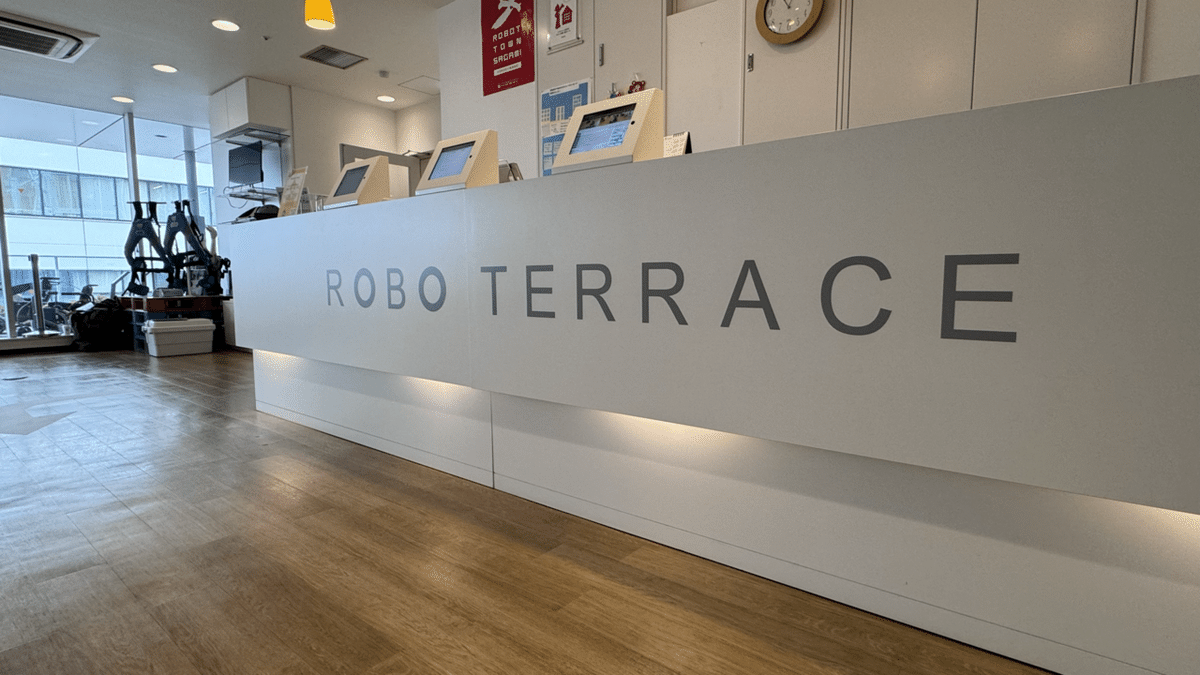
ロボテラスは実際にロボットを見て、触れることができる体験・展示スぺースです。
県内の相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町の10市2町が2013年2月に国から指定を受けた「さがみロボット産業特区」内で、「生活支援ロボット」の普及・啓発を目的として2014年12月24日に藤沢市辻堂に開設されました(2018年8月1日から公益財団法人湘南産業振興財団)。
「生活支援ロボットってなに?」
「どんな事ができるの?」
「どんなロボットがあるの?」
そんなロボットに関する疑問や質問にロボテラスがお答えします。
LOVOTをはじめ、たくさんの愛玩ロボットもいました。

WHILLの車椅子をはじめ、モビリティ体験も! タブレットでも動く車椅子!

甘噛みハムハムで、はむはむしてもらいました。結構、好き。

姿勢を検知するカメラがあり、姿勢スコア100点でした! 100点って満点でなかなかでないらしいです、嬉しい!!

様々なロボットやアトラクションを体感しました。
ゲーミフィケーション x テクノロジー
ゲーミフィケーションの考えを取り入れ、楽しみながら身体を動かすことができる…っていうことを体感しました。
例えば、愛玩ロボットとの触れ合いで動物アレルギーがあるような独居高齢者などが、ペットセラピーのような使い方があるかもしれない。
センサーやVR体験なども楽しみながら、身体を動かしたり、他の人と競い合うことで楽しめる。フレイル対策や運動不足解消にもつながる可能性を感じました。

なかなかこうしたテクノロジーを同時にたくさん試すことができる場はないので、ロボテラスのような場があることで、高齢者施設や福祉施設の方々も導入検討の時に役立つだろうなとも感じました。

Fujisawa SST - サスティナブル・スマートタウン
Panasonicの工場跡地を利用したまち、Fujisawa SST。
単なる再開発や住宅街ではなく「想い」を持ってつくられたサスティナブル・スマートタウン…Fujisawa SST…どんな場所かはまずは公式動画をご覧ください。
Fujisawa SSTの公式ウェブサイトにもあるように「究極の理想」追い求めていることを視察して感じました。
私たちは、単に最先端のスマートタウンをつくるのではありません。究極の理想を追い求めた街をつくります。神奈川県藤沢市にうまれた『Fujisawaサスティナブル・スマートタウン(Fujisawa SST)』は、先進的な取り組みを進めるパートナー企業と藤沢市の官民一体の共同プロジェクト。
大きな特徴は、1‚000世帯もの家族の営みが続くリアルなスマートタウンとして、技術先行のインフラ起点でなく、住人ひとりひとりのくらし起点の街づくりを実現することです。
私たちはまず100年ビジョンを掲げ、それを達成するためにタウンデザインとコミュニティデザインのガイドラインを設けました。その目標を共有した住人たちがくらし、交流し、より良いくらしをつくるアイデアを出していきます。
そして、住人の生の声をタウンマネジメント会社がすいあげ、新しいサービス・技術を取り入れ、サスティナブルに街を発展させ続けていきます。そうした、くらし起点の画期的な仕組みが、エネルギー、セキュリティ、モビリティ、ウェルネス、コミュニティ、さらに非常時まで…くらしのあらゆる場面で『生きるエネルギー』をうみだし続けていきます。
アイデアだけではなく、実際にそこに人々が「普通に生活している」まちなんです。

住民が生活している場でもあるため、視察する前にタウンマネージャーの方からFujisawa SSTについて説明と注意事項をレクチャーしていただきました。(SST内での写真は許可されたところを除いてNG)

今回、自動配送ロボットの見学もさせてもらいました。なんと特別にOriHimeによる案内をしていただきました! OriHimeが活用されているところをみて、感慨深かったです!

自動配送ロボットは数年前から実装されており、SSTに住む方々に野菜や焼き立てパン等の配送をしてくれているとのこと。センサーが様々ついており、人と相対したときには自動で止まってくれます。
管理センターでSST以外にも複数台を管理しており、「何かあった時」はオペレーターが遠隔で操作できる仕組みもある。

印象的だったのが、SSTに住む子どもが自動配送ロボットを見かけると「ばいばーーーい!」と言ったように声をかけているところでした。当たり前に受け入れられているということもあれば、すごく身近な存在になっているんだと感じました。
再開発による可能性
スマートシティやスーパーシティはどのまちもチカラをいれて取り組みをしていこうとしています。
いま、最も注目されているまちのひとつがトヨタ自動車さんがつくろうとしている裾野市(静岡県)の「ウーヴンシティ」です。
新しいまちができるタイミングや再開発をするときに「テクノロジー」を活用していく。そのためには「コンセプト」が重要です。
テクノロジーはただの便利な道具でしかない。
「再開発をしたなかで、どんな暮らしを想像しているか」をコンセプトとして提示して、理解した方々に住んでもらうそんな仕組みが必要です。
新しいまちと旧いまち
新しい再開発のまちはスマートシティとして、コンセプトをしっかりとつくったうえで、で新しいテクノロジーや取り組みを進めていくことができると感じました。
一方で、市内全域をFujisawa SSTのようなスマートシティにすることは難しいとも感じました。旧いまちに取り組みを入れようとすると様々な障壁があると感じたためです。
たとえば、自動配送ロボットであれば「道の広さ」「道の段差」といったちょっとしたこともそうです。旧いまちは住民同士が「コンセプト」を共有した状態で暮らし始めたわけではありません。
再開発によって「スマートシティ」というよりも「スマートタウン」として生活できる場…エリアがあることと旧いまちに合致したテクノロジーを活用したまちづくりは分けて考えたほうが良いとも感じました。
スマートシティを市域全域に広げるには時間がかかってくるかもしれないですが、できるところから「あぁ、なるほど、そういうことね!!」を実感し理解できる場をつくっていくことで広がっていきます。
まずは、ひとつ、市民の方々が理解し、「あぁ、なるほど」と言える場をつくる。
カラダは単なる乗り物…なのかも
分身ロボット「OriHime」が今回、Fujisawa SSTのまちを案内してくれました。
OriHimeを乗り換えて、瞬間移動する場面がありました。カラダは単なる乗り物だ…と強く感じました。リアルアバター、だと。
何を言っているかわかんない…って思われるかもしれないんですが「リアルアバターだ…カラダは単なる乗り物だ」とも感じました。
Orihime が2台いて、1台は屋内で説明をしてくれたんですよ。その後に、自動配送ロボットに乗っているもう1台のOriHimeに「ナカノヒト」が瞬間移動したんですね。
意識というか魂が瞬間移動したわけです。
めちゃくちゃ不思議な感じがしました。
実際にナカノヒトは病気等で自宅にいながら案内をしている。OriHimeを動かすのではなくて、複数台設置し、意識(接続)を別のものに飛ばす。
書いていてわかりづらいというのはわかるんですけど、やっぱり、不思議な経験でした。ぜひ、体験していただきたい。
岡崎市でもスマートシティ推進を
岡崎市でも「岡崎スマートコミュニティ推進協議会」として、少しずつ取り組みが進んでいます。
直近だとnoteにも書いたようにこうした実証実験を実施しています。
愛知県から「スマートシティモデル事業」として岡崎市が認定されていることもあり、実証実験を行っていました。
自治体だけ、企業だけではこうした実証実験や未来をつくっていくことはできません。自治体x企業x市民といった連携・共創があるからこそ、新しい未来をつくっていける。
既存の取り組みとあわせて、新しい取り組みもどんどんと取り入れていく。「シン・温故知新」の取り組みを推進していく。
未来のあたりまえの仕組み、まちをともにつくっていきましょう。
さぁ、共創だ!
◯ 【岡崎市政への挑戦】ひるた浩一郎が岡崎市の新しい若きリーダーへ、意向表明の記者会見を実施(2023年10月6日)
岡崎市の新しい若きリーダーとして、岡崎市政へ挑戦します。
岡崎市の未来をともにつくっていきましょう!
記者会見の動画や想いをまとめています。ぜひ、ご覧いただき、あなたの声を聴かせてください。
いいなと思ったら応援しよう!

