
前衛書試論04──書の「名」と制度
古賀弘幸
十─七 「名」と画面
前回、上田桑鳩「愛」を手がかりに、書に与えられる「名」とはどのようなものなのかについて考えた。
繰り返しになるが、前衛書の成立については、「戦後の自由な思潮が伝統に拘泥しない書表現を生んだ」あるいは「西欧絵画などに影響されながら、文字を構成する線の表現を重視する態度が筆線の自律的な表現へ進展し、それは前衛書を含む現代書を生んだ」といった説明をされることが多い。しかし、前衛書に代表される書表現が書の内部からのみ生まれた、と考えるのは不十分である。それは展覧会制度の中で行われる、ある意味でそれ自身記号論的な、一種の形式的な戯れのようなものである(本稿では、前衛書、墨象を厳密に定義することはしない)。ここで論じようとするのは、必ずしも個々の作品の価値ではない。「前衛書」がジャンル化されていることの意味を考えようとするものである。
たとえば、前衛書第一号と目される比田井南谷「電のヴァリエーション」にしても、その表現の斬新さは疑うべくもないが、一方で、「古代文字「電」をもとに発想した筆線のデッサンである」という作家の意図を表明する「電のヴァリエーション」というタイトルが付されていなければ、この作品のインパクトは減じられたのではないか。
というより、名(作品を定義づけるタイトル)と作品(視覚像としての「文字」)の分離と再統合こそが前衛書を準備したのではないかと思われる。
戦後の書作品のタイトルをランダムに観察し、この「分離と再統合」をもう少し具体的に検証しよう。書の「名」が「読み出し型」でつけられることはいまでも一般的に行われる。しかし昭和の書作品には、名と作品の分離と再統合を示すタイトル、つまり単なる画面の「文字」を読み上げるだけのタイトルではなく、佐々木健一が言う、「近代的なタイトル」も見られるようになっていた。
たとえば、書が日展に戦後はじめて参加した、一九四八年の第四回日展に出品された大池晴嵐の作品は「無題」と題されている(第五回展出品作では「失題」)。写真版で見る限り、良寛詩を行草書で書いた、伝統書の範疇にあるもののように見えるが、日展の書作品で「無題」と題されたもっとも早い作品である。
また、松本芳翠の「雄飛(大鵬一挙九万里)」(一九五四、第十回日展)は、楷書の大字作品である。「雄飛」というタイトルは、画面のどこにも書かれていないから、いわば作品とタイトルは分離されている。一方で、曖昧でありながら、画面に書かれている荘子のテキスト「大鵬一挙九万里」に雄大な飛翔という(単に伝説上の鳥が遠くまで飛ぶという意味以上の)象徴的な意味あいを帯びさせる効果を果たしている。これが画面「大鵬一挙九万里」とタイトル「雄飛」との再統合である。ところが、その意図された命名に対して、タイトルにはさらにカッコ書きで作品の全文の読み(大鵬一挙九万里)が加えられている。これは作品を同定しようとする、日展事務局の配慮だろうか。
また、手島右卿の「象書」(右卿独自の呼称)では、いわば表現主義的なタイトルがつけられている。サンパウロ・ビエンナーレにも出品された有名な作品「崩壊」(一九五七、独立書展)には、淡墨で草書「崩壊」の二文字が書かれているが、筆線は割れ、点画がバラバラになったような、あたかもタイトル「崩壊」を連想させるような表現が選ばれている。作家本人も第二次大戦の経験との関連を語っている。この作品においてタイトルは、「文字」(書かれている文字列)と同じであるから、その意味では「読み出し型」であるが、タイトル、画面に書かれた「文字」、表現の三つの契機が矛盾しないかたちで象徴的に結び合わされている。これは書表現において、「文字」とその視覚的な様相(書体・書風・表現)と、タイトルによる外からの美学的な価値づけが、一致して作品に奉仕できることを示している。
前衛書では必ずしも表現が「文字」の意味と同じ方向を向いていないことも多い。「文字」を書いていない作品もある。であれば、表現の方向をコントロールする権限を持ったタイトルの重要性はいっそう高まるはずである。つまり作品に即して作品を説明してくれる文字列がなければ、表現が宙吊りになってしまう可能性がある。「名づけられていないもの」は、展覧会の制度に拒否されてしまったはずである。後述するようにそれを上田桑鳩の「愛」は象徴している。いくつかタイプごとに例を挙げよう。
◎井上有一「愚徹」(一九五七)
◎上田桑鳩「獅子吼」(一九六四)
「文字」とタイトルは一致しており、さらに作品における表現が重ね合わされている。つまり表現主義的で、右卿の「崩壊」型タイトルである。これらの作品においては「文字」の意味(ここではタイトルも同じ)が作品が収斂すべき象徴的な価値であり、さらに意味と表現の方向が同じ方向を向き、タイトルにおいて統合されることが目論まれている。有一「愚徹」では、「愚に徹する」という作家の強い意志を体現するようなごつごつとした、そして読むことを拒否するような筆致をタイトルが象徴的に統べている。
また桑鳩「獅子吼」では、「文字」の意味において、身を震わせるような怒り、あるいは自他を叱りとばすような作家の意志、その大音声を体現するような振動する筆線が書かれ、それをタイトルが統一体としての作品を統べている。
◎森田子龍「蒼」(一九五九)
前衛書では表現に幅はあるものの、一文字または数文字を文字として書いた作品が多くを占め、その「文字」がそのままタイトルになっていることが多い。これは作品の動機が文字にあることを示し、「書」作品であることの根拠を保持しようとしているのであろう。少なくとも単なる〈絵画〉ではなく、そこには言語的な何かが強く主張されている。ただ、なぜその文字が選ばれたのかは必ずしも明確ではなく、作品の「文字」、そしてタイトルの意味作用は不分明である。この作品をあえて読むならば、蒼ざめて孤立する自己(という「文字」の意味)を「蒼」字の量感を通じて表現したという意図が読み取れるだろうか。
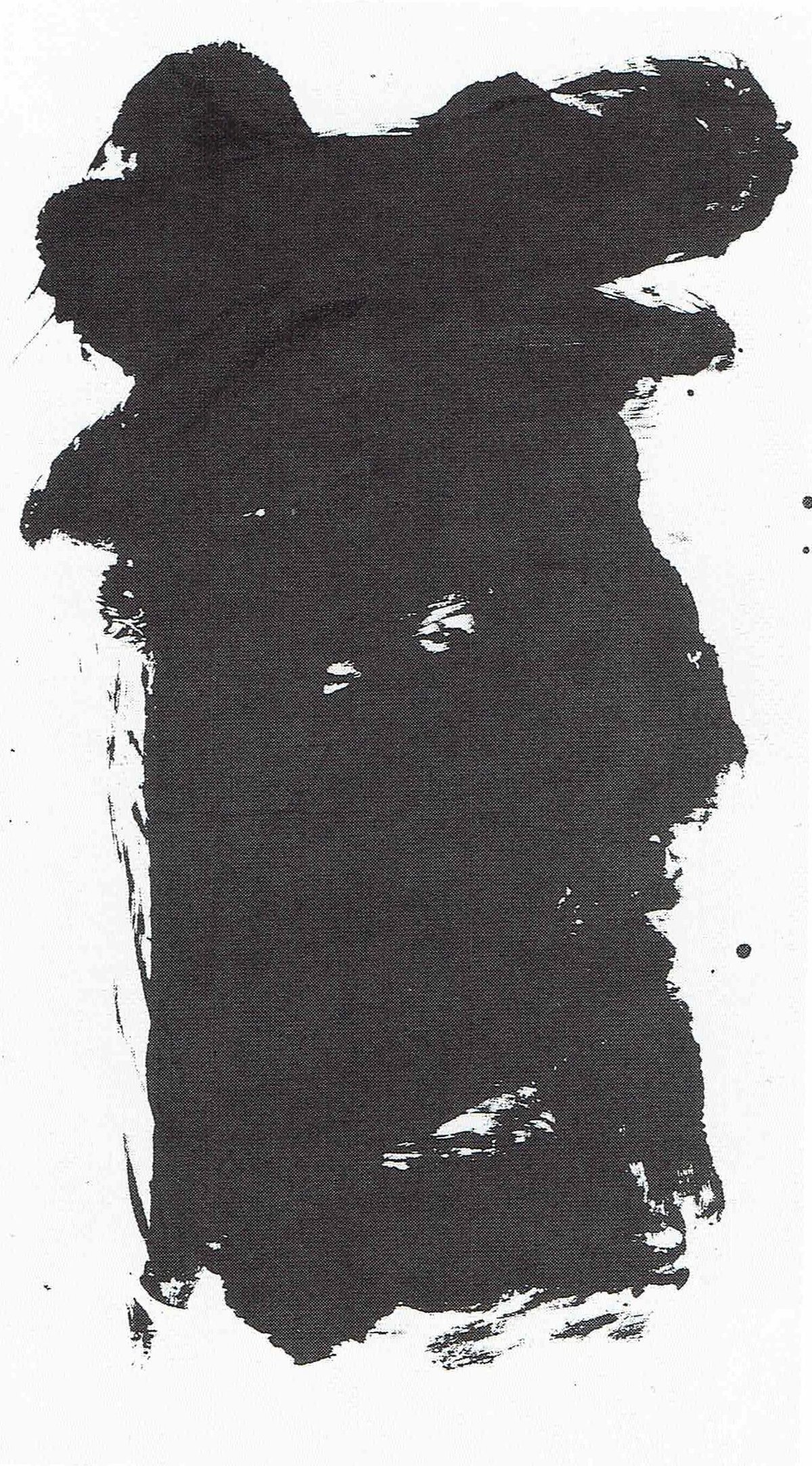
◎比田井南谷「電のバリエーション」(一九四五)
◎宇野雪村「MEI」
雪村の作品は「明」の草書をもとにしているようである。しかし漢字音を英字表記にしたものや「…によるコンポジション」「…によるバリエーション」といったタイトルは、文字を絵画的に変奏することが作品のテーマとして表明され、「文字」の意味とまったく無関係ではないことをほのめかしながら、またはそこから進んで離れようとすることを表明している。いわば「蒼」より文字の意味への関心は薄く、「発想は文字にあるが、作品に書かれているのは意味作用を持った文字ではない、線によるタブローとしてこの作品を見よ」とタイトルが宣言している。

◎篠田桃紅「見ぬかたち」(一九六一)
◎田村空谷「古代幻想97 光と影」(一九九七)
◎山本大廣「封印・都市」(一九九七)
文字を構成するかのような筆線によってはいるが、タイトルと一致する「文字」は書かれていない。文字をまったく離れる表現もある。ただし、文字に由来する筆線の情緒を表現に利用している、とはいえるだろう。その情緒は少なくとも言語的なものから離れようとしている。この文字との関係の曖昧さを、現代絵画に影響とされたと思しき詩的なタイトルが表現している。タイトルそのものも曖昧であるが、その二重三重の曖昧さが空間的な広がりを与え、作品の価値に貢献している。
◎比田井南谷「作品64─25」(一九六四)
「無題」的タイトル。美術・音楽作品全般にも共通するが、こうした一見無機質にも見えるタイトルは、作品を読もうとする視線をはじき返し、宙づりにし、タイトルの美学的な権能を脱臼しようとしている。作品に「命令」することをやめ、過剰な意味づけをしないで自由に「絵」としてみてほしいという意図が感じられる。その一方で、「無題」というタイトルがそうであるように、作品の解読には必要であるはずのタイトルをあえて脱色することで、「あらゆる言語的なコンテクストを外す」というコンテクストを逆説的に作っていることになる。
一方、宇野雪村は、ある対談で
たとえば「空」と書いてあるとすると、「そら」と読みますね。「あっ、これは青い空かな、梅雨の空かな、曇り空かな」なんて考えたりする。そういうふうに、読めるということは、そうした連想作用を起こす可能性が強いわけです。(中略)哲学的な意味における、あるいは仏教的な意味における「くう」という意味で書いたとすると、「そら」と読まれるとおかしくなってしまう。読まれること自体が誤読になる。そういう意味からすると、連想を伴わない題名をつけておいたほうがいいということになる
と発言している(『毎日書道講座・前衛書』所収、深瀬正頼との対談「書の前衛とは」)。この発言は書とその名の分離と再統合がどのように作品の価値(鑑賞行為における判断)に影響するかを説明している。つまり、タイトルが画面に向かって明確に命令しないことは、必ずしも自由な解釈を許すものとは限らない場合もあるのである。これもある意味でいかなるタイトルであっても「無意味」ではありえないことを示している。
展覧会のプレートに記された、あるいは図録に印刷された作品の傍らにつけられたタイトルは、どんなものであっても、作品表現の方向を変容させうる。「文字」とタイトルの関係において、読みの方向がコントロールされることで、書作品は矛盾を含む緊張を強いられることもありうるが、現代書・前衛書は、その緊張を積極的に利用しているといえるだろう。このことは、もともと書が言語的な契機から離れることはないことを証明しているともいえる。極端な場合、書のタイトルは作品の「文字」を裏切る契機にもなりうるし、両者のずれ、齟齬が、その間に浮かぶ、新しいポエジーを生むこともありうる。こうした例の一つとして桑鳩「愛」を考えることができる。
ところで、この作品を含む比田井の作品の多くは、「文字」によっていないが、線による情緒ばかりではなく、漢字の結構に依拠したと思われるものがあり、〝文字〟は書いていないが、その意味で〝文字〟的である、という特徴を持っている。それが作品の「顔」を作っている。
十─八 上田桑鳩「愛」
上田桑鳩が作品「愛」を第七回日展に委嘱出品したのは、一九五一年のことである。この作品には、「品」の一文字がやや行意を帯びた楷書で二曲屏風に大書されている。漢字を知っており、書作品という前提があれば、ほとんどの人がこれを「品」と読むだろう。桑鳩自身も「日展に出品した品の一字を書いた二曲屏風」としている。仮に「読み出し型」のタイトルを付するとすると、「品」となる。
画面に書かれている「品」の字義は、白川静『字通』によると、祝祷が入った器「サイ」に従う会意文字で、「品」は多くの祝祷を行うことであるという。また『説文解字』では、「口」は人間の口の象形であって、「品」は「衆処なり」(多くの人)とする。転じて多種の意となり、現在行われている「品」の字義は、人間や事物を価値づけすることに関係する。一方タイトルの「愛」の字義は、「後に心をのこしながら、立ち去ろうとする人の姿」(『字統』)、または「すり足でそっと歩く」意であるとする(山田勝美『漢字の語源』)。転じて現在の字義は、人や事物を尊重し、共感を示す語である。
したがって、常識的に考えれば、「品」は「愛」という観念となんの関係もない。つまりこの桑鳩の作品では、「文字」のテキストとタイトルは分離されているだけではない。再統合にも失敗している。このタイトルは「近代的なタイトル」には違いないが、ほとんど「不可能なタイトル」というべきものである。前回冒頭に記した印象はこのことに発している。
桑鳩はこの作品について、日展の自作解説に「一年ばかり前から私の脳中に岩か雲のような形の想影が去来し、それを表現したかつた。それには品字が最も適していたので、これを用いることに決めたものの、その形を如何にするかを決しかねていた。今度孫が生まれて、人と獣とも分からぬような醜くも、あどけない、赤ん坊の顔を見ているうちに、強い愛情を覚えること、ともに決定しなかった品字の形が決まつた。それは祖父が生まれたての孫に対する愛の衝動を表徴する私としての形であつた」(『日展史』一七)と記しており、ある形を表現しようとするのに、「品」字が選ばれ、孫への愛情を通じてその表現が明確なものになった、ということであろうか。またハイハイする様子を書として造形したものだというエピソードも伝わっている。
このエピソードを手がかりに、作品を次のように読むことは可能であろう。──幼児がハイハイしながら、新しい何かをつかもうとしている。それは新しい人間が、新しい言葉=文字をつかもうとする瞬間を想像させた。その姿に桑鳩は、「品」という文字を借りながら、もとの字義を破棄するようにして、「品」に新しく「愛」という名を与えた。この再命名を通じて桑鳩自身も、新しい「愛」、つまり世界との肯定的な関わりを獲得し直そうとしたのだ──。
桑鳩がこのような意味を作品に与えようとしたのかどうかは、まったく不明だし、新しい「名」(「愛」)を与えられた「文字」(「品」)が新しいポエジーを孕むとは必ずしも思えないのだが、それでもこのタイトルはこうした鑑賞を可能にする。「名」には、物事を創造し、聖別する働きがあり、その一方で物事を系列化する働きもあり、そしてさらには新しい名によって、そのような世界を更新する機能も含まれているからである。
ひいては、芸術作品のタイトルは名と画面が矛盾していることによって、言葉への一種の批評の契機も持っているだろう。たとえば、「今」という文字が書かれた画面に「古」というタイトルをつけた場合を考えてみよう。「今」を「古」として捉えなおすことは何を意味しているだろうか。──世界に新しくしかも不断に生まれる「今」は、瞬時に世界の縁へと押し出されていき、「古」に変質していく。しかも「現前する瞬間」は「今」という古い言葉によってしか名づけようのないものである──仮にこのような解釈をすれば、あたかも「今」という観念を、タイトルによって読み換え、問い直そうとすることがこの作品の主題になるだろう。
こうした思考実験でもわかるように、仮に書者の意図とは異なっていても、タイトルは作品を新たに読み換える道も開く。これも「近代的なタイトル」の効果である。
十─九 「名」の制度
「愛」が出品されたとき、日展の運営陣は、「書」部門の扱いの問題と絡んで、この作品に強く反発し、「かねて書の前衛化に神経を尖らせていた日本画の松林桂月ら日展当局者は、どのようにしても「愛」とは読みかねるこの作を日展の趣旨とは反するとヤリ玉にあげた」(田宮文平『「現代の書」の検証』)という。
柳田泰雲は、第七回の日展評で、そのタイトルには触れていないものの、桑鳩の意図は頷けるが、結果はつまらない、とした上で、「あのなくもがなの……そしてあまりにもこじつけな……」と桑鳩の自作解説を難じている。さらに「かうした自己主張は、なにも日展でやる必要はなく、寧ろ他のそれにふさはしい場所を撰ぶべきでしょう」(『日展史』一七)と述べている。これが当時の日展運営陣の意見を代弁しているとも見える。この事件を皮切りに、さらに第九回展では作品が出陳拒否され、書き直しを要求されることなどもあり、一九五五年に桑鳩は日展を脱退する。
これは、展覧会という制度に桑鳩が反旗を翻した、というより、この制度がいかに作品の「名」に敏感であるかを示すエピソードである。前回も見たように、書の「名」はもともと分類のための指標であった。近代以降、それまでの制作物や書画に、西欧の論理のもとに「芸術」あるいは「美術」という名=ジャンルが与えられ、さらに「洋画」「日本画」「工芸」「書」といった分類枠によって、分類・管理され、教育の媒体となり、展示されるようになった経緯については、美術史研究で近年さかんに論じられるところである。現在の「書」には、「漢字書」「仮名書」「少字数書」「近代詩文書」「前衛書」というさらなる下位の分類枠がある。
この分類枠=ジャンルの制度は、とくに公募展では便宜のために設けられていることが多いが、それだけではなく、ある制作物を美術「作品」として、「この枠の名のもとに……として見よ」という美学的な定義を行う、ある「大きな名」に他ならない。
つまり、分類枠=ジャンルはある作品に「これは彫刻でもなく工芸でもなく、書作品としてある」と宣告し、作品の解説をあらかじめ与えるのである。そうした名の枠の中で、一点一点の作品は、「書作品」として認知される。
そのように見られることを期待しつつ、書を書くものは、展覧会が規定した分類枠にそって、「作品」を自己規定し、表現を選択して制作する。そして出品票あるいはプレート(キャプション)に「小さな名」=タイトルが書き込まれる。そのプレートには、作者の名も書かれているから、作品が作者の個性の発現であるという動機は保たれている(落款もそのシンボルである)。
このようにして、タイトルとプレートは、作品との分離と再統合を通じて、作品を定義し、その周辺に鑑賞を可能にする、展覧会制度と相似の「場」を準備する。大きな「名」の中の小さな「名」は、展覧会で系列化され、鑑賞行為を可能にするのである。つまりタイトルとプレートによって、作品が定義されていなければ、「書を見ること」ができないのである。
「前衛的な」書作品は、展覧会場で次のように見るものに語りかける。
この一枚のパネルを芸術作品として、書作品、しかも伝統的な書「としてではなく」見よ。しかも私の名のもとに、ほかならぬ私が書いたものとして見よ
書を見るものは、書かれているはずの「文字」の意味、そうでない線の集まりと、表現との一致(あるいは不一致)をそのタイトルとプレートにおいて確認する。たとえば「ああ、確かにこの線の集まりはタイトルに書かれているように「古代」を感じさせる何かを持っている」といった確認である。
前衛書のさまざまな表現は、それを書くものが書表現の幅を拡大し、変化させようとする試みと考えることができるが、その試みは、同時に作品タイトルと表装によって、みずからをかけがえのない、固有の「作品」として改めて定義されようと欲している。ところが、制作者による、この小さな名づけの欲望は、もともと展覧会側の分類の制度が整えたものであった。つまり、「前衛書」はその出発点がどこであれ、表現の動機がどのようなものであれ、極めて制度的な産物としてあるのである。
前衛書の「自由な」表現は、繰り返すように、歴史的な書体を意識しないこと、書写材料の概念を広げること、文字や言語のイメージを絵画的に変奏しようとすること、文をなさないこと、筆致表現の誇張または極端な拡大といった特徴を持っている。ところがもはや、これらの表現は、分類枠として与えられた前衛書のアイデンティティを保持しようとして、大きな「名」、分類枠の中でそれに適合する可能性を持つがゆえに選ばれるものとなっている。さらにタイトルとして小さな名を与え、変奏を加え、ポエジーを喚起しようとする。現在の前衛書はそのようなものとしてある。ある意味では表現の類型化は当然の帰結である。
冒頭の問いを繰り返そう。桑鳩の「愛」は前衛書であろうか? もしそうであるなら、どのようにしてそうなったのか?
この作品は、何より「品」という文字が大書された作品であり、先ほど挙げたような前衛書を特徴づける表現も伴っていない。その意味では、この作品は前衛書たりえないだろう。書の作品として普通に鑑賞できるはずである。ところが、「愛」というタイトルが与えられた瞬間、画面の「品」は、裏側をこそぎ取られたように、中空を漂い始め、身分を保証してくれる、送り返されるべき場所を失ってしまう。「愛」は、作品を定義することに形式的に失敗した「不可能なタイトル」なのである。「愛」は作品表現が特異であることによってではなく、タイトルづけの「失敗」によってみずからの作品価値を成立させている。
この失敗は形式的であるが故に、いわば行き所を失って、つまり「書」ではあるがこの場(ここでは日展)にはふさわしくないものとして、上位の「場」(つまり「書」一般)に追いやられてしまう。そして、この作品は名づけの失敗の特異さによって大きな「名」の下位に「前衛書」という新しい「名」(書ではあるが分類しにくいと分類されたもの)を改めて獲得する。「愛」の矛盾は、前衛書という新たな分類枠において解消される。「愛」は一個の作品にすぎないが、「前衛書」という新しい分類枠を「前衛書とは、表現であるよりむしろ「名」である。従来の古くて小さな名を捨てて(読み出し型のタイトルにこだわることなく)、近代的なタイトルによって、新しい名のあり方を獲得することなのだ」と宣言しようとする。これがジャンルとしての「前衛書」が誕生するということである。
さらにこの分類枠は、「書」を巡るもろもろの制度の系列の一部だから、書全体の制度的な定義にも関わり、また望むなら「美術」「芸術」といった、より上位の枠を定義づけにも関わりうるだろう。つまりこの名づけの失敗は、「書とは」「美術とは」どのような形式を持つべきか、という問いを呼び起こしうるのである。
こうした作品と名のあり方は、書の伝統的なあり方によるものではなく、タイトルによる分類と、矩形の画面を並べて観客に見せる、というその表象形式をその特徴とする、近代の美術館制度が移入される過程で生じ、その結果言葉に依拠する書の特質において起こったことだろう。
「愛」は、大きな枠組みと一個の書を作品たらしめている「形式」の連環を戯画的に暴露することにおいて、「前衛書」なのである。
◎参考・引用文献
市村弘正『「名づけ」の精神史』(一九九六、平凡社)
ミシェル・フーコー 豊崎光一・清水正訳『これはパイプではない』(一九八六、哲学書房)
岸本太郎編『毎日書道講座・前衛書』(一九八八、毎日新聞社)
日展史編纂委員会編『日展史』(一九八〇~、社団法人日展)
田宮文平『「現代の書」の検証』(二〇〇四、芸術新聞社)
