
疑わしきは…の原則どこに 周防正行監督が司法に抱いた三つの驚き:朝日新聞デジタル
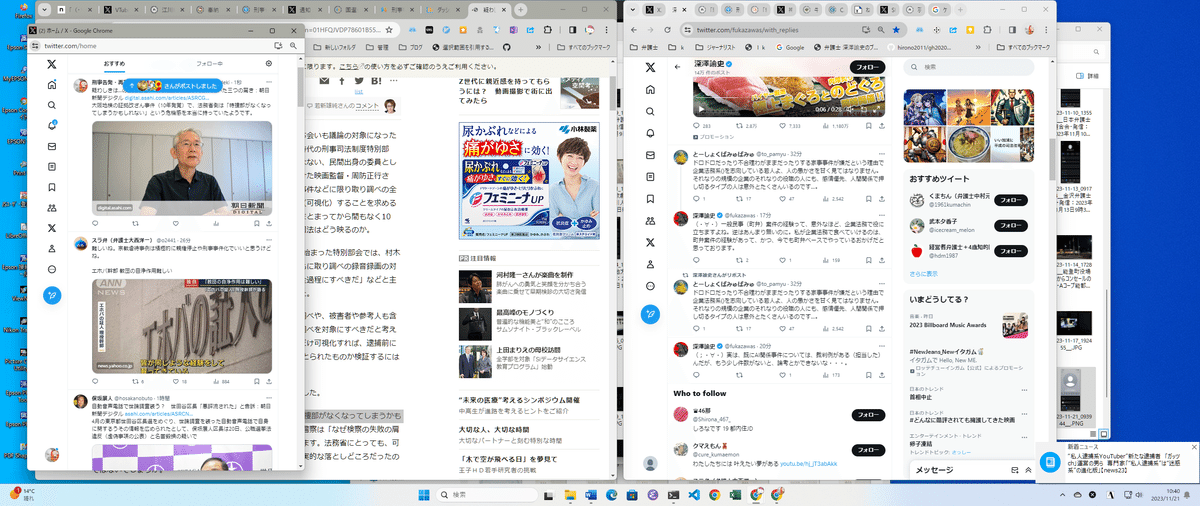
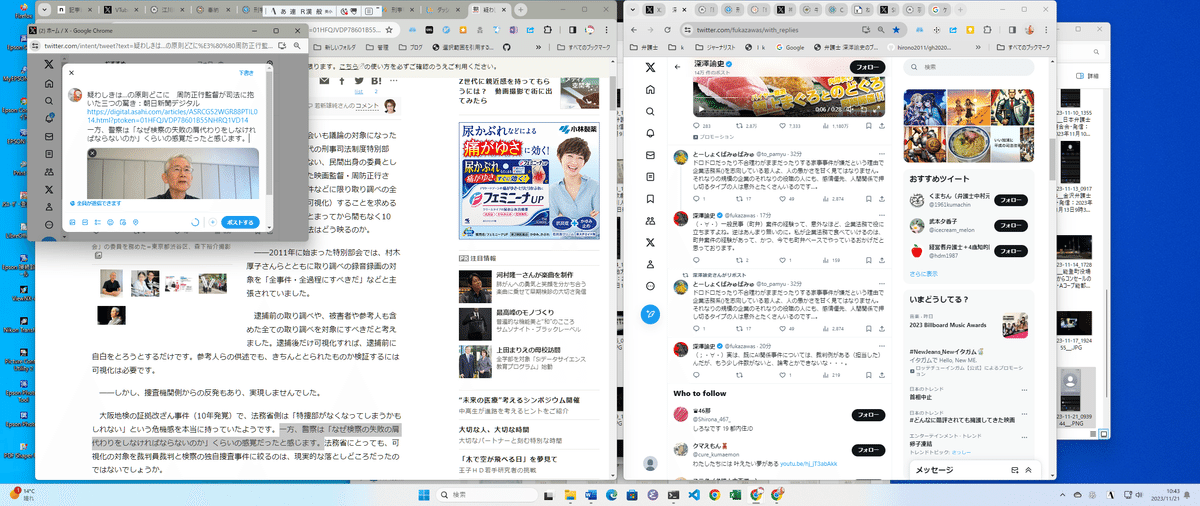



逮捕前の取り調べや、被害者や参考人も含めた全ての取り調べを対象にすべきだと考えました。逮捕後だけ可視化すれば、逮捕前に自白をとろうとするだけです。参考人らの供述でも、きちんととられたものか検証するには可視化は必要です。
――しかし、捜査機関側からの反発もあり、実現しませんでした。
大阪地検の証拠改ざん事件(10年発覚)で、法務省側は「特捜部がなくなってしまうかもしれない」という危機感を本当に持っていたようです。一方、警察は「なぜ検察の失敗の肩代わりをしなければならないのか」くらいの感覚だったと感じます。法務省にとっても、可視化の対象を裁判員裁判と検察の独自捜査事件に絞るのは、現実的な落としどころだったのではないでしょうか。
疑わしきは…の原則どこに 周防正行監督が司法に抱いた三つの驚き:朝日新聞デジタル https://digital.asahi.com/articles/ASRCG52WGR88PTIL014.html?ptoken=01HFQJVDP78601B55NHRQ1VD14
――刑事司法に関わるようになったのは07年公開の「それでもボクはやってない」を手がけたことからですね。この作品を作ったきっかけを教えてください。
02年の年末、新聞に痴漢冤罪(えんざい)の記事が掲載されていました。痴漢をしたとして強制わいせつの罪で起訴され、一審で有罪になった被告人が、二審で無罪になったという内容でした。記事は、被告人に痴漢をされたという被害女性の供述が「人違い」だったと立証することで無罪を勝ち取った、と報じていました。
疑わしきは…の原則どこに 周防正行監督が司法に抱いた三つの驚き:朝日新聞デジタル https://digital.asahi.com/articles/ASRCG52WGR88PTIL014.html?ptoken=01HFQJVDP78601B55NHRQ1VD14
さらに彼らは、真犯人に自らの罪を認めさせ、反省させて、更生への第一歩とすることが、自分たちの使命であり、やりがいであると思っているのではないでしょうか。出所後、自分を訪ねて来て「あの時はお世話になりました」とお礼を言われて完結する。これこそが取調官の使命だと感じている。
要するに取調室の中で「裁判」を完結させることが最も素晴らしい取調官の姿だと信じている。それこそが取調室を神聖な場所ととらえる彼らの感覚なのでしょう。
取調官及び捜査機関は、遠山の金さんでもなければ、裁判官でもない、ということを深く自覚してほしいです。
――取材を始めて20年以上経った今も、刑事司法に深く関わっているのはなぜですか。
疑わしきは…の原則どこに 周防正行監督が司法に抱いた三つの驚き:朝日新聞デジタル https://digital.asahi.com/articles/ASRCG52WGR88PTIL014.html?ptoken=01HFQJVDP78601B55NHRQ1VD14
取調官は「遠山の金さん」ではない
――山積みされた刑事司法の問題を改善するために必要なことはなんでしょう。
人質司法の問題で言えば、日産のカルロス・ゴーン元社長が保釈後に逃亡した際、裁判所と弁護士は批判にさらされました。一方、勾留され続けた村木さんが無罪になった際、「なぜ勾留を認めたんだ」という裁判所への批判の声はどれだけあったでしょうか。
裁判官も「釈放して何かあれば、批判されるのは自分だ」と思えば、「検察の言う通り、勾留しておこう」という気持ちになるのではないでしょうか。私たちが人権とは何かを理解し、捜査機関や弁護士、裁判所の行いを注視して、まず、いま何が行われているかを知ることが重要です。
疑わしきは…の原則どこに 周防正行監督が司法に抱いた三つの驚き:朝日新聞デジタル https://digital.asahi.com/articles/ASRCG52WGR88PTIL014.html?ptoken=01HFQJVDP78601B55NHRQ1VD14
