
【現場の気づき】授業参観は満席なのに…学級懇談会で保護者が減っていく話✨

こんにちは!小学校教員のささです。
今回は、学級の懇談会について、現場で感じている課題と、その解決策についてシェアしたいと思います。
1. 懇談会参加率低迷の現状と課題
先日、懇談会があったのですが、参加率について考えさせられることがありました。
懇談会は授業参観の後に行われることが多いですよね。私の学校も、5時間目に授業参観を行い、子どもたちが下校した後の6時間目に学級懇談会を設定しました。
学校側は懇談会の参加率を把握するため、参加人数をチェックします。しかし、保護者の方々が「参加する」「参加しない」を判断する時点で、いくつかの疑問が湧いてきました。
保護者は懇談会に「参加したい」のか?「参加したくない」のか?
これが最初の問いです。なぜなら、私のクラスの懇談会参加率は、3割から4割程度だったからです。
懇談会は、子どものことについて保護者と教員が話し合う場です。しかし、
「そもそも懇談会で何の話をするのか?」
が最も重要なポイントだと感じています。先生が一方的に学級の様子を伝えたり、写真や動画を見せたり、今後の学校行事の連絡をするだけなら、それは懇談会ではなく、単なる事務連絡になってしまいます。
懇談会であるからには、教師と保護者、または保護者同士の対話が重要になるはずです。そのためには、学校側が適切なテーマを用意する必要があるのではないでしょうか。
2. 一方通行の連絡会から双方向コミュニケーション型懇談会へ
なぜこのテーマを取り上げたかというと、先日懇談会があり、そこで感じたことがきっかけです。
従来の懇談会は、先生が一方的に学級の様子を伝え、写真や動画で子どもの様子を紹介し、今後の学校行事や連絡事項を伝える、という形式が多いのではないでしょうか。

しかし、これでは懇談会ではなく、単なる連絡会です。
懇談会は、教師と保護者が子どものことについて話し合う場であり、双方向のコミュニケーションが不可欠です。
そこで、私は保護者同士が繋がることを意識した懇談会を企画しました。
3. 保護者同士の繋がりを生む「おしゃべり懇談会」
今回の懇談会では、保護者同士の交流を深めるため、「テーマカードでトーク」と題して、トークテーマを用意しました。
近年はコロナ禍で懇談会が少なかったこともあり、同じクラスの保護者同士でも意外と知らないことが多い状況でした。小学校では多くの子が同じ中学校に進む可能性があり、これから数年、もしかしたらもっと長く関わることになるかもしれません。だからこそ、お互いを少しでも知っておくことは、保護者同士の連携や、子どもたちのより良い成長にも繋がると考えました。
具体的には、子どもに関するテーマを20個ほどカード形式で用意し、4、5人の小グループに分かれて自由に話してもらう企画です。

普段は控えめな保護者の方も、小グループだと話しやすいようで、子どものことを思い出しながら、話が広がっていきました。
例えば、以下のようなテーマで会話が弾みました。
「最近、お子さんとどんな話をしましたか?」
「最近、お子さんと喧嘩した話はありますか?」
「最近、お子さんに言われて嬉しかったことは?」
「お子さんの成長を感じた瞬間は?」
どのグループも和やかな雰囲気で、笑い声も聞こえてきました。「顔は見たことあるけど、ちゃんと話すのは初めて」という保護者の方も多かったようです。20分程度の短い時間でしたが、予想以上に盛り上がり、保護者同士の距離が縮まったように感じました。
4. 「お喋り」表現が招いた誤算
懇談会後、とある保護者の方から嬉しい言葉をいただきました。「今日みたいに面白い懇談会なら、みんな参加すればよかったのにね」と。
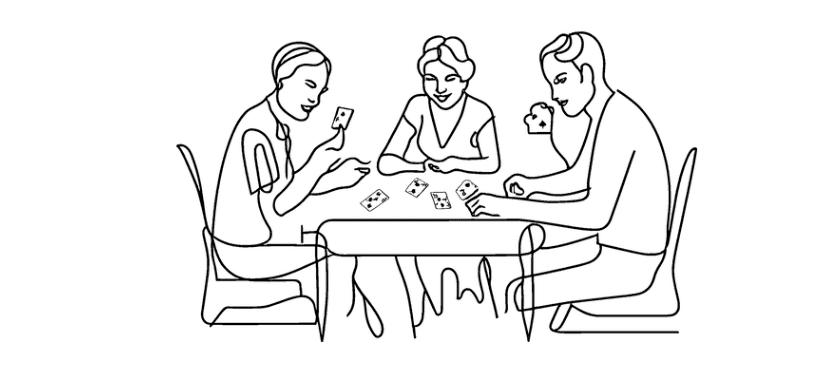
そこで、「どうして参加しないのでしょうね?」と尋ねてみたところ、意外な答えが返ってきました。
授業参観で配布した懇談会の資料に、「保護者同士でお喋りをしましょう」という時間を設けることを記載したのですが、それを見た保護者の方の中に「ちょっとそれは…」と感じて、参加を見送られた方がいたようなのです。
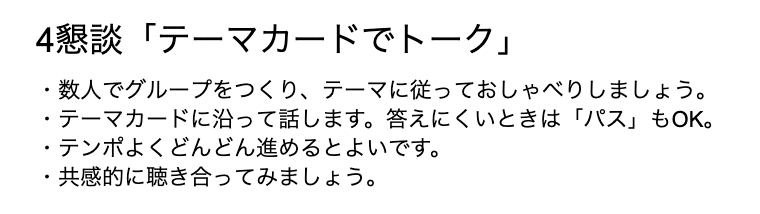
良かれと思って企画した「おしゃべり懇談会」という表現が、参加へのハードルを上げてしまった可能性があることに気づきました。
もしかしたら、初対面の保護者の方と話すことに抵抗を感じる方もいるのかもしれません。懇談会に何を求めているかは人それぞれで、先生からの一方的な説明だけを求めている保護者もいる可能性も考慮する必要があると感じました。
5. 懇談会に求められる情報提供と対話のバランス
懇談会は、子どもの成長について、学校と家庭がそれぞれの立場から意見交換をする、非常に意義深い機会です。
学校側が「これを伝えたい!」「情報共有したい!」と思っていても、保護者の方々がどんなことを思っているのか、どんな期待や不安を抱えているのかを、ざっくばらんな雰囲気の中で聞き出すことも大切です。
懇談会という名称に、「かしこまった話し合い」のようなイメージを持つ方もいるかもしれません。「懇談する」=「おしゃべりする」という表現に抵抗を感じる保護者の方も少なからずいるのは事実です。
学校としては、懇談会の参加率が上がることはもちろん嬉しいです。しかし、保護者の方にも、時間の都合や家庭の事情など、様々な事情があるため、参加を強制することはできません。
それでも、保護者の方々に「参加してよかった」と思える懇談会にするためには、私たち教師側の準備が重要です。有益な情報提供はもちろんのこと、保護者同士が安心して話せるような雰囲気づくりや、楽しい時間が共有できるような仕掛けも必要かもしれません。
懇談会は、情報提供と対話のバランスが重要であり、参加者のニーズに合わせた柔軟な運営が求められるのだと改めて感じました。
まとめ:より良い懇談会に向けて
今回の懇談会を通して、保護者の方々のニーズは多様であり、一律的な懇談会では満足していただけない可能性があることを改めて認識しました。
「おしゃべり懇談会」は、保護者同士の繋がりを深めるという点では一定の効果がありましたが、参加を躊躇させてしまう側面もありました。
より良い懇談会を目指すためには、以下の点が重要だと考えます。
懇談会の目的を明確にする: 情報共有、保護者同士の交流、個別相談など、懇談会で何を達成したいのかを明確にする。
参加者のニーズを把握する: 事前にアンケートなどを実施し、保護者が懇談会に何を求めているのかを把握する。
多様な形式を検討する: 一方向的な説明会形式、グループワーク形式、個別相談形式など、目的に応じて適切な形式を選択する。
ゆるーいな雰囲気づくり: お茶やお菓子を用意したり、リラックスできるBGMを流したりするなど、雰囲気を和らげる工夫をする。
「おしゃべり」という言葉の再考: 親しみやすい言葉を使うことは大切だが、誤解を招く可能性も考慮し、表現を慎重に検討する。
今回の経験を活かし、保護者の皆様にとって有益で、参加しやすい懇談会を企画していきたいと思います。
この記事を読んで、皆さんが懇談会について感じたこと、ご意見、ご感想などありましたら、ぜひコメント欄で教えてください!
