
子どもたちの「知りたい」を反映させた社会科の学習課題・学習計画を短時間で立案! ロイロノート×Google keep×ChatGPTのコンボでみんなハッピーに
はじめに
私は小学校の社会科の授業において、子どもたちの「知りたい」という問いをスタートにしてそこから単元を貫くような学習問題を設定しています。そして単元で追求したいことを学習計画として子どもたちと一緒に作成し、追求をするという流れで単元をデザインしています。児童にとっては「知りたい」がそのまま学習の中心となるわけですから。
今回はその効率性を大幅に向上させる方法を自分なりに流れるようになってきたのでお伝えしたいと思います。この方法は、ICTツールを駆使して、授業計画の立案プロセスを劇的に時短すると同時に、充実感のある結果をもたらしました。その秘訣を紹介します。
賛否あるとは思いますが、こんなやり方もあるんだなぁ的な捉えで読んでいただければと思います。今回は小学校6年の「武士の世の中」の単元を例にお伝えします。
今回使うICTツール
①ロイロノート
②google keep
③ChatGPT
1.ロイロノートでスピーディな「問い」の共有と収集
最初に、教科書の扉絵や概要の説明といった社会的な事象と出会い、基礎情報をもとに「武士」について外観を捉えるインプットを行います。
その後、ロイロノートアプリを活用し、「武士」についての疑問や知りたいこと、調べてみたいことをロイロノートのカードに記入し、提出箱に提出します。提出箱は共有をかけている状態のため友達からどんな疑問が出てくるのか素早く確認することができます。クラス全体からの情報を瞬時に収集しました。

手書きノートよりもはるかに迅速で、効果的な方法です。文字情報だけでなく、注目すべき「問い」、単元のねらいに迫りそうな「問い」を書いた児童を指名し音声言語でクラス全体に共有します。ここまでは割とフツーな使い方です。
また、自治体・学校によっては導入していないとは思いますが、教材を配布・回収・一覧できるサービスであれば転用可能です。
2.スクショを撮ってgoogle keepへ保存
その後、教師が提出箱に提出されたデジタルカードの一覧を画像データとしてスクショを保存し、Googlekeepにアップロードします。このプロセスは数十秒で瞬時に行われます。手作業でのデータ入力や整理の手間が大幅に削減されます。注意点としてはこの段階で個人名を伏せるモード(無記名モード)にしておくことが大事です。

3. テキストデータの簡単抽出:
そして、Google keepの機能、「画像からテキストデータを抽出する」を活用します。これにより、手動でテキストを入力する手間が省かれ、時間が節約されました。ここまでの作業は教卓でわずか数十秒です。
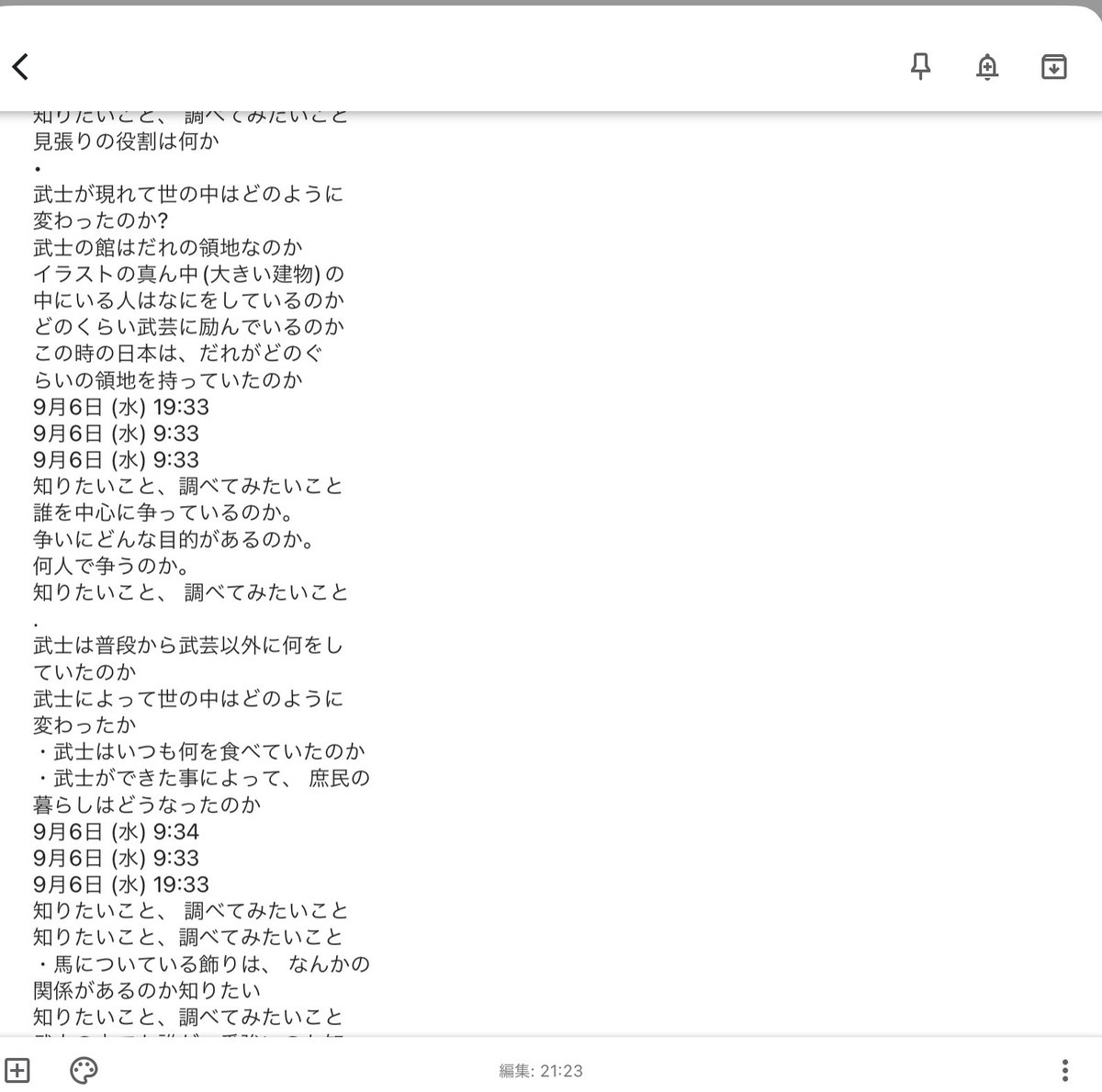
4. ChatGPTのスマートな整理:
抽出されたテキストデータを、ChatGPTに整理を依頼することで、重要なトピックと質問が自動的に抽出されます。これにより、教師がデータを手動で解析する時間が大幅に削減され、効率性が向上しました。ちなみに学校アカウントでは使用できないのでここでは個人アカウントで運用しています。



5. よりスピーディな学習計画の策定:
最終的に、ChatGPTを介して整理された情報をロイロノートの上にコピペし、児童に配布したり、画面配信機能を使ってラインを引きながら検討することができます。
こうすることでクラス全体の「問い」が整理されたテキストデータを眺めながら、単元全体のの学習計画を迅速に策定しました。もちろん授業者としておおまかな計画は準備した上で教壇に立っていますが、児童たちの関心に合わせて焦点を当て、授業計画の立案が劇的に時短できました。

終わりに
もちろん、子どもの意見を黒板に書き出し、付箋などを使って類型化していく作業をクラス全体で行うこと自体には大きな意義があるとは思います。しかし、今までの実践を振り返ってもこのアナログの作業を入れることでどうしても指導時間がかかりすぎてしまう傾向にありました。
この方法を活用することで、子どもたちの声を尊重しながら、授業計画の策定時間を大幅に短縮し、同時に充実感のある結果を実現しました。まさに、児童も教師もみんなハッピーになり得るのでは。
ICTツールの力を借りて、授業の質を向上させることができることを試してみてください。
