
大分+長崎+佐賀 蔵元アーカイブズ 2002〜05(2) 大分・藤居醸造

2002.12.21 by 赤木牛一郎

■あの『自然麦』で有名な、藤居醸造さんにお邪魔する。
次に伺ったのは、大分県南部に位置する大野郡千歳村にある藤居醸造合資会社さんである。
無農薬原料を使った『自然麦』が有名だが、屋号を商品名にした『井田萬力』も最近見かけることが多くなった。同社は麹から「もろぶた」を使った完全な手作りで麦焼酎を造られている。けんじさんは8月にこちらにお邪魔しており、再訪となった。
時間がだいぶ押してしまって、冷や汗。とにかく午後5時に到着して、事務所へと伺う。店は小売りの店舗(タイトル画像)と、その左にもうひとつ「焼酎工房」と名付けられた自社焼酎専用のプレゼンテーション棟(画像左下)のふたつに別れていた。


工房の内部は、民芸調の造りでなかなか良いイメージの設えである。試飲用の甕の数も多く、思わずヨダレがじゅるっ。陶器製のコップなどグッズ関係も充実している。
というわけで、遅刻のお詫びを申し上げて、専務の藤居淳一郎氏にご挨拶申し上げた。

■けんじさんが、豊後麦『兼八』の双璧と讃える『舞香』。
試飲・展示部屋の隣りにある事務所でお話を伺う。
けんじ「『兼八』と、『舞香』『自然麦』が、大分の双璧と思ってるんですが」
専務「いえいえ。まぁ、うちの場合は出荷するやつが無いんですわぁ、『舞香』の場合ですねぇ。ですから来週から詰めて出さないと、お客様をお待たせするわけにはいかんですからねぇ」
猛牛「『自然麦』は福岡でも見かけることが多いですばってん」
専務「『自然麦』は卸さんにも出してるんですが、『舞香』は専門店さんだけです」
猛牛「通りでなかなか見かけんわけですたい」
専務「やっぱぁ、酒屋さんと顔の見える商売していかんと、うちのような小さい蔵は伸びていかんちゅーことがありますからなぁ」



けんじ「販売しているお店については?」
専務「四ッ谷君とかち合わないようにと思っているんですけど。一緒に売ってらっしゃる店も多いですよね」
隊長「はい」
専務「蔵それぞれの味わいというのがありますから。鹿児島の芋は蔵の個性がいろいろとあるじゃないですか。大分の麦ではそれが少なかったんで、逆に個性を出してやろうと、5年くらい前から取り組んで、お客様に少しづつでも解ってもらえるんじゃないかと思いましてね」
けんじ「それ以前はどうだったんですか?」
専務「やはり軽いタイプを造ってまして。イオン交換が流行ると大分の蔵の多くもそれを始めたわけです。でも、同じ事やっていても伸びないなと思ってですね。常圧蒸留器もあるし、それを活かして美味しい焼酎ができればいいかなと。まぁ、全員が全員好んで貰えるかどうかは別ですが、好きな方に飲んでいただければと思いました。味わいを重んじる方にじっくりと飲んでいたくちゅー方向性に、段々と持っていったわけです。」
けんじ「5年前から『自然麦』とかを始められたわけですか?」
専務「完全常圧100%だと、『じいさんの置き土産』を最初にやったわけです。」
けんじ「次が『舞香』と・・・。藤居さんの焼酎は、四ッ谷さんみたいなインパクトは無いですけど、どちらかというと渋いというか“通好み”というのも変ですが。こう、落ちついて日常酒として飲むという感じで好きなんです」
専務「『自然麦』の場合は、最初から常圧で入るのが難しいというか馴れてない方向けに、少し大人しく仕上げてるんです。香りを残して、キレを残すというタイプ。で、『舞香』は常圧100%で、香りとまろやかさを残してます。まぁ、のんびりと“やつがい”していただく焼酎というか・・・」
猛牛「やつがい?」
けんじ「やつがい!」
猛牛「やつがい?」
専務「ああ、つまり晩酌のことをこちらではやつがいと言うんですよ」
猛牛「なるほど!」
というところで、藤居醸造さんはかつて正調粕取焼酎が主力だったことが判明した。事務所の中に、かつてのセイロ式蒸留器が保存されていたのである。


また大東亜戦争敗戦後の米不足の時期は、芋焼酎を造っていたという。当時の芋の粉砕器も同様に残されていた。 この辺りも、筑前の蔵元さんで伺った話と同じ歴史的経緯が見て取れる。
古い道具をしみじみと眺めていたら、「では、実際に蔵を見て下さい」との専務のお言葉。後ろにくっついて、見学させていただくことに。そこには手造りの往古の時代が息づいていた。
■麦を蒸す樽や新調なった麹室など、道具も古式床しく・・・。
まず拝見したのは、麦を蒸す樽。この樽に麦を詰めて下部の穴から蒸気を通すようだ。本当に古式床しいとはこのこと。現在では樽の職人さんが少なくなったので、補修が大変だという。けんじさんの話では、麦を樽で蒸す蔵はここだけではないか、とのこと。


麹室は、今年の秋くらいに新調なったそうで、以前よりも広くして作業性を高めたとの専務の話だ。「これでゆったりと作業が出来ます」と専務。完全な手作業で、もろぶたを使っているのは、県内でも珍しいといふ。
温度調節のために、屋根に4つの通気口が開いている(画像右下)。床に近いところに設置されたヒーターと、この通気口を適時開閉することで、麹造りの最適な環境を確保している。





仕込みの時に使われる道具類もやはり竹や木の伝統的なものである。
専務「あの櫂なんかも、一度プラスチック製を使ったことがあるんですが、どうもしっくり来ない。重たいし、使いづらくてですね。結局元の木に戻しました。それにやはり木でないと味が違うような気がしまして、ね」
わては先日お邪魔した宮崎県諸塚村の『園の露』さんの空気を思い出した。
蒸留機は昇りの部分にとても気を遣っているそうである。
専務「あそこでどの成分を残すか残さないかを考えるので、どのように手を加えるかが、考えどころです」
蒸留器については常圧と減圧の両方が設置されていた。





保温性を高めるために、それと麹室の外壁内、およびタンクの土台部位分に籾殻が詰められている。
麹室では5トン車で15台分の籾殻が運ばれて、壁や屋根などに詰められたそうだ。それにしても凄い量だなやぁ~。
貯蔵庫の横には、瓶詰めのラインと巨大な甕が鎮座ししていた。甕には、未だ商品化の予定はない長期貯蔵酒が、すやすやと登場を待つ。



■待望の試飲で、エースの醸『舞香』にグッと来ちまったぜ!
一通り見学させていただいた後は再び事務所に戻って試飲タイムである。俺は待ってたぜ!
『自然麦』『舞香』、そして蔵だけでしか販売されていない『自然麦』の原酒を頂戴する。この原酒については昨年ある酒屋さんにお邪魔した時に、いただいた事がある。これも麦の香りがプンプンとして、旨かった。
とにかくわての好みとしては、なんと言っても『舞香』の練れた麦の味がいいですばい。まさに“エースの醸”。風味が濃く、じっくりと飲むのに最適。けんじさんがお勧めに挙げるのも解る気がする。

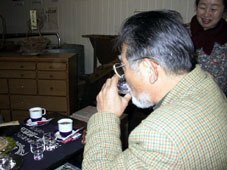
わては『舞香』と屋号ネーム入りの陶製コップを、けんじさんと隊長は原酒を購入して、そろそろ家路に就くこととした。お忙しい中ご案内いただいてありがとうございました。
◇ ◇ ◇
個性の強い味わいで全国的に熱烈なファンを増加させた四ッ谷さん、そして昔ながらの造りをしっかりと守りながら大分麦焼酎の新しい顔を造りだそうと奮闘されている藤居さんという、2社にお邪魔させていただいた。
ガリバー2社が鎮座する大分麦焼酎の世界で、生存のために「自分らしさ」が必要だったのは、とても理解出来る。似た味では企業体力の差で太刀打ち出来ないのだから。
また味の個性化に対して追い風が吹き始めてもいる。「らしくない焼酎」から、「らしい焼酎」へと、ゆるやかではあるが、時代は個性的な味わいを求める嗜好へと移行している感じがする。現に多くの人が『兼八』に感動したように・・・。
たぶん四ッ谷さんや藤居さんが着手し開拓したレーゾンデートルが、今後の台風の目になるのだろうな。それは、今がたとえ牛歩であったとしても、着実に前進し加速度を増してくるのは間違いないと、二人の若き醸造家とお会いしてそう思った。
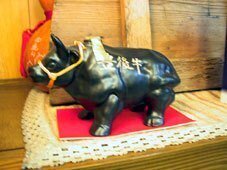
(了)
